どこを向く、その無垢なる眼差しの彼方に
五月五日、子供の日にちなんで、
これまでぼくが感銘を受けてきた、
子供たちの活躍する映画特集を組んでみようと思う。
子供が主役の映画といっても、それこそ千差万別なのはいうまでもないが、
同時に、それを見る当事者の年齢、精神性、状況によっても
大いに思いは変わってくるはずだ。
ぼくが小学生の頃、初めてみた映画らしい映画、
それがたまたまテレビでやっていた
ルネ・クレマンによる『禁じられた遊び』だったと記憶しているが、
そう、だれもが知る有名なメロディのギター曲を思い出す、あれだ、
ブリジット・フォッセーという子役扮する
ポーレットという戦争孤児の女の子の話で、
その頃、映画というものがどういうものかさえわからないまま、
単純にその悲哀にみちたドラマにかじりついて、
勝手に感動して、ひとり涙腺をゆるませていたことを思い出す。
遠い日の思い出だが、まだ純情さしかなかったころの話である。
いずれにしても、子供のいるスクリーンという空間においては
実に魅力的なテーマを担う、重要なファクターであることは間違いない。
ただ子供という素材を使ったから、必ずしも名作になるわけでもないが
名作と呼ばれる映画のうちには、子供という素材がうまく機能して
往々にして感動を呼ぶというストーリーは枚挙にいとまがない。
やはりどうにもこうにも、人間である以上、
琴線に触れてくるものなのだろう。
子供をどう扱うかで、匠としての基準が変わってくる、
いわば、映画作家としては、ひとつの指標とさえいえるのかもしれない。
それだけ、難しく、かつ魅力的な素材なのだ。
なかには、どうにもあざとく、見ていられないようなものも多い。
つまるところ、ダシである。
だが、それを差し引いても
大人にはとうてい醸しえぬ雰囲気、まなざしでもって
大の俳優たちを食ってしまう大物子役までいろいろあって
やはり子供のいる風景は豊かな詩情を生み出す。
ここでは、単に子供が出ているからという安直な理由から
騒ぎ立てようとするつもりは毛頭ない。
むしろ、そういうものは積極的に排除して、
映画として、真に心に訴えかけてくるもの、
そこにたまたま子供という存在が、その映画の核心をにぎっている、
という作品のみを厳選してとりあげてみたい。
もちろん、独断と偏見、我が偏愛だけをぐだぐだと書き連ねるまで、
直感だけがたよりの、なんの根拠もないところである。
ただひとつ、言えることは、
自分もかつては子供であった、という事実のみである。
よって、スクリーンを彩る子供たちのなにかと
自らが經た、記憶、匂い、思いなどが
重なり合ったり、ずれたりしながら、
多分にノスタルジーをそそりながらも、
交感を繰り広げるものがあるからなのだろう。
特集:天井桟敷の子供たちへの凱歌
- 退行か前進か、永遠の三歳児にグラスを掲げよう・・・フォルカー・シュレンドルフ『ブリキの太鼓』をめぐって
- この詩情、この奇跡、あなかしこあなかしこ・・・ヴィクトル・エリセ『ミツバチのささやき』をめぐって
- 詩情をはさんだポエティックランドスケープ・・・伊藤智生『ゴンドラ』をめぐって
- こどもはたから。こどもはちから。羽ばたけわんぱくこどもどもの詩・・・フランソワ・トリュフォー『トリュフォーの思春期』をめぐって
- ジグザク気取りのない田舎の町なみを行く少年に微笑みを・・・アッバス・キアロスタミ『友だちの家はどこ?』をめぐって
- 紙製の月への思い、後ろ髪引かれるにつき・・・ボクダノビッチの『ペーパームーン』をめぐって
- 離れ難きは他人なり。僕のロードムービーはここから始まった・・・ヴィム・ヴェンダース『都会のアリス』をめぐって
- 森林経由、フランス発日本行きの物語・・・諏訪敦彦/イポリット・ジラル『ユキとニナ』をめぐって
- ベトナム幻想、未だ醒めやらず・・・トラン・アン・ユン『青いパパイヤの香り』をめぐって
- 新緑の季節に、青春プレイバッカーな僕がふといたずらに降りてくる・・・ワリス・フセイン『小さな恋のメロディ』をめぐって



![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-200x200.gif)



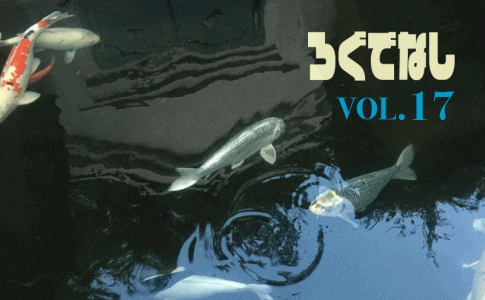





コメントを残す