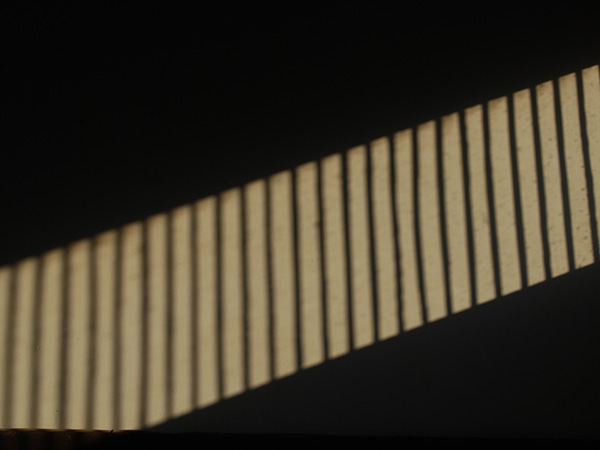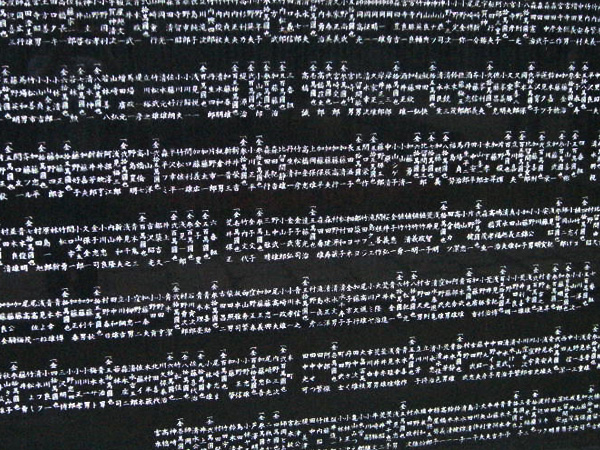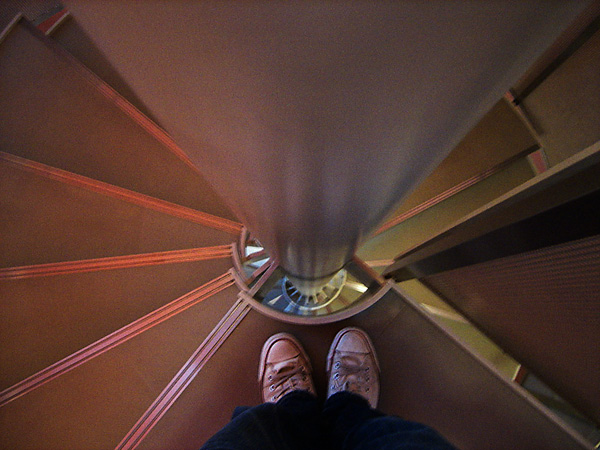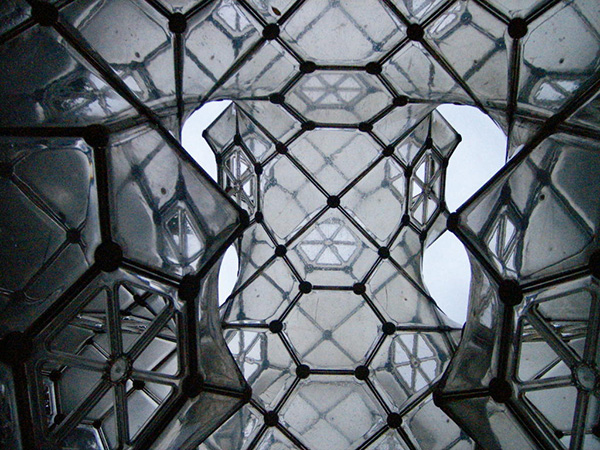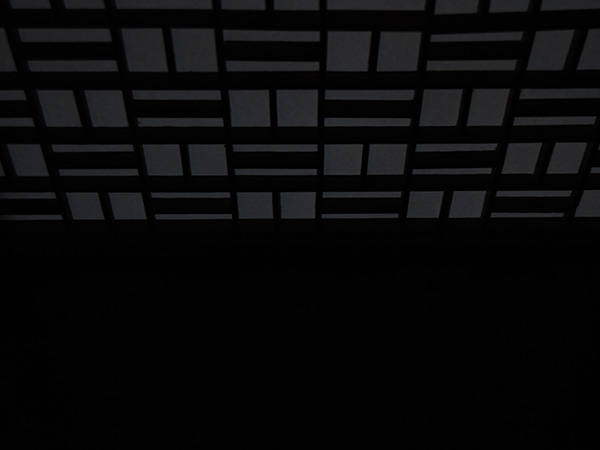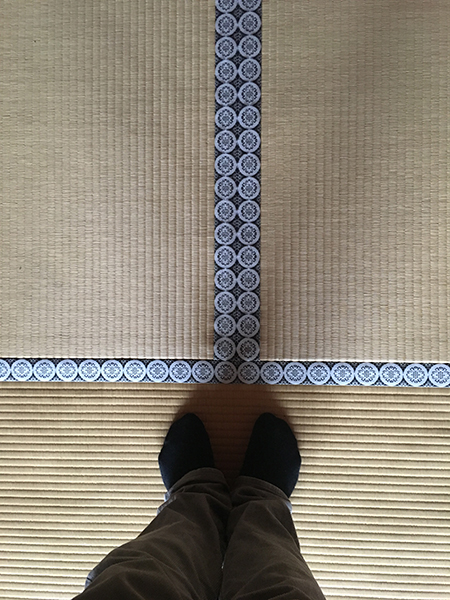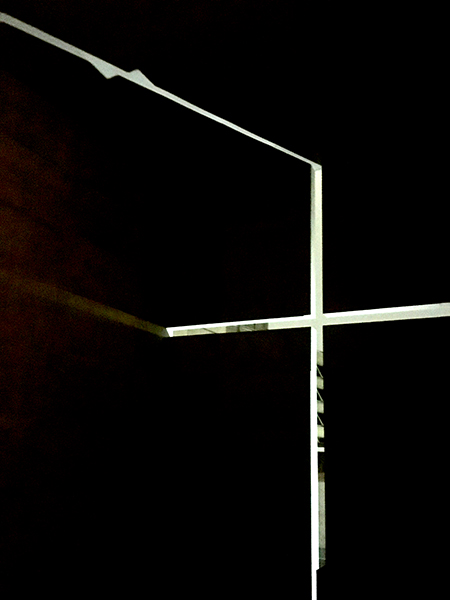僕が達したいのはこの正確さだ。すばらしい、だがそこまで語ってはならないのだ アンドレ・アングル
放蕩グラファックギャラリー
伝家の放蕩グラファックス、はじめに形ありき
目の前に映っているものは同じはずなのに、人によって、まったく解釈がちがってしまうのは、だれもが経験として認識しているはずである。それが写真の場合は顕著に現れる。同じ被写体のはずが、ほう、なんだこれは、とあらためて目をしばたかせる瞬間というものが確かにあるものなのだ。日頃見慣れた風景やなんて事のない対象物が、なにやら新鮮にみえてくるということが、こうしたマジックによって明らかされてしまうのが写真の面白さではないだろうか?
また、写真はしばし、嘘をつくもの、といわれる。概ね、このところずっとこのことばかりを考えていると、あるとき、こう思えた。被写体が仮に人間であろうと、風景であろうと、モノであろうと、究極のところなんであろうと、写真をとるという行為は、「愛の行為」そのものなのではないか、と。要するにその事物を所有したい、近づきたい、そして一体になりたいと願うわけなのだ。その想いがカメラを通してイメージを捻出するだけなのだと。
自分の視点でものをいうと、まずは雰囲気があり、形があり、色がある。そのどれかに心つかまれ、直感的に写真を撮ろうとするのだが、そのなかで、わたしという欲望は、写真のデキそのものよりも、瞬間瞬間の出会い、つまりは瞬時に陥る恋のようなものとして考えてきた。別段写真そのものに意味をもたせようとして、シャッターを押してきたわけでは決してないのだと思う。それによって、後日化学液の洗練を受け、あるいはメカそのものの即時的な処理によって、この世に現れた実像たちは、おそらく、そのとき自分が、この目で見たという視覚の再現以上の物語を覗かせてくれるかもしれないし、また、率直にも、見た情報以下の、ほぼなんの価値もない、時間の抜け殻や虚無の残骸をそこに転写しているに過ぎないのかもしれない。
これらをひとつひとつのイメージをとらえなおし、新しく世界を提示し直すことはできるだろう。仮に、たった一枚の写真だけではどうにも存在を主張できないものであっても、渡り鳥や魚群のように、大量にイメージが立ち並ぶと、それだけでにわかに輝き始める世界というものがある。そうなると、結局数がものをいうことになるのだが、それは単なる数量の問題ではない。対象への思いの産物なのだ。そのとき、その瞬間にそこに居合わせたはずのカメラマンは、その事物に対して、何らかの誘惑を受け反応したのは事実だが、その理由は正直なところ、全てあとづけでしかないのだ。瞬間的にメカニックなファロスの勃起がおき、対象にむけ、ひたすら射精というプロセスを繰り返しただけのことである。それは自然の摂理に思えるし、本能なのだ。それがまぎれもなく、自分自身の正当な感受性の健全なる証明なのである。
だから、この場合、一見マスターベーションにも似てはいるが、それとこれとをへだてるのは対象への愛おしさ、すなわち愛の熱量なのだと考えている。マスターベーションよりももっと神聖であると同時に、もっと自然で、もっと祝祭的でかつさらなる官能性さえも呼び起こすものとして、それは他者への眼差しをどこかで意識的に宿しているからなのではないか、と思う。もっとも、その対象にエロスを感じて、本能に基づいて撮りえた写真については、まぎれもなく愛が映り込んでいるものと信じているのである。それが写真を撮る動機なのだが、自分の関心はただそれだけのことでしかない。間違ってもインスタ映えなどというような考えはないのである。
ここまで、もっともらしく我流の写真論を語ってきたが、デジカメ〜スマホといったものの進化過程で、すべてはもっと単純で、即物的なものへと移り変わろうとしている。そうした時代の変遷に逆らえず、ひたすら画像(写真といわない)を量産しているのもまた事実なのであるが。