天使よ、この海岸では透明な悪魔が薔薇を抱いている。
ポール・エリュアールに 瀧口修造
詩、あるがままにあるがためのわが言葉の隊列
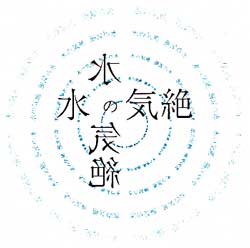
それこそ、中学生の頃は、中原中也だの三好達治だの、そう言った叙情的な詩ばかりを読んで勝手に文学青年を気取って見せた。が、意識の成熟に伴って、フランス文学の洗礼を浴びると事情は打って変わった。フランス近代詩を中心にしたシュルレアリスムの詩に感銘を受けた。意味はひとまず置いておいて惹かれるものがあった。アンドレ・ブルトンを始め、ポール・エリュアール、スーポー。あるいはコクトーの地口やアポリネールのカリグラム。少し遡れば、ランボー、ヴェルレーヌ、ボードレーヌ、マラルメといった流れの中に真実の詩というものを見出した気がした。日本では西脇順三郎、瀧口修造、北園克衛など、前衛的な詩にすっかり魅入られてしまっていた。そうした思いは今もなお消えてはいないのだが、どこか無意識下におりてしまっている。
思えばあの頃は単にそのスタイルに惹かれていただけかもしれない。意味を超えたコトバの連なり、そしてその魔法のごとく現れるコトバを追求していくうちに出会う偶然性。そのうちに、自分も同じような試みにはまってゆく。なれぬパソコンのキーと指の戯れ。あるいは紙の上の落書き、独り言。思考は後でついてくるのだと思っていた。冷静に読むと意味が見えてくることもあるようなないような、そんな言葉の連なり。どこかしらイメージとの戯れが稚拙に存在しているやもしれない。そこにはさほどとりたてて情が揺さぶられるわけでもない。ともすれば、当時のカオスが再びどこかで残り香のごとく立ち上ってくれるだろうか。
とはいえ、ジャズのインプロヴィゼーションにならいて、方法論は、ひたすらに自動手記というやつを試みた。マッキントッシュという、どこかおもちゃのような親しみやすい道具との出会いが、詩を書く契機になったのかもしれない。いつのまにかそれらは瓦礫の山のように蓄積していた。今読み返すと、なんだかよくわからない。即物的で青臭ささえ漂う。詩なんてこんなものだと勘違いしていたような気もするが、それでも詩は生まれた。兎にも角にも書かずにはいられなかったことは確かなのだ。まずはやってみることだ、といわんばかりの挿絵や字体、それには理屈なしで勝手にできあがったのだ。アンチエリアスオフのぎざぎざ感が、コトバとはうらはらに、いまではある種の瑞々しい感情をのぞかせるのがおもしろいといえばおもしろかった。現存する最初の詩集だ。
水の気絶 Poetry Improvisation 93 より
自由のひととき
巨大な珊瑚の稲妻が
ふとした散歩に出くわした
はち合わせの影
傷を手に擦り込んでいるもうひとつの手
ここは偶然にひどくなれた輩たちの島
ひとりのときを狙って誘惑する
蛇はなんども盗まれてしまう
毒が回る前のあなたの呪文が
気を失って 握り締めたままの手
まぶたの開閉のさざなみ 星の頂から降りてくる鳥たち
雷鳴 それを耳にして森は大きくなった
殺し それを目の前にしても 海は窓を開かなかった
光が篭を作って 自分の鳥を待つ
汽笛が変遷する 帽子のような頭を一周する
編まれた雨のテーブルで
指は光っている 星は焚かれている
両翼の虹 いたって自在に空を渡る
自由のひとときはすべすべの肌に澄んでいる
永い気絶
薔薇の純度から吹く風
それは眠りの美しい木
それは声の美しい鳥
星からの呪文が雨をさらに透き通らせる
道は夜の一部分を煙にする
道は手足を悩ませる
どこから香るのか
香り高い耳
香り仄かな目
人々が噂する花束のように
空の均衡が膜のようにはためいて
それは海よりも深い眼差しで
夢よりも遠く
夢よりも近くにあった
僕は星を抱きしめる
愛くるしい狂気を貪り
そして沈黙するために
略奪
星から夜を略奪して
炎はさらに勢いを増している
くちびるのなかには小さな稲妻の狩り
雨のなかをみなぎって 走って行く蛇の僧侶
それはおまえの手を噛んだ
手は青白く透き通った
血の跡もなく
もはや壊れ行く眼球は溺れていた
痩せた影法師の小さな洞穴
額のたくさんの夜禽
それは星をすり潰して
なかの恋人たちを風にばら撒いた
土煙の小屋で
星は蜜のようにじっとり濡れて
月のつむじは気を失っていた
『高貴な唇』より
母と悪魔と新しい日々
さすらいの日々に紛れ
蠢くけだるい羊水に融け出した君は
ママンとデーモンの双方にくちづけをし
にじりよる太陽さえも
漆黒の覆いでねじ伏せてしまう
ひとりでに進みゆく小舟の揺れは
存在の輝きに、また躍動を夢見て飛沫をあげた
生まれ出る出発の勇みが
骨を包みやがて引き締まった夜の筋肉で自ら破状するとき
それはママンをもデーモンをも末梢するだろう
裂けてゆく頭部の蠢きに訪れた
あらゆる優しさと
あらゆる浄化の眼差しで
えぐられた恥部を洗い清めるがよい
世界は開かれた、おお君よ
激しさの弾頭がかすめゆく中
それは泣く
それは気高く泣くだろう
その気高さを君が纏うだろう
死者の震えに似た君が
それを抱き締める
柔らかい肉襞のような君が
それを抱き締める
ママンもデーモンも君を失った哀しみに震えるだろう
あらゆる君らしさの前にすべては消え失せる
おお、世界よ!
無限の迷い児
不実さのうなり
嘆きの大地の足元は
目まいのざわめきに薄笑いを浮かべる
軽やかさの曲がり具合にも
おお、逃げ出すように数ミリの移動
不可視の移動によって
それは女神の苦悩を呼び覚ます
酩酊に音楽は必要だとばかりに
およびのかからぬ老木
愚カラスの伏す窪地
スロオモオション
スロオモオション
ある点からある点へ
生きた砂と砂
君は感じないではいられない
乾きが君を悩ますであろうということを
垣根の外には無限がある
垣根の外を眺めること
ゆっくりと身をつくろって
チャンスを窺い
それは喉を鳴らした
待っている
待っているのは………
もう一度、見よ
美しい広がり
果てしない思いの日々
合図 号令の類に耳を傾け
幽霊のように浮遊し
言葉なき世界でもつれ合う
それは雨を伴って
ただ待っている
お前は無限の中の迷い児を知るだろう
ここにはたくさんの視線がある
たったひとりでも
そしてそっと毛布でもかぶせられるだろう
見ることの恐怖
見えないことの美しさ
それを神がひもとくのだ
それを延々と神々が調べあげるのだ
聖なる書物のように
投げ出された軌跡を
君は読み上げる
高らかに
生きよ、無限の迷い児よ
ラララ
風に紛れるための色を捏造し
そうだ、指を立てよう
君の、もっとも勇敢な君より
言葉を盗むこととする
ゆえに
在る、ここに
さもなくば
死滅の谷間で蠢く柔肌喰いの餓鬼とでもなろう
あるいはボロボロの水銀灯など
君の頑な肉体を開放するための手段を選ばず
何人の前であれ、君は君であり続けようとする
否定できない山々が聳え
が、神などとは申すまい
この道は切れ切れになって
息も同じく途切れがち
一度想いが増せば
けだるさの梯子を駆け降りて行く猿を始末しはじめるだろう
まずは手足を、という風に
口はまだ達者だというのであれば
そのままにしておくだろうし、
ただ気ままに階段をひとつずつ外しにかかる目まいから目まいの物語
所作、あるいは震えを時刻に換算する知恵を授かりながら
それを封印するデーモンになら
君は喜んでついて行くだろう
君はあらゆる俗称の戴冠をせせら笑うと同時に
君の中の醗酵に気を奪われる
そうして人生を作り替えて行く
そうして迎える朝
例えばうわばみとして
君は水を欲し、あるいはすり抜け
大海の最中で波に飲み込まれるように
自らの透明を削り込んで行く
あるいは闇の化身の霊長となるための
それはもっとも美しい過程なのかもしれないという風に
であるが
信じるだろうか
神無くも信仰を持つ君が
まさに今この世に鼓動と眼差しを持つ君が
目を覚ますことなどありえはしないなどと
その格調高き調べのような眼差しで眠り続けるだけなのだという事を
孤独詩
詩と永遠
つぶやきに人が群れるなら、詩にだって群れていい。
だが詩には群れない。
だれひとり群れたがらない。
詩が群れることを許さない。
詩は軋み、詩は揺れる。
そんな孤独な言葉を詩と呼んでみる。
そんな美しい瞬間を詩と呼んでいる。
詩は人と同じように裸で生まれる
無防備に一人ただ裸で立つ。
けれども、衣服を纏い、装飾を施し、詩のような香りを漂わせるものがある。
この世の眩しさで
それは言葉を詰まらせる
それは言葉をつまらなくする
この世の貧しさで
それは言葉を歪ませる
それは言葉をバカバカしくする
やがて無防備にさらされる屋根のうえを歩きだし
そして叩きつける雨つぶにまで懇願する
どうぞこのまま止まないでほしい
叶うならもっと強く叩くがいい
でなければ私は目覚められないのだと
でなければ私は無秩序に歩き回ってしまうのだと
手のうちにある狂気が滲み出して
無垢なるものを傷つけてしまうかもしれないのだと。
この世の暴君たちは、雷鳴の裁きを知らない
この世の無粋ものたちは、夜の叫びを知らないまま死んでゆく
そうやって夜を繰り返す
そうやって日々を繰り返す。
それが慈悲なのか、摂理なのか。
鳥の羽のように折りたたまれた聖なる静寂を呼び戻す
やがて詩の流した血は雨に溶けるだろう
雨に溶けだした詩の血はやがて川になるだろう。
この不毛な地で
けれども誰にも気づかれることなく
誰に出会うことなく
今日が終わる。
明日がやって来る。
ここで行き止まりだ。
磨きすぎた鏡に、そっと手を触れる。
まるでそこからやってきたかのように
深い眠りに似た品格。
まるでそこから先が始まりのように
長く純粋な階段がどこまでも続く。
詩は永遠をこだまする。
こだまする永遠を詩と名付けてみようか。
存在と無
地べたにゴロンと裏返ったセミを拾い上げ、木に戻す。
しかし、セミはもはやセミではなかった。
飛べず、鳴けず、ただ無力だった。
ちょっとだけ、かつての名残をみせ、
ジーと鳴き、手足をバタバタさせたのを見た
しかし、どうやら、そこまでだ。
諦観だ。
とはいえ、何も発しない。
何も語らない。
語れないのか、語る必要がないのか
そんなことは知らぬ存ぜぬ。
この世に有ったことの証は、今この瞬間の目撃にしかない。
シンプルだ。
裏も表もない
過去も未来もない。
今だけが合言葉。
知らない未来におののくこともない。
まだ見ぬ未来に目を輝かせることもない
死だけが優しく時を待つ。
今、この一瞬だけが事実なのだ。
それ以外は綺麗さっぱりと消滅の途をたどる
どうやら、感傷的なのはこちらだった。
どうやら、それはセミではなかったのかもしれない。
この世にごまんとある錯覚は
何にだって化けるのだ。
何にだって溶けるのだ。
そんなことが日常茶飯事だと理解している。
君とわたし
怖がらなくていい
苦しまなくていい
君にはわたしがついている
わたしには君がいる
暗くはないさ
声が出なくてもいいさ
君はわたしを知っている
わたしは君を知っている
それ以上のものは何もないさ
それ以上のことは何もないさ
君を欺こうとするものは全てまやかしだ
まやかしが君を誘惑し続けても
君は君でいいのだ
光が足りなくてもいいさ
息が苦しくてもいいさ
君がいつまでも君なのだから
わたしはそれ以上のわたしではない
じっとして待つもいい
それが嫌なら行くがいい。
君にはわたしがついている
わたしには君がいる
それがすべて
全てはそうなのだ
君とわたしはいつもそうなのだ。

