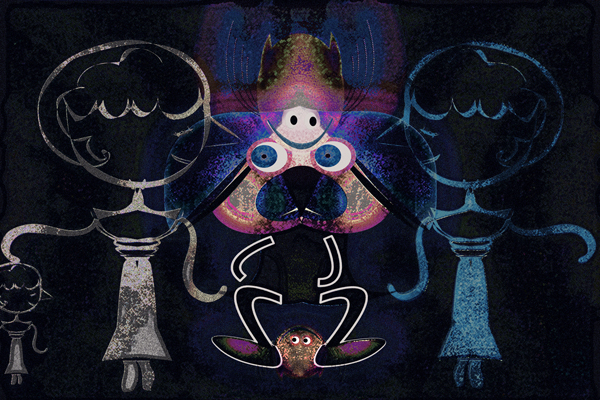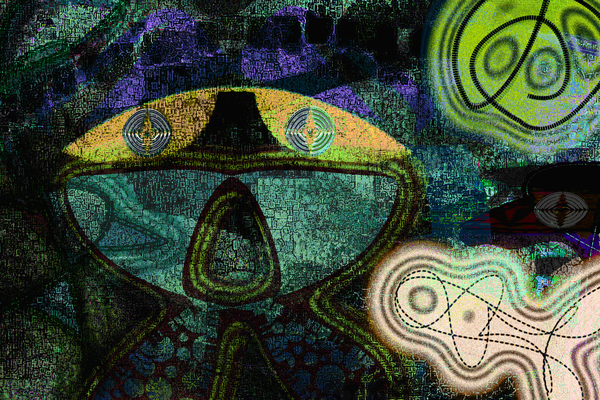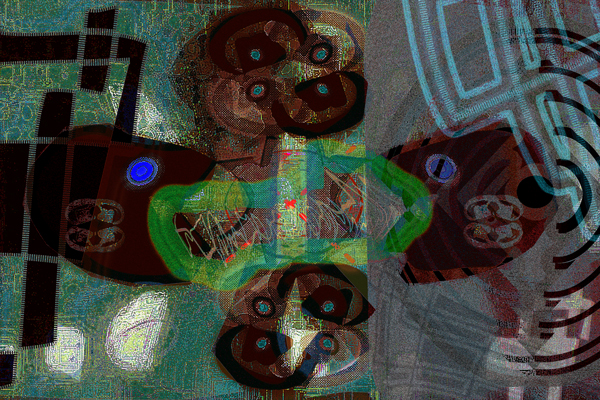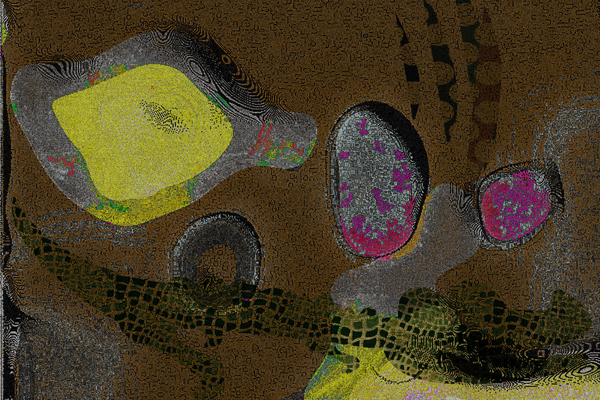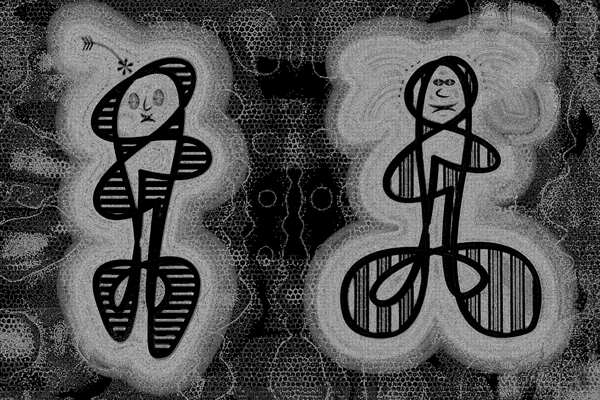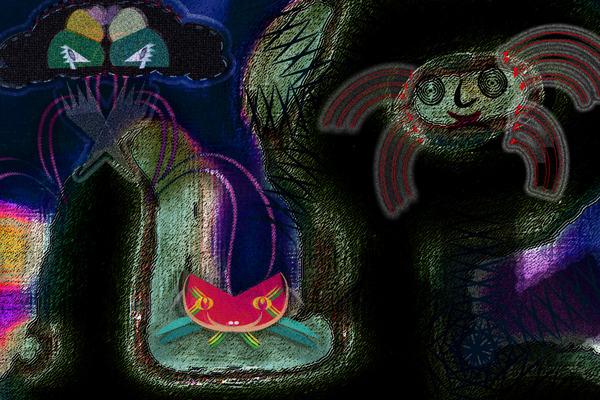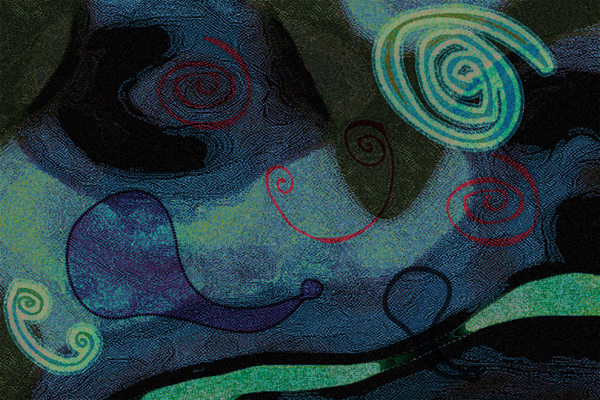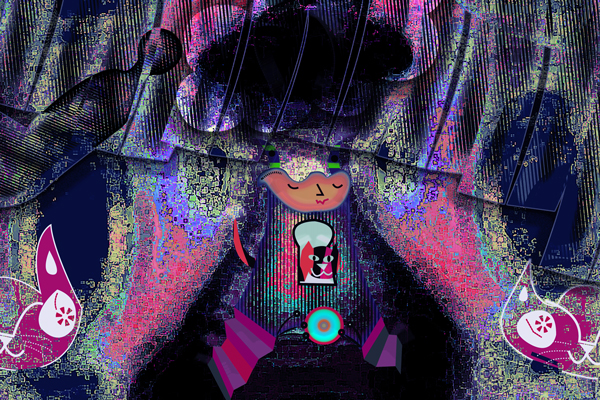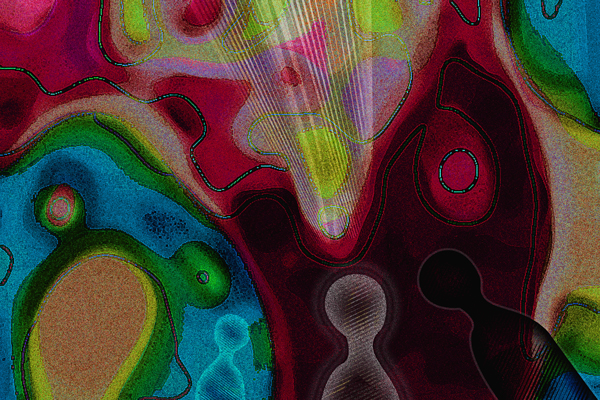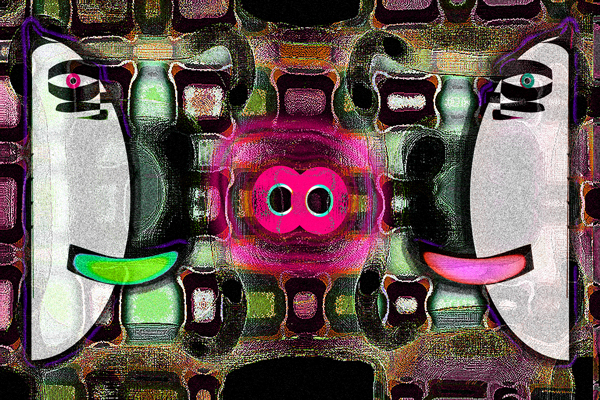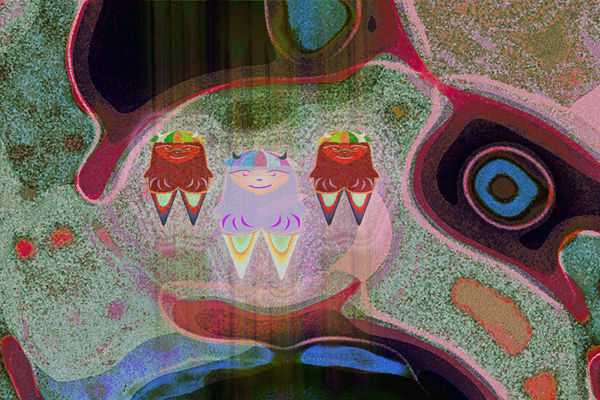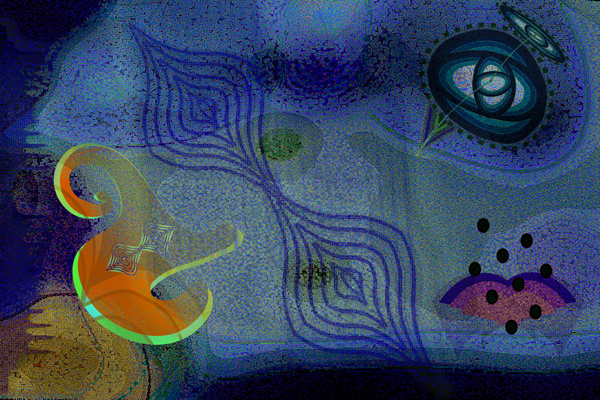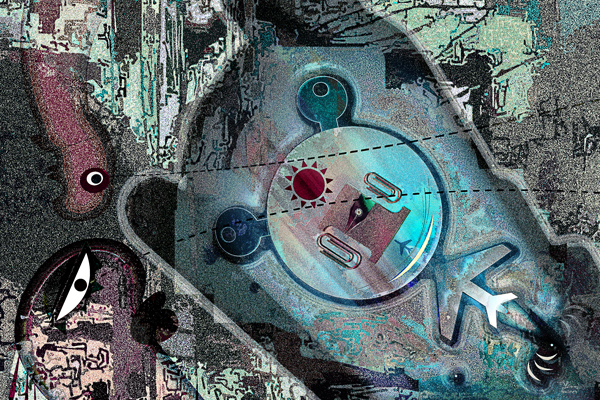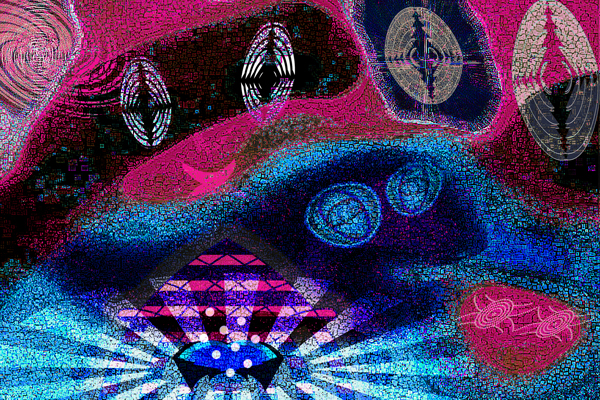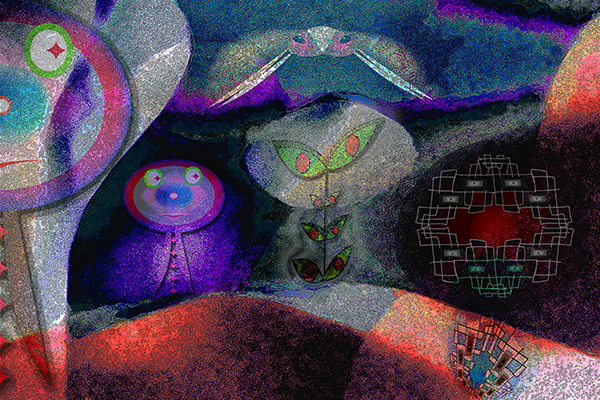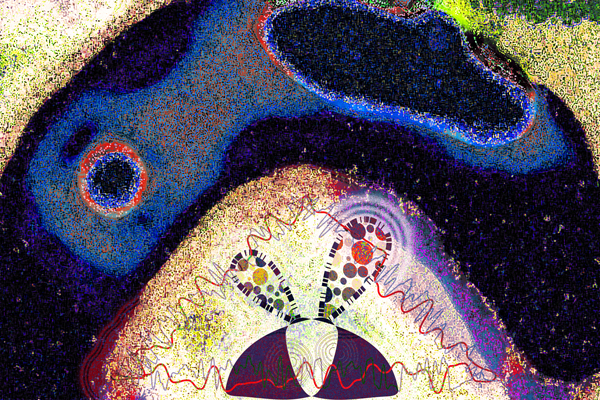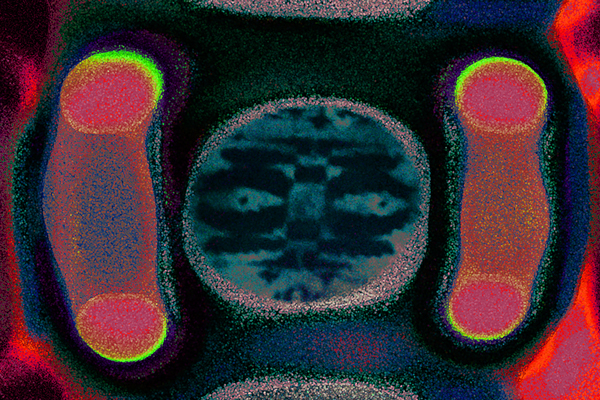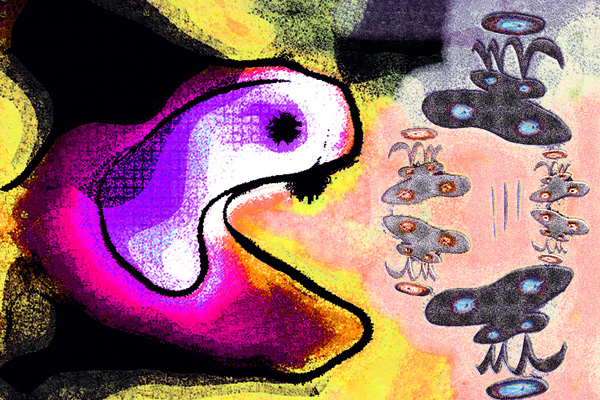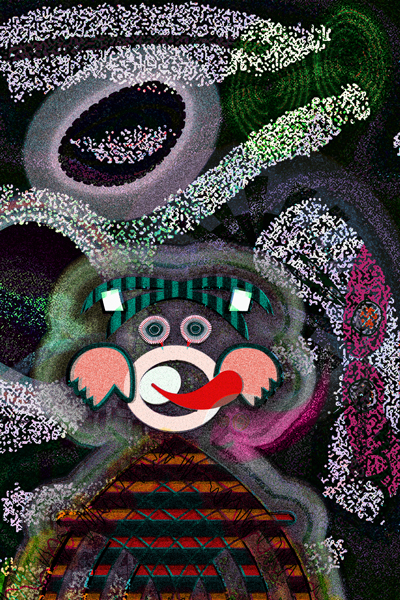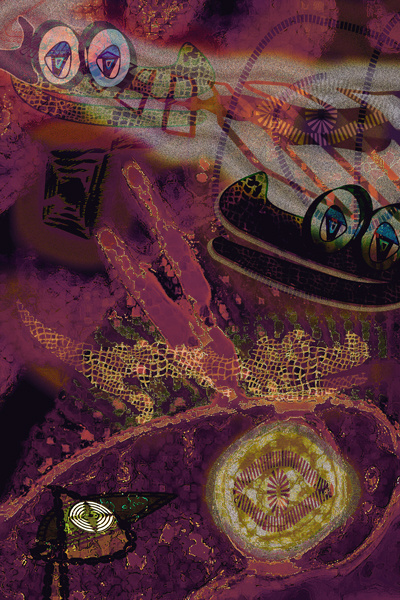予期せぬことを予期しよう
トミ-・ウンゲラ-
イラチョプギャラリー
Illustrator×Photoshop=Illustchop

ある時、偶然手にしたといっていいのがAdobe社の定番画像ソフトIllustratorであった。アルバイト先のPCのデスクトップ上に、たまたまインストールされておった。まだまだ一般庶民には認知されていない時代の話。それに触れるなり、直感した。あっ、これぞ、お絵書きソフトなのだと喜んだ。(むろん、そういう用途でインストールされていたわけではなかったのはいうまでもない)。
このアプリケ-ションとの出会いは、ちょっとしたトキメキだったといっていい。いまでこそ、マック(IPAD)で絵やデザインするのは当たり前になったけれど、手を汚さずに絵を描き、あとはプリンタ一台あればアウトプットでき、しかも中身を物理的に無形のデータとして常備携帯できうるというのは、なかなか新鮮な出来事だった。なにより、マッキントッシュそのものがひとつのあこがれ品、高嶺の花であった時代だったから、当時高額だったお絵書きソフトを操れるなどというのは、夢のまた夢というべきか。そこに活路をみいだしたる我が好奇心は、なんと、大胆にも自腹をきって購入する(当時のverは3.2だった)をという賭けにでた。確か当時十万弱はしたはずである。ほぼ直感的に、これは先々のメシのタネになるわい、と思ったのか思わなかったのか。要するに、今後末永くおつき合いいたすであろうことをどこかで見抜いていたのである。そこからまがいなりもオペレーターからデザイナーになり、まんまとそれは効をそうし、今、こいつなしではちとつらい、いうなれば必需品。完璧なパートナーたる共犯関係を結んでいるのである。
とはいえ、いきなりプロ級に扱えたかというと、当然ノー。誰に教えられるでもなく、ただ闇雲に子どもがやる切り絵、貼り絵のような感覚のみで、 まずはフリーハンドによってランダムに図形やらペイントなどで描きなぐってできた、稚拙かつプリミティブな図形たちが生まれ、そこからああでもないこうでもないと、さらにせっせと編み続けることで生まれていった一連のキャラクターたち。
さらに互換性という便利な利便性により、兄弟分のPhotoshopという同社の別ソフト上で、新たな手作業を加えて、誕生したのがこのイラストたちの馴れ初めというわけである。ビットマップだのベジエだの、はたまた解像度だのRGBだの、何一つ理解してはいなかったのだが、そんなことは全く知ったこっちゃなかった。気になどしなかった。結果として、事後、必要に応じものごとを理解するという仕組みをたどったに過ぎない。
最近ではヴァージョンが随分進んで、WEBにも印刷にもにもびしっと対応している。いったい、君たちどこまでゆくのだ? と、ずいぶんと多機能もりだくさんで、使いこなすのも大変にはなっているのだけれど、今思えば当時手にしたVer3.2などは、初歩の初歩ということもあって、今思えば、ずいぶんシンプルな構造だったようにも思う。
こうして、どんどんとわきあがる欲望に応えたのが、イラストというべきか、ペインティングというべきか、ジャンル分けはこの際どうでもいいのだが、加工のプロセスと言葉の遊戯として、ひとまず「イラストチョップ」と名づけておいたにすぎない。つまりはadobeが誇る印刷に欠かせない定番ソフトの二大看板を、巧みに組み合わせ操ることができたわけである。
こうなると、創ってなんぼ、見てなんぼの世界。その際意味などどうでもよろしい、響きが良いだけだ。単純な図形であれ、構図であれ、発想であれ、それが様々な環境、加工を経ることで、新たな生命体へと生まれ変わることの自在さを、あえて強調したいのだが、しょせんその工程での発見が加わり、できあがったものはその結果でしかない。フィルター処理にも随分と親しんできたものだ。従来は写真のレタッチに使う機能を、我はひたすら絵を描くという視点で探求してきた。こうして、自分自身、手描きではできない世界を、MAC上で、しかも、決してコンピュータ臭くない、という領域を無意識下におきながら、どちらかでいうと、どこまでも絵としての質感を意識しながら、ひとつの形にはたどり着けたかと思う。
余談だが、あるとき、尊敬するMAC使いの代名詞たる某有名グラフィックデザイナーのワークショップに通ったとき、講義のあとおそるおそる見せたところ、それを見て、あまりにも稚拙だといって歯牙にもかけられはしなかった。あのときの師の顔は忘れがたいものがある。それはほんのちょっとした挫折とはいえ、そこで挫折して放棄することもなく今がある。稚拙とはいえ、それらのイラストに罪はなかった。たえず進化するであろう、誕生物たちが愛おしいことに代わりはなかった。いつしか、毛虫たちが蝶に変わる瞬間を夢見ていたのだ。
作品はたえず仮死を擬態する。それを生かすも殺すも創造主のさじ加減一つである。その成長は、不可視の状態にて孵化するひとつの神秘を教えてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいだ。