やなぎに風というけれど
いっさいの杞憂は
ゆうべんなる
えいえんのまえに
ようのないこと
◆ヤドカリ、曲がりなりにも間借人
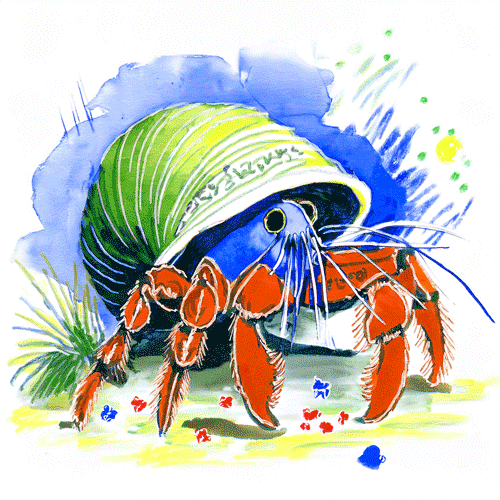
子供の頃、デパートの屋上や、歩道橋の上で、ヤドカリを売ってたのをよく見かけましたっけ。確か天王寺にある阿倍野の歩道橋の上だったと思う。そこで買ってきて家で飼ってましたね。水槽に砂を敷き詰めて、キュウリや煮干しなんかをあげてました。テレビの番組だったか、ニュースで、野生のヤドカリを見たとき、おかしかったのは、洗剤のキャップか何かに間借するおバカな(変わり者?)やつがいたんですよ。どこか無理がありますよね? といっても、貝殻だってどこかで見つけてくるのだし、適度なものがなかったのかもしれない。それが ただ殻じゃないとやっぱりどこか貧弱で違和感はあります。きっと尻をかくすことができればいいのかもしれない。でも、そこに個性があルトいうのが面白い。少なくとも、自分で見つけてくるといという自由のなかにロマンがあるというか。。。
近頃、この日本でも、ホームレスがふえているようだけれど、もともと生物に家なんかないはずなんですよ。ねぐらであったり、洞穴だったりするだけで。人間、住む場所は必要だし、マイホームも欲しいけれど、それよりも大切なことは、いつまでも自由でいたいという気持ちじゃないでしょうか? 家は間借しても、心だけは借りるわけにはいきませんからね。ローン地獄で首がまわらないマイホーム設計なんてまっぴらだし、それならダンボールで家を作ります。夢見る箱男、悪くないんじゃないでしょうか、その感じ。ヤドカリへの共感がつのるのです。
◆雪、あたりジーン世界

むかしから、雪を見るとなぜか嬉しくなるんです。一月生まれ、生まれた日に雪がふっていたそうで、身体が覚えているんでしょうか? 雪印乳業のマークは、典型的な雪の結晶の形に由来するイメージとして、どこか記憶に焼き付いていますね。調べてみると、雪の結晶というか、氷の結晶とひとくちでいっても。その形にもいろいろヴァリエーションがあるんですよね。基本的には六角形。あとは枝が複雑かどうか。
雪というものが、ああいうグラフィカルな図形の集合体なんだ、と考えるとちょっと面白いですね。これは、水の分子が氷になるとき、六角柱の形でくっつく特性があるらしいんです。北野たけし監督の「HANA-BI」で半身附随の刑事(大杉漣)が絵「光と雪という題だったか?」を描くシーンがあって、よくみると雪がすべて雪というという文字で構成されているんですね。面白い表現だと思いました。
白くて、しかもひとつの集合体で、しかも永遠から遠いあの雪というイメージは、確かにロマンティックだけれども、はかないうえ、別の所で狂気を秘めた怖さを隠しもっております。そう、それが雪山の恐怖、そういうのは山男ではないのでピンときませんけれど。。。
そういえば、雪男(ユキオではありません)雪女という幻想も、ある意味ロマンではないでしょうか? 雪をモティーフにした物語りは実に多いですけど、哀しいものが好きです。都会に住む限り、ほとんど雪という雪はめったにお目にかかれませんが、たまぁに遭遇する時は、交通=ひとの足を混乱させる元凶になっているだけで、ほとんど、嫌われものでしかないといった感じで、雪好きには肩身が狭いものです。雪やこんこん、あられやこんこん、のこんこんとは、来ん来んの意だとばかりに思いつづけてきたものにとって、目が覚めたとき、窓の外が一面銀世界、という光景は、いつみても新鮮なお伽の国なのです。雪のシーンで心に残っている映画はというと、コクトーの「恐るべき子供達」では雪合戦のシーン、あとはフェリーニの「アマルコルド」、あとは大島渚の「少年」なんかが印象的ですね。
◆ユートピックス
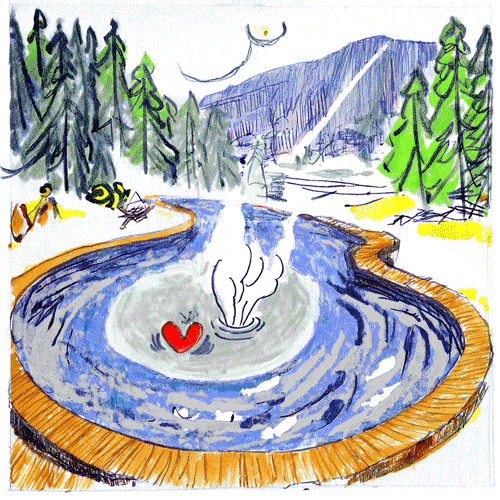
家で湯を張り、湯船掃除が面倒この上ないのではあるが、湯船に湯をいっぱいに張ってザブンとはいる。そして肩までつかって、いい湯だな、ってな調子で疲れをとる。ま、近ごろじゃ、猿でも温泉に浸かる時代ですからね。そんなわけで、怠け者よ、しからば温泉へでも行きたまえ・・・・
温泉と行っても、都会に住んでいれば、それなりのお風呂スポットがあふれております。たとえば荻窪にある「なごみ湯」なぞ、そんな輩には満足のちょっとした居心地の良い湯を提供してくれる場でしたね。サウナはとくに好きじゃありませんが、やはり湯は最高ですな。小生、とりわけ気にいったのは、アルス玉などというものを敷き詰めたアルス風呂、足触りが妙に心地よく、はまってしまいました。そういえば、小さい頃母の田舎の富山の銭湯には、薬湯などがありましたっけ。風呂上がりの珈琲牛乳は格別の味。風呂というものが、単に清潔を保ち、疲れをとるだけの場から、楽しむという空間になっていくのは、このうえなくうれしいっすね。そんなとき、日本人でよかった、ではなく、自分でよかった、となるのであります。
◆ユーワクワクのけもの道
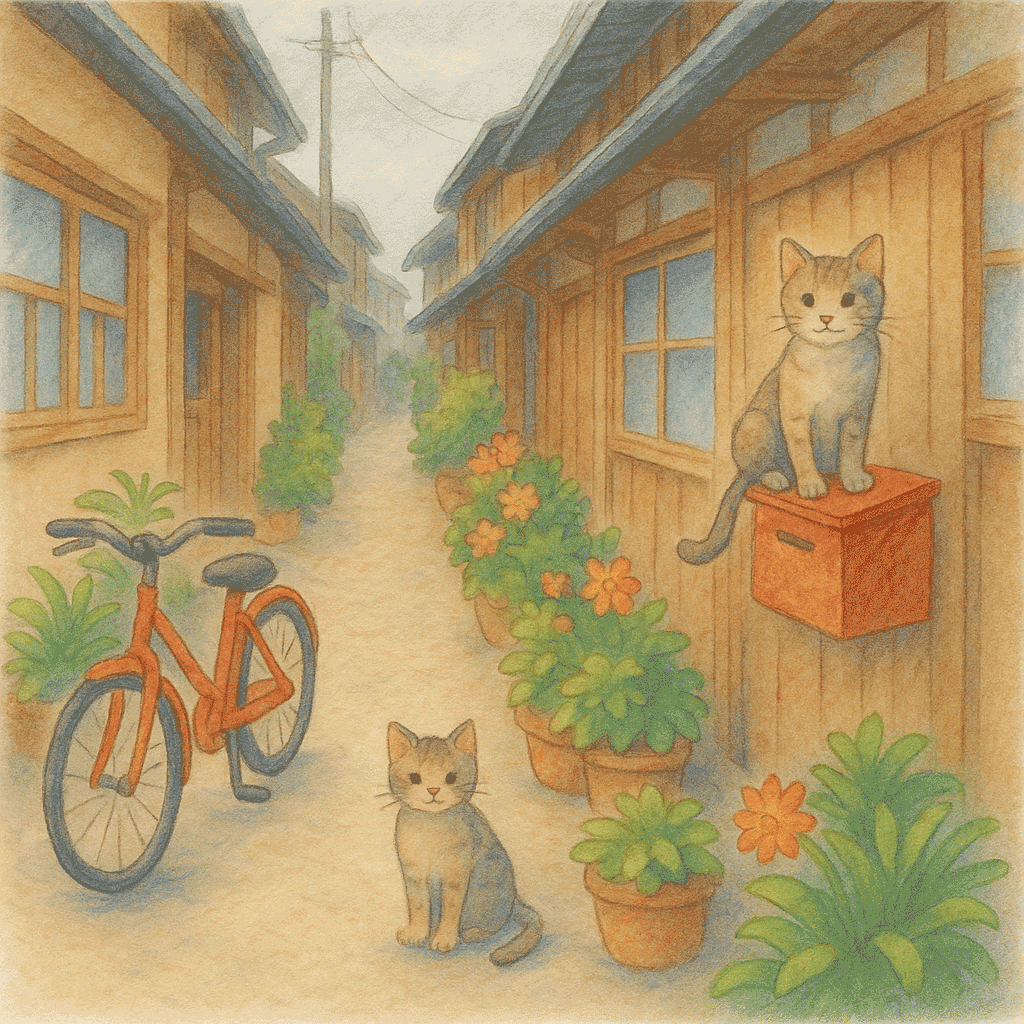
路地好きというやつは、おのずと動物好きでして。カメラをもって出かけるときもこうした路地は必ずチェックいたします。とりわけ、路地と猫とは相性がいいみたい。で、彼らには秘密の場所や、通り道があったりして。これって、もともと人間でも子供の時からどこかに身についている感覚じゃないでしょうか?
もっとも、いま、大都会の子供たちは遊び場の確保さえままならない感じだし、昔ながらの路地というのも少なくなっていますが。ふとしたところ、おもわぬところに残っていますね。
犬や猫というやつは、元来自由ですね。身体を縮めて柵や網を見事にかいくぐっていきます。時折、人為なのか、廃虚風の建物には、獣たちの仕業なのか、気になる穴があって、どうやらそこが動物版不思議の国への入り口のような感じに無防備に一目につくことがあり、タイミングよく、野良くんたちが、ひょこっと顔をのぞかせたりすると、こちらも嬉しくなります。まさに、誘惑のアナでござります。
◆妖精、妖怪そんなもんかい?
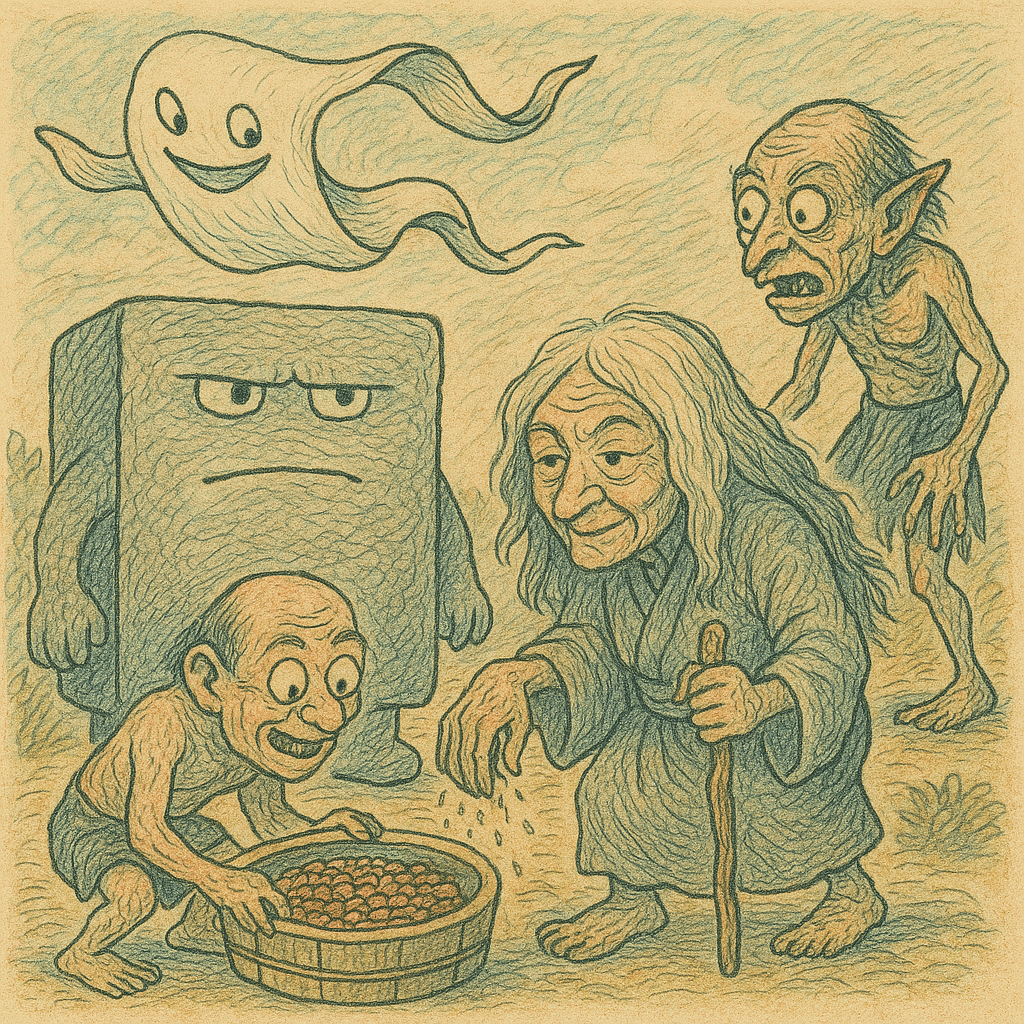
なにやら、昨今は妖怪ブームといいますが、自分が妖怪好きになったのは、最近、しかも偶然で。わたし、妖精を見たことがあるんです、とそんなことをいういかにも妖精が好みそうな不思議な女の子がいて、その女の子は水木センセイのファンだといっておりました。ファンレターも出したのに返事がもらえなかったと申すほどの熱のある子でした。で、そこから何とはなしに、水木漫画に注目するようになり、それで改めて妖怪に親しむようになったのですよ。なるほど、確かにゲゲゲの鬼太郎は昔から知っていましたし、好きでした。名前は当然有名でしたが、個々の妖怪となると……。
妖怪舎から限定の妖怪フィギュアが発売されていて、これがなんだか、不思議に気を惹くんです。有名なところでは、一反木綿とか小豆あらいとかが好きですね、人に危害を加えない妖怪たち。中には、ちょっとと思うようなのもいないことはないのですが、よくよく考えれば、想像の世界ですからね。ネーミングと性癖で好きなのはなんといっても、ぬらりひょんですかね。人の家に勝手に上がり込んで、お茶を飲んだり、煙管を吹かしたりしてそれで帰ってゆくだけの妖怪で、でも、家のものにはなぜか気づかれないらしい。ぬらりひょんとはよくいったものです。べとべとさんというのもいますね、こちらはもっとわけがわかりませんが、ただ独り歩きの夜道、ぬっとあらわれ、脇道に寄って、「べとべとさん、お先におこし」というとおとなしくいくそうです。???、ですが、まあ妖怪ですので、この世の理屈だけでは割り切れるものではないのは当然か。
そういえば、河童やタヌキも妖怪扱いですね。昔フジTVでやっていた「ごっつええかんじ」のまっちゃんのキャラクタの中で、河童の親子というのがあって、最初は凄く威勢がいいのが、そのうち人間にぼこぼこにやられて……というあのキャラがとても好きでした。妖怪といっても、トモダチになれそうなものなら、別段かまわないんですよ。
◆陽気に惹かれて、轢かれんぼ
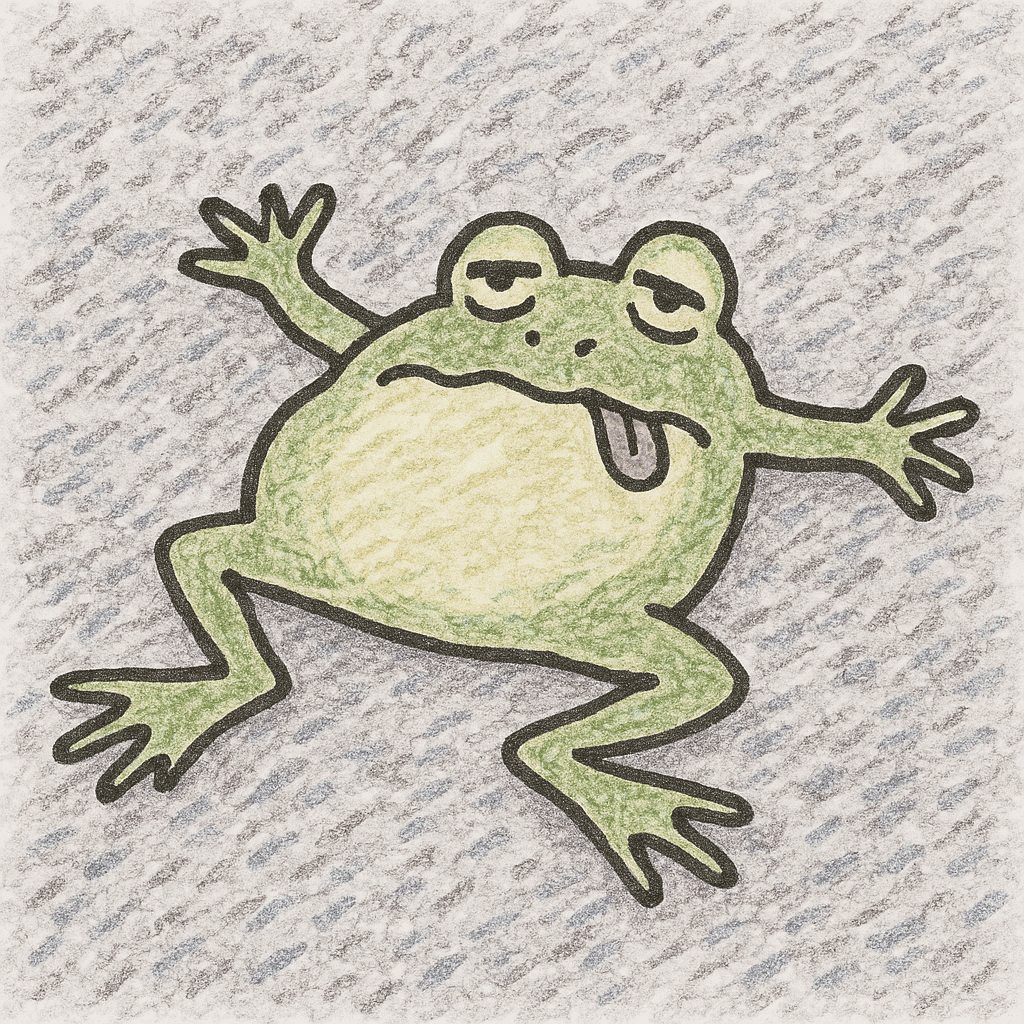
段々と春が近づいて、みんなうれしそう。そう、土の中では一足先に春のピクニックの身支度? 民家からひょこり現れるツチガエルくん。仲睦まじくカップルで飛び出したのはいいけれど、アスファルトの道路なんかにのこのこ出てきたときにゃ、車や自転車がビュンビュン行き交ってるから、くれぐれも気をつけなきゃいかん。グッシャリ御陀仏、ハイサヨナラなんてことになりかねないよ。近くに草叢や河川でもありゃいいんだけど、何せ住宅街。困ったものだ。ぼくが通らなきゃ、君たちは……
それとは別に、アマゾンに生息する通称ピパピパ、その名をヒラタコモリガエルという、バンザイをしたような格好で、川底にひそむ扁平なカエルがいる。母ガエルはスポンジのように柔らかくなった自分の背に卵を埋め込んで、子守りをするという珍しいカエルとしても知られており、その名前ゆえに、単にピパと呼ばれ、ペットとしても人気があるのだそうだ。
◆預言者のアルチザン

預言者という名のキーボード知ってる? アナログシンセのなかで、いわゆる「名機」とうたわれるだけあって、80年代のテクノ~ポップミュージックサウンドには欠かせない「音」職人こそが、「Prophet5」である。YMOの『テクノデリック」やJapanの『Tin Drum」の音のたいていががこれによって作り込まれているんだよね。結局使うのは人間。デジタル時代になっても、この名器を愛し続けるのは、その元ジャパンのリチャード・バービエリのような地味でかつ繊細な人。
リチャードといえば、このプロフィット5。いつしかそれぐらいきっても切り離せない、道具になっていったようだ。ニッポンのケンイシイやタケムラノブカズといったポストYMOのクリエーターたちはこぞって、その音を絶賛しているしね。ジャパンのメンバーは、この預言者の音が相当お気に入りみたいだけれど、リチャードは、キーボードひとすじの、本当の職人さんみたいに、実にひたむきに「味のある」音を、今もこのシンセで豊かに作ってみせてくれてる。つまみを左右ちょっと動かすだけで、微妙に音色が変化するアナログの代表選手。ノイズを絡めたどくとくの曇りあるストリングス系は十八番で、すぐに、リチャードだってわかるなあ。デジタル機は数値がものをいい、頭で考えるよりは、ひねりを聞かせて音をいじる、盆栽を愛するように、そして、調味料を振るように、この感性で未来は、必ずしもデジタルのみにあらず、と予言されるのであります。そういえば、、当時は数百万もした高額もので、なかなか手がでなかったけど、欲しかったです。
◆郵便配達優雅便
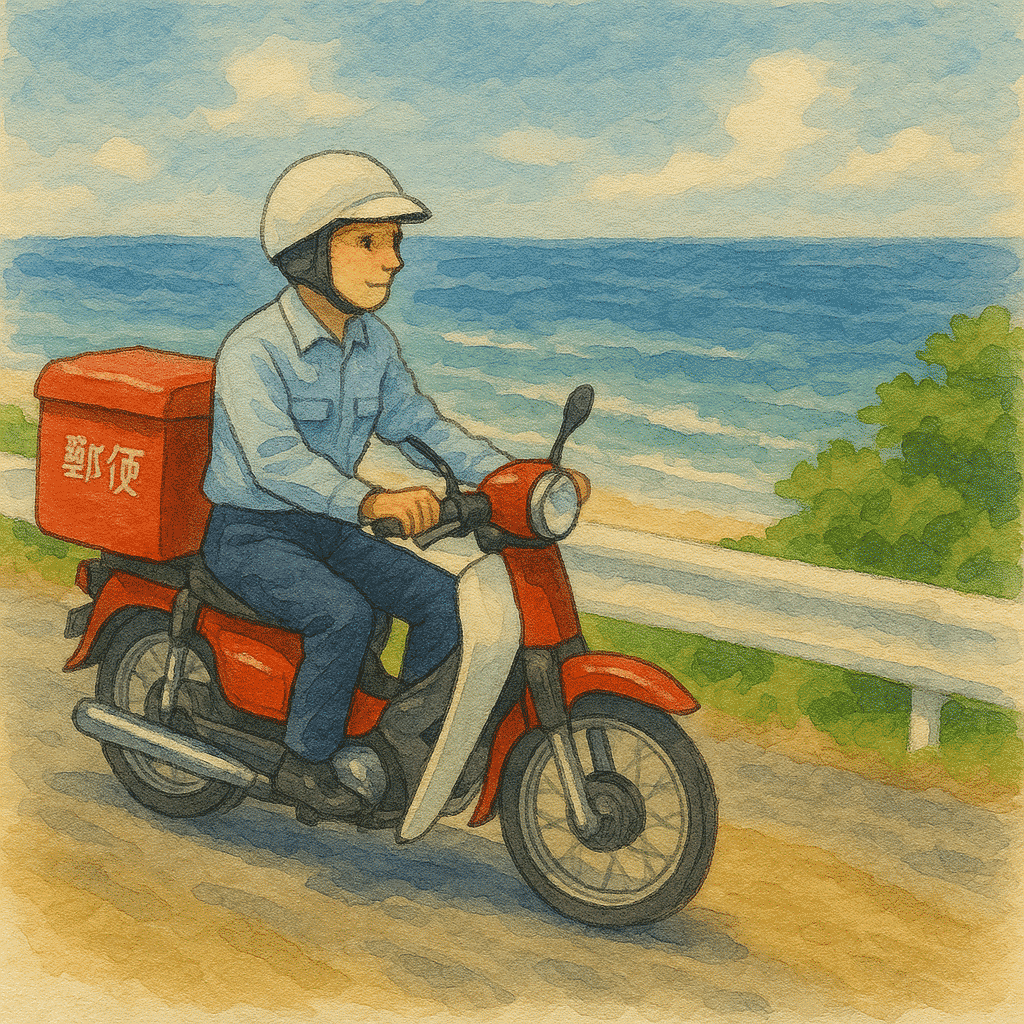
ジャック・タチの『のんき大将脱線の巻』のフランソワが繰り広げるドタバタ劇の可笑しさ、あるいはブコウスキーの自伝小説「ポストオフィス」で描かれる、酒と女とギャンブルに身をやつすチナスキーの哀愁、あるいはジャン=ジャック・べネックスの『DIVA』では、人気オペラ歌手の歌声を黙ってカセットに録音するロマンティックなジュール。あの美術家横尾忠則さんに至っては、デザイナーになる前に憧れた職業が郵便を配ることだったというのだから、郵便配達と言う職業も、少しは“夢溢れる職業”のひとつだったんだなと。そんな僕自身、少しばかりの間、郵便配達のアルバイトをしていたことがあります。
真夏の太陽にジリジリ焼かれ、雨の日はカッパを着込んで、郵便物を濡らさないようにと気を配り、雪が降れば降ったで、バイクが転倒しないように神経をすり減らし、皆が休むお正月は一年で最も忙しい繁忙期・・・その上、やれ郵便物が届かないだの、配達時間が遅いだの、おまけに誤配をしたら叱られ、庭先の植木鉢を倒しただのといいがかりをつけられ、その割に給料は安いとくる。一体誰が好き好んで、郵便配達などに精を出すだろう。 むろん、マイナス面もたくさんあるし、郵便局の体質そのものは、いわば親方日の丸体質で、いかにも時代遅れで、面白くもなんともないのだけれど、爽やかな五月や秋晴れの日に、一人バイクに乗って目的地へ向かい、配達をそそくさと終えて、人知れず、適当に一服するというのも、今思えば貴重な体験だったなと。四六時中他人の目を気にしたり、面倒な人間関係に囲まれて仕事をするよりかは、はるかにお気楽モード。幸い、自分は記憶力には自信があり、ルートを覚えるのも苦じゃなかった。一番面白いことは、他人の情報が郵便物からかい間見えてしまうってこと。もちろん、わざわざ、情報を盗み見したり悪用したりすることはないとはいえ、どうしても見えてしまう部分というのがあって、その人の状況、その人暮らしぶりがわかってしまうこと。全く関係ない人間の私生活に触れることへの好奇心は、他の職業では、あまりないんじゃないかとは思いますね。もっとも、そんなことが面白いと思えない人には通じない話だけれども。
◆吉本行くか?
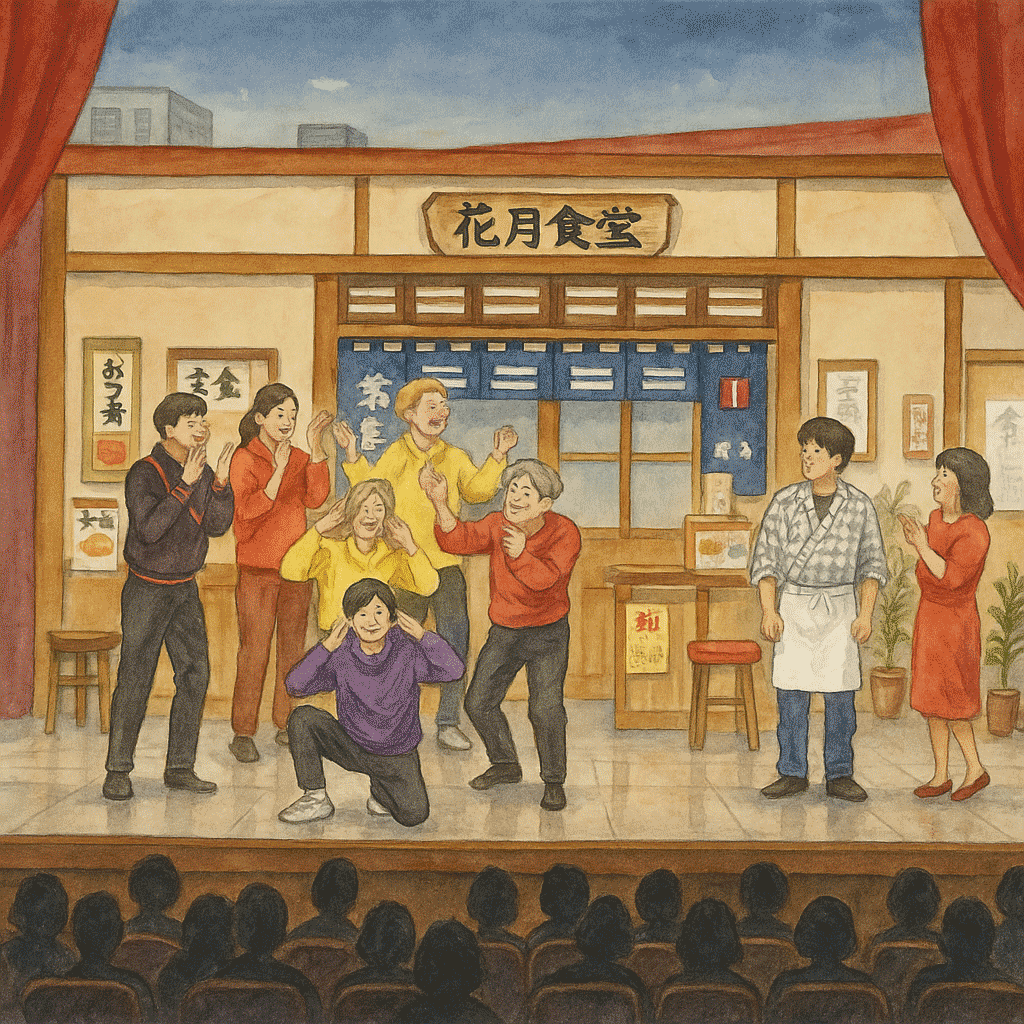
お笑いのメッカ大阪の吉本新喜劇というは、昭和の大阪では、確かに絶大なる文化の一翼を担っていたんだろうな、とは思いますね。学校では面白いこと言ったりクラスの人気者は、ギャグの一つや二つを真似るパクるのは常套句だったし、先生は、そういう度が過ぎる子供に向かって「吉本行くか」などと冗談を飛ばしていた呑気な時代。土曜日には、学校から帰って吉本新喜劇をテレビでみながら昼飯を食う、というのも覚えていますね。
最近では芸人の株も上がり、吉本は一つのブランドになっているほど全国的に認知されたカルチャー。現在吉本新喜劇の座長を勤めているのがあの小藪というピン芸人。昔の芸人さんにはない感性をお持ちのようで、若い層からも支持を受け舞台の外でも大活躍。つくづく時代を感じますが、所詮吉本は吉本。笑ってもらってなんぼの精神が脈々と受け継がれていて一安心。
僕が好きだった吉本の芸人は、おばあちゃん憑依芸をスタイルにした桑原和男とい人で、元座長で、最古参の吉本メンバーで現在でもまだ活躍されているとか。「ごめんください! どなたですか? お入りください、ありがとう」の逆とか「神様〜」と色々会社の対偶などを嘆きつつ、「〜ご清聴ありがとうございました」と〆るギャグなんかが大好きでしたね。
◆焼板の町並み
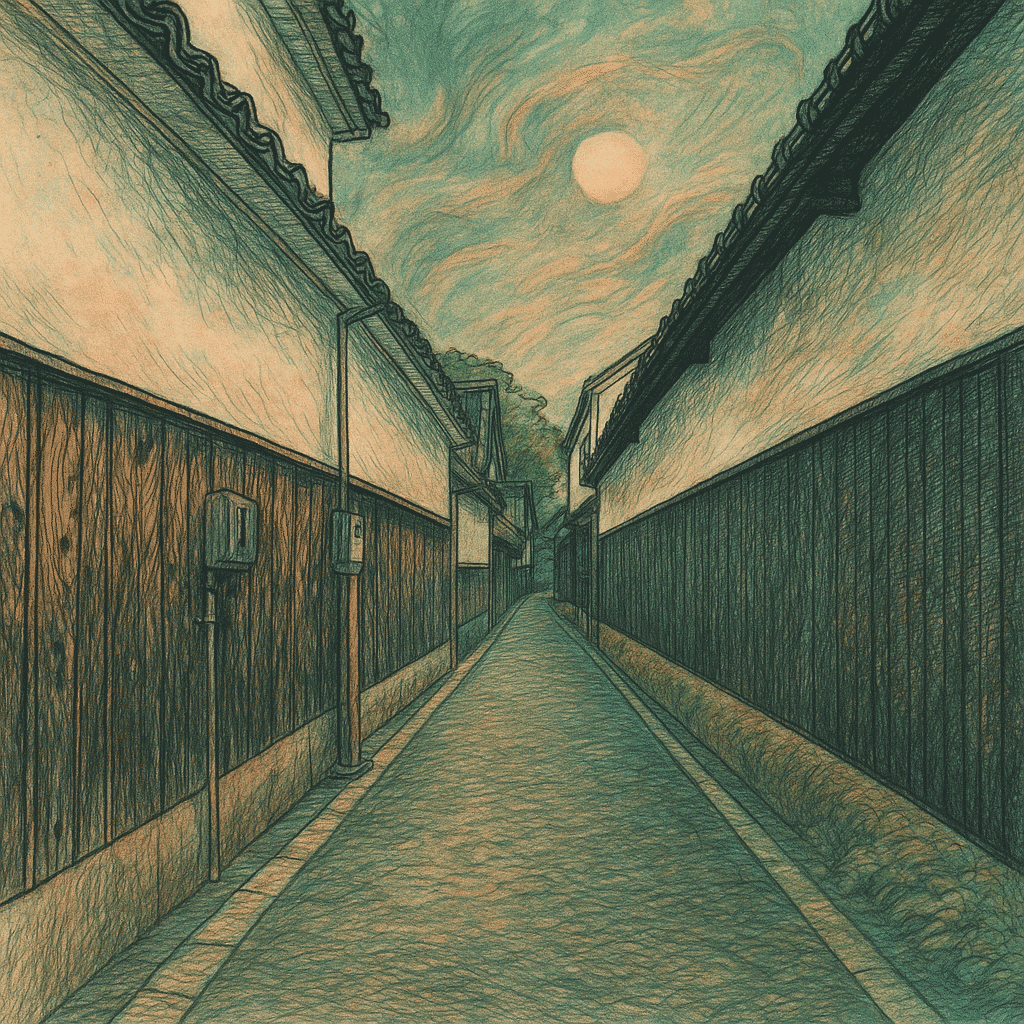
焼き板ってご存知でしょうか? 杉の木を文字通り焼いて炭化させた外装材です。ある時、岡山あたりをローカル線に乗って旅をしていた時、電車の窓から見える黒い日本の家屋が気になって調べてみると、「本焼き板」というものだとわかりました。とりわけ、岡山県は、その風土から特に焼き板の家が多いんだとか。瀬戸内に面した特に海岸線などは、湿気があり、家を長持ちさせるためにこの外壁が使われているのだそうです。炭でコーティングすることで耐水性・耐久性が増すのですね。いわば生活の知恵です。その炭も長い年月を経てところどこ禿げてきたりして、そこは風情ともうしましょうか、私のようなグラフィック好きな人間にはたまらないのです。実際に町に降り立って自分の目で確かめると、なかなかの情緒を感じ、家を建てるなら焼き板、漆喰がいいな、なんて想像したりするのは楽しいですね。
◆夢自動生成アプリ
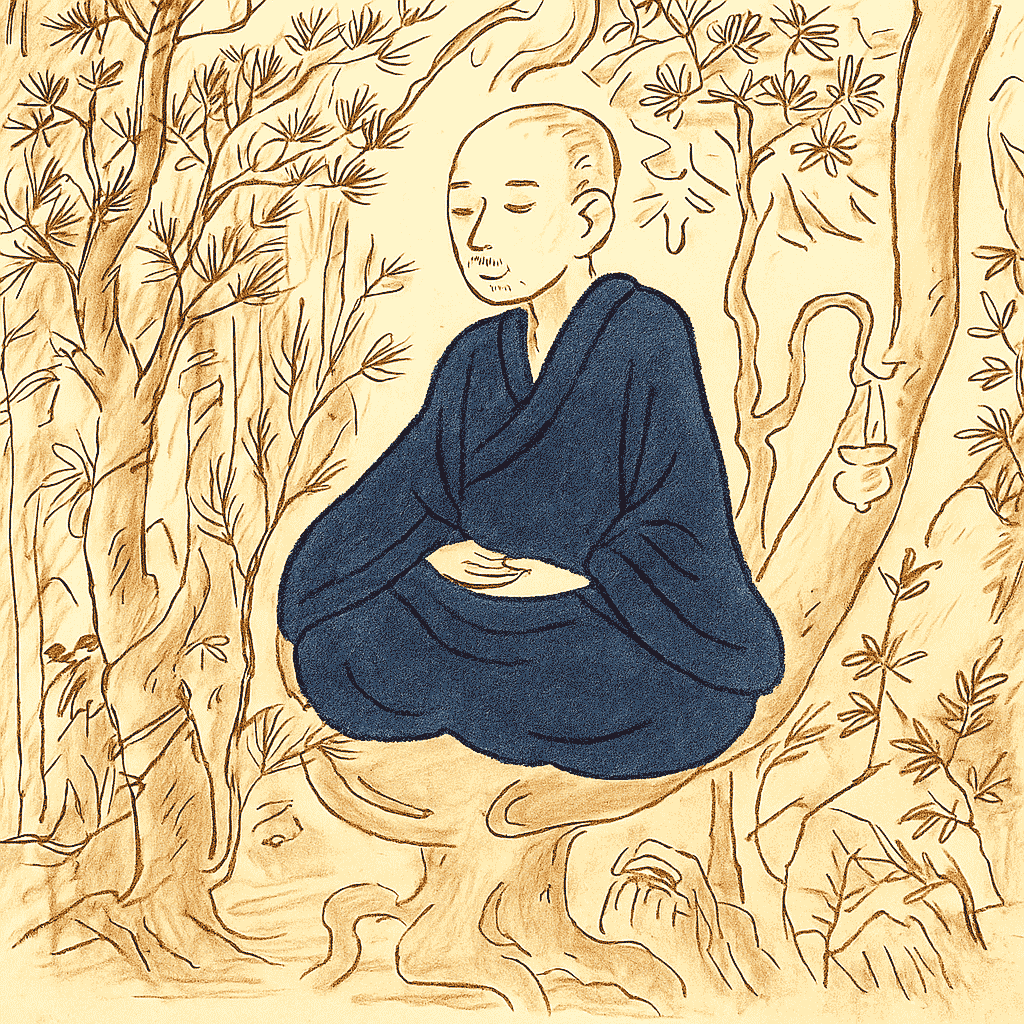
睡眠時にみる夢のことですが、単に生理現象、という言葉が適切かどうかは別として、これほど、その内容的に個人的なものはなく、それを実証できるものはこの世に全く存在しないというのが不思議なぐらいです。それって空想の類いということでしょうか。その毎晩見る、あるいは見たはずの夢について、朝を覚ましてから必死に思い出そうにも、なかなか敷居があると感じる人も多いんでは? これは記憶がいかに心許ないか、ということの証明でもあります。かくいう自分でも、書き留めようと試みたことは何度もありますが、これがやはり長続きしないものですね。かりに、自動夢記憶装置なるものができたら画期的なのになあと。まさに夢見る話です。そもそも、夢というものに実態がない以上、記憶との戦いは永遠のテーマ。そんな夢を記して残した人がおります。鎌倉時代に明恵上人という高僧のことで、『夢記』という夢日記を残していることでその名が知られている人物です。おまけに、自戒の意味で右耳の先を削ぎ落とすという、まるでゴッホのような、狂気の沙汰に出た人物としても、知られていることで、ぼくは昔からこの明恵という人に関心をもってきたのです。その思いに馳せて、紀伊国(現和歌山)の湯浅にある明恵上人紀州八所遺跡や京都栂野の高山寺に足を運んだりもして、時空の旅を試みたものです。明恵は、夢のなかで、お釈迦様と対話したり、亡き母に抱かれる夢、あるいは地蔵と遊ぶというような夢を見たのだといいますが、僕が一番ぶっ飛んだのは「「満天の星、われの上に降りそそぎぬ。身に触れし星は光となりて消え、心の奥に光あふるるを覚ゆ」つまり、空より星降る夢によって宇宙と一体化する感覚をもっていた、というところなのです。これはまさに、スピリチュアル体験というか、現代感覚というか、明恵上人がひとかどならぬ人物だったことを、まさに言い得ている話に思えるのであります。

