ベトナム幻想、未だ醒めやらず
ベトナム料理は好きで何度か口にしたことはあるけれど
ベトナムという国へは一度も行ったことはないし、
知り合いがいるわけでもないのに
なぜだか、なんども足を運んでいるような気がしている。
あのベトナム語の響きが音感的に耳に残っているのだ。
何かを優しく咀嚼するような響き、
同じアジア圏の言語の中でもとりわけ親近感がある。
『青いパパイヤの香り』という映画がある。
おそらく、初めて観たときの印象が
そんなベトナム幻想に荷担していることは間違いない。
1994年に公開の映画だから、
おそらくそのあたりに観たのは間違い無いのだが
とはいえ、いつ誰とどこで観たかの記憶がない。
手元にあるメモからは
映画自体、随分と心奪われた映画であることだけが残されている。
実際に、ある程度残像を思い浮かべることができるが
あまりに断片的だ。
言葉にするとなると少し戸惑いがもたげ始めるのは
あまりも美しい映像、音響や美術セットの素晴らしさ、
俳優たちの演技への共感などによる余韻だけで
十分に満たされる映画だと感じたからだと思う。
この映画に対する共感は、おそらく
この監督自身がもつ、日本及び日本映画に対する尊敬の念が
行き渡っているから、ということもあるのだろう。
田舎から出てきた奉公人のムイが
不安げに奉公先を探すファーストシーンなどは
溝口の『赤線地帯』のラストシーンを彷彿とさせるし
悪戯盛りの男の子が、気を引こうとして
ムイにちょっかいを出した後必ず放屁するあたりのギャグは
あの小津安二郎の『お早う』を思い出させてくれる。
そして何より、ラストシーンには
夏目漱石の『草枕』が引用されて幕が下りるのだ。
アジア圏とはいえ、決して近くはないベトナムという国に
映画を通じて郷愁を覚えるというのも変な話だが、
この映画を観終わった後、日本人であること、
ひいては東洋の国に生まれたということに
なぜかひどく幸福感を覚えたものだった。
やはり文化的な側面に違和感がないからだろう。
その幸福を巡って書いているつもりなのだが
ここではストーリーを追うことはやめておく。
そこに居合わせるだけで幸せな映画というものがあり
まさに、『青いパパイヤの香り』は
眼差しをスクリーンと共有するだけで十分なのだと。
とはいえ、年月を経て見直してみると
この映画の良さがもちろん再確認できるが
細部を言葉にしてみたい欲望にかられてくる。
まずは何と言っても主人公ムイが可愛い。
その後成人したムイも子役との違和感も全くない。
激しい主張など微塵もないが、
時折のぞかせる女の眼差しにゾクっとさせられる。
そして全編に流れる音楽の素晴らしさ。
サウンドトラックは同じベトナム人のトン=ツァ・ティエ
という人のスコアだが
その東洋的、異国情緒溢れる現代音楽が
少女ムイの心情を巡って、雄弁に思いを伝えてくる。
また、ユーモラスなシーンでは打楽器がメインで
情が複雑に絡むに従って弦楽器の比重が増してゆく。
実に官能性を帯びた旋律が艶めかしく入ってくる。
そして、これまた生き物のように艶かしいカメラワークが素晴らしい。
この監督はほとんどカットを割らず、
移動でワンシーンそのままを見せることが多い。
この辺りも溝口作品を観ているような緊張感がある。
あたかも濡れた肌をゆっくりなぞるような、
そんな官能を帯びた動きに
視線はうっとりさせられてしまうのだ。
また、昆虫や小動物、パパイヤの実といった生物に対する
執拗な視線が
音や映像とうまくマッチングして効果的に挟まれている。
ムイはそうした生命の神秘そのものに、関心があるのだろう。
ベトナムという土地のかもす空気が
そんなところからも手に取るように伝わってくる。
そうした共感とともに、
少女ムイから大人のムイに成長する過程が
女として目覚めてゆく官能性というものを伴って
とても奥ゆかしく、
洗練された美意識を伴って描かれており、
なるほど監督トラン・アン・ユンが
フランス国籍を持つベトナム人であることを
いやが応にも意識させられる。
祖国を離れ、フランスで映画を撮ることで
西洋的で培った美意識と
祖国への郷愁めいた感情による詩情が
嫌味なくうまく混淆している。
10年後、成人したムイが見せる主人への慕情。
初めてドレスアップし、口紅を塗るシーンがあり
それを主人が見ているシーンに
この監督のもつ奥ゆかしい美意識を見る思いがした。
それはどこか、日本人が忘れているような感覚というべきものかもしれない。
その後トラン・ヌー・イェン・ケーは公私ともに
トラン・アン・ユンのパートナーとなった。
『シクロ』『夏至』と続けざまに観たのだが
やはりこの処女作が今でも一番強く記憶に深く焼き付いている。
Sky Snake · Makoto Kubota
久保田真琴のこのSPA ASIAヒーリングシリーズは、アンビエントミュージックでありながら、メディテーションミュージックの趣向もあり、身を任せるには非常に心地よい響きがする。アジアの蒸せるような暑さに清涼をもたらす。『青いパパイヤの香り』のベトナムの空気にも溶け合う、そんな空気感に満ちている。










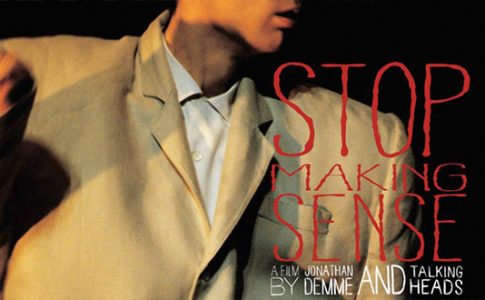


コメントを残す