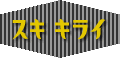なんでも自分のものにしてもって帰ろうとすると、難しいものなんだよ。 ぼくはみるだけにしてるんだ。そして立ち去るときには、それを頭のなかへしまっておくのさ。ぼくはそれで、鞄を持ち歩くよりもずっとたのしいね。
(スナフキンのことば)ムーミン(トーベ・ヨハンソン)
日常という名のステキを集めよう

日常にこだわる真の詩人なら、ペンをもつ前に、まずは天からの思召したるそのエーテルに配付された、あらゆる言語の解読から試みるかもしれない。そうして、意味もなくあたりをうろうろし、あたかも、不審人物のごとき様相を呈しながらでも、彼/彼女独自の言葉を発しながら、場合によっては、おとがめを受けるやもしれぬ喧騒を利用しながら、新境地開拓に勤しむに違いない。
日常の倦怠が成熟すれば、非日常の連帯を呼び、風の色まで変えることができるのではなかろうか、などと一体何処の誰が考えうるだろうか? 実際のところ、そうやすやすとは、巷の倦怠感など一掃できやしないものだ。だからこそ、その目で見、その耳で聴いて、直に触れ確かめるためにその足を使うのが真の詩人たちだ。よって、詩人はステッキに固執する。素敵を纏い、素敵を従え世界を歩きまわるための杖を携えて。
ステッキの達人、といえば晩年ステッキを愛用していた詩人瀧口修造。あるいは光の男マン・レイ。またはアルト-。はたまた、トリュフォーが映画の詩人と敬意を評したオーソン・ウエルズが、映画史に燦然と名を残す伝説の三分強の長回しで幕を開ける『黒い罠』で、自ら演じた巨漢の悪徳刑事ハンク・クインランか。老いのささえさえも、詩人が持てばステッキな日常を演出するしゃれた小道具というわけだ。が、ここに、「彼自身によるロピュ」というテーマにおいて、頬杖をつく前に、ため息をつく前に、小粋に一息いきつくために、日常のステッキなるものを、アトランダムにロランバルト先生風に書き留めていこうと思う。そんなわたくしと、ちょいと小粋な言葉のプロムナードはいかが?
ステッキ目録

- 愛がなくともアーガイル
- 哀愁の蝉ナール
- 愛す、といえばハーゲンダッツ
- 青空散髪
- アクセント、イノセント
- 熱燗好きのお銚子もの
- あっというまの天然感想記「あっぱれ」
- アフロな吸盤に吸い寄せられて
- 雨を彩るアジサイ日記
- ありがとうをいつもポケットに
- アロエは素敵なナイチンゲール
- いカスケット
- いまどき、河童どきあ
- イラスト付きの図鑑
- 美しき兄弟愛
- 永遠のタオル児ブルーズ
- 映画のチラシ
- 絵本deエヘン
- MCに頬笑むシーン
- お茶目なお茶会
- おっさん的クロワッサン症候群
- 乙レンズで、突撃だっ
- 男の子はみんなパトリックの……
- オノマトペ
- オムライス、ケチャップ皇帝
- おれんちのオレンジメモリー
- ウッシッシー、思わず微笑むプリティな海底物語
- 越中富山はええとこやっちゃ
- うなぎの寝床でドジョウ三昧
- 牛を求めて、自分に出会う
- おふくろの味を捻り出してみよう
- アンフラマンスを告白します
- 映画マトリョーシカ
- 仰げば尊しの奥義なり
- インスタ蝿、ぶんぶんぶん
- 粋を凝らしてサイレントムービー

- 蚕趣味?
- 角砂糖がとけて行く瞬間
- かさねぎはおまかせ
- 可視はしかし不可視で深し
- カプリコーン同盟
- カモンカモンHey家紋
- ガラスをつたう水玉たち
- 殻のあと
- カラーペンシルハーモニー
- 軽さの詩学、カリグラム
- カレー度スクープ
- ギャグのセンスで風起こし
- 銀色の友だち
- クスクスと思い出し笑い
- ゲーム小僧の血が騒ぐ
- グググの知太郎
- 幸か不幸か効果ON
- 声とエコー
- ここは甘党、ココア党
- 心をつなぐはてにをは
- コードレス、ノーストレス、つまり高度です
- ゴーヤは良い子?
- 幸福の機械
- コーヒーと珈琲
- ゲラは地球を救う
- 究極の鍋将軍は?
- 逆回転でプチタイムトラベル?
- 心の地図を刷新しよう
- ギョっとするスーパー
- 古都の磁力、こと京都の魅力
- 粉もん悶々、忘れじの庶民感覚
- コースターゴーゴー
- 競馬新聞読本
- ご飯、味噌汁、お漬物
- 黒板に宇宙を見る
- 幸運ぞろぞろ、数字マジック
- グッズの誘惑
- カワハギ釣り
- 香りたらしのアロマ美学

- 借景庭園
- ジュスイ、ジスイスト
- 食器アーティスト
- じりじりとするだんじりの跡
- 人力ドラムンベース
- スイスイスーダラなスイミングプール
- 鈴カステラ
- す、す、すっ、素敵な巣あれこれ
- すっぱいを恐れるべからず
- スチールドラムとカルピスの水玉関係
- 素直なこころで砂遊び
- 砂のプリン
- 住み込み稼業
- セカンド・ロゴ
- 雪ない想い
- セプテンバーは9ートな月
- 全集もの
- せんべいをかじる音
- そば湯でババンババンバンバン
- 空耳だわ-
- 植物界のタヌキは部類の戦略家
- ストーブリーグ
- すり鉢職人
- 寿司は寿司屋に限るの巻
- ザ・名画座の灯
- 舌達者は赤がミソ?
- 樹木のカモフラージュはイカすかも
- スピリチュアル、あるある?
- センセイ方のこっけい中継
- 縄文頌
- 自負するGIFアニメ

- たいそう素敵なクリスタル東欧
- たこやき名家の名言集
- ただただダダ茶マメがありゃあいい
- ダッフルコートのある風土
- たまには玉砂利またきてじゃりじゃり
- タンポポ&コーヒー
- チェスクセ?
- 茶呑白書
- チャバスクリプト
- チャリキ本願
- 包め伝播少年
- つばめの巣のある家、またはその玄関
- 飛び乗れ青春十八切符っ!!
- 手の官能
- 天使の食卓
- 動物行動学入門
- トマトメイトブギウギ
- 小さなスケートリンク
- 棚田がだんだん好きになってきた
- 伝統色に照らされて
- 手書きメモリィ
- 電動に感動、歯磨きブラッシュアップ
- とりつく島のある時間

- ナイショ、ットモード
- 軟体難題食物連鎖の話
- なんだかんだで古書街が好き
- 肉球スタンプ
- 偽シャーベットのススメ
- 入道、夏のニコッ展
- 猫とふくろうとファン倶楽部
- ネルドリップで、頭をひねる
- 粘土細工、楽しんでクレイ
- 覗きたくなる水溜り除きたくなる水溜り
- 猫騙し、猫魂
- 人間ばん馬、塞翁が馬
- 人間観察の奥義
- 喉仏を拝む

- 廃屋めぐり
- はい、チーズ
- 波形八景物語
- 禿げたペンキとヒビのガラス
- ばってらめぐりて
- バドミントンの羽根はね‥‥
- パームサイズラヴリー
- ふぁんたす竹林
- ふっかつロマンポルノ賛歌
- ふぅ~じっこちぁゃんが好き
- ブーケの心得
- 無精の悲劇を卑下にせず
- ブラシでコスップレ
- プリティーアプリケーション
- 古びるところが素敵なのさ
- ヘイ、ミスターベイスマン
- ベジエさんは愉快だな
- ボサッとするのもいいもんだ
- 星型肛門
- ベレーの下に広がる無限の暗闇に一抹の光を投げたとせよ
- ひょーいドン
- 引っ越しアーカイブ
- ほらみてごらん、マンホーラーに光あれ
- 古着小僧ぶる〜す
- ブラウンキャットエレジー
- ヘイミスターパイプマン
- 双子の神秘の玉手箱
- ピンクアラカルト
- 美術館めぐり

- マドリストという名の窓
- マニュアルカメラとEYEの行為
- マメな話
- マロンブランド
- Mr.チンのカンタンレシピ
- 蜜泥棒
- 矛盾に賛成の反対なのだ
- 結んで開いて、おむす美学
- めがねにかなう六角形
- もじもじするよなふぉんとの話
- メンタンピンイッパツツモドラドラ
- 升酒ブラボー

- ヤドカリ、曲がりなりにも間借人
- 雪、あたりジーン世界
- ユートピックス
- ユーワクワクのけもの道
- 陽気に惹かれて、轢かれんぼ
- 妖精、妖怪そんなもんかい?
- 預言者はアルチザン
- 郵便配達優雅便
- 吉本行くか
- 焼板の町並み
- 夢の自動再生アプリ
- 揺れる魔球

- ラララジー男の生活スタイル
- らせんの殺し屋
- ランチタイムビジーねす
- 律動玉手箱
- 路面電車のロマン族
- 列車ガタゴト駅弁カタコト
- レモン水を凝らす
- わがタイガードラマ
- Y字路帳を目を奪われて
- ロイヤルミルクティーとはチャイまんねん
- 朗読ムービー