「写真」とは、「ほら」、「ね」、「これですよ」を交互に繰り返す、一種の歌に他ならない。
『明るい部屋』みすず書店 ロラン・バルト(花輪光訳)より
写真というものについて、日々撮るのに夢中な人は増えたと思うが、
果たして、何人の人が、「写真とは?」
なんていうテーマについて考えるだろうか?
考える必要があるわけでもないが
考えてみることも時には必要なのではないだろうか?
なんのために写真があり、そして撮るのか?
その上、見せるのか?
で、結局写真とは一体どういうものなのか?
それを考えない限り、本当の写真の魅力、
写真もつ親和性にはたどり着けない気がしている。
そんなことが一人頭の中で、
まるで的外れな、壊れたシャッターのように
カシャカシャひとりでに鳴っているのであるが、
写真は写真であって、はて、それ以上のことがあるのかしら?
とでも言われると、明確な答えを導き出す自信はない。
いや、それ自体そもそもが不可能なことなのだ。
つまり、一つの論理でもって、さも真理であるかのように
主張したいわけではないのだ。
はっきりと、確信は持てないが、
写真というものは、こういうものではないのか?
というような問題提起はできるし
そんな訓導があれば、
それこそ、じっくり耳を傾けてみたい。
さらに、その先に、映し出された写真なるものがあり、
なんらかの因果関係があるならば、
おそらく、写真に対する思いは、
少なくとも、全然違ったものになるのではないか、
そんな思いがあるのである。
自分は写真家でも、それに関わる生業を営んでいるわけでもない。
単なる興味本位な写真論は、以上が全てである。
つまりは、目の前にある一枚の写真から
一体、どれだけの情報を読み取りうるのか、
自分で自分に課しているゲームに過ぎない。
ここにそうした聡明な写真家たちを招いて、
じっくり講演でも聞きたいものだが
そんなことを願うのは現実的ではない。
せいぜい、その写真を眺め
自分でそれを考えるしかないのだ。
そんな時に手にする本がある。
僕の場合はロラン・バルトによる『明るい部屋』という本だ。
随分と若い時に、この本に感銘を受けたものだが、
どこまで本書を理解していたのか、実のところよくわからない。
ただ、有名な言葉、ストゥディウムとプンクトゥムは
以後曲がりなりにも、写真をみる基準になっている。
ストゥディウムとは、「一般的関心」ということを意味しているのだが、
バルトは書く。
気楽な欲望と、種々雑多な興味と、とりとめのない好みを含む、極めて広い場のことである。あるものに心を傾けること、ある人に対する好み、ある種の一般的な思い入れを意味する。
ストゥディウム(一般的関心)が、つまり「一般的思い入れ」であるのに対し、
プンクトゥムとは、「破壊(または分断)しにやって来るもの」なのであると。
刺し傷、小さな穴、小さな斑点、小さな裂け目のことでありー、しかもまた。骰子のひと振りのことであるからだ。ある写真のプンクトゥムとは、その写真のうちにあって、私を突き刺す(ばかりか、私に痣をつけ、私の胸を締め付ける)偶然なのである。
ここに一枚の写真をひいてバルトは説明する。
それはアンドレ・ケルテスの「子犬」という写真である。
これは僕も大好きな写真の一枚だが、
子犬を抱いた一人の少年が、こちらをじっと見つめている。
生まれたばかりの子犬を抱いて、ほほずりしているこの貧しい少年(ケルテス 1928年)は、悲しみと愛着と恐れの入り混じった目でカメラを見つめている。なんと不憫で切なくて思慮深い様子であろう! だが実は彼は何も見ていないのだ。彼のまなざしは愛と恐れを心のうちに引きとめているのである。写真の「まなざし」とは、そういうものなのである。
バルトは写真のまなざしについて、こう続ける。
ある種の雰囲気がもつきわめて稀な特質を生み出すのは、この人騒がせな視線の動きなのだ
風景でも、人物が写り込んだ記念撮影でも構わないが、それ自体は
その写真からの情報を「ストゥディウム」として受け止めることができるが、
そこに、特定の人物、あるいは、決定的な何か、
見るものの眼に映る何か別のもの、特別な事象によって、
その写真に偶発的にも意味が生まれ、
それによって、写真そのものに新たに付加価値が生まれ、
副次的な物語なり、息吹のようなものが芽生え始める・・・
というようなことを「プンクトゥム」だと言っているのだと
自分は、なんとなく解釈しているのである。
まあ、こうしたバルトの概念は、写真というものの
一つの見方であって、いわゆる一般共通認識というものでもない。
なぜなら、その一枚の写真においては、
せっかく「ストゥディウム」という認識はあっても
「プンクトゥム」が生まれないケースだって多々あるだろう。
逆に、ストゥディウムとプンクトゥムはその写真の中の共時性というか
共存するものなのだと、バルトは書いている。
しかし、実のところ、この『明るい部屋』が感動的なのは、
そうした写真への見方、眼差しを超えた、
バルトの愛する母親への深い鎮魂歌であるという点である。
訳者である花輪光氏がそのあとがきの中でいうところの
「母の神話を感動的に歌いあげる作者の純粋無垢な姿勢」にあるのだと。
それは母親に対し、愛と憎しみの葛藤の果てにあった
プルーストとの決定的違いなのだとも言っているのだが、
まさに『明るい写真』は、母との関係を
写真を通し、「それがかつてあった」ことを
ただ確認することしかできないという、バルトの深い喪の悲しみが
写真というものへの眼差しに同調しており、
テクストの理論を越え、胸を締め付けて来るのである。
つまりは「プンクトゥム」としてのテクストに
なり得ているということなのかもしれない。
私を突き刺す写真、あるいは魅入られし写真家たちの眼差しへの考察
- ある日、ある時、午腸内の肉声を聞く・・・牛腸茂雄『SELF & OTHERS』をめぐって
- イライラ感よ、さようなら。イーラのカメラ愛に微笑みを・・・イーラをめぐって
- 陰翳をめぐる写真とエクリチュール、畳に佇むフーガ・・・アンリ=カルティエ・ブレッソンをめぐって
- 遠くて近い、近くて遠い秘密の扉・・・ビル・ブラントをめぐって
- 田園に現れたストレンジャーは、虚空を切り裂く光でもって記憶を刻みつけたという・・・細江英公『鎌鼬ー田代の土方巽』をめぐって
- 愛を維持する地上の街、地上の星・・・イジスをめぐって
- 永遠の砂丘少年・・・植田正治をめぐって
- 双子座の季節にフリークスは微笑む・・・ダイアン・アーバスをめぐって
- 重力にあらがういちびりたちの美学・・・フィリップ・ハルスマンをめぐって
- 円を為すフォトシークエンスの終わりなき物語・・・ドウェイン・マイケルズをめぐって



![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-200x200.gif)
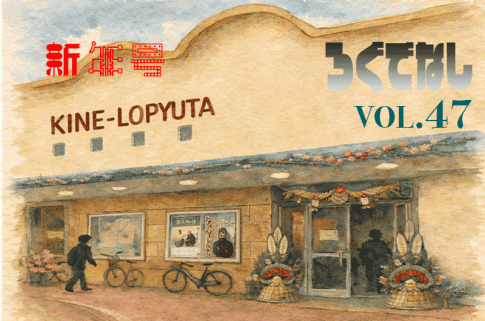








コメントを残す