自然光を積む眼差し
不思議な感覚だが、いつの間にか気がつけば
自分が撮る不意のスナップショットの眼差しが
どこか、ますますルイジ・ギッリの写真のもつ“間”に似てきた気がしている。
無自覚であり、単に思い込みにすぎないといればそれまでである。
とはいえ、なんらかの影響を受けているのかもしれない。
ギッリ同様、被写体は主に静物が中心であり、
面と向かって人にカメラを向ける機会は驚くほど少ない。
ルイジ・ギッリの写真には、何も言わずに、
ぼくらの眼球をそっと、自然に振り向けるそんな導きがある。
優しさなのか、それとも厳しさゆえか、あるいは諦観なのか。
それは「写真」という形式を借りた言説行為であり、
それ以上に「見ること」そのものを問い直すメディテーションに思えてくる。
ぼくが初めてギッリの写真に出会ったのは、たまたま入ったギャラリーで
ギッリの写真展が行われていたのだ。
それはあたかも偶然の「覚醒」のような経験だったといえる。
同じイタリアの画家ジョルジョ・モランディのアトリエを撮ったシリーズであり、
地味な室内の、無味乾燥な事物たちに魅入っていた。
イーゼルや、花瓶、漏斗などが並ぶ粗末なテーブルは
さながら自然のようにそこに存在していたが、
もちろん、この写真には主人公もドラマもない。
ただ、物たちがシーンの謎を投げかけ、静かに佇む間だけがそこにある。
ナトゥーラ・モルタの流れを汲む、
動かぬ事物であり、いわゆる静物画的写真。
おそらく、それは視線による、ものの存在そのものの「覚醒」の、
その瞬間の体現への期待なのではないか、と思った。
いうなれば、誘う写真でもある。
そのときから、ギッリの写真は特別なものとなった。
そこから、モランディの絵画への興味が始まった体験でもあった。
ギッリはこう言っている。
私は常に、写真とは現実を変えたり隠したり修正したりするのではなく、“見るための言語”であると考えてきた
この慎重な語りかけは、写真という手段を使っているにもかかわらず、
写真そのものの技術性や意図性をはなれた視線を感じさせる。
当然のようにある事物、違和感のないフレーミングにおいて、
そのなかで人物はもはやアクターではなく、
ひとつのオブジェとして混ざりこんでいるのをみるだけである。
ギッリが撮った一連の静物は、F11・1/125・自然光によって切り取られている。
もちろん、それにはそのときそのときの写真家の意図があるだろうが、
そこに透明な光による「世界の覚醒」を視るのは自然なことだろう。
その一見、温もりからへだった無機的な画面に
しずかな呼吸と奥深な野心を感じ取って、だんだん離れがたくなる。
それこそが、ぼくが感じるギッリの写真の魅力だ。
さらに、特筆すべきは、ギッリが人を撮る場合には
裏側から人物を撮ることが多い点だ。
つまり、背中は顔よりも多くを語らないし、そこには言説も感情もない。
アトリエにある事物、部屋の空気同様、そこに二重の視線が静かに置かれている。
しかし、その視線の先には「世界」が広がり、
写真を見つめる者は、その世界をともに覗き込むことを要求されるだろう。
背中を撮ることは、その人を覚醒させるのではなく、
わたしたちに視覚の共有を求めてくる行為でもある。
後ろ向きの人物の視線とがかぶる。
「見る」とは、そもそも、だれの視線で、なにを見ることなのか?
ぼくはふと、エドワード・ヤンの映画『Yi Yi: A One and a Two』の中で
父親からカメラを買い与えられ、人の背中ばかり撮っている、
あの写真のことを思い出していた。
少年ヤンヤンの、大人への一歩、すなわち、観察し存在を認める眼差しだ。
ギッリの風景写真は、人の存在をごくまれにしか含まないこともあり、
そこには時間の止まった、少しひんやりとした
「記憶」の形をみて取ることができる。
手を入れない花瓶、単語のみが書かれた標識、あるいは本棚の背表紙といった
わずかな陰の気配のみが漂っている。
それらが共通するのは、すべて「だれかがいた」
あるいは、「かつてはそこになにかがあった」ことを示しながら、
現在はただの風景として広がっているにすぎない場の刻印だ。
これらすべては、ギッリが写真を通して教えようとした、
見ることの訓練であり、視覚の内面へ降りる行為なのかもしれない。
そう思うことで、ぼくはギッリの視線や、写真のなかの視線との
不思議な共鳴を感じるのだ。
それはけっして勝手なイメージや感性ではなく、
実在している世界の視覚結構を細密に見つめること、
あるいは「あるもの」を「また見ること」の感性とつながるのである。
おそらくは、モランディもギッリも、同じ辺境へと降り立ち、
誰も気づかぬ部屋の隅や、舗道の無言の光景にさえ、
実在への偏愛や崇敬を込めて、
それらをそっと「覚醒」へと導こうとしたに違いないのだ。
そう思ってギッリの写真の眼差しに寄り添ったとき
「終わらない風景」とは、終わらない視覚の記録であり、
ぼくらが、いつでもその光に復起することをゆるされた場所だということを
おぼろげに知覚しはじめるきっかけなのだ。
Late October : Harold Budd · Brian Eno with Daniel Lanois
ギッリのナトゥーラ・モルタ以上に、静謐な情動が静かに脈打つイーノのアンビエントミュージック。前作の『Ambient 2/鏡面界』と並んで、バッド + イーノのコラボに続く第二弾。まさに秋の夜長の背後に流れているだけで、心洗われる思いがしてくる名盤だ。バッドの即興的なピアノ演奏をベースにしつつ、イーノの電子処理や音響空間的な手法で“拡張”し、そのまま発展・変容していく余白を持たせ、イーノとラノワがその余白に風を吹き込むような役割を果たしている。ここにも、言葉はいらないのだが、感傷に酔うこともなく、ムードに流されることもない音の風景に身を任せることは、ギッリの写真の眼差しに交差する光が感じるかもしれない。






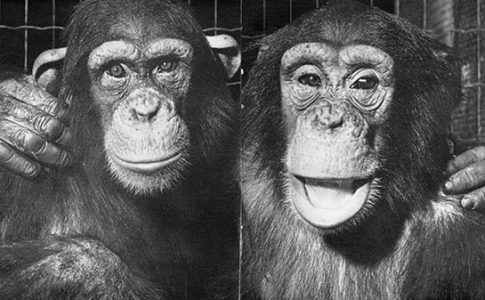






コメントを残す