永遠の駄々っ子は、無頓着、しかし無関心ではなく。
究極の表現というのは何もしないことなのかもしれない。
そう思うことがある。
これはある種謎かけにようでもあり
いかにもマルセル・デュシャンの請け売りみたいな発想だが、
それも当然のように、鑑賞者と表現者では温度差が生じる。
手ぐらい動かしていたいし、脳内の方でも
あーでもない、こうでもないと
とりあえず思考だけはやめようとはしないだろうし
そう考えるのが正常だと思いたいのだ。
人はカタチがないものには常々不安を感じるものではないだろうか。
そうやって何か形あるものを信仰し、
つまり、具体的に、と要求することを日常化している。
そんな率直で、なんのひねりのない思いにどっぷり浸かっていると、
あえて、形なぞ犬にでも食わせてやれ、などと放棄したくなってくる。
曰く、凡人たるもの、デュシャンのようには、かっこよくいかぬものである。
自分は目の前に絵なり、造形なりを目にすれば
色、形に惹かれるという本能を前に、無為に抗いたくはないと思う。
素直に直感的にとらえ、まずは見たままを重視することに注視する。
いったん関心を心で消化した後なら、
初めてコンセプトなり、制作工程について、想いを馳せるにいたるのだ。
あくまでもコンセプトや意味など、二次的なものなのだ。
かくなるシンプルな見方でこそ、
永久不滅の純粋な感受性を保っていられると信じている。
そうやって、興味の対象に向き合ってきたのだが、
いろいろ心惹かれる美術、およびその具現化アーティストについても、
これまでもランダムに言及してきたが、
まだまだ取り上げきれいないアーティストたちがあまた脳裏に散乱している。
興味だけが膨らみすぎていっぱいに情報が錯乱する場合と、
あまりにも思い入れが強すぎるがゆえに、
もしくは切り口が多面的にありすぎるがゆえに
どこから手をつけていいかわからない、手つかずの場合とで、
その両極に脳は悩みを抱えるわけである。
そんな渦中にいる人を、
こうして思い出したように、ポツリポツリと取り上げていくのは楽しいのだが、
そのアプローチ方法は直感的にならざるを得ない。
仮に、映画や文学の、単なる一作品への言及と言うのなら
比較的思いのままに言葉が進むのだが、
アーティストそのものの概要、その生き様にまで踏み込んで、
真摯に向き合っていくとなると、
どうにもこうにも行かぬ場合が得てしてある。
ピカソ、ダリ、ゴッホ、そしてマン・レイあたりが
そんな対象かと思われる。
がしかし、そこは壁を超えねばならない。
義務にあらず、使命にあらず、
ただ無関心ではいられない衝動だけを頼りに、
どうにかして言葉をつなぎ合わせてゆくにおいては
屁理屈ばかりじゃつまらない。
そこで今日は、長らくアプローチを温めてきたマン・レイについて、考えたい。
幾度となく取り上げてきたシュルレアリスムの画家、
あるいはダダイズムの運動の渦中にいた芸術家の中で、
マン・レイだけはちょっと他のアーティストと違っているように思われる。
何が違うかということの前に、
まずもって、大好きなアーティストであると言うことなのだが、
要するに、ウマが合うのである。
もちろん、マン・レイはどう転んでもマン・レイであるからして、
こちらの意の範疇に容易に収まりきれるアーティストなのではないが、
勝手にシンパシーやら、偏愛の眼差しを向けてきたのは
他でもない、マン・レイこそは
この現代において十分通じる多様性、柔軟性を持ちつつ、
その上で、ある種の親しみを兼ね備えたタイプであるからに他ならない。
要するに、時代だの権威だ、世間で言う有り体の制約に邪魔されず、
ひたすら自由な意志への快楽を拠り所に生きたアーティストだったからだ。
では、改めて、マン・レイとは何者だったのか?
何も改まる必要もないのだが、エマニュエル・ラドニツキーとして
アメリカに生まれたユダヤの血を引くこの生粋の駄々っ子は
マン・レイへ、すなわち“光の男”として自らの転機を察知し
どうにも違和感しかなかった生まれ故郷を後に
パリへと趣き、再出発を決意する。
しかも、それを二度も繰り返したのである。
それにしてもマン・レイとは、なんと運命的な名前だろうか?
ネーミングセンスにも味がある。
仮に日本語で「光男」などと訳そうものなら、
ずっこけてしまう微妙さまで漂ってくる。
そう言われれば、写真家として、その名を馳せたことは
つとに知られているし、
人によっては写真家マン・レイしか存ぜぬという輩もいるのだろう。
文字通り、光を自在に操った男として記憶されている。
しかし、当人は決して肩書きに甘んじるような男ではない。
画家であり、映画作家であり、そしてオブジェ作家でありと
実に様々な顔を持つアーティストとして、
実に興味深い創作の数々を投げかけてくれた人物として
いくらでも称賛できるのであるが、
ダダ、シュルレアリスムの運動においては、
実に適度な距離、存在性を示していたに過ぎず、
いわば特別な立ち位置にいた人ではないか、
そう思うのである。
誤解を恐れずにいってしまえば、
マン・レイこそ永遠のアマチュアであって、
永遠のアート少年を地でゆくような人だ。
間違ってもシュルレアリスムの法王ブルトンと
理論や主義で渡り合うようなタイプではない。
これがエルンストあたりだと
実に重厚で厳粛なる中心人物としての扱いになるわけだし
生涯の友であったデュシャンだと絶えず美術史をにらみつつの言及となる。
もちろん、マン・レイが写真芸術に与えた影響は
ソラリゼーション、レイヨグラフといった技法はもとより
ポートレート写真やモードの分野においてさえ
決して小さくはないのだから
その切り口で大いに讃えてしかるべきところである。
思えば、自分が高校生あたりの頃
最初に買った芸術系の写真集が
たまたま、みすず書房から出版されていた一万円そこそこの
マン・レイの写真集だったのは何かの縁であった。
残念ながら、すでに手放しており、
手元に眺めることはない代物だが、一つ忘れられぬ思いがある。
その写真集には、メレット・オッペンハイムだの、
キキ・ド・モンパルナスだの、
マン・レイの助手および恋人であったリー・ミラーといった、
入れ替わり立ち替わり、ミューズたる被写体になっていたわけだが、
その中のポートレートに露わなヌードも含まれており、
何を思ったか、日本の検閲は
猥褻物として、陰毛を四角く黒で塗りつぶしており、
事もあろうに、あのマン・レイの作品を
メタ・レディメイド作品として扱っていたわけである。
なんとも大胆不敵な事象であるが、
当のマン・レイは、そんなことを知るよしもなかったに違いなく、
これは今思えば、最高のジョークだと思わなくもない。
マン・レイの作品は、常に、諧謔と実験精神に満ち溢れていたがゆえに、
決して、ダリのようにドルの亡者になることもなかったし、
デュシャンのように、晦渋なる謎解きを放ち
鑑賞者に憂いを授けることもなかったのである。
アメリカの風土並びにニューヨークダダの機運に 馴染めず
二度も往復を繰り返し、パリをその拠点としたマン・レイの
そうした性分は、それゆえに
ひたすら純度を保ち続けてきた気がして、
今尚、そのみずみずしいダダ精神、
シュルレアリスティックでシニカルなエスプリを感じさせる。
それは生涯の親友として付き合ったデュシャンとは
真逆のようであり、
マン・レイのあらゆる芸術に宿っている一本の骨格として
記憶されている。
モンパルナスのマン・レイの墓碑にある次のような言葉。
これぞマン・レイの真髄といったところか。
Unconcerned But Not Indifferent
無頓着、しかし無関心ではなく
写真、オブジェ、絵画・・・
そこに恋愛や友好関係を含んでも構わない。
なんだって構いはしない。
そう、マン・レイの生み出した、
あるいは関わったあらゆるものに共通する思いがここに集約される。
そんな対象を前にして、無関心でいられるはずもない。
無関心などと言う無粋とは無縁だ。
しかし、だからと言ってなんなのだ?
So What!
マン・レイを、この生粋の駄々っ子を
そう、実に無頓着に今日まで扱ってきたイデの実態である。
それが最大のオマージュだとして刻印しているのだ。
Dadada Ism · Yapoos
ダダな曲や音楽家はいろいろあれど、その直接な響きを体現した曲はこれだ。戸川純のYAPOOS1992年リリースの「DADADA ISM」のタイトルトラック。ファンの間でも戸川純の最高傑作との呼び声も聞く名盤だ。こんな曲をポップに響かせうる生粋のニューウエイブシンガーが戸川純だ。ジャリ、カンディンスキー、ツァラ、ピカビア、そしてデュシャンの名前が上がるが、マン・レイははいっていない。もっとも、マン・レイの場合は、ダダイストであり、シュルレアリストでもあるが、その資質あ、駄々っ子よろしく、子供のように無秩序かつ自由、そんな精神を持った反骨精神溢れるクリエーターだから、なにもダダの括りに拘る必要などないのだ。




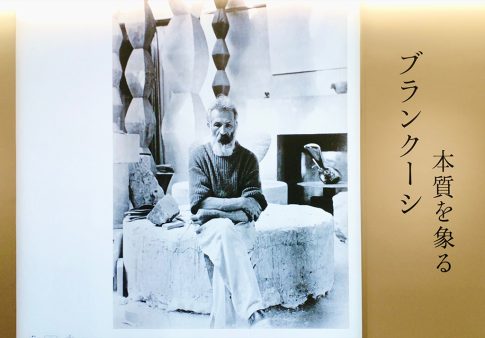








コメントを残す