夢を夢として語り継がない、魂の救世主の存在論
あまりにまばゆい存在を前にしたとき、
人はしばしば「見ていない」ことに気づかない。
ブレット・モーゲンによるデヴィッド・ボウイのドキュメンタリー映画
『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム(月世界の白昼夢)』は、
その矛盾を鮮やかに描いた華やかなドキュメンタリーだ。
デビッド・ボウイ財団初の公式認定映画ということで、
30年にわたりボウイ自身が保管していた膨大な量のアーカイブから
厳選された未公開映像をもとに編集された内容は、
ボウイ本人によるナレーションによる哲学をも織り交ぜ、
ファンにとっては見応え、聞き応え、申し分ないものだった。
ムーンエイジ・デイドリームからは、文字通り月世界、
つまりは狂気の時代に生きるものたちの夢物語を嗅ぎ取ることが可能だ。
そこに君臨するのは、アイコンであり、預言者であり、モンスターであり、
そして何より「夢の顔をした現実」、それがデヴィッド・ボウイという眩しい存在だ。
だが、映像と音の炸裂、ヴィジュアルの過剰な美、
そして彼自身の肉声だけに支えられたこの映画は、
結果として、ボウイの“不在”そのものを描いている。
これこそ、スコトーマの原理、すなわち盲点なのだ。
以下、これは、なにもここで真面目に語るべき内容ではないのかもしれない。
人々は、この狂気のエンターテイメントへの驚喜と狂気を混同するだろう。
ボウイがまとった仮面をはぎ取る必要も無ければ
その偉大な軌跡が揺るぐわけではない。
それは奇妙な逆説といっていい。
こうして、ボウイが全編に“映っている”のに、
彼の人間的な息づかいはほとんど聴こえてはこない。
それは監督の怠慢でも編集の失敗でもない。
むしろ意図的な演出であり、もっと言えば詩的な転換なのだ。
ムーンエイジとは、まさに、このAI時代の申し子としても
永遠に創造の宇宙を衛星のように照らし出すことだろう。
この映画には「語り」がない。
当然である。
語り始めると、物語が変色することになる。
年表もインタビューも、ボウイを補完する証言も存在しない。
あるのは、彼自身が語る断片と、無数のビジュアル・レイヤー
そして“熱狂”の記録なのだから。
それは、ロック・スターがいかにして「文化」に食われていくかを、
皮肉にも証明している。
ボウイはそのことを熟知していたし、だからこそ変身を繰り返した。
ジギー・スターダストからアラジン・セイン、シン・ホワイト・デューク、
そして晩年の“ブラックスター”まで、彼はアイコンであり続けることで、
逆説的にアイコン性を解体したのだ。
けれど、私たちはそこに一人の“人間”を重ねたがるのはムリもないことだ。
名声や神話の背後にある“日常のボウイ”を求めたくなるのは、
彼の存在が、あまりに完璧な「フィクション」であったからにほかならない。
そうなると『ムーンエイジ・デイドリーム』を観終えた後に残るものは、
やはり奇妙な余韻である。
ボウイを“見た”のに、何かが抜け落ちている感覚だけが残る。
それは、たとえば彼の孤独、彼の愛、彼の眠る部屋の空気。
つまりはそういったものが、まるで「編集段階で意図的に切り取られたかのように」存在しないのだ。
だが、それこそがこの映画の真実であり、ボウイという存在の本質かもしれない。
語られないことでしか語れないもの。
映されないことでしか見えてこない輪郭。
この映画は、ボウイという名の“まぼろし”を再生するのではなく、
彼の「不在のかたち」をそっと提示している。
ボウイははたして、救世主だったのか?
確かに、ジギー・スターダストは地球を救いに来た異星の預言者という設定だった。
しかし、それはメシアではなく、むしろ存在を問いを投げかける者であった。
「人は何者になれるのか?」
「自己とは固定されたものか、それとも演じ続ける仮面か?」
「芸術とは、逃避なのか、それとも暴露なのか?」
それをロックというメディアを通して、われわれに提示してくれたスター。
彼の存在は、これらの問いを答えのないまま観客に投げ返してくる。
その身をもって、言語・性・存在・死の境界線を撹乱し、
ただ“そこに在る”という奇跡のような存在論で、見る者の魂を揺さぶり続けた。
それゆえに、彼は“魂の救世主”たりえたヒーローだったのである。
癒す者でもなく、赦す者でもなく、ともに狂い、変身し、共鳴する者として
ぼくらは熱狂し、いまも強くその記憶が離れない。
映画のタイトル『ムーンエイジ・デイドリーム』「月齢の白昼夢」。
夢は夢である限り、美しい。
けれど、ボウイは夢を夢として終わらせなかった。
彼は白昼夢を現実の地平に持ち込み、変装し、滑稽で、真摯で、
絶えず自壊しながら立ち上がることを選んだ。
その変遷は、長く壮大な絵巻ものとして、ロック史に刻まれている。
その道は苦しく孤独でもあっただっただろう。
それでも彼は、夢を見るすべての人々の「仮面」であり続けた。
“私がボウイであり、あなたもボウイになれる”という奇妙な共犯関係を、
彼はステージの上から、黙って差し出していたのだ。
『ムーンエイジ・デイドリーム』は、ボウイの人生を総覧する作品ではない。
それは、むしろ亡霊のように彼がささやく、詩的なエコーのようなものだ。
だからこそ、私たちは、今、そこにある種の喪失感を抱く。
それは、「もっと彼の素顔が見たかった」「彼の苦悩を知りたかった」という単純な欲望などではない。
むしろ、彼の不在を通して、自分自身の問いと向き合わされるだけである。
夢を夢として語らない。
神話に甘えない。
偶像を崇めない。
そのすべてを飛び越えて、なおも語り得ぬ光として、ボウイはそこにいる。
そして私たちは、彼の“いない”映像のなかで、そっと問いかけるのだ。
あなたは、まだそこにいますか?
それとも。。。
“I’m an alligator, I’m a mama-papa coming for you
I’m the space invader, I’ll be a rock ‘n’ rollin’ bitch for you”「オレはアリゲーター、父でも母でもある、キミを迎えにきた
オレは宇宙からの侵略者、ロックンロールする魔女になるさ」
― David Bowie, “Moonage Daydream”
この異形の言葉たちが、ロックンロールの予言書として
いまも宙をさまよっている。
まるでどこにも届かないラブレターのように、
ぼくらはそれを懐に抱きしめている。
地球に降り立ったのは、
神でも天使でもない。
銀のまつげに塗料をかさねた、夢のかたちをした者だった。
David Bowie – Moonage Daydream (Live at Hammersmith Odeon, London 1973)
ジギー・スターダスト。
言わずとしれた星塵から生まれたメッセンジャー。
彼は、祈られる前に踊り、崇められる前に自己を脱ぎ捨て、
誰よりも“なりたいものになる”、そう使命に駆られていたのだ。
「おれはアリゲーター、きみたちのママでもパパでもある」
お前に会いにきた、光線銃を頭に向けてくれ」
そう言ってぎらつく彼は、宇宙からの侵略者を名乗ったが
その姿は、どこか傷を背負った殉教者のようでもあった。
ジギーは夜の夢ではなく、白昼夢のなかにいた。
目を開けたまま見る幻。真昼の空の下、
まぶしすぎて見えないものの名を、彼は歌に託すしかなかった。
変身するたびに何かを失い、仮面をかぶるたびに、内側の顔が消えてゆく。
彼はそれでも前へ進んだ。ロックンロールという名の、カオスの舟に乗って。
それは救済か、呪詛か、誰にもわからなかった。
ステージの上で、痙攣的なギターサウンドに煽られ彼は燃え尽きた。
最後は観客の熱狂に燃やされながら、灰になるまでに燃え尽きた。
そして、夢の終わりはいつも、祝福とともにやってくる。
けれど――
すべては夢なのだ。
彼が消えても、耳の奥で誰かが喚き、叫ぶ。
ステージの熱狂は永遠を刻印する。
月に照らされた夢という甘美な狂気を引きずりながら。。。
“Freak out in a moonage daydream, oh yeah.”
このライブ版「moonage daydream」は、『Live at Hammersmith Odeon, London 1973』として、D.A. ペネベーカー監督によってフィルム化され、1983年に映画『Ziggy Stardust and the Spiders from Mars』として公開されたものだ。、まさに。映像と共に、ジギーの終焉を見守る観客の熱狂、ステージ上の虚飾と真実の交錯した伝説的瞬間を音・映像で現在によみがえらせている。








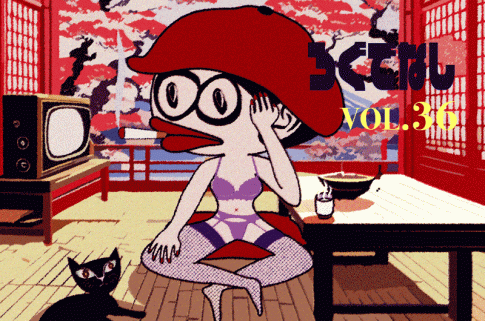




コメントを残す