写真とエクリチュール、陰翳をめぐる畳に佇むフーガ
まだ、今のように、スマホなんかがなくて、
カメラはカメラとして、独立して機能していた頃の話。
ライカのカメラが欲しいな、なんて漠然と思っていたけれど、
とうとうそんな名機ライカには縁がなかった。
それでもニコンなんかの一眼レフカメラを首からぶら下げ、
街中を闊歩したものである。
ライカというと、真っ先に思い浮かんだのが、
アンリ=カルティエ・ブレッソン、
フランスの著名な写真家であることは言うまでもない。
写真家集団「マグナム・フォト」で有名だ。
“決定的瞬間”をカメラで切り取ることに長けた写真家ではあり、
それらの写真もとても魅力的なのだが、
ここでは、むしろ、そうした観点をはなれ、
我々日本人には馴染みのある
日本座敷の静謐な一枚を巡って、考察して見よう。
『決定的瞬間』とは、1952年に出版された、
ブレッソンの名を世界に知らしめた写真集のタイトルだが、
英題The Decisive Momentからの意訳だと、
文字通り、その一瞬を切り取って、
シャッターチャンスを逃せば二度と同じ瞬間をみることができない、
という意味でとらわれがちだが、
仏原題では、Image à la sauvette「逃げ去る映像」という意味だから、
やはりちょっとニュアンスが違う。
ニュアンスにこだわるフランス人らしい表現だと思う。
それは写真からも読み取れる。
たとえば、この日本間の静謐なショットをみると、
『決定的瞬間』というよりは「逃げ去る映像」というニュアンスの方が
より本質を理解しやすいと思う。移ろいとでもいうのか。
実をいうと、このことは、ブレッソン云々というよりは、
谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』という随筆について、
思いを巡らせていたところ、たまたまブレッソンのこの一枚が、
とってつけたかのように、頭に去来したまでである。
ちょうど、古都京都や奈良の古刹を訪ねているときに、
そういえば、谷崎は『陰翳礼讃』のなかで、
「日本の建築の中で、一番風流に出来ているのは
厠であるとも云えなくもない」と、
厠についての風流をしみじみ書いていたのを思い出し、
自分もその趣向を実感したものだから、
ならばと、もう一度『陰翳礼讃』を読み返してみた。
その際に、このブレッソンの写真と、谷崎の随筆が、
ものの見事に合致したのである。
まさに、これぞ“決定的瞬間”の前に感嘆させられた。
もしも日本座敷を一つの墨絵に喩えるなら、障子は墨絵の最も淡い部分であり、床の間は最も濃い部分である。私は、数寄を凝らした日本座敷の床の間を見る毎に、いかに日本人が陰翳の秘密を理解し、光りと蔭との使い分けに巧妙であるかに感嘆する。なぜなら、そこにはこれと云う特別なしつらえがあるのではない。要するにたゞ清楚な木材と清楚な壁とを以て一つの凹んだ空間を仕切り、そこへ引き入れられた光線が凹みのある此処彼処へ朦朧たる隈を生むようにする。にも拘らず、われらは落懸のうしろや、花活の周囲や、遠い棚の下などを塡めている闇を眺めて、それが何でもない蔭であることを知りながらも、そこの空気だけがシーンと沈み切っているような、永劫不変の閑寂がその暗がりを領しているような感銘を受ける。思うに西洋人の云う「東洋の神秘」とは、かくの如き暗がりが持つ不気味な静けさを指すのであろう。
谷崎潤一郎『陰翳礼讃』より
まさに、ブレッソンの日本間の写真のために書かれたといってもよいほど、
その世界観をズバリ言い表しているといえる。
谷崎の『陰翳礼讃』が、あらゆる文化的側面において、
日本のみならず、世界中で賞賛を浴びているのは、
やはり、その美の奥行きが、デジタル世界では、
いかんともしがたい美意識とつながっているからだろう。
この時代だからこそ、改めて吟味される、
美の秘密だということに、今更ながらに気づいた。
このほか、羊羹への美しく絶妙な言及や、
歌舞伎や能などを通しての陰翳の違いや効能、
また、日本人のアイデンティティたる肌の色と陰翳のバランスなど、
日本人のもつ美の本質が風雅に綴られている。
羊羹への言及は何度読んでも美しい表現である。
「玉のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光りを吸い取って
夢みる如きほの明るさを啣んでいる感じ」と表現した羊羹について、
人はあの冷たく滑らかなものを口中に含む時、あたかも室内の暗黒が一箇の甘い塊になって舌の先で溶けるのを感じ、ほんとうはそう旨くない羊羹でも、味に異様な深みが添わるように思う。
と言うのを読むと、無性に羊羹が食べたくなるのが
自分のなかで定番になっているほどである。
『陰翳礼讃』について、この本のあとがきで、
吉行淳之介が、こんな風に書いている。
西洋人の老年の死は、巨象が老いて大きなまま衰えてゆき、やがてはどたりと倒れるという感じである。日本人は、植物が枯れてゆくような死に方になる。これは抜きがたい体質の違いだが、その体質からそれぞれに美点欠点が引き出されてくる。要するに、日本人の体質に深くかかわり合う「陰翳」というものについてのユニークな意見を述べたものが、この作品である。
西洋人を象、日本人を植物に喩えたのは言葉の妙だが、
やはり、長い文明の歴史に沿って、
陰翳の美が形成されてきたこの国の誇るべき文化を、
自分もまたようやく、理解できる年齢になってきたということなんだろうか。
改めて日本人に生まれて来てよかったと思える、
そんな瞬間がここにあるのだ。
FEET · Hiroshi Yoshimura
昨今、再評価の波が押し寄せているのが日本のアンビエントミュージックのパイオニア吉村弘である。音楽家というべきか、サウンドデザイナーと言うべきか、吉村弘の構築する音の風景は、この日本の風土そのものに根付いた息吹を感じさせるものだ。都市や空間をも意識したその奥行きある設計は、皮膚感覚にも優しく染み込んでくる。その吉村の5thアルバム『GREEN』は、名盤の誉たかきアンビエントミュージックの傑作だ。



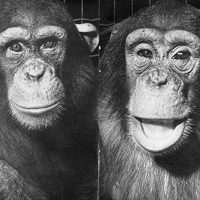









コメントを残す