シャルル・ボードレールをめぐって
そんなことからも、ボードレールって親しみやすい詩人だったのね、 なんてことにはまずならない。 なるはずもない。 わかっているとも。 ここに詩集が一冊。 シャルル・ボードレール『悪の華』
 文学・作家・本
文学・作家・本そんなことからも、ボードレールって親しみやすい詩人だったのね、 なんてことにはまずならない。 なるはずもない。 わかっているとも。 ここに詩集が一冊。 シャルル・ボードレール『悪の華』
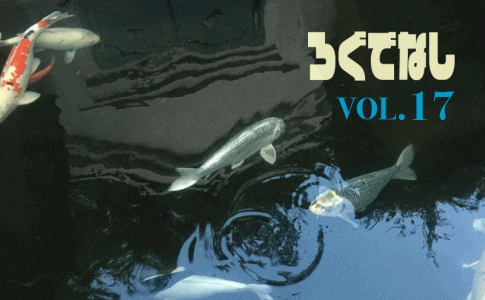 特集
特集細野晴臣、というか、はっぴいえんどの名曲「風を集めて」にあるように ぼくはひたすらに風を集める。 そして、大空を駆けたいのです。 何人にも侵害されることのないぼくだけの世界で、 ぼくは風に棲まう自由な魂たちと交感することが歓びなのだ。 そんなわけで、まだ間に合う、風を感じることに特化して ここに特集を組んでみよう。
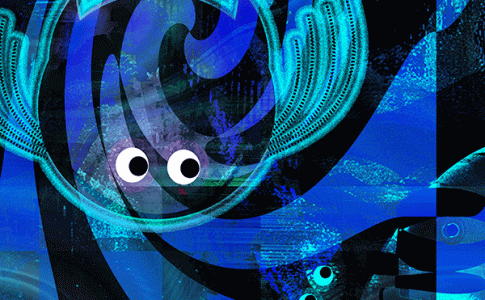 音楽
音楽この麗しき季節の風のなかに、ポエジーを感じるということ、 すなわち、それを体現した音、あるいは音楽を聞き分ける耳をもつことだといいたいだけだ。 あれこれ、小難しいことはさておき、軽くそんな音楽に聞き耳を立てたい。
 映画・俳優
映画・俳優誰にだってどうしても忘れられない、そして外せない映画というものがある。 といえば、そのなかに『小さな恋のメロディ』をあげぬわけにはいかない。 そう、ちょうど、メロディが金魚を公共の水場に解き放って眺めるシーンのように、 ただただその光景を眺めてみていたいのだ。 蓮華の花咲く野原を、どこまでも手押しトロッコで 地平線に向かって遠のいてゆくあのラストシーン。 そんな二人の姿を、ずっとずっと見ていたかったのだ。 そこは理屈じゃないのである
 映画・俳優
映画・俳優ベトナム幻想、未だ醒めやらず ベトナム料理は好きで何度か口にしたことはあるけれどベトナムという国へは一度も行ったことはないし、知り合いがいるわけでもないのになぜだか、なんども足を運んでいるような気がしている。あのベトナム...
 映画・俳優
映画・俳優そうした緊張感を絶えず観る側にさえ強いるほど、 ある意味固有で雄弁なる映画である。 が、以前には見られなかったファンタジックで、 より意識的なフィクション空間がそこにあり、 子供というファクターを通じて 新しい物語に行き着いた監督自身の境地が 垣間見れるような気がした。
 映画・俳優
映画・俳優当時、小津安二郎を心の師と考えていたヴェンダースにとっては まさにフィリップ・ヴィンターとアリスの関係は 限定的ではあるが運命共同体、 つまりは擬似家族として、旅を通して絆を深めてゆくことになる。
 映画・俳優
映画・俳優ヴェンダースの『都会のアリス』が ボクダノビッチの『ペーパームーン』にあまりに類似しているというので 脚本の修正を余儀なくされたという事実は知っている。 いみじくもどちらも1973年の映画である。 一方がヨーロッパ、一方がアメリカという違いはある。
 映画・俳優
映画・俳優なんといっていいのか、こんな映画があるのだという思い。 それも全く意識していなかったイランからの贈り物。 イランという国が急に身近になった。 キアロスタミはそれ以後、巨匠の風格を醸し 我が国でもそのスタイルに魅せられ、多くの人に支持された監督である。 残念ながら、3年前の2016年にすでに他界しているが その残された作品は今尚みずみずしい輝きに満ちている。 キアロスタミでなければ撮れない映画ばかりが 燦然と残されている。
 映画・俳優
映画・俳優こどもはたから。こどもはちから。羽ばたけわんぱくこどもどもの詩 原題は『L’ ARGENT DE POCHE(おこづかい)』なのに、なぜか邦題が『トリュフォーの思春期』・・・このいかにも、な興行の経緯が気には...

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ
住所
123 Main Street
New York, NY 10001
営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日: 11:00 AM – 3:00 PM
