肉を縛って、心を放つ、男と女のリビドー道巡り
「官能」というテーマから考えていくと
必ずぶち当たるのが、倒錯の美意識である。
ここでは、単刀直入にSM映画といってしまおう。
かの団鬼六氏によるSM作品の原点にある『花と蛇』は
企画としてまんまとヒットし、
以後、手を替え品を替え、その花たる女優を取っ替え引っ替えしながら
現代にまで、引き継がれているテーマである。
裏文化ながらも、マニアたちにとって、奥深く
これほど甘美な世界はないのだ。
その原点は、「ポルノ度」の極めて高い小沼勝の手によって
換骨奪胎された、この『花と蛇』によって始まったと言えようか。
日活ロマンポルノ界のマリリン・モンローと言わしめた
谷ナオミとのコンビによって
薄暗い渦中にも、堂々陽の目を見た重要な作品である。
この『花と蛇』を見て、谷ナオミに胸をときめかせたという、
今や中年以降であるはずの紳士たちも多かろうと思う。
あるいは、その筋の道に引き込まれたマニアもまた
少なからずいるのであろう。
自分の経験値だけでは、まず、このSM的境地
倒錯の美を推し量れるだけのものは何もない。
ひたすら、文学や映画程度で知った浅い知識を元に
いっぱしのマニアに肩を並べようなどとは
つゆほども思っていないが、
実際の光景を目の当たりにすれば
やはり、自分自身の見聞の甘さを露呈するばかりである。
何しろ、フィジカルに理解することができないのだから、
全ては想像の域を出ないものであり、
言ってみれば、脳内エロスの戯れに過ぎないのだ。
しかし、その映像の世界に身を投げてみることなら
臆することなくできてしまうのだ。
それはもはや本能と言っても過言ではない。
ズバリ、自分にとっては『花と蛇』への関心は、まずそこに尽きる。
これは映画的快楽に他ならないのだと。
いや、そうして目を丸くして、時に顔を引きつらせ、
時に頬を緩ませ、身を乗り出しながらと、
せわしなく心も身もかき乱されながらも、
この『花と蛇』の住人になってしまった以上後戻りはできない。
SM映画というものも、案外面白いものじゃなかろうか、
とさえ思えるようにはなってはいるのだ。
少なくとも、この映画はその入り口として、開かれている。
そして、この小沼VS谷ラインによる禁断の世界に
目が釘漬けになってしまったのは、その世界が眩しいからである。
ただし、田中陽造の脚本に、小沼勝が辣腕をふるった演出からは、
次の『生贄夫人』での、恐ろしく追求され、
鬼と化した官能の驚愕ほどには至っておらず、
谷ナオミの甘美さにうっとりしながらも、
ただ一言、SM映画という枠では収まりきれない、
映画的な面白さだけを抽出する他ないのだ。
だから、間違ってもSM映画を得意に語るつもりなどないのである。
その点においては、同じSMと一言で言っても
サド文学に挑んだ、神代辰巳の『女地獄 森は濡れた』の方が
よほど問題作であり、厄介な作品なのである。
まずはこの『花と蛇』が、マザーコンプレックスの男
片桐のトラウマに始まっており、
そのいびつな過去がSM的流れにのっかった形で進行してゆく。
幼い頃見た母親と黒人ジミーの淫らな姿が、
真の男性化を妨げていたのである。
そのあたり、いささかも深刻さがないのである。
しかし、このようなトラウマを背負いながら、
息子は静子という女の調教を通じ、次第にSMに目覚めると同時に
自らの精神的母親殺しにも目覚め、
幼きコンプレックスから解放されるに至る。
そして、自らの性的不能までをも克服するのである。
全ては母親の仕組んだ罠だったのだと知った息子の成長過程に
たまたまSMという禁断の治療があった、そういうことなのである。
同時に、あれほどまでに貞操的、淑女っぷりに
身構えていた他者たる社長夫人静子が、
みるみるうちに官能の波に飲見込まれてゆく様子は
愛玩動物のごとく愛おしさをましてゆく。
坂本長利演ずる変態社長の命令によって、
半ば強引に飼育を仰せつかったことを利用し、
この貴婦人を淫美な世界へと落とし込んでゆく過程の、
すなわち調教の儀が実に面白い。
竹による足枷状態の静子を、母親がしゃしゃり出て浣腸するシーン。
その凄まじい効果音によって、この陵辱シーンが
実にコミカルに、実に戯画チックに描き出されているのだ。
あるいは、吊し上げた女体の股間にとろろを塗り込んで、
痒みで、身悶えさせるというようなシーンも挿入される。
この時の谷ナオミのなんとも言えぬ煩悶ぶりがエロスだというなら、
確かに官能的ではあるが、まさに人間生理の
生々しい現場の再現に反して、コントのごとく味わうことができる。
それにしても、このSM観音像の苦悶の表情は、あまりにも人間的だ。
この世の苦しみを一身に受けた眼差し。
それは同時に、美しく、甘美だ。
そうやって次第に行為が日常化し、
静子はかつてのように、変態夫のもとに自ら戻ってゆく。
しかし、一旦その快楽に目覚めた女は、
もはやかつての貞操観念に縛られた女ではない。
このことが重要なのだ。
そして、そんな女に仕立て上げた片桐にとっては、
離れらがたいファムファタルとしての存在に最後まで付いてゆく。
つまり、すでに母親にとって変わる存在なのである。
かくも女とは不思議な生き物だ。
男から見れば、神秘と言っても、謎と言っても構わないが、
どれほどSMという快楽に精通しようが、
女のフィジカルを理解できる男など、この世にはいない気がする。
それをひたすら追い求める変態の夫や、トラウマを抱えた男に
「男ってかわいいわ」などと呟く女の恐ろしさを真に理解しているとは思えない。
まさしく蛇の化身によって調教されているのは、男たちの方なのだ。
一体、SMの魅力とはなんだろうか?
考えれば考えるほどに、泥沼に落ちてゆきそうだ。
相手を自分のいうままに調教する側と調教される側が真っ二つに別れるわけだが、
そこは文字通り理想の夫婦のように一体化し、
お互いの欲望を満足させることで成立する、
言うなれば、一見すれば相互扶助のようにも思えてくるが、
門外漢には、理解するには難しい。
小沼勝の場合は、まさに、一度手離れした女が
調教の果に、男の元に帰ってくるという
男のロマンさえが描きこまれているが、それもまた幻想であり、妄想なのだ。
それはむしろ、男のロマンチシズムの反映であり、
そうした絵空事を映画の虚構の中で、
エロティシズムとエンターテイメントの間で
ゆらゆら揺らめきながら、最後は、
本能の帰結として、手の内に戻ってくる様を描き出す所に
匠の術があるのだと確信する。
しかしながら、原作者である団鬼六氏は
この映画の脚本にすこぶる不満を示したという。
なるほど、わからないでもないのだが、
団鬼六的世界からほど遠いSMの世界とは、一体なんなのだろうか?
興味は尽きないが、原作もまだ未読の身で、
そんな深いテーマを簡単に導き出せる自信は全くない。
少なくとも『花と蛇』に漂う官能性が
どこか楽観的なまでに、喜劇性にも助けられた映画的快楽のおかげで
実に滑稽じみた、人間の性の生々しさであるにも関わらず
その営みに、卑猥さやいかがわしさというもの以上に
むしろ、哀れな動物の習性のようにさえ思えてくるのだから、
やはり、SMという行為に、並並ならぬ思いを掲げる人間にとって
物足りない思いに駆られるのは必然なのかもしれない。
Lou Reed – Vicious
『花と蛇』に匹敵する音楽を探し出すには少々骨が折れる。単に倒錯的かつ官能的であればいいというものでもない。もっとも、そんなゲームに頭を悩ませる時間はもったいない。ならば、ルー・リードの『TRANSFORMER』の一曲目を飾る「VICIOUS」はいかがだろうか? 文字通り「悪意」のある毒のある、痙攣的な音が聞こえてくる。こちらはまさにジャン・ジュネの世界であり、小沼ワールドからは近くて遠い気もする。ミック・ロンソンのピリピリするギターが突き刺さって、まさに「花で打たれる」気分を味わうことになる。ベルヴェット・アンダーグラウンドを離れたルーが、まだとんがっていた頃、血気盛んなロックンロールをやっていた頃の音であり、歌である。男と女ならぬ、男と男の鬩ぎ合い。ボウイがプロデュースしたルーの3rdアルバムに渦巻く倒錯的なムードがたまらない。






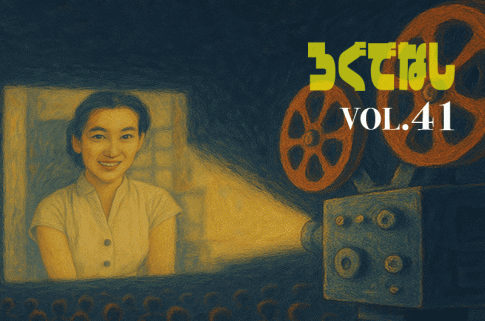






コメントを残す