憧れのデ・ボ・ラ姉さん
特技というほどのことじゃないけど
僕には、だいたい相手の兄弟構成を
直感的に嗅ぎ分ける、そんな能力があるように思う
男性に限りだけど、お姉さんがいるかどうか
ということならだいたいわかる。
その際には、ほぼ仲良くなれるのが不思議なところで、
なんらかの傾向が合致するのかもしれない。
まだ何にも目覚めていないような中学生の頃、
日本でもいろんなアイドルたちが
入れ替わり立ち代わり現れたけど
あんまり興味の対象じゃなかった。
そんな僕が毎日のように聞いていたバンドがブロンディで
その紅一点だったのがボーカルのデボラ・ハリーで
思春期における憧れの女性像の一人だった。
リアルな女性としてのタイプでもなんでもなかった
縁もゆかりもない、海の向こうのかなり年上のブロンド女
デビー(デビューした時は三十路を超えていた)のことが
どうしてあの頃、あんなにも好きだったのか、
色々考え初めてわかったことがある。
それはおそらく憧れの対象というような
そんな甘ったるいものではなくって
いうなれば世間なれしない弟にとっての
優しい姉貴のような存在だったような気がするってことだ。
気恥ずかしくもちょっと青臭い話になるんだけれど。
身近にいて、夏休みのたんびにイメチェンしてゆく
そんな活発な姉貴を横目で見ながら
奥手な自分もドキドキしながら成長していく、
まさにそんな感じだったという気がしている。
デボラ・ハリーはその唇に保険をかけていたぐらい、
セックスシンボル的イメージが強かったけれど
少なくとも自分にとってはそういう対象じゃなかった。
ブロンドでド派手なメイクをしようが
時に蓮っ葉な街角女風だったり
スケスケのドレスやパンチラで挑発しようが
コケティッシュで小悪魔風だったり
モンロー風お色気路線で妖艶に振る舞おうが、
パンキッシュにシャウトしようが、
男の子のようにいたずらっぽくも
どこか骨太、太っ腹で、
本当は心優しい面倒見の良さそうな姉御肌として
惹かれていたんだと思うな。
日本でいうと、さしずめ風吹ジュンや高橋恵子、
あるいは梶芽衣子あたりに該当するんじゃないかな。
同性の視点はわからないけれど
かっこいい憧れのお姉さんという感じとは違った。
だから姉と弟のような関係性といえば
なんとなく収まりが良いと思う。
そもそも、デボラって人は、
可愛いとか美人とか、若いとか年増だとか、
様々なアメリカンモードのイメージのなかで、
当時はファッションリーダー的な存在だった。
でも、仮にも弟の立場にすれば
そんなことはどうでもよくって、
というか、そういうモードの世界に疎くって
ただ傍にいてくれさえすれば心強い、っていう
そんな支柱のような存在だったような気がするのだ。
だけどブロンディの曲が大好きだったのは本当だ。
ひとえに曲が良かったのだと思う。
おかげでこちらの耳も肥えていった。
出始めこそ、ニューヨークパンクというふれ込みだったけど、
ロック、レゲエ、ディスコ、オールディズ、ラップに至るまで
とにかく何にでも果敢にチャレンジするそんな活発さが魅力だったし
なかなかご機嫌なアメリカンポップチューンは
いわゆるアメリカっぽい安っぽさというものが一切なく
そのうえでてクールでキャッチーなサウンドだったから。
だから、僕はブロンディを
ニューウェイブのバンドとしてひとくくりに聴いていた気がする。
実際にブロンディ人気は、
アメリカよりメッカイギリスで火がついたのである。
いまでも好きな曲はいっぱいある。
驚くほど古さを感じさせない。
特に4thアルバムの『Eat to the beat』が好きで、
「Union City Blue」や「Shayla」を聴くと
いまでも当時の青春が甦ってくる。
なかなかの名盤だと思う。
続く『Autoamerican』では、さらに実験性が加味され
そう『夢見るNo.1』が大ヒットしたアルバムで
発売と同時にレコードを買って
実によくきいていた一枚だ。
ともかくデビーの歌が大好きだったのである。
だから、意味もわからず、
「Die Young Stay Pretty」や「Atomic」「Call me」など
歌詞カードとにらめっこしながら歌詞を覚えて
構内でブロンディの曲を口ずさんでいると
当時学校にいた外国人英語教師にへんな顔をされたのを覚えている。
おかげで、英語の成績が一気に伸びたものもデビーのおかげだ。
最近の傾向はちょっとわからないけれど、
フレデリック・ワイズマンのドキュメンタリー映画
『モデル』を観ていたら、
当時七十年代後半あたりは、
自由大国アメリカでさえかなり封建的なシステムが
すっかりできあがっているのがよくわかる。
エージェンシーに売り込みにくるモデル志望の女の子が
身長170cmに1cmとどかないというそれだけで
はねられてしまうシーンである。
身長170cmに満たないモデルは、
可愛かろうが、ファッショナブルだろうが
容赦無く門前払いを食らったというのである。
つまり、モデルは大きくないと価値がない、
というわけなんだな。
もちろん、ファッションショー用の洋服というものが
そうした小柄な人を対象としていない、
という事もあるのだろうか。
しかし、個性を競うファッションの世界で
たかだか背の高さで全てが決まってしまうなんて
夢も希望もない話じゃないか。
そんな閉塞的なシーンに歯向かうようにして
あの頃のデビーはファッションアイコンとしても尖っていたし
その後のマドンナなんかの先駆的存在として
カリスマ性は衰えしらずである。
デビーはスタイルだってそんなによくはないし
ちょうど160cmぐらいの日本人体系で
アメリカ人にすれば小柄だで
どこか親しみやすさがあったのも手伝って
好感をもったのかもしれない。
それにブロンディの楽曲はもともと、
どこかアメリカン的なロックとちょっと違っていた。
ギターでリーダーだったクリス・ステインのセンスが
多分に反映されているからだと思う。
クリスはビジュアルアートの学生で
ストリートで写真をとっていた頃に
デビーと知り合って意気投合し、ブロンディを結成。
曲が売れた時も、世間はデボラ・ハリーあってのバンド
というレッテルを貼りたがったが
デビーは反対に断固としてバンドにこだわった。
そういうところで、マイク・チャップマンとは正反対なほど
全然高慢さがない人だった。
実際に、人気絶頂時に白血病という
重病に苛まれたクリスを看護するために
彼女はバンド解散の道を選ぶような情動を持った人だ。
そんなデビーのカッコいい姉御っぷりを本能的に嗅ぎ分けて
親しみを感じていたんだと思う。
EAT TO THE BEAT
プロデューサー、豪腕マイク・チャップマンの手腕も大きく
前作の『Parallel Lines』がすでに全米でトップ10を飾るヒットアルバムで
その地位をいよいよゆるぎのないものにしたのがこのアルバム。
これが間違いなく、ブロンディの最高傑作だと思う。
とにかく、お得意のストリートパンクチューンから
ディスコ、レゲエ、バラードなんでもございの
すぐれたポップな楽曲が、いろとりどりで素晴らしいのだ。
僕個人にとっても、このアルバムによって洋楽への道がひらけた
実に、思入れのある一枚なのだ。
僕はまだ一度もニューヨークという場所にいったことはないけど、
どこかで、ブロンディのなかのニューヨークへの憧れのようなものがあって
それだけで長年夢見るように生きてきたような気がしている。
つまりそれが「Union City Blue」だ。









![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)
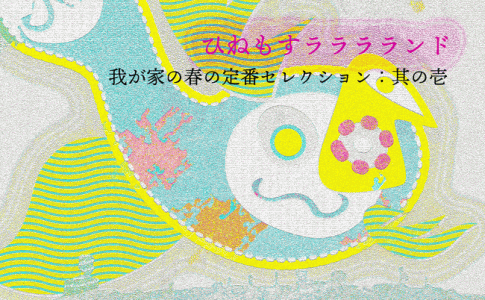

コメントを残す