ロックという大海をめぐるジャパンにまつわる東方見聞録
ひとことでロックというジャンルは、語れない。
とてつもなく広い、大海のようなものだからだ。
時代とともに、これだけジャンルレスでカオスな音楽大系が出来上がると、
一体、何がロックで何がロックでないのかなんて考え始めても、
ラチがあくはずもない。
もちろん、ポミュラーミュージック(大衆音楽)のなかから発祥し
進化をとげたロックンロールが、ロックへと変遷して、
そこからは枝分れ式にポップミュージックという
広漠な母体に再度吸収され、常に多様化し続けているのが、
“ロック”と呼ばれるものの総称だ、
ってことぐらいには、なんとかたどり着く。
たとえば、チャック・ベリーのロックンロールと、
セックス・ピストルズのパンクロックとは、
それこそバターとマーガリンぐらいは違っている。
それに、エレクトロニクスが主体だからロックではない、
とか、ファンキーだからロックンロールではない、
といったようなそんな不毛な論争もいらない。
同時にファッションでもあったパンクが、
社会を反映した個人の生き方でもあったから、
ムーブメント付きの社会現象の一環として捉えることには抵抗はないし、
そこでロックの親戚ぐらいに捉え直したところで、
目くじらたてることではないと思う。
何からはじめても、絶えずこのロックという概念には
物言いがついてきてしまうのだ。
セックス・ピストルズを解散させた直後、
「ロックは死んだ」という名言を発した
ジョニー・ロットン改めジョン・ライドンの発言の真髄は理解できる。、
だが、乗り換えた次船『Public Image』号が、
当時どれほどの衝撃であったかを語るのは、
そんなに難しいことではないにしても、今あらためて聴くと、
PILのファーストにしたところで、
やはり“ロック”であることに何ら変わりはないのである。
ロックを否定し出来上がったものが、所詮ロックであるなら、
ライドン氏は大いに嘘つき呼ばわりされていいのだが、
次に出た『Metal Box』や『Flowers of Romance』には、
完全にロック幻想とやらからは、自由に解き放たれ、
その他あまたのニューウェーブの洗礼とともに、
歓喜の宴の始まりで胸が昂ったものであった。
ロックと呼んでしまうには違和感がある、
そんな音楽というのは確かに存在する。
だがしかし、それもまたロックの自在性のなかでは、
ロックと呼んでもニューウェーブと呼んでも、
ポストロックと呼んでも、オルタネイティブと呼んでも、
そんなことにあまり意味は見いだせはしない。
ロックという概念については、この辺で置いておこう。
そんな70年代後半から80年代初頭にかけてのロックムーブメントというのは、
PILのような、ロックを解体したニューウェーブが、
あれやこれや闊歩した百花繚乱の時代である。
とりわけ、イギリスという国は、ニューウェーブのメッカというにふさわしい
先鋭的な脱ロックバンドでひしめいていた。
そのクリエイティブなバリエーションは、
今でも通用する様々な個性を誇示し、栄華を誇っていたものだ。
それらは、従来のプログレやカンタベリー、
ホワイトソウルやレゲエなどと言った既成のジャンルの上に、
様々なエッセンスを取り入れ、
ネオアコやらダブやらスカやらアシッドやらガレージ、
ゴシックロマンやらエレクトリック、テクノなど
次々と新しいムーブメントを巻き起こし、
枚挙にいとまがないほどの多様性のなかで、
各々が80年代に跋扈し、90年代を生き延び、
2000年以後もさらなる進化を続けているといえる。
イギリス人なのになぜかジャパン、その不思議な出世劇について
さて、ここでようやく本題に入ろう。
そこにジャパンという、真可不思議な存在のロックバンドがあった。
リーダーであったデヴィッド・シルヴィアンは、
かつて“世界で一番美しい男”と称されるほどに眩しい存在であり、
その実弟のスティーブ・ジャンセン、
学生時代からの親友ミック・カーン、
同じく校友であったリチャード・バルビエリという
気心の知れた四人で結成されたジャパンは、
その後、広告をツテにやってきたロブ・ディーンを加えた五人で
ポストパンク地において、1978年本格的にデヴューを果たした。
流れは、明らかにニューヨークドールズ風の出で立ちで、
サウンドとしても、デヴィッド・ボウイやT・レックスなどの
グラムロックのエッセンスから強力に影響を受けつつも、
モータウンなんかの黒人音楽風のファンキーなリズムを母体にし、
いかにも文学青年的な難解な散文調の歌詞を、
無理くりに官能的に歌いあげる、と言ったスタイルのシルヴィアンが、
フロントマンとして君臨し、
特定のジャンルに分類するにはちょっとユニークすぎる、
というべきアルバム『Adolescent Sex』にてデビューした。
まさに、いびつなロックである。
そこは、先輩バンドクイーンと同じように、
遠く異国の日本で、まずは火が付いてしまったことが、
のちのバンド運命のカギとなるとは、
当時メンバーの誰一人として考えてはいなかったという。
そのバンド名からして、なんとあざといバンドだろう、
だなんてことは思ってはいけない。
単なる異国情緒的なイメージを勘違いしたロンドンの若者たちによる、
純粋な若気のいたりとして、ジャパンは華々しくデビューしたが、
当初は母国ですら奇異な目で見られ、
まともに取り上げられることすらなかったのだ。
演奏がとりわけ上手いわけでも、曲がとくにキャッチーでもなかったが、
シルヴィアンを筆頭に、その耽美なルックスと奇抜なファッションセンスで、
そのバンド名がもたらした縁とばかりに、
日本の若い女の子たちを中心に話題をさらってしまったのである。
それがいまでは、元祖ヴジュアル系バンドとして、
日本の音楽シーンに対する影響も少なくはないのだから、
ジャパンというバンド名には、不思議な因縁というか、
言霊が宿っていたのかもしれない。
セカンドアルバムまでの活動を、
当人たちはのちに口をそろえて苦々しく回想し、
シルヴィアンに至っては〝ゴミ〟だと吐き捨て、
若気の至りとばかり取り合うのを拒むあたりは、なんとも真面目な彼ららしい。
この『Adolescent Sex』、あるいは『Obscure Alternative』という
初期二枚のアルバムは、当人たちの思いをよそに、
今では逆説的に評価されたり、そのサウンドゆえの
コアなファンがいたりするのが面白い。
確かに、そのサウンドは何かに影響は受けつつも、
独自のサウンドを発信していこうという
強い意志のようなものは見うけられる。
おそらくは、ボーカルのシルヴィアンの歌い方への好み、
あるいは英語を母国語とするかしないかによって、
受け止める感想も違ってくるのだろう。
だが、この直後、ジョルジュオ・モロダーをプロデューサーに迎えて
制作したシングル「Life in Tokyo」あたりから
徐々に変化がはじまり、三作目『Quiet Life』あたりには、
ロキシー・ミュージックの影響下にある
英国伝統のエレガンスを身にまとった、
ロックとエレクトロニクスの融合へと方向性を高め、
より洗練された音と風格とを武器に、
イギリス国内においても、めきめき頭角を現しはじめることになる。
その後は、日本が誇るYMOのメンバーとの交流なども経て、
まさに蛹から蝶に脱皮を成し遂げるかのように、
気がつけば個々メンバーの個性もすっかり確立され、
このあたりからは、他のアーティストとの交流も活発になり、
名実共に頂点を迎えることになる。
その間の活動はわずか四年ほどで、あっけなく終焉を迎えるのだが、
彼らは、最後にひとつの奇跡のようなアルバムを発表する。
フォルカー・シュレンドルフの映画と同名のタイトル『ブリキの太鼓』だ。
まさに東洋的な音階や複雑なリズムを駆使した
エレクトリックポップの金字塔と呼んで良い名盤だろう。
ドラムスのスティーブ・ジャンセンの正確無比な卓越したドラミング、
超個性的なミック・カーンのフレットレスベース、
リチャード・バルビエリのアルチザンよろしく
幽玄の美を感じさせるシンセの音色をバックに、
デヴィッド・シルヴィアンのあのゴージャスで魅惑的な声と、
内省的な歌詞の歌がのっかったアルバムは、
時代の空気に左右されることのない、
今なおも古びることのない唯一無二のサウンドが構築されている。
彼らにとっての最高傑作が、
いみじくも実質わずか四年ほどでの解散と結びついてしまったことは、
ロック史においては惜しい出来事ではあったが、
同時に始まった個々のソロ活動を経て、彼らの歴史を振り返ってみることは
現在では、各々がそのあくなき活動を地道に継続していることからも、
実に感慨深いものがある。
外観はどうみてもあのニューヨーク・ドールズのまねごとにすぎない、
ロンドンの若者たちとしてデヴュー後、
長い遍歴のはてには、巨大なロックビジネスには当てはまらない、
実験的かつ先鋭的な音楽家への道へと進化していった過程を見ると、
それこそは、ワガチから、イナダ、ハマチ、ブリへと名前を変え、
立派に変貌を遂げる、どこかあの出世魚を連想させるのだ。
まさに出世バンドと呼びたくなるような見事な変貌ぶりを見せたのが、
このジャパンというバンドの不可思議な魅力ではないだろうか。
「あの頃の僕らと今の僕らを並べてみても誰も信じないだろうね」
とシルヴィアンは回想する。
確かに、妖しいまでのメイキャップに身を包んだ、二十歳そこそこの彼らと、
デレク・ベイリーと言った実験的な音楽家たちや、
ロバート・フリップ、ボルガー・シューカイと言ったロック界の重鎮たちと
肩を並べて渡り合うアフターシルヴィアンとを比べても、
同じ土俵では語り尽くせないほどの衝撃がある。
とりわけ、このデヴィッド・シルヴィアンがたどった道のりは、
常にポップミュージックとのアーティスティックな表現者の狭間にいて
ややもすれば、他の追随を許さない
求道者の域にも達してしまったかのような存在で、
重みのある作品を発表しつづけている。
1990年には、『Rain Tree Crow』名義での再結成を試みたが、
単発で消滅してしまった。
シルヴィアンとそれ以外のメンバーとの間に生じた軋轢、溝は深く、
以後修復されることはなかった。
残念ながら、その盟友のミック・カーンは
2011年にすでに癌で他界してしまっている。
あの強烈な個性同士のコンビネーションを再現できないのだから、
ジャパンの再結成はもはやありえないのだが、
それでも個々の活動は、その根底では繋がっており、
再結成とまではいかなくとも、なんらかのカタチで
再び同じステージに揃った姿を見せていただきたいものである。
ジャパンをこよなく理解するための10枚のガイドアルバム+おまけ
NewYork Dolls: NewYork Dolls
当人たちは当時完全否定していたようだが、ケバケバした女装ファッションでデビューした、当時のイメージ、ビジュアルはあきらかに、ドールズの影響下にあったのは間違いないところ。なんたって、ボーカルがデヴィッド・ヨハンセン、ギターがシルヴェイン・シルヴェインだからね。
Quiet Life: Japan
プロデューサーにロキシー・ミュージックのジョン・パンターを迎えての3rdアルバム。
洗練されたエレクトロニックミュージックを展開し、まさにヨーロピアンな香り高きアルバムは、ジャパンの最初の転換期であり名実共にイギリス国内でも認知され始めた記念すべき代表作となった。
Dance: Gary Newman
ジャパンのメンバーで、一番最初に対外的セッションの道を始めたのが、ベースのミック・カーンであった。
ジャパン色が色濃く反映されたゲイリーニューマン名義のファーストソロアルバム。
ゲイリー自身がジャパンのファンで、ジャパンの日本でのツアーにまで追っかけできていたんだとか。
Tin Drum: Japan
ジャパンのラストスタジオアルバムにしてエレクトロニックポップの傑作となった本作。
地味な名曲「Ghosts」はイギリスのヒットチャートで5位に記録されるほどヒットした。
Technodelic:YMO
日本のミュージシャンとの交流も盛んに行われ、とりわけメンバーがリスペクトしていたのがYMOで、この辺りは相互間での影響が見え隠れするほど蜜月期を迎えていた。
ジャパンの『ブリキの太鼓』には明らか影響を及ぼしているのが伺える。
RIO:Duran Duran
ニューロマンチックムーブメント隆盛期のイギリスで、当時ジャパンが与えた影響は大きく、数々のフォロアーを生んだ。
なかでもデュラン・デュランはジャパンをリスペクトし強く意識していたバンドで、ビジュアル的にもサウンド的にも影響が窺い知れる。
The Brilliant Trees:David Sylvian
ジャパン解散後、シルヴィアンの方向性は脱ジャパン。
エレクトロニクスミュージックから、アダルトなコンテンポラリーミュージックへの転換を果たした記念すべき第一弾。
シルヴィアンの新たな航海がここに始まった。
坂本龍一のサポートが以後のソロ活動に及ぼした影響は小さくない。
Catch the Fall:The Dolphin Brothers
ジャパン解散後、メンバー間で最初に結びついたのが、
ドラムスのスティーブとキーボードのリチャードのドルフィンブラザース名義のユニットで、ジャパンやシルヴィアンのソロ的雰囲気は踏襲されてはいるが、
ポップでキャッチーなトラックも多く、スティーブ・ジャンセンの兄譲りのボーカルが堪能できるアルバム。
Rain Tree Crow:Rain Tree Crow
解散後、実質的な再結成アルバムだが、シルヴィアンがジャパン名義を断固拒否。シルヴィアンソロの延長上にはあるサウンドではあるが、新たに持ち込んだインプロビゼーション的アプローチは新鮮。ただし、結局はバンド内力学は変わらず、この一枚をもって再び空中分解を余儀なくさせられる。
ISM:JBK
デヴィッド・シルヴィアン抜きのジャパンの面子3人で結成、
活動してたのがこのJBK(Jansen ,Barbieri, Karnの頭文字をとったバンド)。
実験的だが、この辺りになると、それぞれがミュージシャンとして、職人的なまでの腕前を身につけているのが窺い知れる。
LIFE IN TOKYO-a tribute to Japan : オムニバス
ジャパンがいかに日本のミュージシャンに影響を与え、愛されていたかが窺い知れるトリビュートアルバム。ワールドワイドではなく、日本から発信されたところに、ジャパンというバンドの因縁を感じずにはいられない。
追加で挙げる以下二枚のアルバムは、ジャパン以降の活動においても、デヴィッド・シルヴィアンというひとりの音楽家が、まさに、ロックやポップミュージックの領域を押し広げ、新たなステージに向かっている、重要なミュージシャンとして記憶されることになるだろうことを証明するアルバムであると思う。
The First Day:David Sylvian & Robert Fripp
デヴュー当時からリスペクトしていた大御所ミュージシャン、ロバート・ フリップとのプロジェクトが具現化。アート志向強かったシルヴィアンが一転、ジャパンがかつてロックバンドであったことを思いださせてくるほど、ロックに回帰したアルバム。しかもあのジャパンのデヴィッド・シルヴィアンが、新生クリムゾンのボーカルに? そんな話もあったらしいが、本人が断ったらしい。ポストジャパンのなかでも、ロック界に名実共にその存在感を示したアルバムといえるかもしれない。
Blemish:David Sylvian
シルヴィアンのソロアルバムのなかでもとりわけ実験性の強いアルバム。 『The First Day』同様、これがあのジャパンにいたシルヴィアンかと思わせるほどの衝撃がある。即興演奏家デレク・ベイリーを迎え、 先鋭的なクリスチャン・フェネスとのエレクトロニックサウンドを融合し、 そこに歌の載せる、というあまりにも大胆な試みに出た唯一無二なサウンドは、まさに他に比較しうるものがないほどの傑作であり、問題作である。思えば遠くにきたものだ、まさにそんなアルバムである。










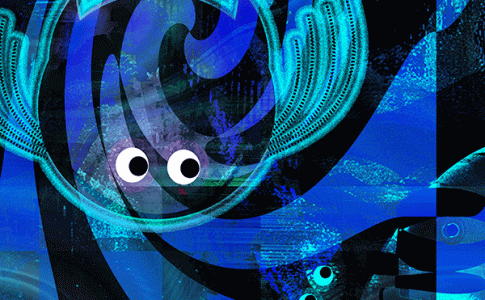


コメントを残す