妄想転じて、禁断の趣味への序奏を奏でよう
世の中には女装癖という、言うなれば禁断の趣味がある。
特殊な環境に身を置かぬ限り、
嫌悪され、唾棄されることも多いと思われる。
一般的には女による男装趣味よりも圧倒的嗜好者の数だと思われるが
それだけ華があるからだろう。
自分はこれまで女装をしたことはないが、
別段嫌悪するまでのこともなかろうと考える人間である。
この先、ますます老いさらばえてゆく現実の前に
今更わざわざ醜態を晒したいとは思わないが、
それでも機会があればやってみたくなくもない。
女達だけの特権、日常を侵食してみたい欲望は
男のうちに無意識にあるものかもしれないのだ。
無論、興味本位からではあるが、
趣味おいて、他者に迷惑をかけるわけでもないことには、
何も目くじらを立てるつもりもないだけであり、
あえてそのような労力を使ってまで
欲望に忠実になるほど、求めてはいないだけのことだ。
どちらかといえば女装趣味、というよりも
倒錯的な世界を描いたものに昔から興味をもってきた。
だから、なんとなくわかったような気分になっているだけかもしれない。
高尚な趣味だとも思わないが、
かといって、卑しむべき趣味でもない。
もっとも、美しいものに憧れることや
心ときめかなくなることは、
人として、はたまた男として寂しいことだと思うし、
たとえ、それが悪趣味と言われようが、
倒錯的だと言われようが、
何者かになろうとする変身願望が
たまたま女であるということにすぎず、
常識や道徳を掲げて、杓子定規に
揶揄する側にだけはなりたくはないのだと考える。
そんな気持ちからというわけではないが、
変身願望なら誰よりも強くもっている気がしているし、
妄想癖は日頃から人一番ある方だと自覚するがゆえに、
なれるのであれば、誰か別の人間、
あるいは擬態昆虫のように自然の一部にでもなってみたい、
などと妄想することはよくあることである。
ただし、ヒーローになって世直しをしたいだとか、
江戸川乱歩の「人間椅子」のような奇天烈な発想はない。
人の視線や評価を必要以上に求める気持ちなど皆目ないのだ。
そうした何か大義名分にかられて変貌するような野暮は
どこにも持ち合わせていない。
どこまでも己の趣味の世界に徹するだけの、
純粋な倒錯にのみ、共感をもつだけである。
今、手元にある一冊の写真集を眺めている。
森村泰昌による『全女優』というタイトルの
それこそ、究極の女装写真集である。
ドヌーブ、ヘップバーン、モンロー、ガルボ ・・・
そんじょそこらにいる佳人とは比べようのないオーラを放つ美の化身達。
大胆にそんな美のアイコン達になりすましてしまう氏の技は
もはや芸術を超えた忍術の域である。
よって、当然趣味の世界という偏狭な枠組みのみで語るつもりはない。
また、芸術という高みにわざわざ同行する意思もない。
ここに、わざわざ美を見出すかどうかはさておき、
眺めていると不思議な高揚感が湧いてくる。
自分ができないことを、目の前のアーティストが一人、
可能な限りのアプローチで個々の女優に近づこうとする行為。
その行為は実に圧巻であり、神々しい。
審美を超えた、何物かであり
言葉より先に、網膜がひたすら圧倒される。
なんだろうか、このエネルギーは。
森村氏が単に女装趣味から、このような企画で
写真集を撮りあげた人間ではないことは明らかである。
これまで、歴史上の人物から名作絵画の主人公たちに至るまで
自在になりきってきたこのモダンアートの旗手が
ジェンダーを越え、表現としてその趣向をとるだけのことだ。
そして、なによりも恍惚感にあふれた
純度の高いなりすましぶりに、
こちらもニヤリほくそえんでしまうのだ。
なにやら危険な危うさと純粋な快楽のぎりぎりのはざまに立って
それを眺めている自分もまたその世界の住人とかしている。
ずばり、男と女の違いは、
子供が産める産めないという肉体的な差はあるにしても
通俗的にいうならば、
公に化粧をして許されるか許されないか、ではないかと思う。
ある種の職業的な武装は別として、
白昼堂々この権利に市民権が与えられたという気配は今の所ない。
昨今はテレビをつけてもオネエ芸人などが堂々跋扈する時代で、
かつてのようなあからさまな差別意識は薄まりつつある社会であり、
仮に、来たる将来、男もまた堂々メイクを施しても
なんの違和感もない時代がやがて来ると仮定しよう。
それはそれだと言い放ちたいところだが
自分はそれを特に願ってはいない。
やはり、なんでもかんでも自由気ままに
己が欲望に忠実に生きる世の中がいいとは思わないからだ。
そうした社会がどう考えても機能的に受け入れられるわけでもないだろうし、
やはり、禁断であるがゆえに、
そうした倒錯趣味の密やかなる快楽を催すのだと
自分は古風に考える人間なのだ。
だからこそ、妄想が妄想として楽しいのである。
その意味では、こうした写真を眺めているだけで
己の欲望はまろやかに昇華されてゆく。
その意味では理性を保てている証しなのかもしれない。
ちなみに、たった一度だけ、
女装する機会に恵まれるとしたら、
誰になりたいだろうか?
そんなことをふと考えてみた。
特定の贔屓があるわけでもなく、
最近の女優、タレントにはまず食指が動かないのだが、
一人だけだと言われると・・・
フェリーニのミューズ、ジュリエッタ・マシーナ演じる
『道』のジェルソミーナの泣き顔。
小津ではなく、所帯じみた成瀬映画のくたびれた原節子もいい。
あるいはグダグダだららだと惰性にひきづられながらも
力強く生きてゆく高峰秀子や
そこれでもかと情念燃ゆる増村映画の若尾文子など、
いやはや、欲望は限りなく無限にあるものだ。
いっそのことピエロや歌舞伎役者でもいいかもしれない。
趣のないハロウイン仮装には食指は動かぬが、
要するに現実から自分を連れ出し、
新たなる別人格へと誘うような変身ができるのであれば
それでいいのかもしれない。
やはり妄想は妄想のままでいいと思う。
あくまで快楽は脳髄のみの快楽で構わない。
なぜなら、自分自身がなくなってしまうような気がするからだ。
せっかく築いた自分の家に戻れなくなってしまうのは悲しい。
何より、安心できる場所は「自分」なのだから。
化粧をすると
私は「私」を抜け出せる
翼やイカズチや、人を石に変える眼差しを持つ怪物になれる化粧がありふれた日課になった人は悲しい
森村泰昌 『全女優』より
化粧が素顔になり下がり
化粧をとると素顔がなくなって
「私」がいなくなるからである
This Masquerade · Leon Russell
女装というかこちらは「仮装」だね。レオン・ラッセルの名盤『CARNEY』収録の「This Masquerade」を聴いて、少しは他人になりすます快楽でも味わってみますか。もっとも、この曲で歌われる世界というのは、仮面を被った人間同士の恋の駆け引きのようなものなのですから、ま、そこはいいとしましょう。この曲はカーペンターズやジョージ・ベンソンにもカバーされている、レオン・ラッセルの隆盛期の代表曲でもあります。










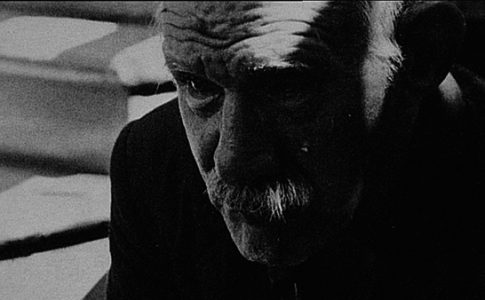


コメントを残す