モノクロからカラーへの天地創造、視線の抽斗
最近、自分が撮りだめたスナップ写真を整理して
一冊の本「On the road」としてまとめた。
あるとき、偶然別の写真家の作品にふれたとき
その触感がなぜか驚くほど似ているかもしれない、と思えたのだ。
それがエルンスト・ハースとの出会いである。
いまさら、でもあるが、いまだからこそ、ともいえる。
ハースは写真家でありながらも、画家としてのエッセンスを醸しており、
その写真が美術の領域にまで通底しているのは明らかである。
そのスタンスに重なる視点を見いだすには、さして時間はかからない。
実際、抽象画と呼んでも良いような写真がいくつもある。
日頃僕自身が取り組んでいる作品に類似するものも随分ある。
ただ、それまで、ハースという名前ぐらいしか知らず
存在が長い間漏れており、
当然、意識することも、影響すらも受けずにきたことが
なんとも不思議な気がするくらい、奇妙な親近感を覚えるのだ。
オーストリア生まれでパリを経由し
アメリカへの移住を選んだハースだが、
その出発点は、決して抽象でも詩でもなく、
第二次世界大戦後のヨーロッパ、難民、社会の現実であることは
この写真家を考えるには避けて通れない入口である。
つまり、彼はフォトジャーナリストとして出発し、
あのマグナム・フォトにも参加しているぐらいだから
ぼくの関心のベクトルとはズレざるを得なかったのかもしれない。
それは、たとえばリー・ミラーとは全く逆のスタンスである。
リーはマン・レイを通じて、ダダ・シュルレアリスムの流れを通じ
関心をもった写真家だったが
晩年にはむしろ戦場カメラマンとして名を馳せ、
その辺りのことは、映画『シビル・ウォー』
あるいは『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』のモデルになったことで
にわかに再認識させられている。
それらはアーティストの本質をめぐる旅なのだ。
写真とは一瞬を切り取るメディアである。
シャッターが切られたその刹那、時間は停止し、
一瞬にして世界は過去形として保存される。
本来、写真とはそうした装置なのだ、と。
しかし、エルンスト・ハースの写真を前にしたとき、
この前提は静かに、しかし決定的に裏切られる思いがした。
なにしろ彼の写真には驚くほど「止まった感じ」がないのである。
むしろ、世界はつねに動詞のまま、ING=現在進行形として、
画面の内外を流れつづけている。
つまり、漂流への意志をはらんだアートなのである。
ハースがそこでモノクロからカラーへ移行したことは、
写真史的には「革新」と呼ばれる。
だがそれは、新しい表現技法を発見したというよりも、
世界の捉え方を移行させたにすぎない。
彼にとって色彩は、象徴でも装飾でもない。
それは、視覚的な快楽を与えるためのものではなく、
むしろ身体感覚を呼び戻すためのガイドたりうるものだ。
ゆえに世界は抽象ではなくなり、
自分の目と手で触れうる、誠実な現実なのだと教えられる。
それは、美にも還元されえない色を絶えず発しており、
「美しい」と言った瞬間に取り逃がしてしまう、危うさを含んだ色だ。
しかも、ハースの写真にはカタチをともなった躍動感を放っている。
その佇まいは、単なるスナップよりも雄弁なのだ。
たとえば、シーンだけが浮かび上がってくるぶれた闘牛。
迷宮の入り口のような真っ赤な薔薇の花びらの接写。
壮大な山風景をバックにしたガラパゴスのシルエット。
火山から噴火する真っ赤な溶岩とその飛沫など。
これら、いわば「色彩の魔術師」と呼ばれるハースのよく知られた写真にみる
ブレ、滲み、色の溶解、それらは失敗でも技巧でもない。
シャッタースピードを遅くすることで、動きそのものを回収する写真が宿すのは、
世界をいったん止めてしまうことへの畏怖そのものであり、
世界がまだ生成の途上にあるという事実への誠実な応答ともいえるのだ。
ここで重要なのは、それでもハースが
「現実を伝える責任」を放棄した人ではないという点であり、
世界はどうなっているのか、
何が起きているのか、
という、常に絶えざる情報の収集家として、記録者として、
そのための有効な道具としてシャッターを切り続けた人だったということである。
写真と絵画、記録と表現、ジャーナリズムとアート、
ハースの全貌を眺めていくと、あえてそのどれかひとつを選ばなかった人であり、
つねに境界線そのものに留まり続けた観察者、かつ表現者だったことがわかる。
だがそれは、曖昧さへの逃避ではなく、
むしろ、曖昧さに耐えるための強度を持った態度だったといえるだろう。
境界に留まるということは、結局何にも回収されないということだ。
まさに漂流者の視点である。
意味にも、ジャンルにも、美にも回収されない。
その代わり、見る者の内部でのみ反応が起きる表現方法。
ぼくがハースへの親近感を超えて感じるのは、まさにそこなのだ。
ハースの写真は、説明を声高に叫ばず
その代わり、その存在を大いにクローズアップさせる。
だが、見る者に問いを投げかけるきっかけを提示し
何かを思い出させてしまう装置なのであり、世界の入り口を意味する。
たとえば最高傑作と呼び声の高い『クリエーション』シリーズにおいて、
ハースはついに社会性や具体的な出来事すら手放している。
そこにあるのは、雲、光、水、色、動き、つまりは
世界が生まれる気配を、文字通り瞬間的にとらえた写真が並ぶ。
ここにはキリスト教の旧約聖書にこだわった宗教的主題が明確に潜んでいるが
世界はまだ完成していない、という感覚の可視化でもある。
世界はつねに生成の途中にあり、
見るという行為そのものだという手触りがある。
だがハースは、写真というメディアを通して、世界を作り替えたりはしない。
世界が作り替わりつづけているという事実を、そのまま引き受けるのだと。
ここで、ひとつの重要な一致を認識した。
偶然性から創作を始める者と、必然性から始めた者が、
最終的に同じ地点に立つことがあるということだ。
ハースは現場と責任から出発し、外周をぐるりと回って、
意味を手放した場所に戻ってきたのだ。
一方で、僕のように、偶然やノイズから始まる感性は、
最初からそこに立っており、
意味は所詮、後追いだと考えるにすぎない。
いうなれば卵が先か、鶏が先か、という問いは、本来意味をなさない。
創造の深部では、少なくとも、
偶然も必然も等価に置かれているということにおいては。
ハースの写真は、一瞬でありながら、決して完了をゆるさない。
過去形ではなく、常に現在進行形。
世界はつねに動いており、意味はまだ固まっていない。
写真が世界を固定するのではなく、
写真が、世界がまだ生きていることを証明してしまうのだ。
その流動性に触れたとき、僕らははじめて理解することになる。
つまり、世界はべつに明確である必要などないのだと。
曖昧さのなかでこそ、人は自分自身の記憶や思考と結びつき、
自分の言葉を勝手に見出すことができる。
こうして、エルンスト・ハースの写真を眺めていると
世界をどう見るか、という態度そのものだということに
改めて感銘を受けるにちがいない。
それは、意味を求めず、美に回収されず、
世界をINGのまま引き受けることという姿勢だ。
それは関心の刷新と好奇心の賜物である。
ここに創造世界、あるいは宇宙の真理があるとすれば、
それこそは「区別しない」という神の視点なのかもしれない。
内と外、偶然と必然、記録と創造。
それらが溶け合った場所で、世界は今日もどこかで生まれつづけている。
ハースの写真は、その事実に触れさせてくれるだろう。
そして同じ感性を持つ者は、時代を越えて、必然的にそこへ立ち会ってしまう。
それは単に鑑賞を超え、影響を離れたところにある同じ視線が、
別の時間、空間に再現されただけなかもしれない。
僕にはまたひとつ、表現の引き出しが増えた思いがしたものだ。
Genesis – A Winter’ s Tale
エルンスト・ハースのことを書いてきたところに、ジェネシスのファースト『From Genesis to Revelation(創世記)』をもってくるのは、いささか安易かもしれない。メンバーはボーカルのピーター・ガブリエル、キーボードのトニー・バンクス、ギターのアンソニー・フィリップス、ベースのマイク・ラザフォードの四人とドラムのクリス・スチュワート。今思うと錚々たるメンツが顔を連ねている。ジェネシスといえば、英国5大プログレッシブ・ロック・バンドの一つとして名高いが、これはどちらかといえば、フォーク・ロック的な作品で、プログレ未満という気配が漂っているアルバムだ。
“In the Beginning” では、旧約聖書『創世記』を下敷きにしながらも、神の声を高らかに宣言などしない。ピーター・ガブリエルの歌声は祈りのようでありながら、どこか距離を保ち、世界を前に立ち尽くす観測者の位置に留まっている。音楽もまた前に進まない。リズムは漂い、構造は固まらず、すべてが未分化のままだ。この感触は、エルンスト・ハースの写真、とりわけ『天地創造(The Creation)』シリーズと驚くほど似ている。ハースの写真にも、やはり、神は現れない。壮大な物語も、明確な意味も提示されない。ただ、光が立ち上がり、色が流れ、世界がまだ分けられていない状態が、そのまま置かれているだけだ。
両者に共通しているのは、創造を語らない強さというべきものだ。創造とは完成ではなく、生成のプロセスそのものだという理解。意味を問いかけず、答えも用意せず、ただ「起きてしまっている状態」に立ち会う。その態度が、音と像のあいだで静かに同調している。その意味で、ジェネシスの『創世記』は神話ではないし、ハースの『天地創造』もまた同じ。どちらも、世界が意味になる直前の、あの震えに立ち会ってしまった記録なのだ。
エルンスト・ハース同様、ぼくはこれまでジェネシスそんなに好んで聴いてこなかった。ただ、いまこのアルバムを聴き直すと、始まりが起きてしまう直前の空気を、そのまま封じ込めた音楽だったんだな、と改めて感じることができるし、長いあいだ「若書き」「失敗作」と呼ばれてきたとはいえ、むしろ新鮮に感じてしまうのだ。このセカンド・シングル「A Winter’ s Tale」などは、アルバム同様、当時大きな反響を呼ぶこともなかった曲だが、トニー・バンクスとピーター・ガブリエルが再びコラボレーションを果たしたという意味でもポップミュージックとしての才能の萌芽が聞こえてくる。プログレを期待すると肩透かしを食うだろうが、まさにバンドとしての“創世記”感が十分に感じられると思う。





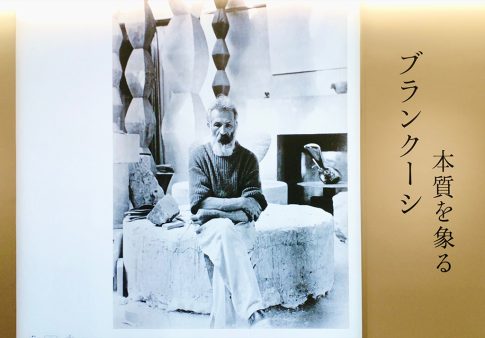







コメントを残す