夢見るアリスは漆黒に佇む
食べ物を粗末にするな、とは
日本人なら、むかしからよくいわれてきたことである。
テレビ番組などで、食べ物を使ってふざけ合うコントのようなシーンを放映すると
必ずクレームが入ったとはよく聴く話。
そうしたモラルの是非はおいておくとして、
それが芸術なら許されるか? という点において、
今回、そこを問題提起したいわけでもなく、
ひたすら、その世界観に魅せられるという想いから、
純粋に、写真家今道子による作品について、触れてみたい。
彼女の作品には「野菜・魚・果実」といった素材が頻出する。
直接の被写体でありながら、《タコ+メロン》や《鮭+鰈+ハイヒール》など、
単に「静物写真」を撮るのではなく、
素材同士を「関係させて構築されたオブジェ」として、
再配置・撮影する手法が特徴的である。
また、彼女の多くの作品がモノクロームであることが重要なのだが、
そのビジュアルインパクトは、実に強烈であり、
詩的好奇心をかきたてずにはいられない
とりわけ、鮮魚の生々しさはグロテクスでさえあるのだが、
色彩を排し、コントラストや質感、光と影の関係で構成されているところに
寓話性がひとりでにあふれだす。
そこに、ぼくはダークアリス的な世界観を読み取るのだ。
この選択によって、「素材そのもの」から余白や「間」を引き出しながら、
見る者の想像力を喚起する余地を残す今道子の写真は
静かに闇の魔力、その魅力をもって立ち上ってくる
ぼくは、そんな彼女の世界観に魅了されるひとりである。
目を背け、排除しようとする生理をも踏み越える禁断の瞬間がある。
色が喚起する即時的な意味を削ぎ、
「形/質感/質量/陰影」のみによって語ろうとする試みは、
中世異端のマニエリスム、アンチンボルドの色彩の魔境に対する美として、
新たな解釈へと誘ってくれるのだ。
彼女の写真が醸す、死せるものへの関心や眼差しは
あきらかにスティルライフ(静物)の一線を越えた異境である。
それは、どこか、ジョエル=ピーター・ウィトキンの世界とも近接するが、
彼女の写真からは、そんなショッキングで宗教的な神話学の匂いは漂ってこない。
純粋なる直感と、実験精神があるだけだ。
そこに遊び心や悪戯心、子供のエロスなどが加算されてゆく。
こうした発想を、彼女はその対象に誰もが手に届く日常から調達し、
それを写真という瞬間の美として捉えるアーティストであるところに
ひたすら親近感が湧く。
ただし、その源泉は、明らかにシュルレアリスム的であり、
彼女が影響を受けたという、澁澤龍彦、種村季弘らが発信してきた
異端の知のイメージを呼び覚ますことになるだろう。
では、具体的に、彼女の作品を挙げてみよう。
「タコ」と「メロン」、この作品名だけでも多層的な《タコ+メロン》での、
生のタコ(あるいは食材としてのタコ)と果実のメロンの組み合わせは、
両者とも“食べられるもの”として、動と静、水生と陸生、
そして動物と植物という対比が浮き上がってくるのだが、
写真にすることで「食材」から「オブジェ」へと変換される瞬間が、
まるで静物画のように、しかし素材の質量・生気が残留しているように見える。
同時に、暗喩的に潜むエロティシズムの刻印。
グロとキッチュの交差がある。
このようなアプローチから、「生きていた/生きていた形跡がある」
「もともと用途があったものが用途を離れて美術物に転化される」といった、
そんなテーマが表層が見るものに臨場感を突きつけてくる。
あるいは、こちらは鮭と鰈に「ハイヒール」という
明らかに“素材的には異質なモノ”を添えた《鮭+鰈+ハイヒール》。
シュルレアリスムのデペイズマンや、優美な屍骸(le cadavre exquis)にも
相通じるところだが、こちらはそこに生の臨場感が伴う。
魚という古くから食文化にある素材が、
高級/人工/ファッションの象徴であるハイヒールと並ぶことで、
視覚的な違和感を生み出すのだが、
この並置が意味するものを考えていくと、
「死と装飾」「自然と人工」「食とファッション」という
異なるドメインの交差を暗示しているように思えてくる。
魚が「生きていた+食材」というリアリズムを持つ一方、
ハイヒールは「装うためのもの」「死とも用途とも別の次元」にあるモノとして、
その対局のコントラストは、まさにブルトン流の「黒いユーモア」として現れるのだ。
そのとき、われわれの視線は、現実と想像の一線を越えた、
イマジナリーな旅路へと誘導される冒険者になるだろう。
その他にも《鰍+帽子》、《コハダとブラジャー》などの
一見して、身体性を生々しく刺激するようなモティーフが現れる。
また、近年、今道子は素材/モチーフをさらに拡張してみせる。
例えば、《シスターバンビ》や《繭少女》《巫女》などでは、
昆虫や人形的モチーフ、繭・仮面・少女像といった記号的な対象が登場する。
これは、初期の「魚・野菜+モノ」という構成を進化させた、
「生/変化/仮構」のテーマへと移行していることをも示唆している。
言い換えれば、単なる静物オブジェではなく、
物語性・身体性・記号性を帯び始めているといえるだろうか?
観るものは、そこに「少女」「繭」「巫女」という言葉が持つ、
象徴空間(儀式・再生・変容)との接続をも読み込むことになるのだ。
その漆黒は暗闇ではない。
闇に葬るのではなく、夢見るアリスは闇を舞台に駆けるのだ。
このダークサイドアリスの世界観に、ますます惹きこまれていくのだ。
Cocteau Twins : Alice
アリス的夢想をかきたてる今道子の写真を眺めていて、久しぶりにエリザベス・フレイザーの声を聴きたくなった。そのイメージはあきらかに4AD的で、そのレーベルを代表するコクトー・ツインズに行き着くのはぼくにとっての必然だ。
彼女のモノクロームのワンダーランドには、
まるでその曲の霧のような遠い声が似合うだろう。
“魚の鱗のざらめを映し、果実の断面を夢に翻訳するその間(ま)に”、月を覆う雲のように被さってくるだろう。
腐敗と優美が寄り添うテーブルの上で、この旋律が静物たちに語りかける。
“これは夢か?” “いや、生なのか?” と。
どうか、この旋律が、それら、魚、タコ、ハイヒール、そして影たちに届くことを願おう。
美しき「アリス的夢想」へ、乾杯!
「Alice」は、Cocteau Twinsのシングル「Violaine」(1996年)に収録で、このシングルはバンドの晩期、英フォントナ/キャピトル契約下で出されたもので、「Violaine」というタイトル曲とともにリリースされているが、エアロスミスのスティーヴン・タイラーの娘、リブ・タイラー主演の、ベルトルッチの”Stealing Beauty”(邦題:『魅せられて』)でも使われている。


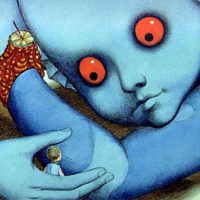


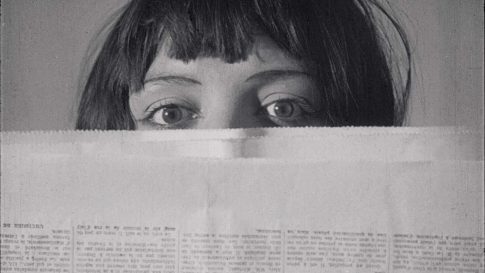


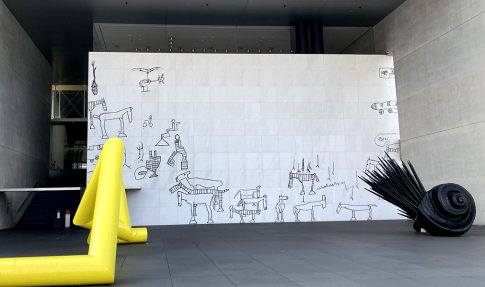
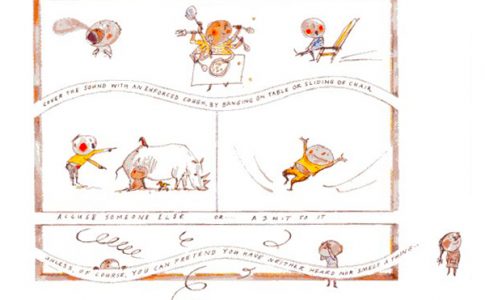

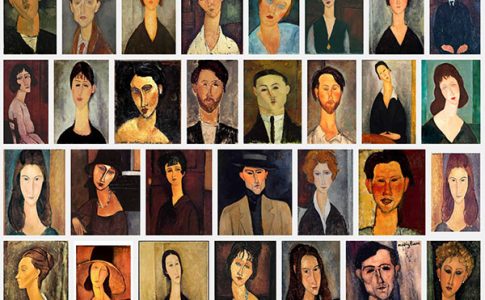

コメントを残す