国境、思想、人種、編曲を超えて
ZERO LANDMINE
2001年の春、TBS50周年特別企画『地雷ZERO 21世紀最初の祈り』で流れた一曲「ZERO LANDMINE」。それはただのチャリティ・ソングではなく、音楽家・坂本龍一の人生が折り重なった「祈りと信念の建造物」だった。
盟友デヴィッド・シルヴィアンの言葉と日本語の訳詞が交錯し、ブライアン・イーノやクラフトワーク、アジアの伝統楽器奏者らが音を寄せ合う。尺八や馬頭琴の響きがシンセサイザーの透明な空間に吸い込まれ、ストリングスは声を抱擁するように広がる。まるで異なる文化や言語が、地雷の埋められた大地を越えて、一つの未来を歌っているかのような一大絵巻となった。
その響きの背後にあったのは、坂本のアレンジャーとしての技術と、世界に向けた眼差しだ。彼は音を束ね、衝突する要素を調和へと変え、異質を響き合わせる。その仕事は単なる編曲を超え、「境界を消す」という行為そのものだった。
80年代の「We Are The World」がスターたちの合唱で世界を魅了したのに対し、「ZERO LANDMINE」は音楽の構造自体に平和の寓話を刻み込んだ。音が重なり合い、文化が交わることが、そのまま「地雷なき世界」のメタファーとなっていおり、坂本龍一というアーティストを振り返る意味で、忘れることのできない記憶である。
坂本にとって、この曲はひとつの総決算だった。テクノロジーとともに未来を描いたYMO、アンダーグラウンドの実験を支えた日々、映画音楽で人間の感情を描き出した瞬間、そして環境活動や社会運動への関与――そのすべてが「ZERO LANDMINE」という祈りの中に結晶した。
「音楽は世界を変えられるか」という問いに対し、坂本は断言しなかった。けれども、彼は行動し、響きを束ね、人々の心に祈りの種を蒔いた。あの日響いたメロディは、21世紀の入り口に立つ人類へ向けた希望の標のように、「ピーター・ガブリエルのReal World Records」の活動とともに、今もなお静かに鳴り続けている偉大な軌跡の一つだったと思う。
この地雷問題に強く関心をもったきっかけには、「昔からダイアナ妃が地雷廃絶を訴えていたことを知っていた」という思いがあったと、坂本自身が語っている。歌詞は坂本の長年の友人、決して社会思想や政治思想を歌わないデヴィッド・シルヴィアンに依頼され、「子供でも歌えるようなシンプルで優しい歌詞を書いてほしい」という注文だけをつけたという。
このプロジェクトには国内外から非常に多くのアーティストが参加している。高橋幸宏、細野晴臣、SUGIZO、桜井和寿、吉田美和など日本のポップス/ロック界の顔ぶれだけでなく、クラフトワークやブライアン・イーノ、Ustad Sultan Khan や Talvin Singh 等、ワールドミュージックや電子音楽の先端にいる人たちまで。曲全体は約18分以上という長大さをもち、前半は世界各地に残る地雷問題の文化的要素を感じさせる民族音楽や環境音の素材が導入され、後半で歌唱と合唱が中心になる構成をとる。聴き手に「問題を知る・感じる → 私たちが歌い祈る」という流れを体験させる設計となっている。
また、演奏/参加形態もひとつではなく、生演奏部分、録音済素材、サンプリング、リモート参加など、多様な形で「地球上のあちこち」を音で結びつける工夫がされており、坂本自身が常に敏感であった、21世紀的最先端のテクロージーが共有されている。また、楽曲だけでなく、ドキュメンタリー映像とともに放送され、その映像には世界各地に残る地雷の現状、被害を受けた人々や団体の活動、また参加アーティストの合唱や演奏シーンなどが盛り込まれて、「歌+映像+現実認識」が一体となる演出がなされている。この企画そのものが、坂本自身が長年培って、育んできた思想をみごとに結晶化している。

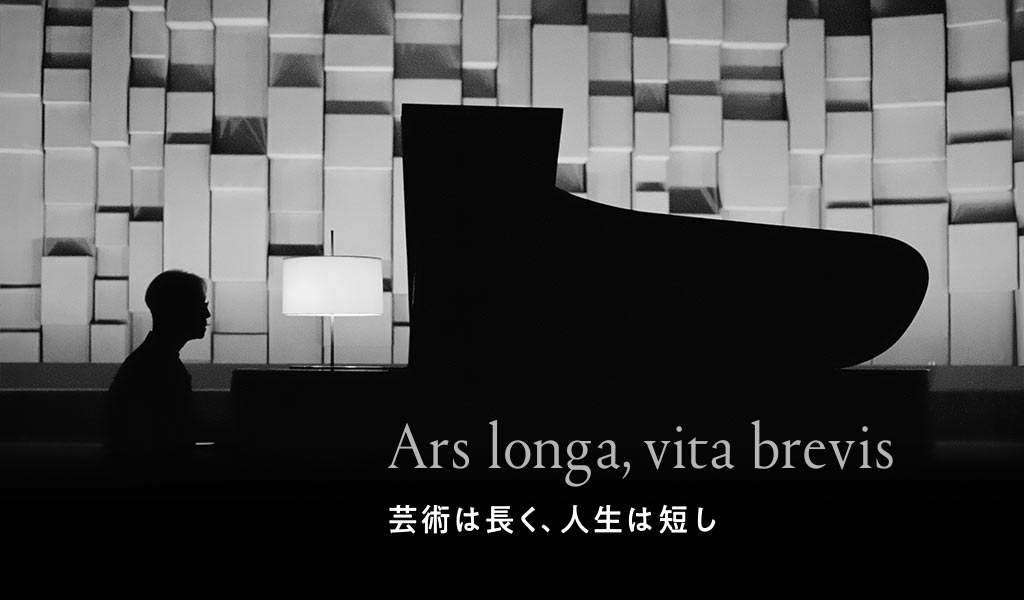



![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)


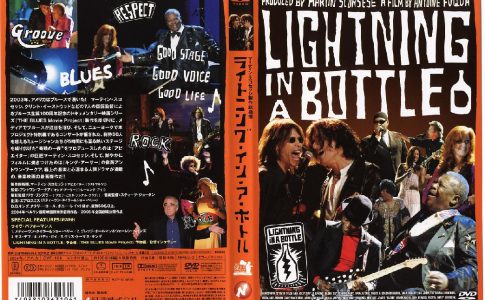
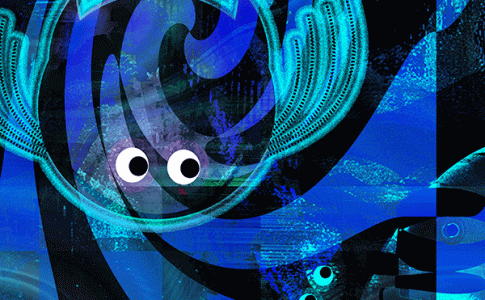



コメントを残す