ブラックジョークで不条理を侵犯する話
天才の考えることはそもそも凡人には理解しがたいものである。
たとえば、不条理文学の金字塔、フランツ・カフカの『審判』。
そこに描かれるのは、誰もが知っているようで、
誰一人把握できない「罪」への追及。
理不尽と無力感が、濃密な霧のように充満する小説である。
そんなものを真剣に受け止めて深掘りしたって
答えなんかに行き着くはずもない。
最初から負け戦さに挑むのは愚かもののすることだ。
だが、そんな原作に真正面から挑んだのが、オーソン・ウェルズである。
ただし、こちらも映画の天才児。
そこは食指がうごかぬわけもない。
1962年、モノクロームの濃厚な陰影をたたえた映像で
『審判』はスクリーンに蘇る。
しかし、ここにあるのは単なる不条理の再現ではない。
ウェルズは確かにカフカの悪夢を生き直した。
だが、その方法は奇妙なほど軽やかで、
そして、なにやら笑ってしまうほどに悪意に満ちていた。
そう、これは間違いなく「ブラックジョーク」である。
まず指摘すべきは、ウェルズが原作を恐れず大胆に再解釈している点だ。
カフカの『審判』は、読者の内面に音もなく忍び寄る絶望の小説である。
だが映画となると、その不条理はむしろ外に奇怪な形をとって吹き出してくる。
たとえば、逮捕に訪れる男たちの間抜けさ。
朝っぱらから命令を伝えるはずが、
要領を得ない説明に右往左往する彼らを前にして、
観客は思わず苦笑を禁じえない。
あるいは、裁判所に出向けば洗濯女に誘導される。
子どもに手を引かれ、まるで歌劇かなにかのような群衆とともに
こっけいきわまわる“裁き”を受けるK。
それに歓声をあげる聴衆。
これほど法の権威のメッキが剥がれた滑稽な光景はないだろう。
いやはや、ファルス、いわば衝撃の笑劇だ。
ウェルズは、カフカの描いた「空恐ろしい正義」を、
意図的に「冗談めかした茶番劇」へと変換しているのだ。
彼自身、映画冒頭で「これは悪夢の理論である」と
わざわざ意味深なナレーションでもって断りを入れているが、
それはつまり、「ここでは何が起きても笑わずにはいられない」
というネタ振りの表明でもあるのだ。
Kを演じたのは、ヒッチコック『サイコ』で知られるアンソニー・パーキンス。
『サイコ』では我々観客の目を、どんどん不安と恐怖に引きずり込んだものだが
ここでのKは、若く、神経質で、どこか間の抜けた男として
映画用に戯画化し、造形しなおされているがゆえに
その一挙手一投足が、次にどんな馬鹿げたことをしでかすのか、
という野次馬気質が大いに刺激されるのだ。
状況を把握しようと必死になりながらも、
そのくせ、どこかで自分の滑稽さに気づいているかのような視線。
ウェルズがパーキンスに目をつけたのは正解である。
そのアンバランスな存在感こそ、まさにブラックコメディの核なのだ。
特筆すべきは、Kが次々に女性に誘惑される奇妙な展開だ。
美しい隣人、情熱的な洗濯女、妖艶な弁護士の秘書……
彼女たちに翻弄されるたびに、パーキンス演じるKの表情は、
困惑と期待の入り混じった妙な生々しさを見せはじめる。
これが滑稽でなくて何だろう。
カフカ原作にも「官能の萌芽」は確かに存在したが、
ウェルズはそれをさらに露骨に可視化し、
絶望の只中に突如挿入される「セクシャルな喜劇」として演出している。
とはいえ、Kは、死に向かって着実に追い詰められていく。
その終着駅だけは可否しようがない。
だがそのプロセスは、幾何学的なモノクロームの造形になかに
ドイツ表現主義的陰影を帯びつつ、まるで道化の迷走劇のように描かれる。
それが、この映画に底知れぬ薄笑いと、
やるせないペーソスを同時に呼び込んでいるのもまたミソなのだ。
ウェルズ自身が演じた弁護士も、これまた滑稽な存在である。
病床に伏しながら、Kに助言とも冷笑ともつかない言葉を投げかける。
その態度には、最初から「無力さ」への諦念と、
どこかで「このゲームを楽しんでいる」という悪戯心がにじむ。
つまり、裁判という儀式そのものが、
最初から、ひとつのブラックジョークとして提示されているのがお分かりいただけよう。
さらには、遠近法を駆使して作り上げたアレクサンドル・トロ―ネルの大仕事、
ワイルダーの『アパートの鍵貸します』のオフィスをも想起させる、
Kの勤務するオフィスの異様さ。
地平線の彼方まで並ぶ机とタイプライターの壮観なセット。
整然としているようでいて、そこには冷えきった狂気が満ちている。
ウェルズは、人間を押しつぶす巨大な組織の不条理を、
グロテスクな美へと昇華したのだ。
ここにもまた、笑うしかない絶望がある。
最終的にKは、誰に助けられることもなく爆死する。
間抜けな処刑人たちはコントのようにさっさと仕事を遂行するのに必死だ。
逃れえぬ運命にもがく姿は、ほとんど料亭の水槽のなかの魚そのものだ。
そして窮地においこまれたKは、最後に「やるならやれよ!」と開きなおる。
この瞬間においてすら、ウェルズは涙と笑いを同居させる。
不条理の果てに待つのは、どうみてもカタルシスなんかではない。
ただ、どこまでも滑稽で、どこまでも哀しい、
かろうじて人間のかたちだけが残るだけだ。
つまりは抵抗と嘲笑と諦観である。
ダイナマイトの爆死とともにコントは無事終わった。
お疲れ様、である。
カフカの『審判』は、ただの悲劇ではない。
それは元より、「自分の手には負えない運命」を前にして、
人がどれだけ可笑しく、そして惨めに振る舞えるか
ウェルズは、その本質を見抜き、
一層鋭い「笑い」の棘を与えてみごとに映画化した作品なのである。
勝負はついた。
ただし、“可もなく不可もなく”というところだ。
かぎりなく曖昧なグレーゾーン。
ウェルズ版『審判』もまた、単なる不条理映画と見なすのは早計だ。
それは世界の「無意味」を抱きしめ、
乾いた笑いに変えた、諧謔の一大叙事詩というべきか。
ウェルズの諧謔精神は、カフカが震える手で描き出した迷宮に、
挑戦的なウィンクを投げかけたといえるだろう。
こうしてカフカが闇に葬ろうとした世界をつなぎとめた盟友、
マックス・ブロートの功績に便乗して、再度確認したかったにちがいないのだ。
そして、観る者に改めてこう問うた。
「笑っていただけましたか?」
それは断食を芸だと称して、観客の目を惹いた「断食芸人」の発想そのものだ。
ブラックユーモアとは、絶望のどん底でこそ花開くということを証明し、
ウェルズの『審判』は、そのことを、見事なまでに体現しているのである。
不条理などとおおげさにいっても、
所詮楽しんでもらうことこそが
カフカへの最大のオマージュ、リスペクトなのだいわんばかりに。
The Trial · Pink Floyd
オーソン・ウェルズ『審判』にぴったりな曲がある。Pink Floydのアルバム『The Wall』の終盤を飾るオペラ調の大作「The Trial」だ。主人公ピンクの内面で繰り広げられる幻想の裁判劇を扱っており、舞台は現実ではなく、彼自身の精神の奥深く、まるで夢の中の法廷のように、声なき訴えが鳴り響く。これを聴けば、だれもがまず、カフカの『審判』を思い出すだろう。両者には多くの共通点がある。まず、「裁かれる理由が不明」であること。ピンクは自身が何をしたのか明確に知らぬまま、有罪を宣告される。Kもまた、自らがなぜ逮捕されたのか、最後まで知らされることなく処刑される。そこには「不条理な法の支配」という共通の世界観が広がっているからだ。
さらに、「証人」として登場する人物たちは、ピンクにとっては教師や母親、元妻といった過去の関係者なのだが、彼らはあくまで彼の内面に潜む記憶やトラウマの化身だ。これは『審判』に登場する弁護士や画家、監視人と同じく、Kの心理的な迷宮の中に現れる“内なる他者”ともいえる存在である。音楽的にも「The Trial」は異様なまでに演劇チックに展開される。管弦楽による歪んだマーチ、登場人物の声色を使い分けるロジャー・ウォーターズの歌唱、サーカスのような狂騒。これらは、カフカが描くシュールな世界と驚くほど似ている。「裁判」がまるで見世物のように機能する点においても、奇妙な親和性を持っているといえるだろう。
興味深いのは、「The Trial」のクライマックスで、ピンク自身の声(あるいは超自我)が「Tear down the wall(壁を壊せ!)」と叫ぶ点だ。つまり、彼は裁判によって罰を受けるのではなく、壁を壊す=殻を破るよう命じられる。これは自己崩壊であると同時に、再生への第一歩でもある。一方、カフカのKはそのような救済を得ることなく、ただ処刑される。しかし、その結末すら「夢だったのでは」と読者に思わせる含みを残している点からも、カフカの法廷も、ピンクの裁判も、現実を映す鏡ではなく、内面の迷宮に突き立てられた真実の断片だと読めるだろう。裁かれる者が本当に向き合うべきは、外の世界ではなく、内にひそむ自分自身。そう思わせるような響きが、このふたつの「Trial」には確かにあるように思える。



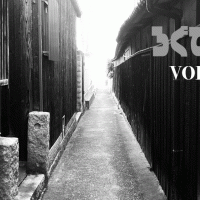


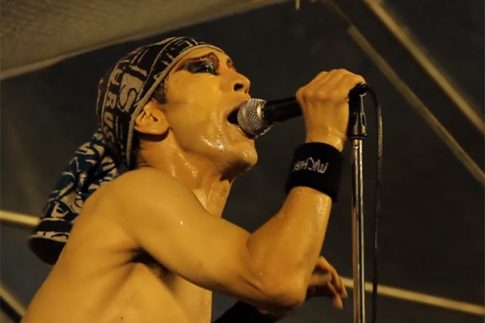

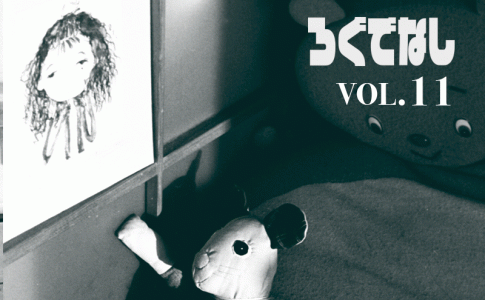




コメントを残す