世の中、ツボに収まりきれぬタコもいる
解剖台の上でのミシンとこうもりがさの不意の出会いのように美しい。
『マルドロールの詩』ロートレアモン
あぶらだこ、あぶらだこ。
あたかも、アブラカタブラのごとく、
周期的に呪文を唱える自分がいるのだ。
あぶらだこ、あぶらだこ。
わたしを自由にしておくれ。
あぶらだこ、あぶらだこ。
ぼくを元気にしておくれ。
思わずそう叫びたくなるような、精神の不安定なときには、
ただあぶらだこにすがるのみである。
聴くだけで即座に自由になれる音楽の魔力。
というか、小さなこだわりや邪念を捨て
とにかくこのまま行こうと思うだけである。
ことは単純なのである。
これぞ、もののあわれ、ではあるまいか?
いや、これは音楽なんだろうか?
少なくとも、当てはまるべきジャンルなどみあたらない。
あぶらだこを上手く収める壺など、
この日本のミュージックシーンには存在しない。
時代が変わっても
それは永遠にそうではないかと思っている。
かつて、オルタナティブと呼ばれていたことがあったのかもしれない。
はたまたハードコアか、ポジティブパンクなのか。
いや、プログレか?
もう、呼び名はなんだっていいが、
どれもが、正解のようで、正解などではない気がする。
すべてが事実であるにもかかわらず。
まさに、つかみどころなきバンド。
その音楽性、存在。
ただただ、聴くのみである。
あまり深く、考えてはいけない。
ひたすら聴き続ければ良い。
意味等問うべからず。
しかし、ひとつひとつの言葉は、決して軽いものではない。
言葉が第三、第四の楽器のように連呼される。
そのバックで、なにやら音らしきものが怒鳴っている。
いや、それは逆なのかもしれない。
がしかし、よくよく聴いているうちに
なにかとなにかがなんだかうまく混ざり合っているのを知る。
それは決して水と油などではない。
なんだか、クセになり、
いつのまにか虜にさえなっているのはどうしたものか。
ヴォーカルの長谷川裕倫という人は、
いったいどこから来て、
何処へ向かっているのか?
はっきりいって天才の類いである。
人間ではないのかもしれない。
動画などをみるとわかるが、
ただ者ではないのは容易にみてとれる。
まさにワンアンドオンリーである。
歌がグニャグニャしていたり、
ワーワーさわがしかったり、
しかし、当人は白樺の木のように、マイクの前に超然と屹立している。
ときに、白日の狂気を叫び、
真冬の空に華々しく花火を打ち上げる。
あるときは海のなかただよう海月のよう。
あるときは糸の切れた凧。
あるときは風に打たれるトタン板のよう。
そして、無に帰すセミのよう。
譬えなんてなんだっていいだろう。
なんなんだチミは?
そうつぶやかずにはいられない。
しかし、好きなのである。
何故だか、聴いてしまうのである。
あぶらだことは、そういうバンドである。
あぶらだこについてのまじめなことを
書く意味なんてあるのだろうか?
ある人は書けば良い
無い人は書かなくてもいい。
自分は、どうやら書けないというのが正解で、
それはきっとこの雄弁な音楽以上に
語るべきものがないからなのだと思う。
ただ、それではあまりにも無責任だというなら
自分は通称『木盤』と呼ばれるだけの、
アルバムに収録された「翌日」という曲に
ひどく痺れてしまったのかもしれない、
と冷静に分析ぐらいはできる。
暑い夏の陽射しの中で、この曲を始めて聴いたときの
あの衝撃が未だに忘れられないのである。
それがいつのことだったか、
はっきりしないが、 随分前だった気もするし、
ついこの間だった気もする。
どうでもいいことだ。
以来、荒野を彷徨う一匹の野良ダコに
懐いてしまった自分がいるのだから。
ただ、残念ながら、現在は活動休止中のようである。
2009年に「あぶらだこ 二十六周年 ワンマン」ライブを行って以来、
われわれは、この異次元の音楽に触れる機会がないのだ。
過去に産出された、その軌跡を追うことしかできない。
しかし、それでもぼくは待ち続けたい。
あぶらだこがこの現在に発信する音の狂気を、
しずかに待ちたいのである。
木盤:あぶらだこ
青い太陽はどこにでもいるし。
「翌日」より
宇宙のように生きたいと思うし。
あぶらだこのアルバムで、どれが一番いいんだろうか?
そんなことを真面目に考えるバンドではない。
ぼくには、このラス曲の「翌日」が収録されているだけで、
これを選んでしまうのだ。
十分なのだ。
ライブ盤の長尺ナンバーも凄まじいが、
とりあえず、このアルバムの「翌日」を聴いて、
この世の偽りに、はやくおさらばして
己の可能性に素直に気づいてほしい。
だれもが目覚めるための、真の歌がある。
だれもが、見誤った人生をやりなおす、きっかけがここにはあるのだ。







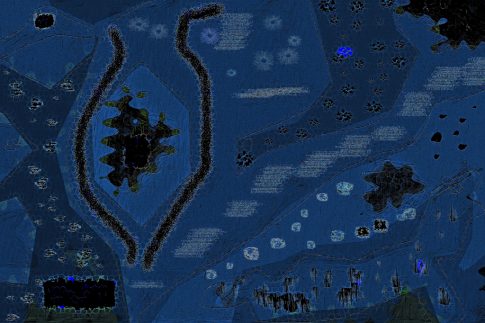





コメントを残す