さすらい道入門
良い映画というのは何度見ても発見がある。
それは、おそらく映画というものが生き物だからだと思う。
これまでなんども見返してきたヴェンダースの『パリ、テキサス』。
この先も我が人生で忘れがたい10本の映画から漏れることはないだろう。
この映画を改まって見直すのって、いつ以来だろうか。
今でも、この映画に再会したいと思うことが時々ある。
孤独を感じる時、自分の境遇がこのままでいいかどうか
頭を悩ませるような時、自信を失ってしまうような時・・・
すなわち、どこかへ旅立ちたい思いからである。
もっと言ってしまえば、人生から逃げ出したい、そう思うような時、
この映画のハリー・ディーン・スタントンが脳裏をかすめる。
これは小さなモニターで観る映画じゃないと思うのだが、
なかなかそうはいかない。
初見以来あれほど感動して,ずっと体内に感覚が残っているというのに
年月を経てみ直すと、いろんなところが抜け落ちているのに気づく。
いたるところに散りばめられた強烈な赤、すなわち小津へのオマージュであり、
ジョン・フォードの映画へのオマージュであるかのような
広大なアメリカのロケーションの素晴らしさ、そのなかの鉄道シーン。
橋の上で叫ぶ聖なる狂人。
あるいはちょい役でジョン・ルーリーが出ていることなど。
もちろん自分の視点もずいぶん変わっているというのもある。
まさにすべてがトラヴィスの記憶のようにあいまいで、
あるときから一気に現実にひきもどされ、
ヒリヒリするような思いがする、そんな映画である。
もし、どこか遠くの知らない国にトウキョウなる街があるとしよう。
どこでもない国の、なぜだか親しみのある、そして気になる場所。
そう、テキサスにパリという町があるのだ。
そんなモハベ砂漠にぽつりたっている記憶喪失のトラヴィスが
弟によって保護され、その弟夫婦をさらに押し切って
息子とともにようやく探し当てた妻を
最後ヒューストンのホテルの一室によび出しておきながら、
わかれわかれになっていたジェーンとシェーン母子の再会を
窓の外から見届けて
自分は再びどこかへ去ってしまうまでの二時間弱のドラマが
当時のぼくの人生にとって、どれほど大きな影響をあたえていたか
今みるといっそうそういう思いがしみじみとつのってきて、
熱いものがこみあげてくる。
なぜだかわからないが、あの砂漠に立っていたのが
ふと自分だったかのような気さえするのだった。
何度見ても揺さぶられるワンカットで綴られるクライマックスの
奇妙な「のぞき部屋?」での感動的な再会と対話。
あるいは、弟夫婦の家で懐かしむ8mmビデオシーン。
ゆっくりと確かめあいながら結ばれる息子と父の心のふれあい・・・
いまみると、弟ウォルトやその妻アンの気持ちさえ痛いほどよくわかる。
その複雑な狭間におかれ成長してゆく息子ハンター。
そして、テーマである「彷徨」へと回帰するエンディング。
すべてが色あせず,やはりこの映画は
ヴェンダースの最高傑作であることは、何十年たっても疑いようがない。
それにしても、今は映画の重要なタームの一つにさえなってしまった
「ロードムービー」という言葉を、最初に意識した映画が
思い返せば、この『パリ、テキサス』からだったような気がしている。
それはたんに地図上の、どこそこからどこそこへ
といった空間移動のみならず、
魂の移動,彷徨という意味をふくんでいるのは間違いない。
それは人生そのものであり、自分探しでもある。
『さすらい』や『まわり道』『都会のアリス』といった
70年代からのヴェンダースの主題は
まさにさすらうこと、探しもとめることそのものにあった。
その集大成が『パリ、テキサス』だったように思う。
残念ながら、次の『ベルリン天使の詩』を最後に、
ぼくのなかでWWとの真の映画体験はストップしてしまった気がしていた。
この『パリ、テキサス』を超える作品に出会えなくなって以来、
ぼくのなかではWWに対しては、
ジェーンを失ったトラヴィスのように
いまだそれがなんなのかを、ずっと探しつづけていかなくてはならないのだ。
のちに見た『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』は
ある意味その答えなのかな、とも思っている。
ヴェンダースという作家は、時代感覚の嗅覚にすぐれているし
もちろん才能もある。
とりわけ、音楽への愛情とまなざしにおいて、
映画史のなかで、もっとも敏感な作家の一人なんだと思う。
『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』にでてくる音楽も
そのミュージシャンたちもとても魅力的だ。
でも、だからといって、ぼくはこの作品が
ヴィムの真の復活だなどとは思っちゃいない。
この手のものは、ヴィムなら感性で撮りあげてしまう。
ヴィムはややもすれば、その音楽愛におぼれすぎてしまう感があって
たとえば『ランド・オブ・プレンティ』においても
そういう色合いが強く反映されている。
確かにサウンド・トラックとしては、
これほど優れたコンピレーションはないと思う。
レナード・コーエンの唄はハートにぐっときたけど、
エンディングに使うのはあまりにもずるいと思う。
『ミリオンダラー・ホテル』然り・・・。
でも、少なくとも映画における音楽が
ちゃんと機能していたのは『ベルリン・天使の詩』までで
以後、WWはなにかを失ったかのように
映像と音楽がバラバラに相互主張しながら
どこか消化不良の映画を量産してきた気がしている。
もっとも、WWを今日までずっと追いかけてきたわけじゃないし
やはり初期から『パリ、テキサス』への流れへの思いが
ぼくには少し強すぎると言っていいのかもしれない。
『パリ、テキサス』でばっちりはまったライ・クーダーのスライド・ギターが
『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』でのキューバ音楽に
すんなりとけ込むのはある意味自然なことだ。
とは言え、映画と言うものは、それほど脳天気なものじゃない。
やはりそこが映画の難しさ、恐ろしさだ。
ヴィムならきっとどこかで気づいているに違いない。
そういっても、ヴェンダースはぼくにとっては
未だ重要な作家であり続ける。
常に一定以上の良質な映画を撮り続けることの難しさ。
映画作家は職業作家ではない、という思いで見れば擁護したくもなる。
ヴェンダースは物語を描くのが苦手だという。
とはいえ、『東京画』で笠智衆や厚田雄春を収めた
ロビー・ミューラーのカメラにやどった、
ヴィムの魂のようなものが、三つ子の魂百まで、
といった映画への愛を信じさせてくれるだけで十分なのだ。
実際『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』や
『ソウル・オブ・マン』といった音楽ドキュメンタリーですら
確かにすばらしい。
しかし、彼が尾道で見た景色が写真に収め
小津への憧憬を示しながら
そうした映画の息遣いを感じることができたことを思い出そう。
ヴェンダースは、あの小津を師として
この『パリ、テキサス』へ至ったのは紛れもなく事実である。
家族のあり方、優しさ、思いやり、
それら漠然としたものが、直接的なものではなく、
どことなく遠回りして、他人行儀でありながらも
自分自身の問題として収斂しされてゆく『パリ,テキサス』の先を
僕は、僕自身として考えてゆかねばならないのだ。
本作脚本は映画デビューとなったサム・シェパードとヴェンダースの共同執筆で
ゼロから練り上げたオリジナルストーリーは、
脚本が半分ぐらいしか完成されてはおらず撮影入り。
撮影とともに、俳優の動きをみて練り上げられていったのだという。
当初、トラヴィス役はそのサム・シェパードを予定していたというが
本人がイメージが近すぎてできないという流れでハリーに決まったらしい。
(ちなみに、その思いがのちの2005年『アメリカ、家族のいる風景』に繋がっている)
撮影方法も順撮りで行われ、最後まで方向性は定まっていなかったのである。
あのピーピングショー(のぞき部屋)の発想も途中でヴェンダースが考えたというし
ラストシーンも、いかようにも撮れただろう。
だが、この映画の結末が仮に、親子三人のハッピーエンドなら、
ここまで僕の心にこれほどまでに深く残らなかったと思う。
二人の再会を見守って再び旅立ったトラヴィスの思いこそ、
僕が繰り返し辿ってきた道そのものなのだ。
もう一度、原点に戻らねば見えてこない風景。
そしてこうつぶやいていた。
とまらずに、歩き続けよう、心の師よ!
僕もまた歩き続けるしかないのだと教えられた映画である。
最後に、この映画のライ・クーダーによるサントラの素晴らしさ。
映画を観ずとも、この音楽とともに、僕のさすらいは続く。
トラヴィスのように。
ライのスライドギターの啜り泣きのように。










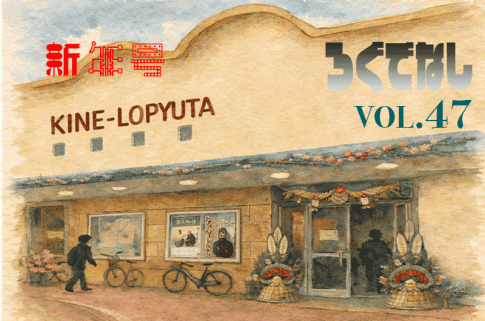


コメントを残す