無邪気な狂気〜ジェルレアリスムはコクトーから始まった。
コクトー24才の処女小説『ポトマック』。
小説というにはあまりも骨の透き通ったような
ゼラチン質の散文である『ポトマック』は、
「鯨と腔腸動物の合の子」という
架空の生き物=怪物をめぐるコクトー流の寓話だ。
人によっては、その内容から、
シュルレアリスムの一連の小説にすぎない、
という生真面目な分類に甘んじて納得してしまうかもしれないが、
そこはやんわり、微妙に違うんですよ、
などと一応は断っておきたいのである。
そもそもが、シュルレアリスムなんて仰々しいものではなく、
たしかに、夢やら幻想やら自動手記やらの感性は、
シュル(一般的にはシュールと言っているが、
正しくはシュルだ)な感性に相応しいといえども、
そこは、とてもシラフで書き連ねたようなものではないので、
そう難しく考えても仕方がないというのが、こちらの見解である。
どちらかといえば、子供のラクガキのような感性に近く、
と言って、そんじょそこらにいるガキどもによるイタズラ書き、
と言った類いのものでもなく、当人なら、一言、
これはポエジー(ポエムとポエジーは似て非なるもの、
といえば事は複雑化するので割愛)のなせるワザ、
と言い切ってしまうに違いあるまい。
が、そこはこうしてわざわざ取り上げている以上、
あえて分かりやすく、ジェルレアリスム
(透明なジェルメデュームのような世界)
という自前の造語に置き換えてみたのである。
ちなみに、他に比類のないものだから、
今のところこのジェルレアリスムは、
これが唯一無二で、継承するものが見つからない。
いうなれば、最初にして最後のジェルリアリスム小説である。
が、そこはひとまず、おいておこう。
内容はというと、ひとつはウジェーヌたちとモルティメ夫妻との話、
もうひとつは詩人の分身ペシケール、
そしてアルジェモーヌがこの夢見る水棲動物ポトマックと絡むという話。
一見、荒唐無稽な散文といえばそれまでだが、
なかば自動手記に近いスピード感、
その渾沌と開けやらぬ夢のような饒舌さが、
いかにもコクトーらしい作品である。
大戦前後に執筆され、その空気が支配してはいるものの、
あくまでも一詩人の創造の秘密がちりばめられているのだ。
矛盾撞着から、模索から、誠実で筋道立った均衡の崩れから、ひとつの真理が出ててくることを確信していた僕だから、この本にたとえば「盲目の建築家」とか「夢遊病の軽業師」とか」「九の数による証明」とか「無秩序の哲学」とかいったような題をつけることもできたかもしれない。
そして、再び十六年後の大戦前後に再び筆をとり
「ポトマックの最後」ではこういってのける。
この本は宿命的な光の下で読まれるべきなのだ。僕達の真の読者は軍隊にいる。この人たちは読書に飢えている。一種の催眠状態の中で、また虚無の淵で書き上げられたこの作品は、僕達がいま体験している、この巨大な謎の中で読まれるのが理想ではないだろうか?
ポトマックの最後
「春の祭典」によってインスピレーションを掻き立てられ
本作品を着手したコクトーは、
これを作曲家ストラビンスキーにオマージュとして捧げ、
『パラード』(舞台)、『詩人の血』(映画)、
そして数々の絵画・ドローイングという
自身のビジュアルイメージの先駆け的要素を
ふんだんに懐胎した作品だと断じることが可能だ。
挿入されたデッサン64点は、若き日の詩画集といっていいし、
今日のイラストレーターばりのエッセンス、軽やかさがある。
生涯にわたり、デッサンをほめられるのを好み、
ひまがあれば大量のデッサンを描き残したコクトー、
線画家としての出発点でもあり、
なにかと興味深いウジェーヌたちの紙面上の狂態をご覧あれ。
この愛すべき作品「ポトマック」は、映画史におけるコクトーの位置同様、
コクトーの作品群のなかですら、その実、
捉えがたく、評価および位置付けるのが難しい作品だ。
とはいえ、その豊かな詩の泉は、
無邪気な永遠の若さを供給している、
実にコクトーらしい夢と直感のアマルガム、
すなわち彼がこだわったポエジーそのもの、というべく作品である。
しばし、コクトーの文学的レトリック、
詩的構文は原文で味わうことなくして、
なかなかそのエレガンスまでは吟味しようもないところで、
なんとも読者泣かせの代物だが、
なにぶんこれ以上ない適任者、といえば、
いわずもがなのタッソー澁澤龍彦、
これぞ名訳で読み齧れるのは、むしろ幸福な事態かもしれない。
ぼくは五里霧中で書いていた。あとで気がついたことだが、そのとき僕は脱皮していたのであり、体の組織が変わるあの危険な状態のなかで書いていた。
詩人としての足掻きが微笑ましくもある、
「美よりも速く駆け抜けた」偉大なる韋駄天詩人の、
若き日の甘くも苦い日常言語というわけだ。
もっとも、詩(ポエジー)はスピードだ、
というのがジャン・コクトー流のレトリックだから、
その実践が作品を次々乗り継いでいったことぐらいは、
いま、だれもが認識している。
かくして本物は、時代をへてもスピードの衰えを知らないままである。
魂のスピード狂は死んでから、さらにスピードを増す。
時代の寵児、いまではそんな野暮ったい美辞麗句、説明的言説など
まったくもって不要だろう。
時代はこのスピードによって分析され捕えられるものだということを、
いまさらながらに証明しつづける、
この呪われたマルチアーティスト、かくなるフレーズが、
いささか時代遅れのように響くのも、
やはりこの先鞭をつけた人物のアウラの輝きが、
永遠のものにほかならないからだ。
僕の生活が支離滅裂で、却って夢に脈略があるのは、僕をあのポトマックと縁続きにするところのものだ。同じ液体が僕らには通っているのだ。僕は犬と狼、かたみに呼びかわすものの中間を行く。ぼくは夢のなかでいつまでも生活しつづけ、昼間の自分のメカニズムのなかで夢見つづける。
神業による紙技か。
そのひとつひとつの世界をみると、
ときに可愛いアナクロニスム、ときに赤裸々なまでの魂の告白だ。
いや、それは夢のように危うい。夢の残滓というべきか。
そう、すべて「手仕事」の産物であることを思い出そう。
「美女と野獣」の野暮ったいファンタジーを見よ、
「ジャノへの手紙」への赤裸々なる思いを見よ。
そしてこの無邪気な「ポトマック」を見よ。
絶えずナルシズムに傾斜しつつ、
他者への情愛もわすれなかったジャン・コクトー、
いまとなってはどれも愛嬌であって、
別段嫌味などカケラもみられない。
本名は、クレマン・ウジェーヌ・ジャン・モーリス・コクトー 。
ここにコクトーは母系の名ウジェーヌをもって、
いわゆるこの処女小説(小説というには語弊があるのだが)「ポトマック」に、
不思議なキャラが登場させたことと
なんらかの関係があるとされている。
死のイマージュと絶えず戯れた彼は、
モルティメ夫妻(mort=父の自殺、petit=自分、
そしてmere=母の合成という説がある)を登場させる。
アルフレッド・ジャリが産み落とした
怪物ユビュの末裔であることは見てあきらかだが、
こちらはどうにも愛嬌がある。
いや、その深層を抱え込んだ皮膚の下に流るる血こそ、
美の秘密そのものなのだろう。
スキャンダラスとは似ても似つかぬ御愛好だが、
夢の世界、ポエジーの深淵はかくも深い。
とりたてて、筋があるわけでもなく、
散文調というのか、雑記調というのか、
定義や解釈を拒否する、ちょっとしたラディカルな意志と、
どことなくもスノビッシュな野心のようなものも
見えかくれするポトマックは、時代を経て、
むしろ、現在においてこそ、
リアルタイムなキッチュさを発揮し、
堂々若々しくおどけてみえる。
以後コクトーの多様性は、
この小説もどきにすでに懐胎されている。
つまりは未来永劫の告知といって過言ではないほどだ。
Be Bop Deluxe:Jean Cocteau
コクトー好きなミュージシャンといえば、ビル・ネルソン。みずからのレーベルもCOCTEAU レーベルと名付けるほど。いろんな曲にそのエッセンスを散りばめているのですが、その全身ビーパップデラックスの曲に、そのものの曲がありますね。まさにコクトー讃歌の一曲。




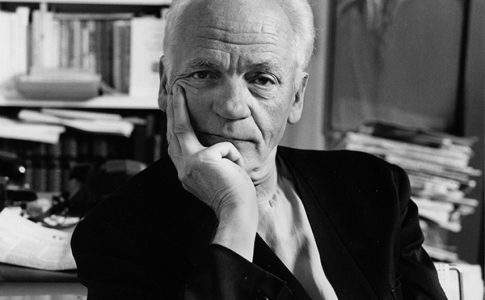








コメントを残す