フランソワ・トリュフォー『大人は判ってくれない』をめぐって
そんなレオーの代表作として、 記念すべき第一作『大人は判ってくれない』の 若き日のレオーをまず、とりあげぬわけにはいかない。 なにしろ、たとえ初々しい13歳だろうが、 その後半世紀も経たくたびれた73歳だろうが 結局はレオーはレオーでしかない、 という絶対的神話性がスタートを切った重要なる作品なのだから。
 映画・俳優
映画・俳優そんなレオーの代表作として、 記念すべき第一作『大人は判ってくれない』の 若き日のレオーをまず、とりあげぬわけにはいかない。 なにしろ、たとえ初々しい13歳だろうが、 その後半世紀も経たくたびれた73歳だろうが 結局はレオーはレオーでしかない、 という絶対的神話性がスタートを切った重要なる作品なのだから。
 映画・俳優
映画・俳優しかしながら、この映画が訴えかけてくるのは 単に脱獄のサスペンスのみならず そこにまつわる人間ドラマにこそ心動かされる映画なのだ。 そこにベッケルのベッケルたるゆえんがある。
 映画・俳優
映画・俳優西川美和による『すばらしき世界』は 佐木隆三による小説『身分帳』という原案からの映画化である。 そうした失敗者、元ヤクザの男が刑期を終え出所後 この社会でどういきてゆくのか、 周りの人間たちの反応とともに、 そうした世間の冷たい視線を浴びながら 生きてゆこうとする男のあがきその様子が描き出されている。
 映画・俳優
映画・俳優例えば、スタンリー・キューブリックのカルトムービー 『時計仕掛けのオレンジ』を想起してみよう。 スクリーンにあふれかえるイメージ、アイコンは、 当時からみればいたく未来的であった。 けれども、今見返すと、どことなくレトロモダン風であり こだわりのキッチュな世界が支配している。 単に、懐かしい気分がするのだ。
 映画・俳優
映画・俳優『ピストルと少年』あるいはこの『少年たち』もまた、 成熟に届かぬ十代の若者たちの周りで起きる、 リアルな憤り、もどかしさを巡って、 ドキュメンタリーのような雰囲気で、 常に逼迫し、何かに追い詰められているそんな臨場感で ナイフの刃のように傷つけ合う激情が晒される。 実にドワイヨンらしい作品と呼べるもので いつもながら、子供たちが実に生き生きしている。 何気ない傑作だと思う。
 映画・俳優
映画・俳優大島渚の『絞死刑』はこんな風に始まる。 ほとんど誰もみたことのない風景が前の前にある。 (死刑をめぐる)問題作なのは言うまでもないが、 この先いったいどんな深刻なストーリー、 どんな恐ろしい結末が待ち構えているのか? 出だしからして緊張を強いられる映画である。 しかし、これは果たして死刑制度の是非をめぐる映画なのか? という疑問が次第にあらわになってくる。
 映画・俳優
映画・俳優天使の代償に蘇生は許されない かつて、アメリカとその均衡を二分化していた大国ソビエト連邦はいみじくも崩壊したが、いまだロシアは広大な領土を持ちえている。じつに不気味な国家である。 そのロシアの底力、とばかり、レンフィルム...
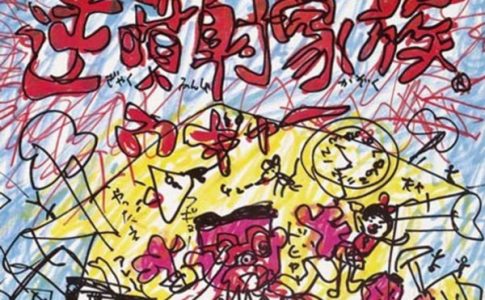 サブカルチャー
サブカルチャーとにかくすごいパワフルな映画です。 そもそも、内容がぶっ壊れている映画、 壊れているが、その壊れ加減こそが石井聰亙の真骨頂である。
 映画・俳優
映画・俳優中島貞夫による和製ニューシネマ、 といった風情のなかで二人の逃避行は、加速する。 はじめは単に金の持ち逃げだったのが、 人を巻き込み殺人にまで発展する。 最後は、その渡瀬の上をゆく肝っ玉っぷりの 梶芽衣子節が炸裂するのだ。
 映画・俳優
映画・俳優ボクは今さっき、ずいぶん久しぶりに 『俺たちに明日はない』を見終わったばかりだけど 十分その乾きは癒されたもの。 ラストシーンの衝撃に至るまで、 フェイ・ダナウェイを愛おしいと何度思ったか。 できれば二人をもっともっと生かしてやりたい 逃がしてやりたいと思ってしまったよ。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ
住所
123 Main Street
New York, NY 10001
営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日: 11:00 AM – 3:00 PM
