不能者、と呼ばれる前に学習しておきたい奇異なる痴情の掟
谷崎潤一郎は単なる耽美的作家ではなく、
痴情のもつれを俗物ギリギリの官能性を持ち出して描き出す作家である。
それゆえに、その作品の映画化は後を絶たない。
つまりは有数の映像的作家と呼んでも差し支えないところである。
内外問わず、これまですこぶる映像を喚起する作家として、
扱われてきた事実は圧巻である。
官能こそは蜜の味、とでもいうべきか。
亡くなった大女優京マチ子主演作品の中で
ベスト3に入るであろう作品は
まず、市川崑の『鍵』ではないかと思う。
まず、巧みな中村鴈治郎。
(谷崎自身はこの選択に難色を示したらしいが、なんとなくわかるような気がする。
個人的には、『雁の寺』などでその片鱗を見せつけた
三島雅夫などが適役ではないかとおもうのだが・・・)
そして妖艶な京マチ子はいうに及ばず
相変わらず不気味な仲代達矢、
そしてわざと器量を悪く演じた叶順子、
さらに、思わぬ伏兵北林谷栄に至るまで、
キャンスティングに抜かりはない。
市川崑はやはり、すごい監督だと、改めて思うのだ。
この手の映画、単純にエロティックな映画、
というのでもなく
通常の男女の心理映画でもなく、
サスペンス調にそれらの要素を絡めつつも
あの禁断の谷崎ワールドを見事ビジュアル化した演出の妙は
まさに市川崑ならではの、終始一貫したスタイリスティクな展開だ。
黒の世界、光と陰の使い分け、
まさに『陰影礼讃』を地でゆく世界を支えるカメラは宮川一夫。
この人のカメラワークはまさに芸術品だ。
どこを切っても日本的な世界なのに、
映画の美は、それに反するような様式美に支配されているのは
この匠あってのもの。
市川崑のエラさは、あえて野暮を省みずいうならば、
文学を引きずらず、独自に解釈を加え作り替える手腕である。
そして何よりも軽妙さ、
まさに観念のエロスをブラックコメディに改変してしまった。
このあたりが、溝口健二の我執との明らかな違いである。
文学におけるポルノ性とは違い、
映画ではそれはより徹底して観念的に展開される。
なにしろ、谷崎の描く『鍵』はもともと
夫婦間のお互いの日記に記された性的欲望の
妄想と現実が入り乱れたアンチモラルな話だったのだ。
そうしたインパクトは
生々しい肉体性を映し出すだけでは不十分なのである。
京マチ子の眉と娘叶順子の野暮ったい眉/容姿の対比にはじまり、
感情を排したような医師木村を演じる仲代達矢、
テレビ体操をしてひっくりかえったり、
アクロバティックに整体を手ほどき受ける中村鴈治郎。
これらおかしみの妙はまさに市川崑の真骨頂だと思った。
ただよくよく考えると、
なるほど中村鴈治郎には上手い役者ではあるものの、
不埒な妄想を抱く老人としては
いささかもの足りない気もしたのも事実である。
それだけが心残りではあるが、
その風貌、どこか作家然とした谷崎潤一郎本人にかぶるイメージがある、
といえば、合点もゆくが・・・
不能=死の関係性。
マジメに考えれば考えるほどコメディに聞こえるだろう。
そこから始まる物語の妙。
まだ普通に性欲をもつ身としては、
いつしか、それになんらかの変調がくるときにでも
またじっくり観てみたいし、読んでみたい世界である。
が、それって怖いような、怖くないような。
まさに妄想が勝手に膨らむのだ。
このあたりは谷崎文学の真骨頂でもある。
しかし、これが文学ではないあたりで、いろいろ問題は出てくる。
映画では日記の盗み見というものに、さほど重きがおかれていないこともあり、
その分、若い木村に、どうやって妻を誘惑せしめるか
というような性壁からの王道の方向性がある。
しかも、最後には、北林谷栄扮する女中という思わぬ伏兵が話を濁してしまう。
農薬を混入させて、このいびつな三角関係が毒殺をもって結末を迎える。
ようするに、三角関係のもつれとして
ブラックコメディに仕上がっている点である。
こういう結末は、市川崑が得意とするところで、
肝心のエロティシズムからは、少しへだった別の世界である。
その点を強く願うものには、いささか物足りなさが残る作品かもしれないが、
そこを離れれば、やはり、この映画はスリリングで面白い。
性を奪われた老人の悪あがきが転じ、
老いてもなお人間を翻弄するこの性にまつわる滑稽なまでの人間ドラマに
エロティシズムという素材を解体した、
ブラックコメディとしての魅力があるのだ。









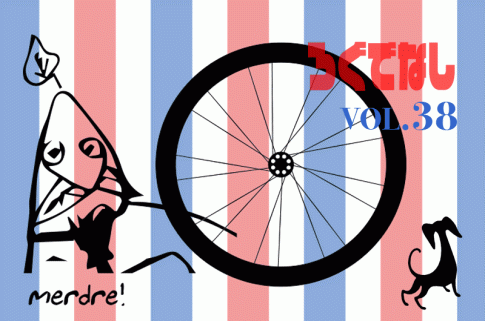



コメントを残す