廃屋でSM道を突っ走る、生贄たちの狂乱レース
「ねえ、苛めて下さってもいいのよ。どんなお仕置きにも私、耐えてごらんにいれるわ」
映画を見極める視線と、ひたすら官能に酔う視線が
決して同じ方向へは向かないのは、当然と言えば当然であり、
その結果、ポルノだと称される映画が、
所詮、虚構のエロティシズムのなかのあくなき格闘なのだという、
作家の内なる声というものは、
これはこれで、純粋に映画と向きあってきた人間にしか発しえない、
ひとつの真実として、常に頭の片隅においておくべきことである。
それをふまえてみても、日活ロマンポルノというジャンルを見渡して、
小沼勝以上のエロティシズムの本質をついた作家を、僕は知らない。
その上で、SMの魅力はなんだろうか?を考えてみることにする。
その答えを、いまのところ持ちえてはいないのだが、
その前に、まずSMというものが、エロティックなものなんだろうか?
エロティックだとすれば、何がどうエロティックなのか?
という問いに、置き換えてみる必要がある。
そこで、『存在と無』のなかで、サルトルが、
「一番猥褻なものは縛られた女の躰である」と書いている、
というようなことを、学生から、他者の存在を問われた三島由紀夫が
かの東大全共闘との討論のなかで、引用していたのを思い出した。
つまりは、エロティシズムにおいては、この他者性が不可欠であるにもかかわらず、
意思をもった他者の主体というものが立ちふさがり、邪魔するものであるから
そこに、あえてその意思を規制するものを置く、
この奪われし自由にこそに、真のエロティシズムの本質があるのだと。
『花と蛇』に続く谷ナオミとのコンビ第二弾『生贄夫人』では
まさに、その縛られた女の躰に、角隠しをした花嫁姿で吊るされ、
陵辱を受ける、といった、猥褻にさらなる強度をつけてみせる。
しかも、連れ込まれたのが山村の廃屋という特殊な場である。
そのセット、カメラワークは惚れ惚れするほど素晴らしい。
そこで展開されるSMは、緊縛、排泄、浣腸、剃毛、ロウソク責め、鞭。
もはや、小沼勝の異常性愛癖満載におけるフルコースが展開されてゆく。
もちろん、それに応えるSMクイーンナオミ様の貫禄は絶大だ。
が、のっけから小児性愛をみせつける、この変態性を強調してみせる夫、
坂本長利の存在もまた、前作『花と蛇』の変態夫から
何倍もヒートアップ、パワーアップした
変態性を遺憾なく発揮しており、
まさにエロスにとっての重要なる他者性を十二分にかねそなえて
谷ナオミの美をみごとにアシストしている。
かくして、変態同志が叙情豊かに、たくみに上品と下品の均衡を保ちながら
くりひろげる宴として、これほど贅沢な享楽はあるまい。
『官能のプログラム・ピクチュア』のなかで、山根貞男氏が
「どの画面にも、ふしぎなくらい猥褻さ、いかがわしさが感じられない」
などと書いているが、
たしかに、猥褻か、いかがわしいか、という点ではそうだとしても、
やはり、こうも真っ向から手を替え品を替え、
見せつけられる変態性につきあわされていると、
随所に滲むエロティシズムを感じないわけにもいかないのである。
そこに、若いカップルが、さらなる生贄として捧げられる。
このあたり、田中陽造による脚本も凄い。
二人は山中で心中を企てたところを、この猟奇的な男、坂本長利に発見され、
意に反して、命を救われてしまうのだ。
しかし、助けた男が良心からとった行為であるはずもない。
若い女、東てる美は、本作がデビュー作であり、
正真正銘、高校を卒業したばかりの未成年である。
そんなところにも、この作品の危険性が忍んでいるわけだが、
セーラ服で現場に現れた当の本人は、まず椅子に座ってタバコを一服、
さらに、谷ナオミだけがきれいに撮られることに嫉妬したというから大物である。
そんな彼女が、縛られ、吊るされ、浣腸されるシーンがこれまたすさまじい。
当人の悶えを受け、それに苦悶をうかべながら
排泄物の処理にあてがわれた谷ナオミとの画に、
壮大なシンフォニーがかぶさってくる・・・
こうなると、エロティシズムなどどこかへふっとんで、
実に清々しささえこみあげてくるのだ。
いったいなんだろうか、このおかしみは。
しかし、これだけでは終わらない。
今度は、恋人の恥辱プレイに反応した若い男の処理に、
谷ナオミがこれみよがしにあてがわれる。
それをみて、男は若い女を犯し始める・・・
こうなると、もはややり放題である。
目の前にある素材を最大限に活用すべしと、
あの手この手でくりひろげられるエロスの狂乱が続く。
一度は、死に臨んだはずのカップですら、
おのおの死の快楽以上の快楽に耽るありさまで
再び喧嘩までおっぱじめては、当初の思いはどこにやら、浄土は遠い。
こうなれば、もはや誰もが後戻りできない。
いつのまにか、夫との愛が再燃している変態夫婦の前になすすべはない。
そんな四人が摩訶不思議な空気のなかで
そろって食事をとるシーンが実に異様である。
それにしても、谷ナオミの肉体は
ここでも、まさに芸術の域に達するほどに、官能性にあふれており、
『花と蛇』に輪をかけて、そのあらわな姿は眩しいほどである。
苦悶に喘ぐ表情とは裏腹に、快楽に波打つふくよかで淫らな肢体。
脱糞シーンですら、芸術にしてしまうのだ。
もはや、猥褻だ、エロティックだ、などという表層的論争さえ
どこか超越してしまっているのがこの女優の貫禄か。
そして、結局はすべてを受け入れて、
これがSM調教の真骨頂というべきもののなのか?
ついには、その変態性に目覚めたみずから肉体を、
夫という他者に嬉々と晒して、微笑むのだ。
ここにもまた、小沼勝によって解体された
別種のエロドラマという虚構がある。
小沼勝は、この美の女神、エロスの仏神と出会うことで
ポルノ道を、暗室の倒錯からスクリーンの娯楽へと導いたのである。
そのあたりのエピソードが『わが人生、日活ロマンポルノ』のなかで
映画という虚構=ロマンを熱く語られている。
SMという不自然なもののリアリティを追うために、自然に見せる演出をしたことを反省した。もっと人間の意外性を、はみ出した部分を、叩きださなくてはいけないのだ。
『わが人生、日活ロマンポルノ』より
結局のところ、SMがどうエロティックなのか、
という命題に、まだうまく行き着くことができないままである。
あえて、その虚構性の快楽が一人歩きして、
エロティックな現象だけが脳髄のエロスとして目に焼き付いてはいるが、
それが本質なのかどうかさえ奇くなってくる。
こうなれば、小沼勝の術中である。
さすがに、団鬼六がこの匠の演出とは相容れないかったのはやむを得まい
これが映画のマジックなのだから。








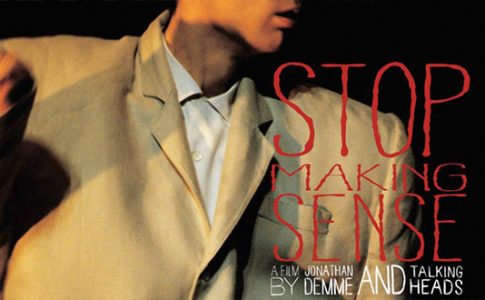




コメントを残す