カルトの正体ここにあり。郁馥たる詩人の血に献杯しよう
詩というものが、
なにものにも支配されず、
いわゆる言葉の連なりや叙情からも解放され、
完全なる自由を勝ち取ると同時に
一人の人間の生き様の中に、
脈々として流れ、宿るものだということを
身を以て教えてくれたのがフランスの詩人ランボーだった。
彼は詩を捨てたのではなく、
砂漠の商人として、新たな詩を新たに生き始めたのだ。
詩人にとっての砂漠、
それは生を渇望する人間にとって、
これほどまでに似つかわしい場所はない。
まさに地獄の季節を生きる神として、
最強を目指す旅の始まりがここにある。
ホドロフスキーの『エル・トポ』は
まさに、メキシコの青い空、砂漠を舞台に、
快楽や幻想の地獄絵図を絢爛豪華に繰り広げ、
一部の熱狂的な支持を得た。
あの寺山修司が狂喜乱舞し、
ジョン・レノンが配給権を買ったという、
誉れ高きこのカルトムービーの傑作をみて、
自分もとにかく震撼させられた。
これほどまでに、
魂を揺さぶられる映画というものがあるだろうか・・・
たちかわり現れるフリークスたち、
殺戮、血、エロス、神話的世界。
宗教的倫理感など、
安っぽいものはここでは全く意味をなさない。
映像におきかえた錬金術的な魔界の風景が
渺漠たるまでにそこにあった。
が、そのまばゆいばかりの幻惑は
詩人の内的宇宙の発露であり
それはひとりの詩人の遍歴によって
幾重にも塗り替えられてゆくのであった。
そのときに懐胎した思い、
ホドロフスキー何者ぞ?
という微熱が内から離れず、
けして寡作ではないこの作家の、
定期的に発表された作品に触れながら、
ようやくこの『エンドレス・ポエトリー』に至って、
その源泉のなんたるかを理解できた気がする。
だか、それが何だというのか、
詩は何人たりとも翻訳など、許してはくれぬ。
かような、特権的言語である。
この映画の主人公アレクサンドロこそが、
若き日のホドロフスキーその人であり、
前作『リアリティのダンス』に続く、
まさに自伝要素の高い作品として、
詩のマジックを借りて出来上がった映画。
それが『エンドレス・ポエトリー』である。
詩に魅了され、詩人になり、
ドリームキラーたる父親を乗り越えて
人生を切り拓いてゆく、
まさにその姿が、夢のように妖しく、
幻惑的でありながらも、
心揺さぶる情感豊かな人間讃歌の絵巻物として、
展開されてゆく。
もちろん、ホドロフスキーに終わりなどない。
そして詩というものが、
永遠を行き来する魂の言語であるとばかりに、
感動的なラストシーンが用意されている。
まさにアレクサンドロは、
永遠とつがった海を、
ひとり船でパリへと旅立ってゆくのだが、
我が人生にも重なる運命の強度が、
最高潮に達したのか、
思わず涙腺が溢れんばかりになってしまった・・・
エンターテイメントとしての『エンドレス・ポエトリー』には、
どこまでも快楽が満ちており、
詩人というものはかように愚かしくも、
阿保でありながらも、なんとも素敵で、
なんと心踊る感性を備えているものなのだろうか。
まさに毎日がカーニバルなのだ。
ホドロフスキーの末の息子アダンが
アレクサンドロを分身のごとく演じれば、
『エル・トポ』で奇しくもデヴューした、
あの裸の少年ブロンティスが、
今やアレハンドロの父ハイメとなり、
あの強烈なインパクトを醸し、
圧倒的な存在感を示してくれたのが、
初めて恋に落ちたミューズ、
ステジャ・ディアスと母親サラ役を
ひとり二役を演じるという、
このオペラ歌手のパメラ・フローレスの擬態ぶり。
そして、90歳の声を聞こうかという、
伝説のカルト作家自身が登場しながら、
血縁をすべて巻き込んだ
一大スペクタクルを繰り広げるのである。
素晴らしきホドロフスキーとその一族、
そしてポエトリーの聖なる血に献杯しよう。
衣装には妻のパスカル・モンタンドン、
撮影監督にはウォン・カーウァイの映画で知られる、
クリストファー・ドイル。
とにかく贅沢な映像のマジカルツアーを堪能あれ。
自分の目で体験するより他、
この映画を語る言葉は存在しえないのだ。
これを観た後では、
1975年に企画した幻のSF大作『DUNE』が、
ドキュメンタリーではなく、
もし本編が完成されていたなら
もの凄いことになっていたんだろうな
そんなつぶやきが漏れてしまうのである。



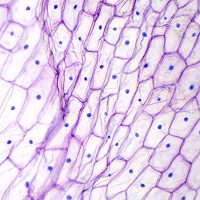









コメントを残す