リテラチュールとシネマのリテラシーを読む
夏は、お気に入りの文庫を数冊荷物に忍ばせて、
ぶらり、バカンスに出たくなる季節である。
本が好きで、文学が好きで、なにより活字好き人間ではあるのだが、
昔に比べて読書量が減っているのは間違いない。
そのインプットにかける時間が足りないと自覚する。
モノとしての本、そのものへの関心が薄らいでおり、
本を買うことも滅多になくなっていることもある。
とはいえ、ネットに無尽蔵に転がるテキストに目を通しながら
日々、ブログにしろ、記事を書く機会、その意欲もまだある。
こうした矛盾をかかえつつ、老後は、気長に読書三昧で、
とはいかないところに、今日の情報過多社会の幻想があり、
多様なメディアに囲まれ生きるジレンマがあるのだと
痛切する今日この頃である。
映画はどうだろうか?
映画に関しては、常に一定量、相変わらずインプットはするし、
関心も日増しに湧いてくる。
とかく、視覚芸術の誘惑には抗えないのだ。
映画を見ることは、物質ではなく、行為であり、
思考のプロセスにとっては最適なメディアだという後押しもあるのだが、
一本の映画から得る情報量と、その考察は、読書にも十分匹敵する。
むろん、読書の快楽とは異なるが、映画には映画の快楽がある。
かつて、名画座などでは、文芸作品がプログラム上に乱立し、
それはそれで、趣きと風情を漂わせていた。
文学の映画化。映画としての詩。
近頃では、話題に挙がる文芸作品からの映画化は珍しくないが、
それまで読んでいた文学が映像に還元され、その世界がどう変わるというのか?
そこにどういう相乗効果があるのか、とふと立ち返ると、
これはなにも、あえて声をあげるまでもなく、深みにはまるのは避けられない。
文学と映画における、この危険な関係性に触れてみることとは
そういうこと、つまりスリリングなのである。
この二つのことなる表現の間を行き来した作家、
たとえば、コクトーをはじめ、デュラスはいうまでもなく、
ロブ=グリエ、寺山修司などは生涯にわたって野心的だったが
ゴダールを筆頭に、テクストを意識的に取り込むスタイルは
映画をいやがおうにラディカルな表現へと押し上げた。
そうした意識に、当初から目覚めていた作家の作品を通して、
あるいは無自覚にも、映画の誘惑に抗えなかった作家たちの、
文学と映画の間にあるリテラシーの解読を、
ここでは視覚のアバンチュールとして、
勝手気ままに解体してみようというのがその主旨である。
もちろん、文学はあくまでも文学であり、
映画は所詮、映画に過ぎない。
同じ物語でも、そのふたつは似て非なるものである。
デュラスはそれをシネマ・ディフェラン(異質の映画)とよんだ。
とはいえ、はじめに文学として成立していたものが
映画というメディアに置き換わったときに生じる化学反応は
一筋縄では読み解けない。
そこにあらたな解釈がうまれおち、
興味深いテーマとして書き換わるというようなことが
起きるということはだれも否定できまい。
あるいは最初から意図されたテクストの磁力が
新たなるテクストとしての映画に再生される瞬間の聖なる体験。
それこそはまさにシネマ・ディフェランと呼ぶにふさわしい。
映画を「詩人による最大の武器だ」と称したコクトーだが、
すくなくとも、ここではまずは、文学ありき。
そして、その上で映画がどうあるのか?
テキストを追う視線が、いつしか映像へと変わるその景色について
言葉を投げかけようというのである。
そのあたりの関係について、はっきり“考察”と銘打つまではいかなくとも、
作品を取り上げて、浮かび上がるものについて考えてみよう。
Bruno Ganz:Andenken (Friedrich Hölderlin):
“Was bleibet aber, stiften die Dichter.”
―「だが、残るものを築くのは、詩人たちである」フリードリヒ・ヘルダーリン 「Andenken(記憶/思い出)」より
こちらは、詩と音響のアヴァンチュール。ヴェンダースやアンゲロプロスの映画でなじみのある俳優ブルーノ・ガンツは、ぼく好みの俳優のひとりだが、ECMレーベルに残したフリードリヒ・ヘルダーリンの詩を朗読したアルバムを通し、文学の可能性、さらに音響から映像へと昇華する気配を追ってみよう。このアルバムは21トラック構成で、ヘルダーリン詩の他、ルネ・シャールやヨハンネス・ベッヒャー、パウル・ツェランも含まれる、文学(詩)と音響との境界をめぐる興味深い探究の響きが聞こえてくる。ブルーノ・ガンツの朗読というと、ヴェンダースの『ベルリン天使の詩』でのペーター・ハントケの詩でなじみがあったのだが、ここでは、さらに文学と詩による境界を越えとする、深い考察へと足を踏み入れる契機を与えてくれる。詩の構造上そのものが、断片的で非線形的であるがゆえに、ドイツ語がわからなくても、その音響だけでも十分心地よい響きと啓示がある。そこからでも、十分この詩情を嗅ぎ取ることができるが、たとえば、ヘルダーリンの「Andenken(記憶/思い出)」は、後期詩の中でも最も謎めいて、五連からなる荘厳な響きをもつ代表作であり、そこに愛、河川、土地、詩人の存在といったテーマが、波のように交錯しながら流れている。それはボルドーを流れるガロンヌ河の美しき流れから、ボルドーの地を経て、大地を離れ遠く海へと連なるといった、土地と記憶の霊性が、詩人の覚醒へと導く詩情として美しく横たわっている。
特集:リテラチュールとシネマのリテラシー、視覚のアバンチュール特集
- 忘却の彼方に番う海・・・マルグリット・デュラス『マルグリット・デュラスのアガタ』 を視る
- ブラックジョークで不条理を侵犯する話・・・オーソン・ウェルズ『審判』を視る
- 男と女の六道めぐり・・・鈴木清順『陽炎座』を視る
- もう鏡はのぞけない・・・塚本晋也『双生児』を視る
- 復讐するは誰にあり?・・・リチャード・ブルックス『冷血』を視る
- 吾輩は語り部である・・・市川崑『吾輩は猫である』を視る
- 失われた空を求めて・・・吉田大八『美しい星』を視る
- 奇書のドグマ・・・松本俊夫『ドグラ・マグラ』を視る
- 禁忌キッズのカタルシス・・・ジャン=ピエール・メルヴィル『恐るべき子供たち』を視る
- 視覚の情念をめぐる不条理の恩讐・・・石井岳龍『箱男』を視る
- 読み語るムジカと聴き視るポエジア・・・文学と音楽をめぐる調べプレイリスト前半(小説編)
- 読み語るムジカと聴き視るポエジア・・・文学と音楽をめぐる調べプレイリスト後半(詩編)

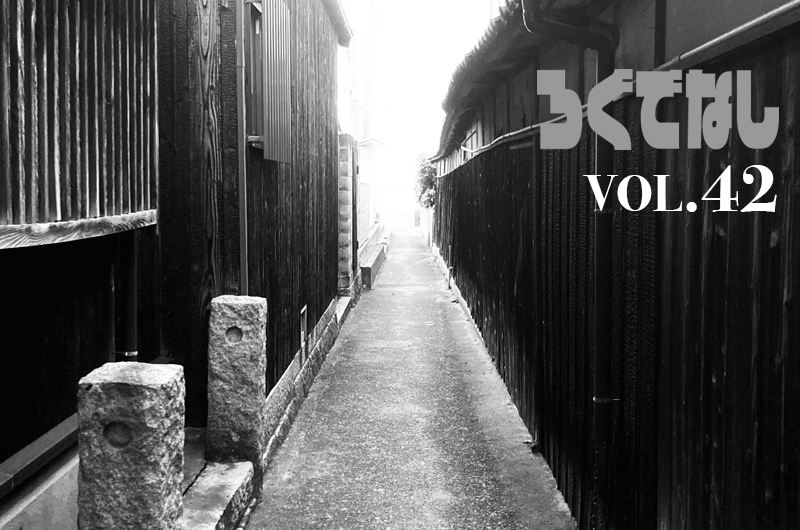





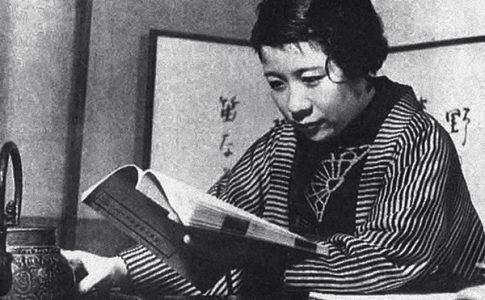

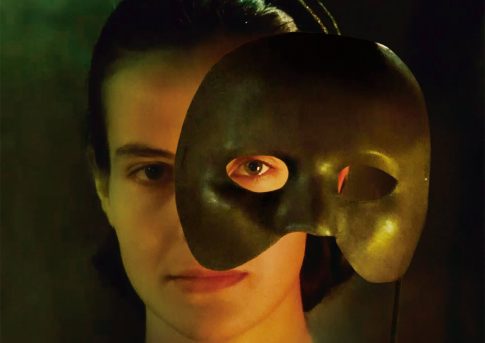



コメントを残す