愛しのヘルシンキ暮色よ、おかえりなさい
カウリスマキが前作『希望のかなた』の後
そういえば、引退宣言をしていたな、というか
そんなことをすっかり忘れていたことに気づいた。
長年カウリスマキとその映画を愛してきた人間からすると
ずっと身近にいる存在でもあり、
何度でも繰り返し過去の作品をあれやこれやと見ているからか、
引退、という言葉がにわかに信じ難く、
どうせ、そのうち戻ってくるだろうぐらいに思っていたのだ。
そこからの見事な復帰作『枯れ葉』でのヒット。
なんだか自分ごとのように嬉しくなってくる。
しかし、これまたカウリスマキらしい憎い“演出”にも思えてくるが、
さて、どうだろう?
これはもう、カウリスマキ好きにとっては
『枯れ葉』は別段目新しい映画でも、気をてらった映画でもない。
その手作り感、朴訥感、淡々感、なんでもいいのだが、
カウリスマキ調と呼ばれる独特のノリは健在で、
いつもながらの画調であるのはいうまでもないが
それでも、季節の変わり目の如く、微妙な変化は感じとれる。
少なくとも『パラダイスの夕暮れ』『真夜中の虹』『マッチ工場の少女』といった
初期のプロレタリア映画三部作の頃と比べると、
より温かみがあり、わかりやすく、親しみが増したような気さえする。
とはいえ、長年カウリスマキ作品のヒロインだったミューズ
カティ・オウティネンも盟友のマッティ・ペロンパの姿も
もはや画面のどこにも登場しないのだ。
それにはちょっとした寂しさはある。
カティは歳をとり、今回は出番がなかった。
マッティに至ってはとっくの前に他界してしまっている。
この『枯れ葉』が、社会の底辺で孤独に生きる男女、
ふたりのラブロマンスを描いた作品という意味では
ゴミ清掃員とスーパーのレジ係との不器用な恋物語を描いた
ちょうどぼくが懐かしむ盟友二人が主役の『パラダイスの夕暮れ』のリメイク版、
そういってもいいのかもしれない。
ここではカウリスマキ作品初出演の二人が、その分新鮮に映る。
まず、主役のアンサ役のアルマ・ポウスティ、
『TOVE / トーベ』でトーベ・ヤンソンを演じた女優で、
ここでの役柄は、いつもながらの薄幸な女性像をあてがわれてはいるが、
どこか希望を感じさせる芯をもった女性として溶け込んでいる。
映画は晩秋だ。
(アキが尊敬する小津映画に多いシチュエーションとも言える)
同時に、ラストシーンをまたずとも
人生の「秋(場末感と申しましょうか)」
そのものを感じさせる深みに彩られている映画である。
失業、貧困、アル中、社会的問題はいざ知らず、
背景にはウクライナ戦争の生々しい傷跡を
しっかりと(テレビではなく)ラジオニュースに忍ばせるのは
芯は熱く、強い男カウリスマキの、
ささやかな戦争への抵抗と嫌悪なのだ。
描く対象は、大抵は虐げられた労働者か、境遇の厳しい移民たち。
常に、社会情勢に敏感でありつつも
底辺には、いつも、さりげない愛を忍ばせて、
ささやかな希望を投げかける映画を撮ってきたこだわりの作家であり、
この『枯れ葉』では、あらたな中年カップルを登場させ
相変わらず、パッとしない者同士が結ばれる様をしんみり描いている。
その過程は紛れもなくカウリスマキの世界である。
特有のロマンティシズムとユーモアが、
淡々とアクセントを刻んでゆく、無駄のない81分。
職人芸とはまさにこのことである。
アンサは職場(スーパー)で
貧しき人に同情したことで理不尽にも職を追われ
皿洗いに就けば、店主が逮捕され、蓄えも底をつき
結局、土木現場の雑用につきながら、かつかつの生活を強いられる状況。
ユッシ・ヴァタネン扮するホラッパは、
移民労働者たちばかりのリサイクル業者の現場で働いているが、
人付き合いが嫌いで、仕事中にもアルコールに手を出すぐらいのアル中で
仕事も続かず、みすみす不幸を呼び込む希望なき生活をおくっている。
そんなふたりが知り合うのがカラオケバー。
縁をとりもつのが歌であり、映画というわけだ。
この二軸はカウリスマキ作品には不可欠な要素であり。
いきなり聞こえてくる日本の歌「竹田の子守唄」からして、にんまりさせられる。
日本人でさえ、なじみの薄いこんな曲をもってくるところに
カウリスマキらしいニクさがあるのだ。
そういえばかつて、『ラヴィ・ド・ボエーム』でも
フィンランド在住の日本人篠原敏武が歌う『雪の降るまちを』を使っていたっけ。
その他にもシューベルトやチャイコフスキーのクラシック曲から
ご機嫌なマンボ曲「マンボ・イタリアーノ」、
フィンランドの大衆歌謡曲などを随所に散りばめながら、
音楽がいつも以上に重要なアクセントになっている。
「この世で寿命が尽きたら地中深くに埋めて欲しい」そんな内容の歌
その名も「悲しみに生まれ、失望を身にまとう」を聴かせるのは、
フィンランドの姉妹シンセ・ポップ・デュオ「マウステテュトット」の生演奏。
カウリスマキが経営する映画館キノ・ライカで撮影されており、
二人が一緒に観に行く映画は(その映画館もキノ・ライカ)
ジャームッシュのゾンビ映画『デッド・ドント・ダイ』だ。
その他、映画館に貼られた様々ポスターからは
カウリスマキの映画愛テイストがこれみよがしに飛び込んでくる。
デヴィッド・リーン『逢びき』やゴダールの『軽蔑』
メルヴィル『仁義』やブレッソンの『ラルジャン』などに思わずニンマリだ。
何から何まで、こうした様々なカウリスマキの嗜好的要素が
宝石にように散りばめられているなか、
ぎこちない二人の愛は秋のごとく、次第に深まってゆく。
お互いに名前さえ知らず、電話番号を書いたメモを無くすホラッパ。
恋する相手をもてなすために、わざわざ食器を買い求め
質素ながらかんばって食事を作るアンサ。
また、彼女の寂しさをまぎらす存在として、
アンサがもらい受ける迷い犬チャップリンは、
実はカウリスマキの愛犬アルマ(そこからヒロインの名前がとられている)で、
こうした表に出ない名脇役までも静かにやさしく寄り添う。
一方、人生の帰路に立たされたホラッパには拠り所はない。
そんなホラッパは、職場の上司に服をもらい
いよいよ覚悟を決め、アンサに会いに行く途中に
交通事故に遭って、病院で生死を彷徨う。
そんなホラッパを支えるのがアンサである。
そこがこの映画のハイライトだ。
かようなまでに、どんなに人生が厳しく、あじけなく、悲惨であっても
カウリスマキの映画はどこか希望を失わない強さと優しさがある。
愛にささえられたホラッパは奇跡の回復をみせる。
そうした情感をミニマムに、そしてさりげなく描き出す名匠。
もっとも、カウリスマキ自身はそうした権威をよしとしない。
絶えずB級作家のノリを崩さないのがいい。
長年培った歩調を改めて繰り返しながら、『枯れ葉』は時代を超えて胸を打つ。
どこかひねくれたおかしみやユーモアを混ぜ込んでゆくその手法は、
引退という名目の充電期間で、さらに円熟味を増したようである。
ちなみに、カウリスマキが小津安二郎を敬愛し、
影響を受けているのはよく知られているが、
『枯れ葉』は以前のどの作品よりも
小津映画の雰囲気漂う映画ではないかと思う。
テーマの繰り返し、そしてスタイリッシュで、厳格なスタイル。
小津の『東京物語』を見て文学への憧れを捨て、
「赤いやかんを探すことにした」カウリスマキは
小津が映画に銃や暴力、殺人といったテーマを持ち込まず、
繰り返し人生の根源を描いた作家であることに感銘を受けたのだという。
そうした思いがこの『枯れ葉』にも脈々と受け継がれているのをみるだろう。
いみじくも、『東京暮色』では、珍しく切ない男女のロマンスを撮った小津。
こちらは、アキによるヘルシンキ暮色。
いつかこの目でその街の哀愁を噛み締めてみたくなる、そんな映画である。
MAUSTETYTÖT:Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin
MAUSTETYTÖT、マウステテュトットと読む。直訳では「スパイス・ガールズ」という意味らしい。ぼくもこの映画でその存在を知った。メンバーは姉妹で、Anna(ギター・ボーカル)と Kaisa(キーボード・ボーカル)の二人組。フィンランド国内では彼女たちのアルバムがチャート上位にランクインするほどの人気を誇り、この映画をきっかけにさらに注目されているのだという。映画内の曲、「Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin」、直訳すれば「悲しみに生まれ、失望に身を包まれて」は、主人公ホロッパとアンザの哀しさや孤独感、そしてかすかな希望を媒体的に表現する“情景としての歌”である。フィンランドの冬のように長く暗い影を帯びた楽曲は、まるで、氷点下の川面に薄く張った氷膜にそっと手を置くような、痛みと快楽が同じ色をしているような、そんな音世界が静かに広がっている。無機質なドラムマシンと、ぼんやりと温度を失ったシンセサイザー、そしてささやきにも似た単音を響かせるギター。この姉妹のハーモニーは冷たさとあたたかさの間で微かに揺れている。「わたしは囚人 永遠に 墓場すらフェンスだらけ この世で寿命が尽きたら 地中深くに埋めて欲しい」なんて歌う感性。そう、カウリスマキ映画のように、「言葉では語れないもの」がある。カウリスマキの目の付け所に狂いはない、というか、流石である。



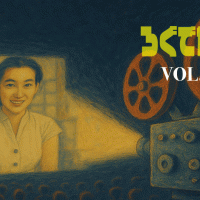

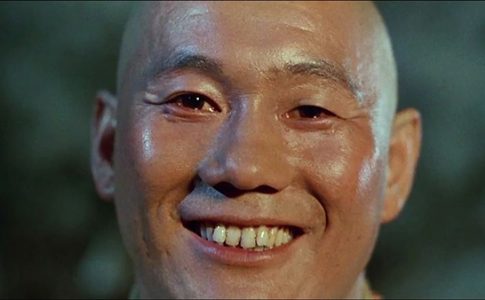
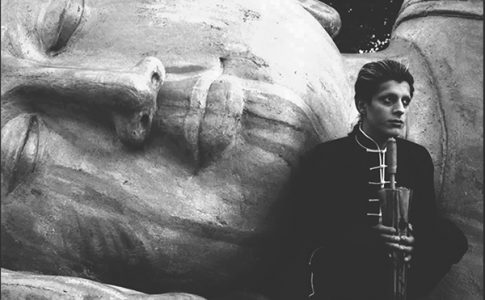






コメントを残す