木漏れ日の向こうの完璧な日
朝の光がトイレ掃除の床に滲む。
平山は黙々とブラシを走らせ、
擦れたタイルに残るわずかな汚れを追い詰めていく。
彼の耳元で、カセットテープの粗末な回転音と共に、
ルーの呟きが聞こえてくる。
Just a perfect day
Drink sangria in the park
ルー・リードの「Perfect Day」。
ぼくはこの名曲を、これまで
今言葉を綴っている以上の深い思いで聴いたことがなかった。
その旋律は、ただ美しいだけではない。
彼のくぐもった声の奥には、どこか諦めに似た寂寥感が滲んでいる。
愛する者と過ごした何気ない一日を“完璧だ”と呼ぶ、その淡々とした口調に
かえって、この世界の不安定さと儚さを鮮明にする思いすら感じるのだ。
平山にとっても、この歌は祈りにも近い思いがするのだろう。
完璧とは、何も無傷を意味しない。
むしろ、欠損や痛み、不在や諦めを抱きしめることで、
初めて手に入る静かな祝福なのかもしれない。
And then later, when it gets dark
We go home
帰るべき“home”はいったいどこにあるのだろう?
平山の一日は、どこにも帰らずに、ただそこに在り続けるだけのように見える。
しかし、木漏れ日の差す公園のベンチで、
木漏れ日にシャッターを切る男の視線に、確かに“home”は存在している。
それは場所ではなく、
繰り返されるルーティンと静かな自己受容の中に築かれた、
彼だけの聖域として描き出される。
実は、ルー・リードの歌には二重性があって
恋人との穏やかな時間を謳い上げる祝福の歌であると同時に、
ドラッグによって得られる一瞬の恍惚と、
その背後に潜む破滅への予感を孕む呪詛でもあるのだ。
「Perfect Day」とは、光だけでなく、絶えず陰影を孕む。
完璧さの中に漂う闇、それが、この歌を永遠のクラシックへと変えたのだ。
だから震えるほどに美しいのだ。
平山の日々もまた、闇を含んでいる。
彼の無口さ、微笑み、静かな所作。
その奥には、かつての痛みや失望、そして諦めの澱が沈んでいる。
けれども彼は、それらを隠そうともしない。
否定もしない。
むしろそれらと共に、掃除をし、木漏れ日を見上げ、微笑むのだ。
You’re going to reap just what you sow
曲の最後に繰り返されるこのフレーズは、
「自分の蒔いた種は自分で刈り取る」という、
祝福とも呪いとも取れる言葉にも思える。
この予言めいた響きが、平山の背中にそっと降りかかる。
彼が今いる場所も、彼がこれまで歩いてきた道も、
全て自分自身が選び取った結果であり、
それを受け入れる覚悟が、彼の所作をこんなにも美しく照らし出すのだと。
映画『PERFECT DAYS』で、この曲が流れるとき、
私たちは平山と共に、東京の街角で、木漏れ日のしたたる路地で、
この世界の完璧さと不完全さを同時に抱きしめるだろう。
ルー・リードの声が歌う「Perfect Day」は、
何も起こらない一日を特別なものへと変える魔法ではなく、
何も起こらないことそのものを、
完璧だと肯定する静かな宣言だ。
完璧な日。
ただそれだけのことが、
どれほど尊く、そして、どれほど儚いことか。
ぼくは教えてもらった。


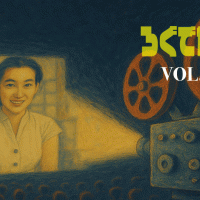

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)








コメントを残す