萌えよドラゴン、母と娘の宝探しロードムービー
いわゆるストーリー追いで済む類いの映画でもなく、
感情に訴えかけてくる話でもない。
実のところ、何が言いたいのかはよくわからない。
そんなジャック・リヴェットの映画を語るにはいささか骨が折れる。
なのに、どこかこなれたマジシャンのようであり、
鮮やかな手つきと、その詐欺まがいの遊び心をも同居させる映画の作り手に
気がつけばどこまでも引き込まれてしまっている。
その上、なにごとかを呟き、だれかと語り合いたい思いさえ込み上げてくる。
が、すべてはなぜだか虚しい。
昨日見た夢について、あーだこーだ
必死にだれかに話しているような気持ちに襲われるからだろうか?
そんな映画に、理屈や詮索の類いを考えて当てはめたとて
容易にすり抜けられてしまうに違いないのだ。
ゆえに人はそれを“映像によるマジック”と解釈し
ひたすら(わかったふりを決め込んで)受け入れるしかない。
マジックのネタ証しをあれこれ想像するうちは楽しいが
いざタネを開示しても俄然興味を失うのに似て、
こちらはその遊び心や想像力に大いにのっかかりながらも、
視点のブレを密やかに楽しむ他ない映画。
その意味ではリヴェットによる『北の橋』は、かつて74年に撮られた傑作
『セリーヌとジュリーは舟でゆく』からの続編、
とはいわないまでも、ファンタジー性やその虚構空間においては
内容は違えど、どこか地続きの映画構造のように映るだろう。
いずれにせよ、物語に容易に収斂されえない展開ながら
本能的な自由を求める奔放さでもって
観るモノを魅了してゆくリヴェットらしい即興性に満ちた
遊び心満載の、謎解き冒険譚であることは間違いない。
ベースになっているのがセルバンテスの『ドン・キホーテ』である。
騎士道物語の深みにのめり込みすぎて
現実とフィクションの境界線を失ってしまった男の冒険譚として有名な、
この物語をリヴェット流に置き換えたのが『北の橋』というわけである。
パリの街の地図を下敷きに、鵞鳥のゲーム(日本でいう双六)と呼ばれる
振られたサイコロの番号に沿って進められてゆく
このヌーヴェル・ヴァーグ的恣意性は、
全編オールパリロケによって、限られた予算と少ない登場人物のなかに、
どこか謎めいた郷愁が押し込められ、
そこから無限のイマジネーションを掻き立てられる不思議な話を扱っている。
まさに現代のロールプレイングゲームの走りとさえいえる内容を帯びているが
いかにしてこのゲームを楽しめるか、
見るものが試され、まるで夢のなかにでも紛れ込んだ時空が広がっている。
その中心人物はパルカル・オジエとビュル・オジエ。
この映画にあって、ふたりのスクリーン上の邂逅こそが
まずは大いなる見どころ、注目ポイントであり
阿吽の呼吸がその面白さの原動力にもなっている。
ダンフェール・ロシュロー広場のライオン像の周りで
どこからともなく鎧を革ジャンに変え
白いミニバイクに白いヘルメットを馬代わり、兜代わりに、
そんないでたちで颯爽と周回するひとりの女
パスカルが演じる現代のドン・キホーテを気取ったバチストが
刑期を終え出所したばかり、閉所恐怖症をかかえた女テロリストたる
ビュル演じるマリーにぶつかり、これを機に仲良くなっていく。
ちなみにそのライオン像もまた、NYの自由の女神をデザインした
オーギュスト・バルトルディ作であるという事を思い返そう。
この物語を理解する上で、「自由」という言葉こそ
念頭に置いておいおくべきキーワードかもしれない。
「1度会うのはまぐれ、2度目も偶然であり得るけど、3度なら運命」
何やら意味深にそう呟くバチスト。
運命の出会いによってなにやら物語が始まるというわけだが、
実の母娘であり、共に脚本に名を連ねているところをみても
ふたりの発想を柔軟に取り入れながら、
自由な映画作りが進められていったのは想像に難くない。
ビュルといえば、伝説の『アウトワン』や『デュエル』等
すでにリヴェット組の主要な女優だったが
一粒種である娘パスカルにとっては、本作がデビュー作であり、
のちにロメールの『満月の夜』にも出演し、将来を期待されたが
誕生日を待たずして前日に25歳の若さで夭逝してしまうことになる。
その意味では、この『北の橋』は
この母娘の共演そのものを刻印した貴重なフィルムである。
そうした成り立ちそのものが、
リヴェット好みの世界観と重なるのかもしれない。
それにしてもこのバチストなる人物は、
なにかを探ろうとしているものの、絶えず挙動不審だ。
今で言うところのメンヘラ女子というやつである。
ポスター写真から目を切り抜いたり、橋の上で空手ごっこをしてみたり、
あるいは巨大な滑り台を前に、奇声を上げて
「ドラゴンだ、駆逐してやる! あんたなんか武器なしで駆逐できるわよ!」
と戦闘的に身構えるシーンなどをみれば
ドン・キホーテが巨人と間違えて風車に突っ込むシーンに
インスピレーションを得ているのかもしれない。
とはいえ、バチストが一体何と、
なぜゆえに戦っているのかまではよくわからない。
これはパスカル自身の声質にもよるのだが、
ほとんど地のままのような気がしないでもない、
どこか子供っぽさと不思議さが同居した唯一無二なキャラクターである。
ひとことでいうと、霞でも食って生きているような女であり、
颯爽と現れ、幽霊のようにどこかへ消えてゆく、
そのなんともつかみどころのない、ある種天真爛漫な女っぷりは
言ってみれば常に仮想の敵と対峙しているがゆえに
尋常の精神状態の人物には思えない。
マリーの恋人であるジュリアンから奪った
そのカバンのなかにあった地図と記事の切り抜きをもとに
いよいよふたりの冒険へと繰り出すのだが、
その地図を媒介させた男ピエール・クレマンティ演じるジュリアンは
ビュルのデビュー作であるマルク’O『アイドルたち』で
すでに共演しており、二人がそれ以来の顔合わせになったこともあり
よりカルトチックな空気感を生んでいる。
最初に断ったように、物語に収斂され得ない展開において
その地図が何を意味し
だれがどういう意図をもっているのかがはっきり暴かれることはない。
とはいえ、バチストがジュリアンの鞄をすりかえてしまったことで
マリーはその恋人によって殺される運命をたどることになる。
そんなわけで、このマリーとバチストが
どうやら危険な遊戯に手を染めているのは間違いない。
そんなバチストを追っているのがトリュフォー映画で見かけたことのある
ジャン=フランソワ・ステブナン演じるマックスだが、
マックスとは?
なぜそのマックスが空手を彼女に教えるのか?
そのあたりを突き詰めていけば、映画のテーマも少しは見えてくるかもしれない。
たとえば、彼女の口から漏れる「バビロン」とは何を意味するだろうか?
元々は古代都市バビロンではあるが
ヒップホップやレゲエで掲げられる「権力」という意味に捉えた方が
この場合、合点がゆく。
つまり、バチストはなんらかの力を前に抗おうとしているのだと。
そう解釈することで、この空手を教えるマックスが
何者かがなんとなくわかってくるような気がする。
「ヤクの売人、監視人、番人よ」というバチストの言葉を鵜呑みにするなら
バビロンの手先、つまりは権力側にも加担する人間でありつつも、
同時に彼女たちを見守る役目でもあるってことにもなろう。
要約すれば、不条理だか不合理だか、とある権力を前に
立ち向かうバチストという風変わりな女の子が
そうした権力側ともなんらかの関係があったであろうマリーと
運命的に出会い、その権力に立ち向かおうとするのだが、
片方はその恋人によって裏切られ、
片方はその権力側?によって守られた、
そのようなストーリーだと受け取った。
いみじくも、1980年代のフランスパリは
当時のミッテランの元、大規模な都市改造計画が行われていた時期であり
映像で見る限り、かなり広大で大規模な都市解体の模様が
随所に映り込んでいる。
そして、ある種のレジスタンスとして、
その記録をこのフィルムに残しておきたかったのかもしれないのだ。
その証拠に、オープニングが
「ずっと昔、1980年10月か11月のこと」という字幕で始まる。
81年の作品なのに、「ずっと昔」のはずもない。
リヴェットはそんな移り行くパリの景観への不当な介入を
快く思っていなかったにちがいないのだ。
さらに踏み込めば、そうした政治的背景に抗おうとする思いが
この『北の橋』のストーリーに見て取れるのかもしれない。
ともあれ、ドン・キホーテの文学的創造性を元に
不思議の国のアリス的謎を散りばめ
そこにリヴェット流の遊戯性を即興的に盛り込んで
パルカル&ビュル、この伝説の母娘の唯一の共演となった本作を、
ウィリアム・リュプチャンスキー、カロリーヌ・シャンプティエという
ポストヌーヴェル・ヴァーグの気鋭のカメラマンを従えて、
5月革命ならぬ、革命戦士の息吹をまとった
ファンタジー系ミステリードラマに仕立てたのだ。
とまあ、ざっと内容をぐだぐだ説明してみたものの
一向にその面白さが伝わらないのがもどかしい。
リヴェット好きなら、その面白さは十分体感できるはずだが
あえて他人に強要すべきものもなく、万人にお薦めはしない。
ならば『セリーヌとジュリーは舟でゆく』の方をお薦めするまでだ。
想像力なくして到底埋め合わせできない、
不思議な磁力に抗えない映画として、
少なくとも、パスカル&ビュルの個性の魅力だけは伝えておきたい。
このパスカルは、私生児でこそないが、ビュルが18歳のとき、
ビーチでたまたま出会ったミュージシャンとの間にさずかった子供である。
(ちなみにその父親はジル・ニコラスという、俳優兼ダンスの振り付け師でもあった人で、写真をみるとパスカルはその父親似であることがわかった)
それ以上のことまではよくわからないが、
この親子を結ぶ摩訶不思議な絆にまつわるエピソードとしては十分である。
ビュルがパスカルのことを長々と語る記事を目にしたことはないが
かつて、舞台から見る景色に、娘の幻影を見るといったようなことを
なにかのインタビュー記事で読んだ記憶がある。
ビュルにとっては、かけがえのない一粒種であったパスカルへの思い。
そう簡単に忘れ去れるものでもないだろう。
それを思うと、やはり『北の橋』は
ビュルにとっても、忘れられない特別な映画だったに違いないのだ。
ちなみに、1980年代のパリを舞台に繰り広げられる、
シャルロット・ゲンズブールがシングルマザー役で主演の
ミカエル・アースの『午前4時にパリの夜は明ける』は
当時のアイコンとして、このパスカル・オジェにささげられており、
映画のなかで映画を観に行くシーンには
ロメールの『満月の夜』、『北の橋』が共にフィーチャーされている。
かつて、ジム・ジャームシュが『ダウン・バイ・ロー』を彼女に捧げたように
次世代の映画人からも熱いリスペクトを受ける魅力的なパスカルの姿を
ぜひその目に焼き付けてほしい映画、それが『北の橋』なのである。
Astor Piazzolla-Libertango
『北の橋』でこの曲が流れだすのは意外といえば意外だったけど、このロックとジャズのとタンゴの融合ともいうべきピアソラの『Libertango』の音色が、パリの街並みを伴って哀愁を掻き立ててくるあたり、なんという選曲の妙だろうか。ちなみに、『Libertango』とは「libertad(自由)」と「tango(タンゴ)」を合わせた造語(かの言葉遊びの達人ルイス・キャロルが好んで使った’かばん語’)である。目に見えない時間の堆積と重み、そして風のようにドラマティックに吹き付ける運命の綾を、この『Libertango』が軽やかに、優雅に寄り添うように流れるのはオツだ。








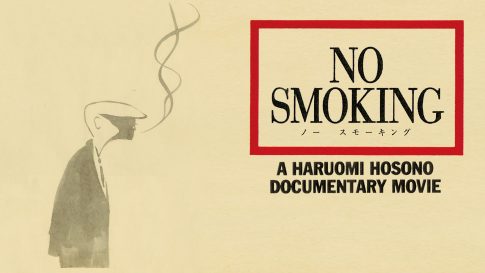




コメントを残す