マッチで夢から覚める話
タバコ、および喫煙者が隅に追いやられる時代。
肩身の狭い思いをしている愛煙家たちには同情するが
それを支えた産業もいよいよ風前の灯、
この昨今のマッチ業界の現状を見れば、それもやむなしか。
確かに、ライターやチャッカマンがあればマッチなんていらない。
電子コンロ(今ではIHクッキングヒーターというらしい。時代感覚というやつはどうにも埋まらないものなのかもしれない)なんかも主流になる時代、誰も困らない。
けれども昭和に生きた人間なら
マッチという名の風情が、なんとなく忘れられないはずである。
それぐらいの感傷なら理解されないこともなかろう。
喫茶店やバーに行けば、大抵名刺がわりにポケットに忍ばせたマッチ箱。
それこそ、デザインを眺めているだけでも楽しかったもので
その筋のマニアもいたことだろう。
さて、そんなマッチに携わる話を、ここで延々とするつもりはないが
そう言った懐かしい味わいがなんとなくくすぐられる映画、かどうかは別として
タイトルが『マッチ工場の少女』で、のっけから
マッチ工場のオートメーション作業が淡々と展開される、
そんな映画について書き始めようと思う。
フィンランドの巨匠、とことわりをいれることもないのだが、
名物監督であるアキ・カウリスマキの
「プロレタリアート三部作(敗者3部作、ともいう)」
要するに、庶民目線の、ちょっと切ないまでの厳しい社会派ドラマだ。
今から40年近く前の映画だけど、スタイル、本質は今とさほど変わっていない。
そこに独特のオフビートなユーモアが乗っかるところに
当時から、安心して見続けられるカウリスマキの名匠たる所以か。
そんなカウリスマキが80年代を代表する一作と言うのが本編。
同じ北欧の童話「マッチ売りの少女」のイメージとは少し違う、いや全く違う、
言ってみればブラックジョーク的なサスペンスの空気が漂っているのだが、
もっと言えば、ちょっとしたホラー的要素もないこともない。
が、そこは定番のカウリスマキワールド全開
ペーソスがたっぷり塗り込まれ、独自の趣旨が貫かれている。
少ないセリフ、感情を排した演技、そして絶妙な音楽センスの3点セット。
その中で主役を演じるのがカティ・オウティネンだ、
今日まで長年カウリスマキ組のミューズを張っている女優。
はっきり言って、美人でもなきゃ、愛嬌のかけらもない。
言うなれば薄幸の女そのものであり、
少女というには随分籐が立っている女(それでもまだ若い)だが
カウリスマキ映画には以降欠かせない女優となる。
それにしてもセリフが少ない。
言葉数、ということだけに限れば
テレビから流れるニュース報道やバンドの歌の方が
はるかに多いのがカウリスマキ映画の特徴である。
単に寡黙というわけではないところがミソだが
セリフを極限にまで削って
その絵、その行動のショットだけで見せてゆく手法は
カウリスマキが親しんだ、どこかサイレント映画を彷彿とさせるが、
大人の絵本といってもいかもしれない。
なにしろ、初めてこの主人公が口を開くのが
映画が始まって13分30秒後、
カフェでビールを注文するその一言だけなのだ。
対人間同士のキャッチボールでいえば
そこからまた9分ほど要して
家を出た兄とのちょっとした近況のやりとりを待たねばならない。
とにかく暗い話であり、救いようがない話なのだが
そこをなんとか笑える、かどうかは微妙にしても、
じわじわこみ上げてくる哀愁こそがカウリスマキの真骨頂である。
主人公イリスの両親はまるで鬼である。
イリスの働きによって家庭が支えられているにもかかわらず
彼女に対する振る舞いや扱いがひどい。
どうやら、父親は義父のようで、どおりで情が薄く冷徹だ。
給料日にそこから服を買っただけでひどい仕打ちをされてしまう。
それでもイリスは希望を外に求め、
バーで知り合った男についてゆく。
とはいえ、その男も別段いい男というわけでもないわりにひどい男で
イリスは一晩の遊び相手、妊娠させられた上に捨てられる。
全くもって救いがない話が淡々と続く。
なんでこうなるの?
なんで不幸ばかりが私を襲うの?
と自暴自棄にでもなってくれりゃ
それはそれで同情できるってもんだが
イリスは黙ってそれを耐え忍ぶのである。
つねに耐え忍ぶことを選ぶのだが、
最後にとった手段は「復讐」である。
孕ませ男に鼠捕りの劇薬を飲ませるというのは、
どこまでも陰湿なやり方ではあるが
陰湿さの描き方がまた独特なのである。
感情を一切入れないことで、表向きの陰湿さにクッションを与えることができる。
乾いた笑い、この辺りがオフビート感覚と言えばいいのか。
とにかく、そうした瞬間のちょっとした間に心が緩む。
しかし切ない。実に切ない。
最後の逮捕劇も、行ってみりゃ殺人犯逮捕劇なのだが
そんな重い気配はこれっぽちもない。
同情するにも感情を押し殺し、
そして不幸を嘆くにも感情はいらない。
ただ目の前の事実を事実として受け取るだけだ。
過剰に装飾されない分、その思いが余韻としていつまでも残るのが
カウリスマキの唯一無二の世界観なのである。
それでも、寒々とした心にマッチ一本程度の火ぐらい
灯したっていいよね、そんな思いのする映画である。
Ralph Towner & Gary Burton : Some Other Time
映画とは何の関係もない音楽だが、ふとこのジャケットが思い浮かんだ。ECMレーベルを代表するヴィブラフォニスト、ゲーリー・バートンとギターリスト、ラルフ・タウナーの1974年の「Matchbook」だ。ヴィヴラフォンとギターのデュオということで“match”というタイトルが使われているのだろう。ちなみに、今懐かしのブックマッチはすでに生産が中止されているものだ。なので、なんともノスタルジックな思いをかきたてるが、音の方は50年前の録音とはいえ、サウンドがクリアで、それこそ新鮮なクリスタルな響きをまとった好盤である。さすがはECMといったクラシカルな趣きとどこか寂しい心にすっとリリカルにはいってくるようなところがある。しずかで空間のひろがりの豊かな室内音楽である。









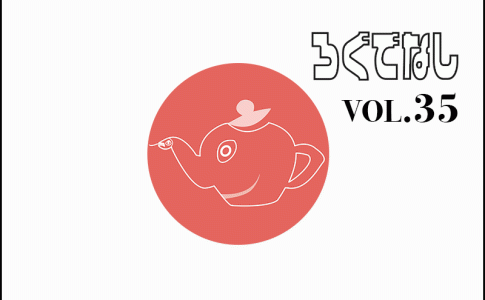
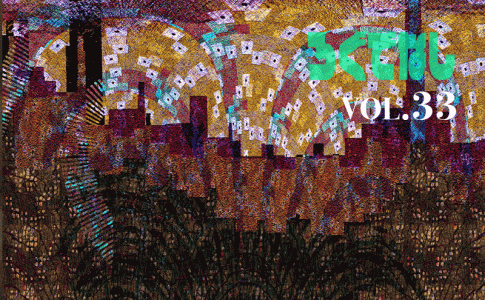


コメントを残す