日本人以上に日本人らしい奥ゆかしさを持つミュージシャン
ジャパンというバンドは、今思うと、
ほんとうに不思議なまでに連帯意識を強く持っていた。
それは、デヴィッド・シルヴィアンとスティーブ・ジャンセンが
実の兄弟であり、ミック・カーン、リチャード・バルビエリにしても
同じ高校出身、馴染みの関係だったということもあり、
ファミリー感が強いバンドであったのは
彼らの音の絆にも、大きく反映されていたといっていい。
それでも、最後は、表に立つデヴィッドとミックの間で、
いわば他のロックバンドにありがちな、仲違いのような形で
わずか五年程度で、その活動が分散してしまった。
ただ、結局二人の確執が問題であって、
それぞれの間の関係は常に良好なまま、気がつけば、
ミックがすでに他界し、デヴィッドにしても、
最近、その活動を半永久的に停止したという噂を聞く。
残ったスティーブとリチャードだけが細々と活動を続け、
すでに真の実力者として認知され、熟練したミュージシャンとして
ゆるぎない地位を築いて、今なお現役で活躍している。
それぞれに、思い入れのあるミュージシャンであることに変わりがないが
とりわけ、その歩みのほどには、随分と温度差がある。
今回は、そのスティーブ・ジャンセンについて書いてみたい。
デヴィッドの実弟として、ジャパン時代は
常に、一歩も二歩も引いた形で、縁の下の力持ちとしての域を出なかったが
ドラマーとしての腕、ミュージシャンとしての進化には驚くべきものがあった。
もはや、ジャパン時代ですら、遠い昔のことのようになってしまったが、
最近では、エグジット・ノースという新たなバンド活動の場を見出し
独自の美学を追求し続けている。
あいかわらず、日本のミュージシャンたちとの交流も活発で
未だ絶大なるリスペクト、人気を誇る玄人好みのドラマーである。
とりわけYMO時代を通して、高橋幸宏との交流は
スティーブ自身、公私にわたって大きな影響を及ぼし続けている。
元はロキシー・ミュージックのオープニングアクトで
サディスティック・ミカ・バンドのロンドン公演の時に
まだ少年だったスティーブがその公演を見て以来のファンなのだとか。
スティーブにとっては一応“師匠“と言うことになっているらしいが
幸宏氏にすれば、お互いに影響を受け合っている関係なのだと言う。
芸達者で、個性が強すぎるミュージシャンが揃うジャパンの中で
対外的な意味でも、テクニックにおいても
誰よりも普遍性を持ったミュージシャンといえば
このスティーブが一番ではないかと思う。
機械よりも正確なドラミングに、
実にこだわりのあるリズムメーカー。
まさにミュージシャンズミュージシャンと言うべき評価が妥当だろう。
おまけに兄譲りのボーカルをとることもあるし、
近年では玄人好みのアンビエントやエレクトロニカにまでおよび
コンポーザーとしてのキャリアも長い。
またジャパン在籍時に始めた写真も
写真集を出したり、個展を開催するほど造詣が深く、
ドラマーを超えたマルチアーティストとして幅広い活躍を見せている。
もともとはジャパンのメンバーの中でも人気は高かったが
最年少で、兄の影に隠れ
その内向的な振る舞いの少年性が魅力的ではあったが
ドラマーとしての成長ぶりとともに
名実ともに目覚ましい進化を遂げてゆくことになる。
遠い記憶の少年性をどこかに引きづりながらも
いまはカリスマ性さえ漂わせた、渋いベテランミュージシャンになっている。
ジャパン時代のスティーブのドラミングやリズムパターンには
ある種の傾向があった。
独自のアクセント、リズム感性を持っており、
二拍四拍にスネアが入ってこないターンだとか
リムショットの多様だとか、 スネアよりもタムを好むであるとか、
あまりハイハットを刻まないとか、
要するに4ビート8ビートといった
とにかくありふれたリズムを嫌い、
凝ったドラミングをただき出すプレーヤーだという印象が強い。
解散して約10年後、実質的再結成した『RAIN TREE CROW』での
『BLACKWATER』と言う静かな曲での
ブラシを使ったドラムプレイもまたそうした一曲だが
これは生ではなく、打ち込みを駆使し構築している。
つまり、生でも叩けるところを、エレクトリックなループも取り入れたりと
アコースティックとエレクトロニカサウンドの融合を
時早くから取り組んでいたスティーブは
ライブでもHandSonic 10やSPD-Sといった
エレクトリックパーカションを取り入れてきたという点で、
かなり柔軟なプレイヤーだと言うことが言えるだろう。
もはや職人領域のプレイをさりげなくプレイできる、
匠のミュージシャンの域に達している。
反面、ミック・カーンやシルヴィアンの
ソロライブにおいてのサポートプレイでは
意外にも身体性の強い、パワフルなドラマーだと言う印象もある。
個人的に好きなドラミングは色々あるのだが
ジャパン時代ではカバー曲の時に顕著に感じる。
たとえば『Quiet Life』でのベルベット・アンダーグラウンドの曲 、
「All Tomorrows Parties」に非凡なセンスを感じていた。
ここではリムショットをうまく多用して
原曲にある呪詛的なムードを一層し
モダンに解釈し直した曲調へ押し上げおり
もはやジャパンのオリジナルといっても過言ではないほどのアレンジに仕上がっている。
あるいは『Gentlemen Take Polaroids』では
マーヴィン・ゲイの曲 「Ain’t That Peculiar」のドラミングも秀逸だった。
リズムボックスの音と絡みながら、
これまた原曲の面影などどこにいってしまったのか、
オリジナリティの非常に高い楽曲となっているのは
紛れもなくスティーブによる部分が大きいように思われる。
『Tin drum』まで来ると、アートの域といっていいほど、
ドラムフレーズが洗練されてきているのがよくわかる。
「The Art Of Parties」や「Still Life in Moblie Homes」 のような
エレクトリックでパーカッシブな音と絡み合った
忙しく複雑なリズムが聴けるかと思えば
「Sons of Pioneers」では究極のプレイが堪能できる。
この曲の作曲クレジットからすると、
ミックのベースのリフから生まれた曲ではないかと推測されるが
スティーブはそのベースの音に合わせ
タムをうまくローリングしながら
ボーカルを邪魔しないように
ミニマルなリズムを構成している素晴らしいトラックである。
まさに侘び寂びの域である。
この手のタム転がしはスティーブの十八番で
『RAIN TREE CROW』での「Black water」もそうだし
「Big Wheel In Shanty Town」でも聞くことが出来る。
その他、シルヴィアンのファーストソロ『Briliant Trees』以降、
スティーブの貢献度は極めて高いように思う。
ソロになってからのシルヴィアンにとっては
実弟であり盟友であるスティーブの存在無くしては
成立しないほどの絶大なる信頼関係が伺える。
そのライブ活動のほとんどで、サポートしてきた。
実験的な音楽からポップ・ミュージックに至るまで
こうしたスティーブ・ジャンセンの自在性は、
2007年自身初のソロ・アルバム『SLOPE』を出すまでは
ジャパン解散後に組んだリチャードとの『The Dolphine Brothers』を皮切りに
シルヴィアン抜きの元ジャパンのメンバーでの
相互扶助的な活動で生計を立てながら
対外的なセッションプレーヤーとして揉まれてきた産物なのだろう。
そんなスティーブにとって
高橋幸宏との相性がよっぽどあうようで
今尚良好な関係を継続している。
そんな二人が初めて共演したのは
1982年、ジャパンのラストコンサートだったはずだが、
その後高橋幸宏の国内ツアーやアルバムに頻繁に顔を出している。
中でも1986年発表のシングル『STAY CLOSE』では
ツインボーカルで息のあったところを聴かせてくれる。
そのPVでは二人の良好な関係性を端的に示しており、
なかなか貴重で微笑ましい映像だ。
幸宏氏のロマンティシズム、
スティーブの初々しいジャポネスク叙情。
二人のドラマーが生み出すコンビネーションには思わず頰が緩む。
スティーブも若いが、幸宏氏も若い。
これは完全に幸宏テイスト主導による小津パロディなのだが、
剣道をするシーンや、女の子を取り合うシーン。
囲碁をしたり、屋台で一杯飲んだり、ダンスをするシーンなど、
ユーモアたっぷりに構成された中に
中原中也を愛する幸宏氏独自の美意識とペーソスが
全編に散りばめられた秀作だ。
このころのスティーブ・ジャンセンには
どこか俳優の細川俊之にすごく似ているときあったのだけれど、気のせいだろか?
イギリスと日本、同じ島国と言うこともあるのか
なんだか、日本人以上に日本人らしい奥ゆかしさ
雰囲気を持った不思議な英国人ミュージシャンである。
そう言うところが、この日本で爆発的な人気を誇った要因でもあるのだろうか。
人間的にも、音楽家としても、リスペクトする声がやまないのは、
そういった、日本人気質をほどなく理解する精神性、相性からきているのかもしれない。
あらためて、スティーブをはじめとするジャパンのメンバーが
いかに日本という国になじみ、
愛されていたかがうかがえるそんなPVでもあるのだ。




![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)

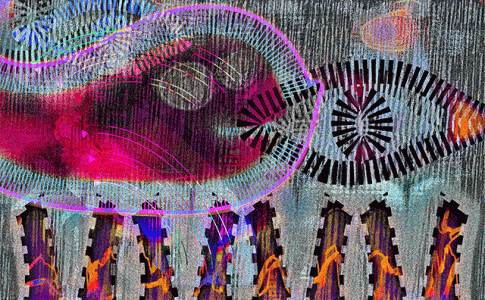

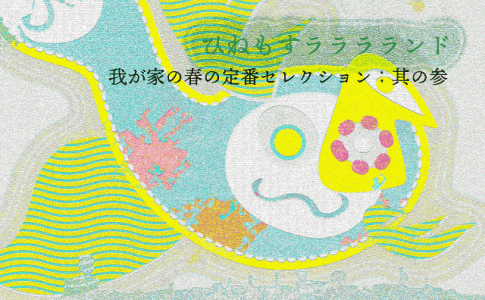




コメントを残す