弔いのあとにさすらいの日々を
ショーケンこと萩原健一が荼毘に伏して早一年の歳月がすぎた。
訃報のニュースを耳にした際には
ちょっとばかし、しんみりとしたものが込み上げたものだが、
実をいうと、晩年のショーケンをみていると、
どこかその魅力というのか、オーラというのか
自分の認識との間に幾分ずれた部分が
日増しに大きくなってゆく気がしており、
ある意味、そのもやもや感、空回り感が、
死という厳粛な儀礼によって
いったんリセットされ、安堵さえ感じるといった、
複雑なる思いをまずは告白しなければならぬのだ。
時代を駆け抜けたひとりのカリスマの唐突すぎる死に
それ以上の言葉がついて出てこなかったとはいえ
時間と共に、それでも何か思いのほどを
書き記しておきたい欲求にいつだって抗えずにいる。
俳優萩原健一、ロッカー兼問題児、享年69歳。
そのどちらにも触発を受けて育ってきた世代の人間として
内田裕也に続いて、昭和のロックスピリットを持った人物の不在感には
やはり、一抹の寂しさを感じるのはある意味当然なのである。
それはどこか、別れた恋人への未練に似ているのかもしれない。
とにかくショーケンという人は
我が世代にとって、まちがいなく代表的なアイコンであった。
とりわけ『傷だらけの天使』のオサムちゃんには
いまなお、いびつなまでの情をかかえこんでいる。
それはなにも自分だけの戯言でもあるまい。
その話だけで仲間意識が芽生えるぐらい
共通認識としてもその影響力には計り知れないものがある。
まさにアキラよろしく
「兄貴ィ」と慕いたたくなるほどのまぶしいスターだった。
グループ・サウンズ全盛期、テンプターズのころ、
言うなればアイドル時代に関しては
流石にほとんど何も知らないも同然だが、
「太陽に吠えろ」でのマカロニ刑事や、
そのあとサード助監督として予定されていた映画『約束』で
主役降板からいきなり主役に抜擢され
あの岸恵子と対照的な非俳優的演技で本格的にスタートさせたのを始め
『青春の蹉跌』や『化石の森』と言った初期代表作、
『雨のアムステルダム』『八つ墓村』、
そして80年代に入りターニングポイントにもなった黒澤の『影武者』
あるいは隠れた傑作伊藤俊也の『誘拐報道』など、
時代と共に円熟味を深めていった軌跡は
今見ても、圧倒的存在感は色あせてはいない。
無論、俳優だけではなくロックシンガーとしても
そのオーラは眩しく輝いており、兎にも角にも
ああいう不良っぽくも、少年のような人っていうのは、
いそうでいない。
しかし、時代の寵児という言葉をあえて使うとしたら
やはり『傷だらけの天使』、通称「傷天」、
このショーケン伝説を世にしらしめた出世作が
約半世紀の時の流れを経た今なお、
一つのカルチャーとして君臨していることを放置できはしない。
演技なのか、地なのか、まさに既成の文法を逸脱した演技は
当時のドラマとしても、全くもって革新的と呼べるものであった。
あのオープニングのおけるショーケンのかっこよさを
一体何に譬えればいいものか?
水中メガネにヘッドホーン、革ジャンを羽織って
ベッドから飛び起きてコンビーフやトマト、クラッカーを食う、
牛乳を飲む、ただそれだけの一コマで
これほどまでに観るものを釘付けにできるのは、
演出もあるが、ショーケンのカリスマ性が凝縮された、
いまだマニアの間で語り継がれている所以だろう。
そのあとの『前略おふくろ様』では
アウトローからうってかわって、純な板前を演じている。
これまた伝説という安っぽい言葉に薄められないほどの
脂ののった充実した演技の幅をみせてくれた。
これは脚本家倉本聡にとっての傑作ドラマでもあり、
ショーケンの天才性、あるいは、役者としての可能性を
押し広げる格好で一世風靡した作品である。
傷天で好き勝手やって境地を開いてきたこの俳優から
あえて自由を奪うことで、
新たな魅力を引き出すことを意図的に狙って書かれた台本である。
このサブちゃんもまた『傷天』に劣らぬ捨てがたい魅力に溢れている。
何しろ、銀幕の大女優田中絹代女史
その人がおふくろさまであり、
輝かしい女優遍歴の、有終の美を飾ったドラマでもあるが、
花板梅宮辰夫や鳶職人室田日出男のにらみの下で揉まれながら、
深川の純朴な半人前の板前を見事に新境地を開いてゆく。
『傷天』と違っているのは、スターショーケン以上に
こうした周りの鉄中錚々たる顔ぶれの役者たちによる
活躍ぶりが目を惹くドラマ仕立てになっている点であろう。
倉本聡が、最終回のエンドロールで、
このドラマを関わったすべてのスタッフに捧げる思いを
明確に示していることに象徴されている。
そうした比較はさておくとして、
何より、ショーケンは、物作りに飢えたクリエーターであった。
その欲求が俳優の道に天才を駆り立てた、と言っていいだろう。
ショーケンが抱えもつ神話性は
当時の文化背景、とりわけ斜陽化激しい映画界から
流れてきたスタッフに彩られた、
今となっては奇跡と言っていいほどの自由さ、
大胆さの中、完全なる現場主導主義の産物として
カルト的な風情を醸し出す土壌にあった、
という裏付けに支えられているところにある。
実際に『傷天』は東宝のアクション映画で辣腕を振るった
深作欣二をはじめ恩地日出夫、工藤栄一、鈴木秀夫、
ショーケンとも仲のよかった神代辰巳と言った錚々たる映画人が顔を連ね、
当然、俳優たちも絢爛豪華なメンツが脇を固めた。
カメラは黒澤組でもまれた木村大作がメインを務めた。
そんな贅沢な背景の元に、
弟分の水谷豊、そして岸田今日子に岸田森
こうしたキャラクターたちの個性的な存在感に惜しみなく彩られた画面は
即興やタブーを厭わぬいくつもの偶然性のなかで、
制約多き今日の電波事情や
そのなかば去勢された社会観からはとうてい考えも及ばない、
不世出の傑作を生み出していったのだ。
ファッションや言動のみならず、
まさにそんな時代のアイコンそのものたるショーケンが刻印されている。
もっとも、私生活では色々問題の多かった人なのは周知のごとく、
むしろスクリーンよりもお茶の間にゴシップを提供し続けた
いわば自業自得のマイナスイメージが、
随分とその経歴に泥を塗ってしまったことは否めない。
いわゆるロックスターとして見れば
それぐらいのヤンチャっぷりなど、どうってことでもない気もするが、
日本ではそれが致命的になるし、まさに不幸でもあった。
何より、そんなつまらないことばかりで世間を騒がしてどうする?
そういう思いだけが苦々しく残った。
度重なる不祥事、そして謹慎。
そしてテレビ界やマスコミからの閉め出し、
結果、お遍路さんを巡礼する姿もあった。
一時は隠遁生活を余儀なくされていたりと
晩節には決して恵まれれなかったのは間違いないところだが、
一応、浮名だけはしっかりと流していたショーケン。
そのことがさらなる誤解を生み、かつての名声にさえ
ケチがつきかねない扱いのまま、他界してしまったことは悔やまれる。
晩年の姿を見れば、過去の栄光で持ち上げられはしたが、
自身が満足するようなものは何一つ残してはいない。
もう少し生きていれば、時代は再び彼を欲したかもしれない。
生来の探究心や好奇心が新境地を開いたかもしれない。
少なくとも、かつてのショーケン全盛期のパフォーマンスを見れば
このカリスマ的存在のスターのオーラに素直に期待せずにはいられないのだ。
ちなみに今日のタイトル「弔いのあとにさすらいの日々を」は
実際の『傷だらけの天使』の最終回
「 祭りのあとにさすらいの日々を」をもじったものだ。
結局、逃亡にも失敗し、ただ塵のように
一人、さすらいの旅に出ざるをえなくなったオサムは
ついに永遠の流浪者になっちまったわけだ。
やっぱり、あなたは忘れられない時代そのものだった。
さらばショーケン。
ありがとうショーケン。









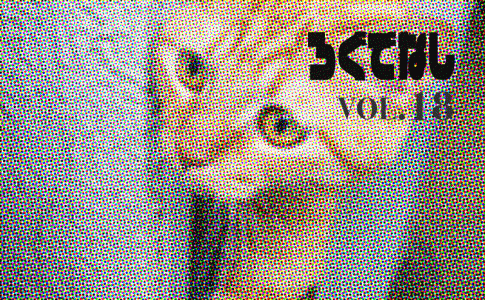



コメントを残す