覚めやらぬ背徳劇場の支配者に告ぐ
美術批評家のロバート・ヒューズは
フランシス・ベーコンという画家のことを
「20世紀のイギリス、いや世界で最も激情的で叙情深い芸術家」と呼んだ。
『叫ぶ教皇の頭部のための習作』が55億円で落札されたというから、
その存在がいかにカネを生むか、いや、存在そのものがいかに
注目を浴びるアーティストであるかがうかがい知れるのだ。
もっとも、ベーコンという人は自作への破壊癖があって
作品の希少価値が高い作家だと言う一面もあるぐらいである。
一筋縄でいくわけもない。
そんなベーコンは好き嫌いがはっきり別れる画家だ。
いわば極端なまでの嗜好芸術である!
確かに、その絵の前に佇むと、言い知れぬ不快感、恐怖、脅迫概念・・・
負の情動に突き動かされてしまうだろう。
だからといって、安易にベーコンの絵が嫌いだ、
などといってしまうことにも抵抗を感じるのだ。
ならば、ベーコンになぞ、触れるまでもない、
と人は思うかもしれない。
そこがベーコンのべーコンたる所以。
その絵をみて、素通りできるような代物ではないのだ。
何か言葉で情動に寄り添いたい気持ちが押し寄せてくる。
その情動は、あたかもホラームービー見たさの好奇心に似ている。
要するに怖いもの見たさ・・・
だれもが抱え込む内なる衝動が
呼び覚まされるような心理なのかもしれない。
だが、あえて、そうした軽率な行動を控えよう。
なぜなら、ベーコンの絵は言語というものへの移し替えには
すこぶる頭を悩ませるアーティストだからである。
同時に、ベーコンという人の生涯はその絵画以上に
興味深い数々の側面を残している。
まずは同性愛者であったこと。
これはベーコンの生涯につきまとう事件性の一端を
確実に握っていたのは間違いはない。
ときに火種になり、ときにインスピレーションの源泉であった。
その生涯は次々と愛人との逢瀬を繰り返す日々であった。
そもそも、ベーコンには子供の頃から同性愛の傾向を抑えきれず、
それが元で家を追い出されて以来、
家具の設計からインテリアデザインに従事し、
グルメやギャンブルに溺れる享楽に悶々とした日々の中に
独自に絵画に目覚めていったという、
いわば愛を求めつづけた文字通りの放蕩息子なのであった。
母親の下着を纏う女装癖があり
食通、衣服、インテリアに対する興味嗜好をもち
アレルギー体質でありながらも
アトリエは足の踏み場もままならないほど雑然としていたというから
その作風通りに一見相矛盾した自家撞着の闇のなかで
激しい衝動のようなものと対峙する激情的な創作活動が
亡き今も衝撃さめやらぬ絵画のエネルギーを放出せしめる
そんな希有なアーティストなのだ。
ベーコンの作品を初めて見たときに
一体なにが起こっているのか、皆目見当がつかなかった。
そのただならぬ気配の中で心かき乱されたのが、
実質ベーコン処女作として知られる
『キリスト磔刑図を基盤とした3つの人物画の習作』であった。
連作になっており、しかも、具象でも抽象でもない。
なにやらおぞましいものに魅入られてしまう体験に
思わず視線が固まってしまったのだが、
当人が語るように、これはピカソの影響、
あるいはギリシャ神話の復讐の女神ユーメニデス、
グリューネヴァルト 「辱められるキリスト」などのモティーフが
バイオモーフィズム(抽象と具象の中間概念)として一体化し
顕在化したものだという解釈に一旦は行き着くことになる。
だが、頭で納得はしても、そう簡単に腑に落ちるような絵でもなく
その謎はいまをもってもどうにも解けそうもない。
深層心理にまで降り立たねば解釈できない代物なのだ。
いつも何となく理解に達した挙句に突き放されてしまう。
しかし、この鳥のような、モンスターのような異物の叫びこそが
以後ベーコンが生涯抱えていたであろう「悪夢」の始まりを
懐胎していたのは間違いなかろう。
ベーコンの絵はこの処女作に代表されるように
時間の連続性や単独のモティーフの変化を刻印した、
言うなれば「トリプティック(三幅対)」と呼ばれるスタイルを好むが、
その中にこそ、ベーコンの本質が隠されているように思う。
すなわち、同じモティーフの中に現れる変化によって
恐怖や不安をより深く、執拗に増長させ多義性を帯びてゆくのである。
角も複雑な心理、感情の戯れがむき出しになってゆく。
いわば宇宙、混沌とした宇宙の連なりがトリプティックによって
かろうじて一つの安定したフォルムが形成されているだけである。
ベーコンという人は、
生涯に少なくと五人の愛人と繰り返し関係をもったが
いずれも同性愛者ということもあり、当時の社会におけるモラルと抑圧が
かのホックニーを引き合いにださなくとも、
その作品にも少なからず影響を与え続けたのはいうまでもない。
とりわけ、数多くの肖像画が残された、
三番目の恋人ジョージ・ダイアーの自殺は
ベーコンの行く末に大きな痛みを与えることになる。
そのダイアーとの出会いのエピソードがこれまた凄い。
ある日の夜、ベーコンのアトリエに泥棒に入った。
それがダイアーで、しかも天井から落ちてきたのだという。
まるで映画のような光景である。
ベーコンの絵に反するような喜劇そのものである。
ベーコンはまさにその天からの贈り物との冗談のような邂逅において
光を見いだし、瞬間的に恋に落ちてしまったらしい。
気の毒なのはむしろダイアーの方で、(といって泥棒に入る方が悪いのだが)
ベーコンの愛人になることは、まさに命がけの冒険の始まりだったのである。
次第にその生活において、精神的に追い詰められてゆく。
無理もない。何しろ、生きるベクトルが全く違うのだから。
不世出の芸術家と、いい男というだけの凡庸で芸術音痴の与太者。
俗にいう酒とクスリ漬けも手伝って愛の迷宮に果てる男。
最後は自殺にまで追いやられてしまうのだから、哀れなるジョージ。
そしておそるべし、フランシス。
この辺りのことは映画『愛の悪魔/フランシス・ベイコンの歪んだ肖像』のなかで、
主にメインに取り上げられているから
人間ベーコンを知る上では興味深いところだが
無論、それだけではベーコンの芸術を到底理解できるわけもない。
まさに神が手を焼く放蕩芸術家ならではの謎と魅力を振りまきながら、
その絵の叫びを見るにつけ、いけないことを知りつつも
関心を持たずにはいられないこの背徳性の先に、
どうにもあらがえない自分と向き合うことになるのだ。
ジョージ・ダイアーのように。
PUBLIC IMAGE LTD.:ALBATROSS
ベーコンの絵も歪むが、PILの『メタルボックスSECOND EDITION』のジャケットも相当歪んでいる。そして音も負けじと歪んでいる、というかうねっている。ジャー・ウーブルのベースの音のブレがすごい。キース・レヴィンのフリーキーでヒステリックなギタートーンもすごい。ライドンの気だるいボーカルもまたすごい、とにかくすごいアルバムなのだ。それでいて、確かな格調というものが横たわっている。まずは一曲目「ALBATROSS」を聴くだけで、このアルバムの凄さがわかる。アルバトロス=あほうどりが何を意味するのかはわからない。だが終始不穏だ。それは叫びだ。どこかベーコンの絵に匹敵しうる、そんな叫びだ。






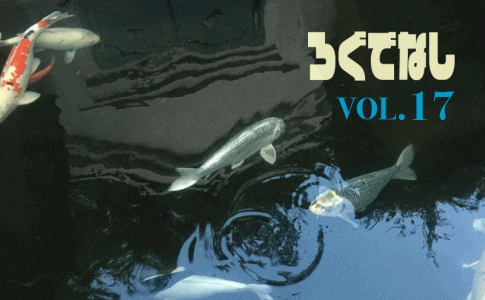




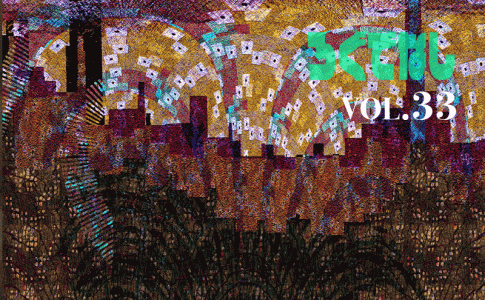

コメントを残す