失われた太陽を求めて
ぼくは太陽と友達だった
あの親しい太陽を
ぼくは失ってしまった
太陽と海を愛した画家、難波田史男のことをご存知だろうか?
知っている人は相当美術に造詣の深い人に違いない。
「私の線は不条理の線だ。線を引くことは哲学的自殺にほかならない」
そうノートに記したこの画家は
その青春の日々を溶かし込んだ
素晴らしいまでの不安定さの中にさらされた、
まさにほんものの線を描き残した画家である。
ほんのものとは、混じりけのない、
何にも似ていない、永遠に朽ちることない、
何人によっても浸食されることのない、
己の魂の赤裸裸なる告白であり、
生の輝きにみちた線のことである。
インクのにじみをともない
日本ではなかなか見受けられないタイプの画筆で、
その分、生前にはほとんど評価らしい評価を受けてはいない。
決して才能が認められなかったというわけでもない。
自らの不条理の中に、嬉々として入り込み、
純粋に絵と戯れ続けた画業は、
世間の評価を切に必要としていなかっただけなのだ。
絵を描くことで水のごとく透明になってしまった魂の画家。
そんな画家を日本の画壇に発見する喜び。
はじめて観た時からぼくの内なる交感が続く画家となっていた。
その画風、クレー+ミロ系といえばいいだろうか、
あるいはヴォルス、フォートリエの系譜というべきか。
しかし、そんなことはあまり重要なことではない。
はだかの目でその絵に対峙しなければ
見えない絵だからである。
原始画、落書き、何なら宇宙からのメッセージとよんでも差し支えあるまい。
ちなみに、22歳の時にその銅版画制作に際して
池田満寿夫に教えを受けたことで
何らかの影響を受けたであろうその画風に漂う魂の風景は
どこか共通のものを感じぬ訳にはいかない。
そのわずか15年足らずの短い間に、
約2,000点ほどの多産な作品群を残しながらも、
どこか完成を拒否するかのような純粋さだけに目を奪われる。
決して絵の出来不出来で評価されうるだけの画家ではない。
みずみずしい魂の線やにじみを継続し表出せしめているのをみて、
いったい、この筆を走らせるその動機がなんなのか?
難波田史男の絵に向かって
思わずそう呟かずにはいられなくなる。
もっとも、その血筋は確かで
父龍起は、70年以上にわたって抽象絵画を手がけた画家として
日本の画壇にその痕跡を残した画家である。
しかし、龍起が直接史男を指導したことも、
また史男が父に影響されて画業に没頭したという事実もない。
その次男として生まれた史男は
幼い頃から、絵の具の匂いと
詩的インスピレーションに事欠かない環境に生まれた幸運に見守られながら、
自身、文学や音楽に親しみ触発されてきた。
アカデミックな教育には馴染まず、
早稲田大学文学部美術専修科へと進み、
「現代美術における小説の役割」という論文を残した史男。
文学を読み耽り、詩を嗜んだことは
難波田史男の絵に絶えず詩的直感を吹き込んでゆく。
わずか32年の生涯ということで、
「夭逝の画家」「青春の画家」と謳われはするものの、
その不遇さを超えた、しかるべき爛漫さは
同じく、太陽や海にたわむれた、
いみじくもあの早熟の詩人ランボーのごとく
さすらいへの憧憬が溢れかえっている。
同じく海で溺死した詩人三富朽葉を愛し
「自分も海で死ぬことへの憧憬をおぼえる」と書いた史男だが、
奇しくも九州旅行からの帰路で、瀬戸内海で転落死を遂げてしまう。
自殺だろうか、事故死だろうか。
真実は謎のままだ。
ポケットにしまいこまれたカメラのレンズキャップからも
『海に消えさった太陽』を拝もうとカメラを構え、
そのまま転落したのかもしれないなどと想像を膨らませる。
死に対する畏敬の念が、より一層神秘のベールに包みこむ。
その謎めいた痕跡を残しての昇天は
あこがれていたクレエの天使につれられて、
ほんとうのFairy Taleに刻まれる運びになっただけなのかもしれない。
この若干約15年の軌跡を企画した、
ステーションギャラリーで観た展覧会、
あるいは東京オペラシティ・ギャラリーでの『難波田史男の15年』
初めてその絵に出会ったときの興奮はいまだ冷めてはいない。
その名がいつしか忘れがたきものになって刻印され続けているのだ。
魂に年齢も、作風も、その数も関係はない。
けれども、難波田史男は絵の表現をこえた
ありとあらゆる魂の遍歴を、その短い生涯に凝縮し残した画家として
永遠に色あせず語り継がれてゆくだろう。
Across The Universe (Remastered 2009) · The Beatles
難波田史男の絵を前に、簡単に宇宙的なものを引き合いに出すのもなんだけど、いかにもジョン・レノンらしい曲の一つに挙がる「Across The Universe」の世界観とは愛通ずるものがあるかもしれない。ちょうどビートルズのメンバーがインドや瞑想や東洋思想にかぶれ出したころの曲だ。宇宙を横切る?「Nothing’s gonna change my world」ぐらいはわかるけど、サビで繰り返される、”Jai Guru Deva, Om”?ってどういうこと? 調べてみると、これはサンスクリット語なんだね。Jai は礼拝時に唱える感謝の言葉、Guruはいわゆる師、そしてDevaは神とか仏陀とかあのレベル、となって、最後Omは瞑想時の掛け声なんだとか。要するに、「(自己のなかの)宇宙と神と師に感謝」ってなことらしい。この「 Universe(宇宙)」というのを自己の内面という意味での宇宙とうけとれば、なんとなくわかる気がしてくる。それを瞑想をとおして体験したジョンのスピリチュアルソングなんだね。





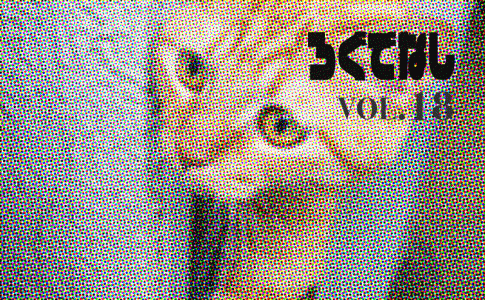







コメントを残す