我が家の春の定番セレクション:其の壱
ここに列挙する音楽は、もう身体にしみこんでしまってるものばかりだ。 だから、書を捨てて街に出よう、じゃないけど 音楽を捨てて街にでたところで、その刻印は消えることはない。 でもねえ、やっぱり音楽は必要だから 聴いていたいという思いは変わりませんね。 そして、音楽とともに、季節感を楽しみたい。 ただそれだけさ。
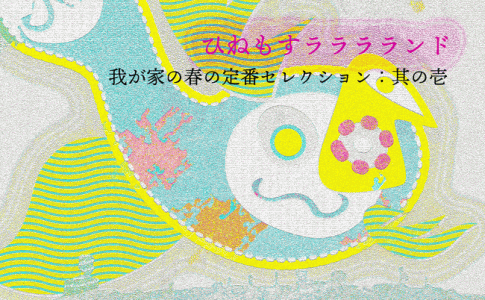 音楽
音楽ここに列挙する音楽は、もう身体にしみこんでしまってるものばかりだ。 だから、書を捨てて街に出よう、じゃないけど 音楽を捨てて街にでたところで、その刻印は消えることはない。 でもねえ、やっぱり音楽は必要だから 聴いていたいという思いは変わりませんね。 そして、音楽とともに、季節感を楽しみたい。 ただそれだけさ。
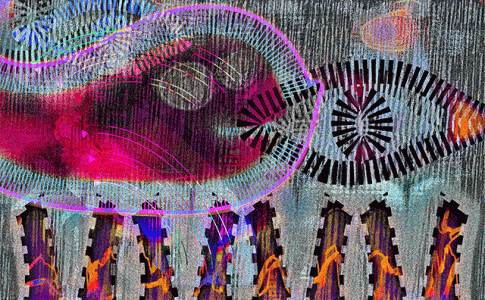 音楽
音楽一雨ごとに、春が潤ってゆく。 もう数日で、三月ともおさらばだ。 なんたって、四月始まりの国、日本に住んでいる以上、 桜の季節に、高揚しないはずもない。 なのに、この世は、いまだばかげた喧騒で、 なかなか本格的な春が拝めない、 というのはうそっぱちだ
 特集
特集とまれ、この桃色素肌の風を纏い、 ボッティチェッリ、春のヴィーナスの庇護の下 森羅万象、息づく生命にかしづきながら、 一足先に、春をおとどけいたしやしょう。 まずは、春を共に楽しむ音楽編からスタート!
 映画・俳優
映画・俳優趣ある本物の浄瑠璃を伴って、 のっけからなんとも風情漂う石畳の上に書かれたクレジットがいい。 真っ赤な字のタイトルは『㊙︎女郎責め地獄』 カメラが真俯瞰で追いながらタイトルバックが次第に赤く染まってゆく。 そこからいよいよ岡場所に入ってゆくあたり、 じんわり痺れる傑作の予感漂うオープニングである。
 文学・作家・本
文学・作家・本その原点は、「ポルノ度」の極めて高い小沼勝の手によって 換骨奪胎された、この『花と蛇』によって始まったと言えようか。 日活ロマンポルノ界のマリリン・モンローと言わしめた 谷ナオミとのコンビによって 薄暗い渦中にも、堂々陽の目を見た重要な作品である。 この『花と蛇』を見て、谷ナオミに胸をときめかせたという、 今や中年以降であるはずの紳士たちも多かろうと思う。 あるいは、その筋の道に引き込まれたマニアもまた 少なからずいるのであろう。
 映画・俳優
映画・俳優さっきこっそりひとりで映画を見たんです。 曽根中生という監督の『ためいき』という作品なんです。 私、こういうの、結構好きなんです。 ちょっと、エッチだけど、 ポルノだからしょうがないんです。 でもなんだかとっても面白い。 こういうの、期待していたんです。 ほんとなんです。 私、変態なのかしら? 自分でも、だんだんはまっていくのがわかるんです・・・
 映画・俳優
映画・俳優そこで、名匠小沼勝の傑作と誉れ高き『花芯の刺青 熟れた壺』。 「壷」と書くだけで、何だか手が股間あたりでうろちょろするような、 そんな淫美な気配がしてくるのは、気のせいではありませぬ。 他にも『熟れた壺』いうんもあって、この小沼という人は、 実に男のツボ、というかエロのツボを押さえた作家なのである。 日活ロマンポルノのなかで、ひときわ道を極める匠である。
 映画・俳優
映画・俳優ポルノだと思って見る人、みようとする人には 全くもって退屈極まりないに映画に違いない。 何も起きやしない。 いや、虚無のようなものが、無防備に突きつけられる。 それもそのはずで、70年代の空気を溶かし込んだ わけのわからない焦燥感に突き動かされる主人公たちの吐息が 官能よりも抒情的に網膜を突き抜ける。 そうしたフィルムのざらつきが今でも色褪せず この網膜越しに感じ取れるからだ。
 映画・俳優
映画・俳優田中登の『真夜中の妖精』を見終わった後に襲われる このなんともいえぬ余韻をどう説明していくべきか。 ロマンポルノという形態のなかに哀しく咲く 、 そして恐ろしくも、無垢なる狂気をはらんだ 大人のファンタジー、といっていいのだろうか。 不思議な感動を覚えているのだ。
 映画・俳優
映画・俳優こうしてみると『白い指の戯れ』での荒木一郎が、不思議と 『勝手にしやがれ』のジャン=ポール・ベルモンドや 『俺たちに明日はない』ウォーレン・ベイティあたりの ちょいワル感がかい間見えてくるのだ。 普通に、ちょっと背を伸ばせば届くような加減がいい。 それにハマってゆく伊佐山ひろ子との絡みもバッチリだ。

クリエーターlopyu66によるアウトプットウェブ
住所
123 Main Street
New York, NY 10001
営業時間
月〜金: 9:00 AM – 5:00 PM
土日: 11:00 AM – 3:00 PM
