精霊の宿る布地
日常世話になってるデジタルの力は、確かに手っ取り早く、
そして秘めたる可能性を容易に引き出してくれる現代の魔法だ。
とはいえ、手から紡ぎ出される、確かな技術と
精神性を宿した職人にしか許されない、
厳格かつ、丁寧で優美な作業の前には敵わない。
そんな手作業への、職人への、ある種憧憬を抱えながら、
日頃、デジタル作業をしているつもりではある。
そんな思いを抱えながら、冬枯れの砧公園を抜けた世田谷美術館で
創設30周年を記念しての開催中の「つぐ minä perhonen」展へと足を運んだ。
ミナペルホネンは、北欧、とりわけフィンランドの空気をまとい
ミナとは「私」を、ペルホネンとは「蝶々」を意味する、
ファッション・テキスタイルブランドである。
ここ、日本を拠点に、ひとつの職人文化を継承する、
そんな生産チームを形成している。
実はこのことが、生み出された生産物共々、興味深く
そのブランドの魅力にもなっているのだと思う。
そうして作られた洋服とはべつに、
そのテキスタイルを通じてみるミナペルホネンの布地には
あきらかに別の「気配」を感じさせるものがある。
同時に温かさと軽やかさをファンタジックながら、
どこかひっそりと佇んでいるものからの声がする、
それがなんなのかをこの目で確かめたかったのだ。
確かに、折り重なる糸の奥で、小さな囁き声が聞こえはしまいか?
刺繍の丸い粒が、まるで瞳のようにこちらを見返すような、
気づかないうちに、布の中に潜む“何か”に見守られている感覚とでもいうのか?
そこで、ふと精霊、と呼んでみたい衝動に駆られた。
そう、精霊のテキスタイル、布に棲まうの精霊の存在。
デザイナー皆川明の図案は、
自然のかたちや生きものをただ模しているだけではなく、
その“気持ち”や“気配”をも布に棲まわせているように思えるのだ。
鳥の羽音、森の影、雨粒のリズム、有形無形の波動を紡ぎ出し
それらは模様ではなく、布の中に宿る小さな命として
みるもの、そしてそれを着る人の心にも入ってくる。
たとえば刺繍の円が並ぶ tambourineは、
丸という単純な形の連続なのに、
なぜかそこに「命のひかり」が灯って見える。
ランダムな揺らぎ、手仕事の微細な乱れを取り込むことで
それはにわかに気配を感じさせ始める。
シンプルでありながらも、静かなミニマリズムとして、
その微妙な不均質さこそが精霊の息づかいであり、
布を単なる模様ではなく、“いのちの皮膜”に変えてしまうのだ。
ミナペルホネンの布に触れると、
どこか身体が安心する、そんな波動があるように思える。
布に精霊が棲んでいる、というより、
布そのものが精霊の器として使われている、といっていいかもしれない。
それは、可愛いぬいぐるみのようなものにさえ漂う気配として
夢見る乙女たちや凛と風を前に立つ淑女にいたるまでを魅了する。
これは、北欧の森に棲むトロールや、
柳宗悦が見出した無名の器に宿る“目に見えない力”の魔力にちがいない。
それは、ブライアン・イーノがアンビエントミュージックに封じ込めた
“空気の中の気配”ともリンクしているように思える。
気配を触ること、そして纏うこと。
そして、それらを有機的に巡回させること、
それがミナペルホネンが醸すブランドイメージだ。
それらすべてと同じ系譜に、ミナの布は立っていることに
親近感を覚えるのだ。
精霊とは、物質の奥に潜む“時間”そのものでもある。
糸の染め、織り、刺繍、試作の反復、
ここには職人の呼吸をもって
それらが層になって、布の内側に沈殿していく時間が
重みを手放した軽さを纏って棲息している。
だからミナの服は、買った瞬間から完成しているのではなく、
着る人とともに時間を重ねるほどに、
布の精霊が目を覚ますように輝きを増すのだろう。
服が“育つ”という現象は、つまりは精霊が成長していくということだ。
会場には洋服のリメイクの展示あったが、
これは従来の消費第一のアパレル文化とは真逆の発想であり、
そうしたコンセプトがブランドに根付いていることを教えてくれる。
100年つづくブランドを掲げるのは、
その精霊の寿命を人の一生よりも長くするためであろうか?
世代を超えて着られる服とは、
布の精霊が次の人へと移っていくということだからだろうか?
彼の服をまとったこともないし、
むしろその精神性に惹かれる個人としては
そのあたりのことは実はよくわかってはいない。
ただ、想像することはできる。
ミナペルホネンの服に袖を通す瞬間、
布の揺らぎ、風のざわめき、刺繍の粒のひそかな鼓動をともなって
人は静かにその精霊と一緒に歩きはじめるという
寓話のなかのキャラクターへと変身することができるのだと。
だが、それらはすべて、
“生活という詩”を紡いでいくための伴走者という意味での暗喩だ。
それこそが、この「TSUGU」に込められたメッセージだった。
布には、物語が棲むと、皆川明はいう。
だとすればその物語を運んでいるのは、
紛れもなく布の精霊たちと呼ぶにやぶさかではないだろう。
彼らは声高に叫ぶことはない。
ただそっと寄り添い、着る人をやわらかく包み、
日々の風景を静かに照らしだしてくれる。
ミナペルホネンの布が尊いのは、
その精霊たちが、“日常を芸術へと変える力”をもっているからだ。
その技が、手仕事のつながりによって、保たれ、
そして、それが優しく循環される。
これほどまでに自然を感じられるファッションに、
未来を託したくなるのは、なんと健全なことであろうか?
いくつになっても、おしゃれでありたいと思う。
ただし、それは、必ずしもおしゃれな洋服を纏うことを意味しない。
特定のブランドに身を任せることでもない。
日常のひとつひとつの所作や思いを大事にしながらも、
そこに棲まう精霊と言葉を交わせるということなのだと、
その延長にあるおしゃれを心から味わうことなのだ、
そう教えられた展覧会だった。
Green Green Grass Of Tunnel · múm
「つぐ minä perhonen」展からの帰り、ぼくの頭の中で再生されていたのは、アイスランドのエレクトロニカバンドMúm(ムーム)の『Finally We Are No One』だった。このアルバムは当時、よく聴いていたのだが、最近はずいぶんご無沙汰しており、半分、忘れかけていたといっていい。このアルバムを再び聴いていると、たしかに、ここにも精霊が棲んでいる音楽だということを改めて思い出した。まさに偶然の必然だ。
こちらは、エレクトロニカであるものの、手触り感があり、ミナペルホネンの世界観にも通じるものがある。どこか体温を帯びた電子音とでもいうべきか。とりわけ、このアルバムには宗悦の無名性、イーノのアンビエンス、そして皆川明の生活をつぐ波動のつながりを合わせて感じとることができる。
ちなみに、ムームはいまでも活動を継続しているが、ぼくがハマっていたころにいた双子の姉妹ギーザ・アンナとクリスティン・アンナの二人は、すでに脱退していることを知った。時間の流れは早いが、このアルバムにただよう辺境の精霊たちは、いまだ、この音の中に棲んで言葉を発しているのだ。






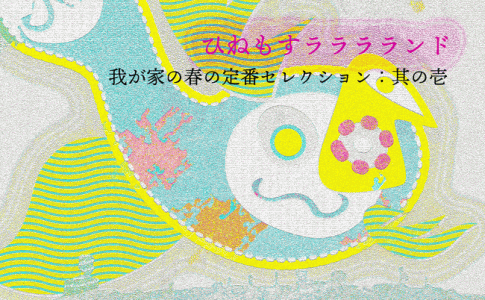






コメントを残す