港町ナント、男と女の泣き笑いの詩情
石畳、路面電車、遊園地、霧にけぶる港、そして米兵水夫。
フランスの西、港町ナントの灰色の空の下、
どこからともなく潮騒の匂いを含んだ風が
石畳をなでるように吹き抜ける。
故郷を舞台にした、ジャック・ドゥミの処女作『ローラ』は、
そんな静かな風景に、アイリスインで幕を開けアイリスアウトで終わる。
これにわざわざヌーベルバーグの作品などと焚き付けたくはない、
そんな昔気質の哀愁がある。
人生の喧噪をひとまず忘れ、少し離れた場所、人々の生活のすぐ隣に、
確かに存在する夢と記憶のかけらが顔をのぞかせる瞬間の愛おしさ。
そこにドゥミは、少年のように、カメラというレンズ越しに、
ぼくらの見るべき“行間”をそっと提示してくれるのだ。
冒頭に「泣けるものは泣き、笑いたいものは笑い」(中国の諺)が掲げられ
マックス・オフィルスに捧げられた映画『ローラ』は、
物語でありながら、詩であり、また記憶の映画、そんな風景が広がっている。
港町ナントの風景が、どこか既視感をともなって胸をくすぐるのは
誰の心にもある”すれ違った誰か”との記憶が
ふわり、スカートが風に煽られるにように呼び起こされるからだろうか?
忘れがたき時間、場所、そして人。
広場を駆け抜ける子どもの声、古本屋の影に潜むような若い青年の姿。
水夫たちが足を運ぶダンスホールキャバレー。
猥雑さなど、全くかけ離れた路地を縫って、刹那の恋物語が綴られる。
風景と登場人物が重なり、どちらがどちらの写し鏡であるのかは判然としないが、
その曖昧さゆえに、ドゥミのロマンチシズムの香りそのものを感じ取れるのだ。
映画の中心に佇むのは、アヌーク・エーメ演じる一人の女性ローラだ。
白いドレスをまとい、子供をつれ踊るように街を歩く彼女は、
まるで過去から抜け出してきた亡霊のようであると同時に、
未来に続く希望の象徴のように美しい。
だが、ローラはただ美しいだけではない。
フェリーニやルルーシュ、あるいはベッケル作品で見せた女の横顔とは別の、
決して言葉にならない記憶の翳りを静かに宿す。
それこそが、だれの胸の内に潜むロマンの実態だ。
笑っていても、目の奥には”待ち続けること”の寂しさが差し込んでいる。
ローラはただ待つ。
七年前に姿を消した恋人ミシェルの帰還を、
子を抱えながらも信じて疑わないシングルマザー。
その信じる力の純粋さは、現代的な目から見れば幻想的ですらある。
だが、ドゥミはその幻想を否定などしない。
むしろそこに、人生の本質、つまりすぐには叶わぬものを、
それでも待つという行為の美しさを見出すために
その孤独を纏わせるかのように肯定してみせるのだ。
ローラの過去の友人である青年ロランは、ローラに心を寄せるが
その想いは、ローラの中では既に定められた運命に抗うものではない。
彼の存在は、ローラにとっては現実のひとつの支えかもしれないが、
決して“未来”を託せる相手でもない。
このすれ違いが描かれる場面は、まるで音楽のように静かに、
そして残酷に流れていく。
この舞台、ナントという町もまた、もう一人の登場人物だ。
ドゥミの愛した町並みがモノクロ越しの映像に溶け込んだ舞台。
霧のかかる港、佇む船、回転するメリーゴーラウンド。
街のすべてがローラの内面を映し出し、彼女の過去を、
そして彼女を取り巻く人々の“願いの残骸”として映し出してゆく。
ドゥミは、それらを切り取るのではなく、
ひとつの流れとして受け入れることしかできない。
なんというロマンティシズムの戯れだろうか?
それはヌーベルバーグにはない儚さと瑞々しさが交互に漂わせながら、
人生とは選択とすれ違いの連続であり、
詩的であるがゆえの悲しみを孕んでいる。
そんな哲学が、映像の行間から静かに滲み出るのだ。
この映画のロマンチシズムは、決して物語の起伏や結末に宿りはしない。
むしろその欠如、あっけない日常の延長としてすれ違うことで生じるのだ。
そんな感情の揺らぎにこそ、本質がのぞく。
ローラが、待ち侘びた恋人の車に乗って去っていくラストシーン。
そのあとをただ見送るロラン。
そこには説明の余地も、声高な感情表現もない。
ただ風景だけが残り、心に余韻を残す。
観客はその余韻のなかで、自らの記憶を探し、
かつての“ローラ”を思い出すのだろう。
この詩的な世界観は、ドゥミの後年の作品にも通底しており、
いわばドゥミの十八番である。
たとえば『シェルブールの雨傘』では、ミュージカルという形式を借りながら、
やはり”すれ違い”と”記憶”を主軸に物語が進む。
明るく色彩豊かな画面の裏には、叶わぬ愛と、
人生における選択の不可逆性が静かに横たわっていた。
そして『ロシュフォールの恋人たち』では、音楽とダンスが炸裂するなかでも、
登場人物たちは過去と未来の狭間で揺れ動き、
自らの夢と現実との折り合いをつけようとする。
これらの作品を貫くロマンチシズムは、単なる恋愛感情の高揚ではなく、
それはむしろ、人生の不確かさのなかで、
それでも何かを信じようとする行為そのものへの眼差しそのものだ。
その意味では、ドゥミは映画を通じて
ひたすらそのロマンを追求した作家だった。
そんな源泉がどこにあるかを示してくれるのが、
パートナーであり、良き理解者だったアニエス・ヴァルダによる
自伝的要素の強い『ジャック・ドゥミの少年期』であろう。
この作品のなかで描かれる若きドゥミは、
家のガレージで自作のアニメーションを撮影し、人形劇を演出し、
フィルムと物語に恋する少年である。
彼が初めて映画に魅了された瞬間、光と影に夢中になった記憶、
そのまま『ローラ』のナントの町に宿っているのを知るとともに、
だれもが子供の頃抱えていた夢の重みを感じることだろう。
ドゥミにとって映画とは、現実を幻想へと変える魔法であり、
失われた時間へのオマージュであり、世界に対する愛の表明でもあったのだ。
ドゥミの映画は、現実を祝福する。
その中に息づくささやかな夢や、
叶わなかった愛の輪郭を美しくも哀しく描く作家として、
それゆえに、映画からもまた、祝福を受けるのである。
ドゥミは『ローラ』に、詩のように繊細で、記憶のようにあいまいな、
それでいて確かに心に残る映画を残した。
アヌーク・エーメの気高いまでの儚さ、
ナントの街並みのグレーと白の調和、
ミシェル・ルグランによる高揚と抒情の旋律、
そしてラウル・クタールのカメラがクールに見つめる”行間”の世界。
それらの凝縮が、人生という物語の傍らに、
そっと咲いた花のように、凛と咲き誇る映画なのだ。
Fairground Attraction – Beautiful Happening
ドゥミの映画を見終わったあとに残る哀愁を、うまく説明するのは言葉じゃなく、音楽の方が相応しいのだと痛感する。真っ先に頭に浮かんだのはフェアグランド・アトラクションの音楽である。ファーストアルバムの『Perfect』もいいのだが、あれから時間を経て、エディの歌声も、バンドとのハーモニーも、落ち着きと穏やかさを増した新作の『Beautiful Happening』も、これまた素晴らしく、そしてドゥミのロマンティシズムにも被る郷愁を掻き立てるのだ。その中からタイトル曲をお届けしよう。まるでドゥミが愛した“行間のドラマ”にそっと寄り添いながら、人生のドラマはこんなふうに美しく起こってしまうのだと微笑むような楽曲が並んでいる。ローラの白、その心の翳り、港町の潮の匂い。それらがこの曲と重なり合うとき、モノクロの世界にもほのかな色が差し込むのを感じる。まるで、あの日のナントに新しい風が吹き抜けたかように、幾重にも重なって来はしまいか?






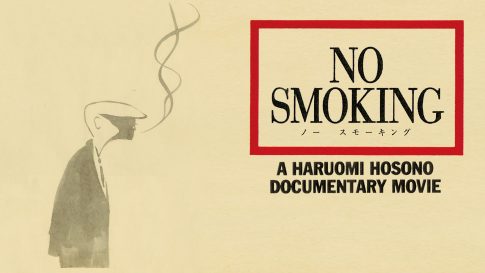






コメントを残す