赤い灯が落ち、そして鬼が仏になった
あれはたしか2006年だったか、
映画作家溝口健二の50回忌の年にシンポジウムが開催され
溝口ファンの自分も足を運んだものだが、
ビクトル・エリセあたりがパネリストとして座っていた記憶がある。
内容は忘れてしまったのだが、
そのときの内容が本にもなっていたと思う。
随分、溝口を知るものなら人間味ある溝口と、
現場での鬼のような数々の逸話、そんな数々の伝説を残した映画人溝口との差は
単に映画だけをみても理解しがたいものがあるはずだが、
溝口の映画は、時代を超えて今なおも新鮮な発見と感動がある。
まさに日本映画界の遺産、誇りである。
そんな日本が誇る大監督溝口健二の遺作『赤線地帯』を久しぶりに鑑賞。
この作品は、溝口の代表作としての位置づけこそ低いものがあるが
今見ると、これはこれで溝口らしい作品だといえるし、
あたしゃ嫌いじゃないな。
要はこの映画、売春禁止法をめぐる娼婦(女)たちをめぐる人間模様であり、
決して、エロティシズムがどうの、という風俗映画でもないし、
むしろ、リアルな人間ドラマであり、
今思えば、風俗史としての側面においても秀逸な映画とさえ思うのだ。
ちなみに「赤線」とは、明治時代以降、日本に存在した公娼制度の陰で、
非合法の売春を取り締まる警察が、これら非合法地帯を地図上に
赤い線で囲んで区別していたというのが語源である。
で、日本で「売春防止法」が公布されたのが、昭和31年(56年)で
実際に施行されたのが二年後の昭和33年(58年)、
で、この映画の上映が1956年というわけで、
当時の赤線業者および世論の空気感は十二分に感じ取れる。
その道を生業とする者にとってはまさに死活問題だったのである。
この映画は五人の娼婦たちのドラマであり、
生涯を通じ、女の不遇さからその解放への意思を描いた、
いわゆる溝口の十八番といっていい題材であったわけだが、
残念ながら、この映画を最期に世を去ってしまう、遺作である。
ここには、溝口が生涯かかえもっていたといわれる
女への贖罪感が色濃く滲んでいるともいえる作品だ。
「どんなに口紅を落としても、あんたの稼業の汚れは落ちやしない」
などと、息子に職業の卑しさをののしられ
絶縁されたショックで発狂してしまう三益愛子演じるゆめ子には
どことなく溝口の妻、千枝子夫人が重なり、
どこかアイロニーに満ちてとても痛ましい気にもなる。
ちなみにこの映画のサウンドスコアは
かつて日曜の朝「題名のない音楽会」というTV番組を受け持っていた
現代音楽界の巨匠黛敏郎氏で
ミュージカルソーなどを使用したミュージックコンクレート、
いわゆる的外れな実験的な音楽を使用したとのことで
公開当時津村秀夫という評論家との間で
音楽論争にまで発展して物議を醸したいわくつきだが、
いま見ると別におかしくもなく、的外れだとも思わない。
むしろかなりマッチングしているんじゃないかと、個人的には思う。
が、当時としては大なり小なり
違和感があったのもわからないでもない。
確かに実験性は強く、不気味な情感さえ漂わせている。
とりわけ、田舎から出て来たばかりの川上康子演じる生娘しず子が、
初めて客を呼び込むラストシーンにそれが溢れている。
夜の帳が下りた吉原の門口に、晴れ着姿でたち、
びくびくと「お兄さん、寄ってらっしゃい…」と通りを行く男たちに呼びかける、
その怯えと諦めが入り混じったその表情を、
カメラは門の外から見た「夢の里」の入口を正面に捉え、
しず子の初々しくも哀しい顔を、みごとに夜の闇に浮かび上がらせている。
なんともいえぬ無垢なる姿に、叙情を抑制した黛のスコアが
いかに的確なものであったかを証明しているのではなかろうか?
そんなわけで、他にもいろいろ言及したい点があるが
特定の主人公なき映画ではあるものの、
五人の売春婦たちの個性がそれぞれうまく描写されており、
病気の夫と幼い赤ん坊を抱え、
貧困の中で仕方なく身を売る女としての諦観と開き直りる、
いかにも所帯染みた娼婦の群像をみごとに演じた木暮実千代の花枝
この人のアクセントが非常に素晴らしいなと自分は思う。
いみじくも木暮実千代は、かつて『雪夫人絵図』において
その官能的な欲望の女を演じたこともあって
いってみれば、お色気ヴァンプとしての魅力から一転、
この地味で所帯やつれした役柄への転生ぶりで
その女優魂をみせつけられたという気さえする。
そのほか、京マチ子演じるアプレ娘のミッキー。
自分勝手な父親との軋轢に抗う強気の娼婦だが
相変わらず、ナイスボディでその女っぷり、貫禄には凄みがある。
若尾文子演じるやすみは、その若さ、美貌で
したたかに客から金を巻き上げ、おまけに仲間内にも金をかしつけ
がめつく生きる女を好演している。
『祇園囃子』での初々しい芸者っぷりからすれば
堂々たる溝口組での立ち振る舞いだ。
もっとも庶民的な娼婦といえば、町田博子のより子だろう。
一度はみんなの祝福を背に、嫁いで外の自由な空気を吸うものの、
現実の厳しさを知って出戻ってくるやるせなき役回り。
「身についた垢って落ちないわね」そんなセリフがなにげに刺さる。
そんな中、一人息子との同居を夢見るその名もゆめ子は、
金歯をちらつかせ、もはや客を取れるほどの若さや美貌はなく、
先にちらりと書いたように、
期待の一人息子に裏切られ、発狂してしまうという、
これまた、実に厳しくも哀しい女の性を抱えた役回りである。
演じたのは「母もの」シリーズで名を馳せた三益愛子で
夫は直木賞作家で溝口とも親交の深かった川口松太郎。
そんなベテラン女優三益にさえ、溝口の容赦なきダメ出しが続いたという。
こうしてみると女の業を描かせたら
やはり天下一品、監督溝口健二の看板に嘘偽りはない。
享年57歳、鬼の溝口がついには仏になってしまったという、
無常のラストムービーがここにしかと展開されている。
そこで、溝口健二自身のことにも少し触れておこう。
溝口を敬愛する外国の作家は多い。
とりわけヌーヴェル・ヴァーグのシネアストたちは
こぞってミゾグチを絶賛したものである。
なかでもゴダールはその筆頭で、『山椒大夫』でのラストシーンを
『気狂いピエロ』で引用し、オマージュを捧げているのはつとに知られており、
来日の際には溝口の分骨が眠る京都満願寺への墓へも
詣でているほどにリスペクトしていた。
そんな溝口だが、作品の出来不出来が激しい作家とも言われている。
『赤線地帯』は佳作であり、決して失敗作というほどでもない。
それはテーマが溝口の十八番だったからだが
例えば『元禄忠臣蔵』や『新平家物語』『楊貴妃』など
少しテーマから外れた作品ではさほど評価が高くなく、
むしろ失敗作だとみなされる場合もある。
助監督を務めた増村保造はそのことを指摘している。
おまけに、現場での溝口は“ゴテ健”と呼ばれ
妥協を許さないその性格から、
演技はいうまでもなく、セットから小道具、衣裳・時代考証など
何事においても完璧を求め現場のスタッフ、俳優たちを震え上がらせたという。
かと思えば、権威にはすこぶる弱く、
映画の小道具を自分のものにしたり
制作費を生活費に流したりという
公私混同身勝手な一面すらあったらしい。
映画においては無類の情熱を燃やし
決してそのフィルモグラフィーに傷が付くことはないが
人間ミゾグチにそうしたエピソードは事欠かない。
そこが溝口のいうおのこの魅力であるのだと関係者は口を揃える。
助監督をつとめ、溝口を敬愛する新藤兼人は
『ある映画監督の生涯 溝口健二の記録』というドキュメンタリーで
そのあたり、関係者の声を自ら集め、その功績を讃えた。
このドキュメンタリーは、そんな溝口を知る貴重な資料であり、
関係者の声を通じて人間ミゾグチの素顔が、
実に生々しく興味深く浮かび上がらせている。
四方田犬彦篇の書物『映画監督 溝口健二』とともに、
溝口という人間を知るには一度は見ておくべし、である。
そこで、触れないわけにいかないのが
溝口といえば、何と言っても田中絹代との関係である。
新藤兼人もドキュメンタリーのなかで、
そのあたりを本人にダイレクトに切り込んでいる。
15本の作品に出演し、数々の傑作を共にした
切っても切り離せないスクリーンの上の絶対のパートナーであった。
事実、多くの証言からも
溝口は田中絹代に恋心を抱いていたのは間違いないという話だが
結局本人にその思いを伝えることはなかったのだという。
絹代自身、あくまで映画監督溝口への尊敬こそあれ
実生活で伴侶となると、
「溝口健二としての演出には惚れているが、亭主となると理想の夫ではない」と言って笑う。
彼女が惚れたのは映画監督溝口の才能なのだと。
このドキュメンタリーにおいては
田中絹代の溝口への思いだけでも十分に価値のある映画だと思う。
単なるゴシップ話、告白ではないのである。
関係を否定していても、田中絹代の女心の情緒っぷりが
とてもよく反映されている貴重な瞬間が垣間見れる。
(恋愛感情こそ自覚しないが)溝口健二という人間
愛されたことは結婚以上の思いがあるのだと締めくくる田中絹代の思いが、
なんとも切なく胸を打つ。
溝口は真の芸術家であったが、田中絹代もまた真の女優であった。
素顔では男と女にはなり得なかったのである。
そうした凌ぎ合いこそが、溝口映画を傑作に押し上げ
田中絹代という宿命の女優を得た溝口の
ある意味成功だったのだという思いがした。
新藤兼人のドキュメンタリーで、そんな田中絹代自身が語る、
溝口の最後を見舞って言葉なく沈黙が続いたエピソードが胸を打つ。
残暑厳しい八月のとある日、スクリーン上の夫婦が
一瞬の夫婦として、心だけで交わした会話の中身を知る術はない。
The Animals : House Of The Rising Sun
溝口健二の『赤線地帯』に、アニマルズのヒットで知られるこの「朝日のあたる家」を重ね合わせてみると、一見無関係に思える両者が、実は同じ魂の震えを伝えていることに気付かされるんじゃないだろうか。ともに女性の視点でみた世界観が反映されており、「朝日のあたる家」はアメリカの伝承歌(フォークソング)として起源が定かでない古いバラッドだが、その歌詞自体には「売春」や具体的な罪状を直接示す言葉はないものの、東京・吉原の遊廓の哀愁と共鳴するかのように、時空を超えた人間の哀しみ、つまりは社会の底辺に生きる人々の声なき声が伝わってくる。ちなみに、アニマルズのエリック・バードンの力強い歌唱と印象的なエレキギターのアルペジオに乗せられたこのバラッドは、全英・全米でヒットチャート1位を記録し、フォークとロックを融合させた「最初のフォークロック」とも評され、以来、あらゆるジャンルのミュージシャンによってカバーされるほどの「音楽史上最も演奏された楽曲の一つ」になっている。





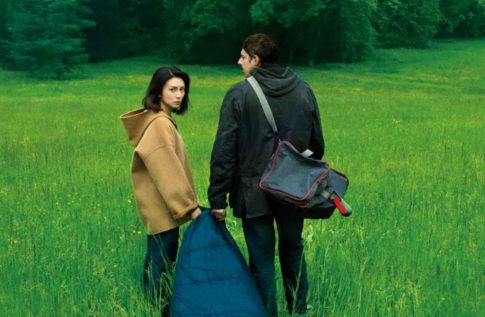







コメントを残す