団地郷の人々
喜劇、とりわけ日本映画で、ちょうどいい具合の
すんなり入り込めるコメディなんてのはこれまでなかなか出会えなかった。
阪本順治による完全オリジナル作品『団地』は
キャスティングの妙も手伝って、
日本にもそういう系譜がちゃんと存在するということを証明する映画だ。
やはり、阪本順治はコメディというジャンルに貴重な存在だ。
岸部一徳、藤山直美、大楠道代、石橋蓮司
まず、この4人のラインナップを見て
なるほど、面白くならないわけがないな、と思った。
顔を思い浮かべただけでニヤニヤしてくる個性がある。
それぞれが阪本組といっていい良好な関係性をうかがわせるが
とりわけ、岸部一徳、藤山直美(+大楠道代)は
『顔』以来の組み合わせであり
歳をそれなりに重ねた円熟味を加味し、
この「団地」というテーマに沿って実に豊に彩っている要素になっており、
絶妙の夫婦を演じているのだ。
まさに昭和を代表する個性をもつ俳優たちが
団地文化のリアル世代であることに不自然さがない。
どうやら僕は「団地」という設定にくすぐられてしまう。
「昭和の風景」に、ある種ノスタルジーをそそられるのはしょうがないことだが
身近に思えたのは俳優たちの自然体ゆえのリアリティだ。
団地には、一度も住んだことはないが、
育ってきた環境の中で、団地は見慣れた風景の一つであり、
団地空間そのものが、あたかも舞台装置よろしく、劇空間になることは
古くは川島雄三『しとやかな獣』、森田芳光『家族ゲーム』
キエシロフスキ「愛に関する短いフィルム」あるいは
トリュフォーの「トリュフォー思春期」、
最近ではフランス映画『アスファルト』などなど、
たびたび見せられてきたので、改めて説明するまでもないのだが、
結局は、空間的に面白いと言うよりは
団地に集まってくる人物たちそのものが面白いのだと言う
当たり前のことに気づかされる。
そこでのテーマはずばり「うわさ」である。
「団地はうわさのコインロッカーや」
とは藤山直美扮するひな子の言葉だが
実に言い得て妙な台詞である。
映画の骨子は、ずばり、人と人の絆に生じる
会話のズレで形成されていると言っていい。
あくまでも物語としての装置であるが
団地は長屋や下町文化からの進化系であり、
マイホームの夢からもれ、現実と日常の中で
人同士の絡みを拒否しない社会、
そこでかろうじて小さな社会という網に引っかかっている感じが
人間味やその面白みを生みだしているようにみえる。
冒頭で浜村淳のラジオ番組がどこからともなく聞こえてくる。
実にうまい演出だな、と思わせる。
ここには今時の洒落た感性は似合わない。
三階に住む山下夫婦は、ついこの間まで商店街で漢方薬局を営んでいたが、
一人息子を交通事故で亡くして、店をたたんでこの団地に引っ越してきた、
というところから始まる。
これが最後のオチにつながっているのだが、
なぜ団地なのか、というところを考えてゆくと
この映画の深み、旨味が隠れているのがしだいに暴かれてゆく。
そこに、かつての漢方の顧客である真城という男が訪ねてくるが
この男は男は後々、この夫婦の運命を変えてしまうほどの不思議な男で
それこそ、大阪弁で漫才のようなやりとりが繰り返される。
まさにギャグの応酬である。
しかし、そのままお笑いエンターテイメントには成り下がらないところが
また阪本順治の魅力でもある。
この夫婦は子供を不意な事故で失って
いまだにまだ傷が癒されていない。
そこで触れる人間関係だけが世の中とつながっている。
そこで宇宙の真理、つまりはこの世のカラクリを知ってしまい
その傷を埋めようと一線を超えてしまうのだ。
唯一SFチックに現れる円盤の存在が、
映画を一気に未来的に高揚させるところではあるが、
それもまた話の流れからの“ネタ”に過ぎない。
もちろん、彼らが日常を捨て、世間を捨てる覚悟を持って
一線を越えるのだが、ここでまた、コメディとしての落ちが待ち構えている。
息子に会うための必須品としての「へその緒」を忘れてしまい、
円盤に乗り込んだ(移動した)時にまで時間を巻き戻して
取りに帰ることになるのだが、
どうやら、巻き戻し過ぎたようで、思わずはっとする。
そこで・・・
ラストに映し出された事柄がこの映画のオチであり
思わず落語のように膝をうって、「上手いっ」となるのである。
中身についてはあえて触れないでおこう。
オフビートで、SFチックな風味もあるが
哀愁が漂う人間コメディがここにある。









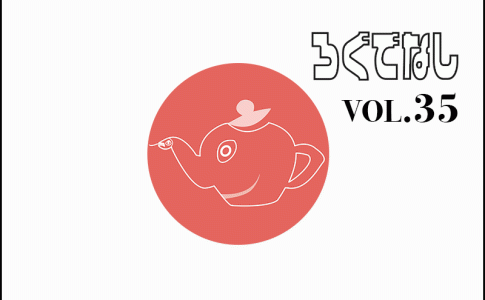



コメントを残す