幾つになってもオペラの灯は消えず
敬老の日はとうにすぎた。
といって、特に敬ってあげたいご老人は周りにはいない。
もっとも、歴史を紐解くまでもなく、
もはやこの世に存在しない先人たちをひっくるめて、
老いたるものへの敬いの気持ちならいつだって持っている。
これから先は老人天国、自分もその引力に抗えずにいるわけで、
やはり見捨てられるのは悲しい。
そんなたいそうなことでもないか・・・
そんな思いに寄り添って、
ダニエル・シュミットのドキュメンタリー映画
『トスカの接吻』について書いてみよう。
初めて見た時の感動は忘れないのだけれど、
年齢を重ねてみる感慨はまた違うものだ。
同時にいろんなものが見えてくる。
人間は歳をとっても本質的に変わらないものだっていう、
そんな見本がここにある。
いいんだわ、老人たちの顔がね、素晴らしいの。
元オペラ歌手、いまや老いさらばえた芸術家たちの、
いわば老人ホーム「カーサ・ヴェルディ」。
老人ホームといっても、あのヴェルディが夢見た
「音楽家の憩いの家」なんだけどね。
ヴェルディはあえて「養老院」という呼び方を拒否してまで
「憩いの場』にこだわった気持ちがよくわかる。
引退した音楽家を100名収容できる三階建ての建物で、
そこには老残とは思えない豊かな表情、
そして声がいつも満ちあふれている。
彼らのかつての栄華・栄光を、嬉々として語るときのオーラ。
そして未だにオペラや音楽に対する愛情、
それらが引きこむエネルギーは圧巻。
そこには、芸術を生きてきたという幸福の灯火が赤々とともっている感じで、
オペラ歌手、というくくりはおいておいて、
これはひとつの美しい人間の生き様が刻印されている。
サラ・スクデーリというおばあさんがやや目立っていて、楽しいんだけど
ジョヴァンニ・プリゲドゥという
くせものの音楽家のおじいさんもいい味をだしてる。
即興で音楽を奏でるんだけど、やっぱり違うんだね。
出てくるんだよね、もう身体に音楽がしみ込んでいるんだよ、
当人はきっと初めて音楽に触れた時の感動を
今尚継続しているつもりだろうし
現役で聴衆の前に立つ気持ちとなんら変わらない感じで歌い出す。
実に素晴らしかった。
それにしても、確かにこれは「ドキュメンタリー」
といわれるジャンルではあるけれど、
ここでは老オペラ歌手、老音楽家はあたかも俳優のようであり、
すべてが「カメラ」を前提にした
生き生きとした生の演技をみせてくれる。
さすがはイタリア、ってとこだけれど
こうしたマジックはシュミットの十八番でもある。
そこにこれら音楽家への愛と尊敬の念が滲み出している。
オペラ好きのシュミットにして、
してやったりの作品に仕上がっているのだ。
『カンヌ映画通り』における虚構ドキュメントは
この『トスカの接吻』で非俳優たちをまきこみ、
そしてこのあと『書かれた顔』へと至ることになる。
あらゆるドキュメンタリーはフィクションである、
というアンチテーゼがあるけど、
つまり、カメラという媒体をすくなからず意識する被写体は、
演技、演じるということに対して、
ときには意識しながら納まっているはずだということなのだ。
シュミットはこうした老歌手のむずむずする気持ちを
うまくカメラで引き出している。
ちなみに、シュミット組の名カメラマン、
レナート・ベルタの仕事に抜かりはない。
その意味では『トスカの接吻』は
ドキュメンタリーとフィクションをまたにかける、
ドキュフィクをゆく作品であり、
その見本のような作品だといえるのではないだろうか。
ヴェンダースの『ブエノビスタ・ソシアルクラブ』もそうだったけど
歳をとっても音楽への愛を抱きつづけている音楽家の表情、
そしてその音や声、その空気。
これはなにものにも真似出来ないある種の高貴さが宿っているんだな。
あんな風に歳をとりたいものだ。
誰しもが思う。
がそれはやはり彼らの特権である。
そう、老いという現実に飲み込まれながらも、
決して従順にその老いに従わないという永遠の躍動を宿した魂を持つ人々。
「悲惨であるはずのものが嘘のような容易さで幸福のイメージを喚起する映画」
そう書いた蓮實重彦の言葉に素直にうなづくしかない。
そこでふと思い出しましたよ。
ばあちゃん、ぼくは元気でやっとります、ひとつご加護のほどを。
日頃の忘却をお許し下さい。
95歳で大往生した我がグランマーのことが急に頭を掠めた。
もう子供はいらないという両親に言い放った一言、
「もう一人産んどかれま(富山弁」
そういって僕は危うく宇宙で一人取り残されることなく、
この世に向かう最終電車に間に合って、無事生を受けたのだった。
Sara Scuderi Sings “Vissi D’Arte” From Puccini’s Tosca
普段、オペラなんてほぼ聴かないんだけど、この映画を見てオペラもいいなって思うようになった。プッチーニのオペラ『トスカ』より、若きサラ・スクデーリが歌う「Vissi D’Arte」。好きなものをとことん愛するっていいなあ。歳はほんと関係ないね。






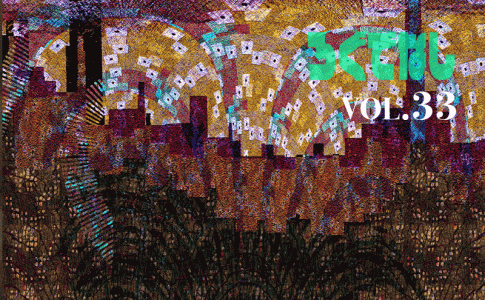

![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)




コメントを残す