仁義と輪、とは?
メルヴィルの『仁義』が、どうして赤いシリーズなのか?
それは原題が『Le Cercle Rouge』、直訳すれば「赤い輪」だからである。
単にそれだけのことだが、肝心のその赤い輪とはなんぞや、というと
映画の冒頭のクレジットで、メルヴィルはこう引用する。
「人はそれと知らず再会するとき、各々に何が起ころうが、異なる道を進もうが、赤い輪の中で出会うことが必然である」
これはラーマクリシュナが聞いたブッダの言葉とされている。
ようするに、人は知らず知らずに出会ったとしても
一度運命の輪のなかに入ってしまえば、
その繋がり(縁)からはけして逃れられないのだと。
赤い糸よろしく、ここでの赤とは
血の通った人間的な関係性を見えない絆として描き出す。
少し強引かもしれないが、概ねそういう解釈になるだろう。
そんなメルヴィル自身の思いが、はたしてブッダの真意かどうかはともかく
あくまでも、映画の中身についてその中で踏みこんでいこうと思う。
つまり、ここでは主な五人の登場人物たちが
各々なんの因果か巡り合うことで、善悪の関係を越え結びついて
この物語を形成している、そんな映画というわけである。
その名も『サムライ』で、武士道なるものを引っ張り出したメルヴィルだが、
ひとつのスタイルとしてフィルムノワール(フレンチノワール)を渋く展開し
代名詞のように語られるメルヴィルブルーによるクールな映像美や演技で
観るものを魅了するスタイルがここでもしっかり踏襲されている。
メルヴィル美学が東洋的な視点、なのかどうかは別として、
少ないセリフ、登場人物たちのクールネス、
モノトーンで暗めの画質といった志向性が
物語の根っこに置かれた渋いスタイルに酔いしれることになる。
フランスではこれが大々的にヒットを記録したというから
やはり、フランス人の嗅覚や嗜好というものは侮れないものがある。
どこかに優雅さ、品格を感じさせるのも納得できるというものだ。
アクションに長けたハリウッドものとはどこか真逆の精神性、
ここにはそんな文化背景が脈々と流れているのを感じとる。
ここでの「仁義」とは、シンプルにいい変えれば男たちの友情である。
ただし、友情とひとことでいっても、そこはメルヴィル、
こだわり、美学という方がより正しい気はする。
気の利いた台詞や感情を激しく揺さぶるアクションもない。
おしつけや強引さ、馴れ合い、過剰な説明など
そこは安っぽい人情劇からはほど遠いストイシズムを漂わせながら
それを楽しめるかどうかがこの映画を見るカギになってくる。
主役は『サムライ』に引き続きアラン・ドロンだ。
まずは5年の刑期から出所するところから始まる。
日本にも「代貸し」というヤクザのしきたりがある。
つまりは罪をかぶって、組織の犠牲になって“お勤め”することである。
ドロン演じるコーレイの場合は、捕まっても仲間を売らず
ひたすら黙ってそんなお勤めに従事するようなタイプの男である。
そんな男が再び悪事の乗り出す。
『サムライ』では妻のナタリー・ドロンと絡ませたメルヴィルが、
そんなドロンをここでは宝石泥棒の一員として
傍にイブ・モンタン演じるジャンセン元刑事のスナイパーを抜擢し
クールにはダンディで対抗しうるキャラとして登場させる。
対抗といっても、ここでは仕事仲間といったほうがいいだろう。
元刑事であるジャンセンは一線を退いたが、どこか負いがある。
アル中になってその依存症に悩まされているのだが
メルヴィルには珍しい、そんなアルコール依存の幻覚シーンをはさんで
かつての縁から、宝石商を襲う一件に抜擢されるのだが
見事な腕前とともに、この仕事をきっかけに
それまでのアルコール依存症をも乗り越えるという、
そんな役回りを演じている。
髭を生やしたドロンのコーレイと
アルコール依存に苛まれるダンディなモンタンのジャンセンが
情報屋サンティの経営するバーでの打ち合わせを経て
脱走犯ヴォーゲルとともに三人組が宝石強盗に入る後半からの一連、
まさに息を吞むシーンはこの映画の見どころだ。
みごとなメルヴィル美学が色濃く反映されており、
仕事人よろしく、男たちは、あらかじめ建てた計画をもとに
屋根伝いにうまく内部に侵入し、
うまく守衛を眠らせ、ひたすら無言で目の前の仕事を黙々とこなしてゆく。
サスペンスさながらの一挙手一投足がいかにも格好いい。
自前の弾丸を鋳造し、その弾で、固定から手持ちに切り替え狙いを定め、
宝石店の警報装置を一発で粉砕するジャンセン。
感情表現など、メルヴィル映画にはまず見られないが
アルコールの香りだけで、その仕事の成就に酔いしれるという
なんとも痺れるシーンをさりげなく挿入したりする。
少しの狂いや焦りも無く、そうした事をやりとげたクールネスがみせる間の妙がなんともかっこいいのだ。
そうして盗み出した宝石を市場に流そうとするのだが、
そこは問屋が許さない。
赤い輪の中の一人、刑事マッティが故買屋に扮して待ち構えるのだ。
そこに、冒頭のブッダの意をなかば強引にあてはめるとすれば
まず先にマッティと対峙したヴォーゲルは
あとからやってきたコーレイにこの罠を告げ逃がそうとするが
そこで刑事マッティの存在には触れない。
もし、刑事が絡んでいることをコーレイが知れば
マッティを撃ったかもしれないからだ。
武士の情け、ではないが、ヴォーゲルの情け、
すなわち、「仁義」というわけだ。
とはいえ、この計画は全員、静かに死をもって終焉を迎える。
勝利するマッティだが、その表情がどこか寂しげにみえる。
この渋いマッティを演じるのが
フランスを代表する人気コメディアン、ブールヴィルである。
このプーヴィルは『仁義』に出演したあと、53歳で他界している。
遺作というわけだ。
そうした一瞬一瞬の判断において
運命の輪を感じ取ったかどうかまではわからないが
冒頭でマッティ刑事が逮捕したヴォーゲルを護送するシーンでも
たばこに火吸おうとして火を着けなかったり、
些細な気配りシーンを思い返す。
あるいは名シーンいわれているのが、
コーレイと、購入したアメ車のトランクに隠れていたヴォーゲルとの出会いのシーンだ。
お互いの境遇を本能的に察知したのであろう、
コーレイにが先に敵意のないところをみせるために
たばこをとライターをヴォーゲルに不躾に投げてみせるシーン。
そうした細やかな所作諸々から、関係を示唆させるのメルヴィルの演出が味なのだ。
一度観たからといって、そうしたニュアンスを
うまくくみ取れるかどうかは人それぞれだが、
見返すうちに、そんな美学にどんどん惹きこまれてゆくだろう。
少なくとも、自分はそれこそがこのフレンチノワールの楽しみ方だと認識する。
まさに大人の映画、メルヴィルの美学たる赤い輪に
自分もまたどっぷりはまってしまったのかもしれない。
Le cercle rouge- Eric Demarsan
メルヴィルの『仁義』の音楽を担当しているのは『影の軍隊』『サムライ』に引き続き、フランスの作曲家エリック・ド・マルサンだ。メルヴィルという人はジャズ好きかつ大のレコードコレクターだったらしい。メルヴィルの映画を見れば、そのあたりのこだわりが如実に反映されているわけだが、メルヴィルの場合、妥協なき完璧主義者としても知られている。実はこの『仁義』も先に決まっていたのがあのミシェル・ルグランだったという。だが、メルヴィルの気に入らず途中でクビになってこのエリック・ド・マルサンに落ち着いたというから、恐るべしメルヴィル、である。中にはノイローゼになった作曲家もいたらしく、いやはや、完璧主義者というのは全くもって手に負えない。その分、このサントラを聞いても、確かに素晴らしいし、音を聞いただけであのクールな画が浮かんでくるのだから文句はないのだが、一本の傑作の裏側には、かくも過酷な現実があるものだ。






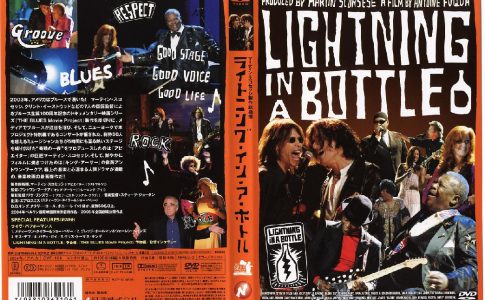






コメントを残す