赦しの季節
秋は何かが実るときであり、同時に消えてゆく季節である
何かが移り変わろうとするには、ちょうどいい頃合いである。
それは、静かに朽ちゆくものの中から、
なおも命を繋ぎ止めながら、
なにかを育くもうとするタイミングというべきかもしれない。
フランソワ・オゾンの新作『秋が来るとき』は、
そんな“生の発酵”のような時間を描いてはいるのだが、
ひとくせふたくせもあるオゾン映画が
平穏に、ただ事で過ぎゆくとは思えない。
とにもかくにも、オゾンは期待を裏切らない。
ミシェルとその親友マリー=クロード。
老境に差し掛かった二人の女性が中心に据えられているが、
共通するのは、子育てにおける悔いである。
しかし、それらは諦観することでしか解決されはしない。
オゾンは過去を抱えて生きることの美しさと痛みを、
あたかも森の光の揺らぎに満たされるように、場を彩ってゆく。
母ミシェルは元売春婦。
映画冒頭、教会のミサに顔を出し
神父が語る「マグダラのマリア」の話に耳を傾ける。
イエスの死と復活を見届ける証人であるとともに、
悔悛した罪深い女として描かれる女性である。
その過去を許せない娘ヴァレリーは、そんな母を拒み、
終始その関係に不穏な空気を漂わせながらも
金銭面での援助もあり、そこに、孫を挟んで、
血の絆に縛られたまま、完全には離れられない。
愛情と嫌悪、赦しと拒絶。
それらが一枚の葉の表裏のように絡み合い、
二人の沈黙の意味が物語に深く影を落としている。
オゾンはここで決して彼女たちを裁くことはしない。
むしろ、ぬぐいされぬ想いを“抱えたまま”老いていくことを
静かに肯定し、後押しするかのように流れてゆく。
老いとは、時間の中で澱のように沈殿していく感情を、
ごまかすことなく、もう一度見つめ直すことなのだと。
しかし、この映画が平坦ではないことは明らかである。
この母娘をつなぐ事件のきっかけは、きのこがもたらすのだが、
オゾン自身の幼少期の体験から着想されたというこの出来事は、
単なるサスペンスの入口ではない。
きのこといえば、秋の味覚であり、同時に死に至る劇薬でもある。
美と毒、恵みと破滅。
その二面性の共存は、この映画の根幹にある“生のあやうさ”の象徴だ。
母がつくる料理は、愛情の表現であると同時に、
娘には無意識の暴力にもなりうる。
過去の因果を知らぬうちにも繰り返し、善意が毒に変わる瞬間だ。
この曖昧さと無意識こそが、オゾン映画の核であり、
人間という存在の不完全さそのものとして、導線を引く。
むろん、彼女に悪意などない。
過去の過ちとて、誰にでもある生きる理由にすぎないのだ。
一方、母の唯一の親友、マリー=クロードには、
刑務所帰りの息子ヴァンサンがいる。
危険な気配を醸し出しながら、物語のカギを握る人物として
母親以上に親密度を増していく。
彼女は、その社会復帰に手を貸すことを厭わない。
世間からはみ出した人々が、かように寄り添い合いながらも
孫という無垢な存在を介して、
やがて、小さな共同体として形づくられていくのだが、
その巧みな演出によって、
観客は、ヴァンサンとミシェルの関係にサスペンスの影を嗅ぎ取るだろう。
彼らはいわゆる“正常な家族”ではない。
しかし、互いの痛みを受け入れるその眼差しに宿る共同意識を分かち合うが
それにはどこか、血を超えた温もりが滲んでいる。
このドラマが多面的に語られるのは、そうした感情の混交にあるのだ。
オゾンはここで、家族という制度の外側にある
血縁に依存しない、理解しようとする“時間の共有”にこそ
人と人をつなぐものなのだという真理へと導いていくのだ。
舞台はオゾンの故郷でもあるブルゴーニュ。
霧、潮風、石壁、木漏れ日美しき森。
その風景は、まるで登場人物たちの記憶のように曖昧で、どこか懐かしい。
都会にはない、自然の美しさと残酷さが共存する場所だ。
光はやさしく、しかしその奥には地方固有の冷徹さをも秘めている。
老いの身体を照らす秋の光は、もう若さの輝きには応じないが、
ひたすら時間の重みを受け入れた柔らかい光が射す。
オゾンはこの土地の空気の中に、「赦しとは、自然の循環の一部である」
そんな哲学を織り込んでいる。
ここでわれわれが再認識させられるのは、
『秋が来るとき』が、“人生の終わり”ではなく、
“関係の再構築”を描くことで
「他者を通して生まれる赦し」とともに、
「過去の過ちをどう生きるか」を描こうとする映画だということだ。
母と娘にある溝は、死をもっても埋まるわけではなく、
その違和感が物語からけして解かれることもない。
オゾンはその存在を視覚として登場させ、内なる対話を描き出すが、
それでも、孫の存在や他者とのつながりを通して、
かかえる孤独を引きずって生きている。
赦しとは、忘れることでも、許可することでもない。
ただ、時間の流れの中で、
相手の痛みを自分の中に置いておくこと。
それを“生き続ける力”へと変えることにできるかにかかっている。
オゾンはその静かな真理を、老いた女たちの眼差しと秋の森に託したのだ。
そこにはもう、生きゆく激情もなく、老いがあるだけだ。
ただ、風が葉を落とすように、人が人を受け入れるという、
その自然の摂理に身を任せるしかないのだ。
こうしてみてくると、『秋が来るとき』は、実に語りにくく、
その行間を読み取ることが試される映画に思えてくる。
そもそも、描かれる善悪そのものが曖昧であり、
誰もが正義、正論をかざすこともない。
また、追求もしない。
われわれは静観することを余儀なくさせられ、おのおの想いを募らせるだけだ。
だがその“語りにくさ”こそが、人生そのものの深さを映し出すことになる。
そのために、だれにも肩入れせず、だれも責めず、
はっきりした描写を避けることで、
物語は完全にわれわれの内に委ねられてゆく。
娘の死が自殺か他殺か、それは観客が決めれば良いのだ。
誰もが過去を抱え、誰もが赦されることもない。
それでも、人は他者の存在によって、
もう一度、自分の人生を生き直すことが許されるのだ。
そもそも罪とは何なのか、赦しとは何なのか?
女が老いていくということは、何を意味するのだろうか?
それを秋という季節、ブルゴーニュという土地に託して、
フランソワ・オゾンは、その“静かな再生”の瞬間を
きのこの香りとともに記録したのだ。
まるで、森の呼吸そのもののようにおそってくる、
ラストシーンの余韻に、今、静かに浸っているところである。
Aaron Neville – Amazing Grace
いわずもがな、讃美歌の中で最もよく知られた曲の一つである「アメイジング・グレイス」を、あえてオゾンの映画に贈るのは、映画の主旨とは、微妙に違うかもしれない。とはいえ、悔悛するあらゆる罪深き魂に贈る歌としてはこれ以上にふさわしい歌もないだろう。いろんなミュージシャンが歌っているが、とりわけ、アーロン・ネヴィルの、天使のような歌声からは、すべてが浄化され、祝福を受けるかのような、そんな感慨に浸れるのは幸いだ。



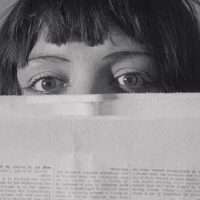









コメントを残す