禁忌カタルシス
コクトーには、ジャン・マレーという長年の愛人がいた。
「ジャン!」「ジャノ!」と呼び合う二人。
いわずもがな、共に同性愛者だったのは有名な話だが、
映画『恐るべき子供たち』で、ポールを演じたエドアール・デルミは
法的な養子縁組ではないものの、実質養子といっていいほどに
コクトーの庇護のもとに可愛がられていた。
コクトーという人の“色好み”には、かようにわかりやすいまでの傾向があり
ギリシャ彫刻を思わせる、骨格のはっきりした美男子が好みだった。
そのほか、わずか20歳で腸チフスで死んだ神童ラディゲもいた。
身も心もこの肉体の悪魔に魂を奪われたコクトーは
その死のショックから立ち直れず、約10年にもわたり
阿片地獄に耽溺することになるのだが、
そんな時期に書いた小説『恐るべき子供たち』で、
ギリシャ悲劇的構造の上に、近親的共犯関係と同性愛と近親相姦という
禁忌な影を落とし込んだ傑作を産み落とすことになる。
とはいえ、コクトーは文学史的にも映画史的にも、
はっきりとした位置づけの難しい作家だった。
本人は、詩人の血の下に、あらゆる創造メディアを駆使しながら、
詩の世界に戯れ、その世界で才能を発揮し、
今のマルチクリエーターの走りとしての認識も高い。
ある意味、属性なき作家として、その名を刻んだ自由の人だった。
『恐るべき子供たち』には、その奔放な男遍歴から毒好み、
そして生涯抱えていた死の観念といった禁断の世界の片鱗が
コクトーの美学として随所に貫かれている作品だ。
一方、この映画を監督したメルヴィルはといえば
前年に『海の沈黙』でデビューしたばかりの駆け出しで、
コクトー文学の支持者でありながらも、
映画におけるアプローチや視線には、必ずしも相容れる関係ではなかった。
自分でもメガフォンを撮る自意識の強いあのコクトーが
それでも若きメルヴィルにその思いを託したのは、
メルヴィルの才能を見抜いていたからに他ならない。
とはいえ、この映画の最大の特異点は、原作者であるコクトーが
ナレーションを通じてこの作品を影から支配していることだ。
小説を読むことと映画を視ることが、こうして一体化するかのように共存している。
監督がメルヴィルであるにもかかわらず、
物語の意味づけは、コクトー自身の声によって導かれているのだ。
その分、メルヴィルの演出において、
ナレーションは、どこか映像に寄り添わず、時にズレを生むことにもなる。
この乖離が、登場人物たちの意志をときに無効化し、
彼らを語られた人形にも変えてしまう。
後期に確立された、統一感のあるメルヴィルスタイルは
ここではまだ確立されてはない。
コクトー本人の声が支配するということが
ナレーションを単なる語りから、
作者=神の現前へと変えてしまうことになるのは必然だ。
それによって、観客は、映像の外から響く声に絡め取られ、
物語の外へ逃れることができなくなる。
そんな物語は、まず運命の引き金として
冒頭での悪童たちの雪合戦で始まる。
ポールの胸を撃ちぬく石を包んだ雪玉。
その引き金を引く人物こそがダルジュロス。
彼はリセ・コンドルセ中等部において
コクトーをときめかせた怪物的で神話的な怪童だった。
その衝撃が、ここにつながっている。
この映画には、コクトー好みのギリシャ悲劇の構造が
深く刻まれているが、悲劇の核は「アナンケ(避けられぬ必然)」であり、
運命は人間の意志とは無関係に発動し、
彼らとて、逃れられないものとして描かれることになる。
その影の主導者たるダルジュロスは、その後姿こそ消すが、
この恐るべき姉と弟にさらに、恐ろしい罠を仕掛ける存在でありつづける。
もちかえった東洋の毒玉だ。
これによって、二人の悲劇はさらに加速する。
ギリシャ悲劇で神託が物語を動かすように、
この雪玉から毒玉へ、不可逆な運命の開幕、つまりは“物理的神託”を告げるのだ。
コクトーのナレーションは全知の視点から、
物語を過去形で語り、登場人物たちの行動を運命として確定させていく。
この「語られることによる拘束」によって、
ギリシャ悲劇的な緊張を、現代の密室劇へと移行させることになる。
エリザベートとポールの関係は、血縁という絶対的な近さに、
依存・支配・同一化・共犯、それらが重層的に絡みついている。
エリザベートという性悪で、かしましく勝気な姉が
常にポールの感情を操ろうとするが、弟なしでは自分を演じられない。
この危うい均衡のなかで、ポールは束縛されながらも、
どこかで姉の支配が崩れることを恐れているのだ。
ふたりは、子供の世界をとびこえ、
完全に二人だけの亜空間として、その遊戯を劇場化させていく。
この回路は外界の倫理や時間感覚から完全に独立し、
自己完結的な宇宙そのものなのだ。
だからこそ成立する恐るべき関係性。
一度足を踏み入れれば、二度と戻れないという危うさ。
これこそがタイトルの「恐るべき」という形容の核心なのである。
姉エリザベートと弟ポールが共有する部屋こそは世界の中心である。
コクトーの生まれたパリ郊外のメゾン・ラフィットの家では
幼少年期、少年コクトーは好きなオブジェに囲まれ、
雑誌の切り抜きと劇場遊びに暮れた日々を過ごす。
そんな思いでがここに再生されている。
スパナ、アスピリンの容器、アルミの指輪、カーラーなど
引き出しには「宝箱」と称したガラクタオブジェがつまり、
文字通り、子供たち独自の言語やルールに支配された空間が築かれているのだ。
たとえば、「出発(depart)」という言葉は
二人の間では夢想に入る、つまりは夢へと通底する暗号として扱われる。
そこには外界の時間も倫理も届かない。
この部屋は、現実から切り離された神話の温室となり
コクトーの言葉を借りれば、「ひとつの身体を共有しているかのように」
二人はその温室の住人として永遠に夢想しつづけるのだ。
映画は直接的には同性愛や近親相姦を描いてはいないが、
その影は全編に漂っている。
エリザベートのポールへの執着は、保護や愛情を超えて恋人に近い熱を帯び、
ポールの気質や外見は、ダルジュロスへの憧れや自己耽溺の気配を漂わせ、
原作ではより明確に、同性愛的ニュアンスと近親的倒錯が描かれているが
映画では、そのダルジュロスに似たアガート(二役)が
彼らの運命をさらにややこしくさせる存在として持ち込まれる。
エリザベートは、アガートとポールの相愛の関係を利用し、
一芝居を打つことで悲劇の扉を開けてしまう。
ポールは毒玉を口にし、エリザベートはその支配に自ら決着をつけるために
自らのピストルで頭を撃ち抜く。
ギリシャ悲劇ではしばしば近親相姦を主題に据えたが、
それは禁忌の破壊が人間の本質を暴く幕切れとなる。
本作もまた、禁断の愛を悲劇の構造に組み込み、
そこから逃れられない運命を私的な悲劇として描いて終わるのだ。
ポールの死は、関係の破壊であると同時に、
エリザベートの死をも重ね、物語に終焉という救済を図るにすぎない。
『恐るべき子供たち』は、氷のように冷たい映像美と、
焔のように熱い声が同居する稀有で歪んだ恋愛映画である。
メルヴィルの冷徹な映像は、コクトーの声とは対照的だ。
アンリ・ドカのカメラワークは、生の躍動をとらえるヌーヴェル・ヴァーグ映画より
室内劇の厳粛さに寄り添ってみせる。
構図は厳密だが、演技に抑揚があり、豊かな感情表現をとることになる。
メルヴィルは「語られないこと」の力を信じた監督だが、
コクトーの支配にある劇中では、行動と沈黙で物語を紡ぐ限度を晒す。
そのため映画には常に、語りすぎる声と語らなさすぎるカメラの緊張があり、
映像は距離を保ち、声は内面を侵食すると言った風に、
この二重の美学が、結果として、作品に不穏な詩情を与えているのだ。
この映画における“恐るべき”とは、単なる破滅的関係を指すのではない。
それは、近親的共犯という閉ざされた回路に絡め取られ、
そこから出られないまま、それを美として受け入れてしまう感性そのものだ。
禁忌を犯すことでしか存在を確認できない関係。
禁忌を超えるために祓う死の代償。
あるいはその関係を外から支配する“語り”の存在。
そして観客までもが、その語りの支配に絡め取られてしまう神話的構造。
こうして、コクトーは映画という武器によって
ポエジーを昇華させたのである。
The Beatniks – Le Sang du Poete
高橋幸宏と鈴木慶一によるユニット、ビートニクスのファーストアルバム、1981年のアルバム『Exitentialism』(出口主義)から、冒頭を飾るトラック「Le Sang du Poète(詩人の血)」。タイトル自体がコクトーの短編映画『詩人の血』(Le Sang d’un Poète, 1930)からのものであり、プロフィット5の音色にみられる80年代ニューウェーブな響きと、コクトーへの敬愛がつまったアルバムだ。今聴くと懐かしい思いがよみがえってくる。当時の僕は、こういう音楽をききながら、コクトーをはじめとする文学に日々浸っていたのだ。



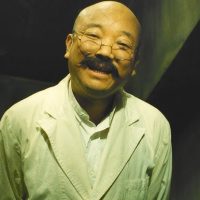

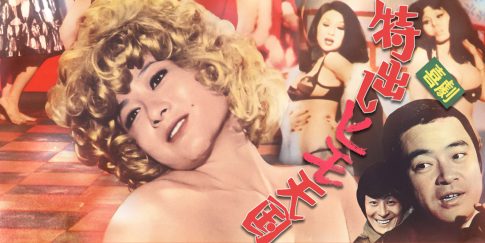




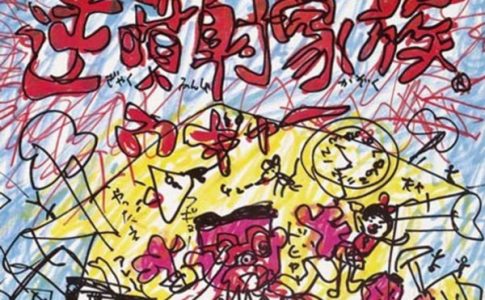


コメントを残す