血よりも濃い黒の物語
今、一人好きな映画作家をあげるなら、と言われたら
ダルデンヌ兄弟と即答する。
今もっとも信用できる映画作家のひとり、
今もっとも注目すべき映画作家のひとり、と言い換えてもいい。
ベルギーが生んだ至宝ダルデンヌ兄弟の映画が
他の映画と明らかに一線を画するのは、
映画が持つエンターテイメント性を超え、
全く映画には関係ないはずの、こちら側、
つまりは自分自身の内面に直で刺さってくる、
そんな本質的な映画を作り続けているからだと思う。
実に、稀有なことだ。
内容がハードな現実でありながら、
すべてがフィクションでもって構築されているにもかかわらず、
生々しく迫ってくるのは、扱う内容がそれ以上でもそれ以下でもなく、
ドキュメンタリー出身の監督らしく、
手法が至ってシンプルで、誤魔化しも過多な虚飾もない
まさにダイレクトシネマの真髄を宿しているからに他ならない。
社会派だの、リアリストだのといった言葉で片付けたくない何かがある。
つまらないお涙頂戴や社会告発があるわけでもなく、
単に事象があり、人間がいる、と言う姿勢を崩さないからであり、
それを我々観る側がどう受け止めるかだけの問題であり、
はっきりした答えも、誘導もない、と言うことだ。
場合によっては救いもなく、何の解決もないまま無情に終わる。
すべてが投げ出されて呆気なく終わるのだ。
それがダルテンヌ兄弟の映画なのだ。
しかし、そうして露わになった物語が
観終わった後もずっと頭に、心に、残ってしまうのは何故だろう?
そこに根差したダルテンヌ兄弟の思いは
決して浅いものでも、軽いものでもないということが
ひしひしと伝わってくる、そんな映画の余韻はなかなか覚めやらない。
そんなダルデンヌ兄弟の最新作『トリとロキタ』もまたしても
そうした映画体験に他ならない。
擬似姉弟によるアフリカからの移民の話である。
この問題は『ロルナの祈り』でも取り上げられたが
ベルギーのみならず、西洋経済大国共通の根源的問題なのだ。
友情においては血が通うことの重要性など、全く問われることはない。
しかし、成熟した社会ではそれが許されない。
それを明確に証明しなけば、恩恵を受けにくい社会ということだ。
ベルギー社会の闇は闇として、そこにさらされてゆく。
まず、ロキタが最初に直面する場面、
なぜ、生まれてこの方離れ離れになって
会ったことも見たこともない弟を弟だと認識できたか?
と問われ、「そう思った」とロキタは答えた。
しかし、世間的にはこれは理由にはならない。
彼女はビザ習得のために、何らかの口実を考え出す中
止むを得ず、「そう答えた」のである。
ときに姉であり、ときに母である心優しいロキタ。
いつもは小柄な弟、しかし知恵があり、勇気もあるたくましいトリ。
見た目は少しアンバランスながらも、
二人は、血が通ってはいないだけで心だけは通じている。
そしてお互いが生きる支えなのだ。
それを証明するのに言葉はいらない。
少なくとも、二人の間には、血族以上に強い絆があるのだ。
状況がそうさせたのか、本能がそうさせたのか。
いずれにせよ、それが重要なのだ。
しかし、移り住む異国で生きてゆくのはそんな簡単なことではない。
殊更一人で生き抜くにはあまりに過酷すぎるのだ。
彼らの状況がそれを物語る。
同じような皮膚、同じような境遇のものが
必ずしも心を分かち合えるわけでもないと言う現実を、二人はわかっている。
シビアに金や利害が絡み、取れるものは子供であれむしり取られるだけなのだ。
ロキタは母親に送金し、おそらく祖国に残してきたはずの本物の兄弟たちに
教育費さえも都合しなければならないという立場である。
しかし肝心のビザがないために
合法ではない、危険な仕事にしかつけないのである。
そう言う状況を最低限の情報として観客たちに伝え共有しながら、
物語はどんどんと深刻な方へと向かってゆく。
ロキタが危険を顧みず、そこでかけたのはドラッグの運搬、大麻の闇栽培。
しかし、いつかはトキという心通じる弟と
普通に生活できる日を夢見ることを信じて日常を送るだけだ、と言う思いがある。
そうしたギリギリの環境、ギリギリの立場がサスペンス調に展開されてゆく。
泣き言など言ってられないのだ。
運命など呪ってられないのだ。
そうして彼女は、人里離れた麻薬栽培工場に連れてこられ半ば幽閉される。
どうしても心の支えとしてトキの声が聞きたくなるのだが
合法ではないが故に、場所を特定されたくない管理者から許可が降りない。
ロキタはそれでパニック障害まで起こしてしまう。
しかし、思いは強く、ならばとトキが命がけでやってくるのだ。
二人には目の前の危険よりも、確実な慰めが欲しいだけである。
この無垢な思いが通じるのであろうか?
しかし、ダルデンヌ兄弟の映画に、
真のハッピーエンドが訪れるわけがない。
トキがやってきたことが組織にばれた以上、
彼らはもはやそこにはとどまることはできない。
ひたすら逃げるだけだ。
二人は、なんとか違法の工場を離れ逃げる。
後先考えずに逃げる。がしかし・・・
この話の結末はあまりに不毛である。
見るものも、演じるものにも、光など差してはこない。
神もいなければ、慈悲もない。
最後、一人残されたトリが、ロキタの葬儀において
ほとんど感情を交えずにロキタを偲ぶ。
泣き叫ぶでもない、愚痴を言うでもない。
この先どう生きて行くかもわからない。
ただ、現実を受け止めようというだけだ。
ダルデンヌ兄弟の、この厳格で、嘘や誇張のない演出に
何故だか、微かな希望を見る。
同じ素人俳優を使い、演技を拒否しながらも
ぶれずにフィクション空間を見つめ続けた作家ブレッソン、
あるいは、移民や社会の底辺に身を寄せる人間への眼差しを
ユーモアとペーソスで描いたカウリスマキ。
テーマやスタイルこそ、そうした映画作家に近いなにかを見出しはするが
ダルテンヌ兄弟の視線は、あえて対象に感情移入させない方向に誘導し、
われわれに問いだけを投げかかける。
目の前に立ち立ち人生に向き合うことを嫌い、
そう言う話題には触れず関心を持たない人は
ダルテンヌ兄弟の映画には行き着かないのかもしれない。
だからこそ、行き着いた人にはある種の連帯感が生まれることもあるだろう。
我々はただの目撃者でありながら、
どこかで主人公たちの生き様に同化してしまっているのだと。
勝手な妄想かもしれないが、トキのような頭のいい少年が、
この先も虐げられた人生を歩んでいくとは思わない。
思いたくはないのだ。
誰にも分からない未来だからこそ、
そこに一縷の望みを託したい気持ちになってくる。
ふたりが歌う澄んだ歌と笑い声がどこからともなく聞こえてくるようだ。
Immigrant Song : Led Zeppelin
キーワードは「移民」。そのニュアンスは、ダルテンヌ映画とは少し違った意味合いを持っているのが、レッド・ツェッペリンの「Immigrant Song」。ロバート・プラントの冒頭の「アアアーアー!!」という戦慄的スクリームがあまりにも有名なこの曲における「移民」は、北欧神話とヴァイキングの侵略をテーマに、歌詞中では「We come from the land of the ice and snow…」と、氷雪の地から南方へ向かう彼らが語られ、“棲家を追われる者”ではなく、“棲家を越え征服する者”が主役である。海霧を裂き、氷河を溶かすほどの咆哮と共に、剣のように海を渡り、雷神の息吹で新たな国土を切り拓くといった空気感が支配する。それがツェッペリンにとっての「Immigrant Song」だ。ジョン・ボーナムのドラムはまさに「戦の太鼓」と化しているのだ。




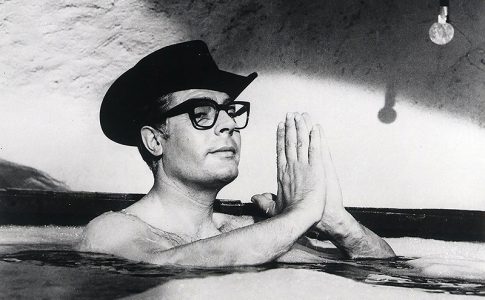



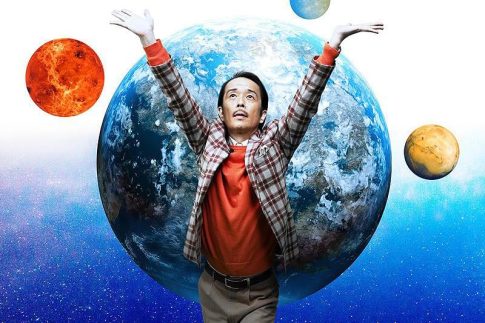




コメントを残す