ねずみとうさぎの化かし合い
義理の姉弟の関係である二人。
姉は彼とは一度も一緒に歩いたことなどないという。
妹やその他証人たちは確かに一緒に彼と歩いていたという。
蒸発者をめぐる考察が当初のテーマだったはずの、
今村昌平による映画『人間蒸発』において、
しだいに雲行きが怪しくなってゆく。
とはいえ、ラストシーンでのいざこざのクライマックスと
その不毛なまでのすれ違いっぷりは圧巻的で
映画として、これが実に不謹慎なまでに面白く、
このスリリングな展開の結末をとくと拝むがいい。
妹佳江はここでは“ネズミ”と呼ばれ、
ある日突然消えてしまった元婚約者の大島という男を追うという、
活動屋たちの興味、食指に乗って、ただひとり俳優である露口茂を伴っての
足取りを追う謎解き行脚に出かけるのだが
途中から、このネズミは映画という魔力によって
しだいに女優然とした眼差しを投げかけ始める。
もはや、自分の目の前から忽然と身を隠したひとりの人間への愛情などスルリとはがれおち、
それまでくすぶっていた憎しみや訝しみの念が呼び起こされ
肉親である姉サヨ、ここでは“ウサギに疑惑の眼差しを投げかけると同時に、
露口への思慕の情をさえも臆せず告白するようになる。
とはいえ、この映画はけしてネズミのものにはならない、させない磁力がある。
つまりは中心には常に映画人としてのイマムラの野心がメラメラと燃え盛っているのだ。
イマムラはそうしたネズミの変化を
けして見過ごさないし、見過ごさないどころか
あらぬ方向へと向かって傾いてゆく映画的バイアスを期待し楽しみながら、
巧みに舵を取ってゆくのである。
まさに職業冥利に尽きるばかり、その悪意は増す。
名目はあくまで「蒸発をめぐる考察」ドキュメンタリーであったはずだ。
しかも露口を除いては、出演者は皆素人たちである。
そこにフィクションとしての罠が潜むのだ。
映画の前半はその蒸発者である大島裁という男の肖像を丹念に追っていく、
いかにもドキュメンタリーとしての体裁を保ちながら、
ネズミという人間の存在意識を根底からあぶり出してゆくことになる。
途中から明らかに、その関心はフィクション空間へと移行し、
ネズミはいつのまにか女優のような表情と、
その振る舞いでもって監督イマムラやスタッフを刺激するようになる。
まさに願ったり叶ったりの展開ではないか。
なんといってもこの映画のハイライトは、
ウサギが婚約者大島と会っていたかどうかを巡って、
その証言者である魚屋の男を交えて、アパートの一室で膝をつき合わせての
事情検証、いわば「追求」の場である。
状況は切迫し、真実をめぐる討議が成されるのだが
「セット飛ばせ」という唐突な監督の合図のもとに、
それが一瞬にして“つくりもの”であることがばらされ、
人が真実だと思っていることも、これと同じように、
フィクション空間での幻想という可能性さえ否定できないのだ、
といわんばかりの大どんでん返しをみせるのである。
そこで終始繰り返されるのは
彼とは一緒に歩いていない、いや確かにみたという水掛け論なのだが、
そこで、ネズミはイマムラ自身に向かって
「真実ってなんでしょうか?」と発する。
同席する監督自身も「わからない」という。
その答えとして、セットからくりの解体、大ばらしなのである。
我々観客は、これがフィクション映画だと、
一応は納得させられるのだが、まさに突き放されてしまう。
いくら時代はちがえども、
個人のプライバシーがまったく無視されることはないだろう。
これほどまでの真実が、仮に本当の話であれば、
ウサギはまさに妹の婚約者殺しの烙印を
公然と押されることにもなりかねないのだから。
後半の展開を見ていれば、たしかに、ネズミの察し通り、
大島とウサギとの間にはなにかしらの関係があったとみるのが
自然な流れのように思われる。
会社への電話の主をめぐっての電話交換手の発言
魚屋の証言、そしてアパートの管理人までもが続き、
いくらウサギが否定しても、状況証拠だけではどうにも分が悪い展開で
そのうえ、霊媒師の登場によって、このウサギは毒殺の主犯として追い詰められる。
観客はまさに、いやがおうにも大どんでん返しの結末を想像してしまうのだ。
真実は確かに誰にもわからないが
映画というものが観客の想像力にゆだねられるものだとしたら、
妹の婚約者の蒸発に、その姉が関与し、
なんらかの物語があったと想像するのは自由である。
個人的にはこのサヨという女性がウソをついているとは思えない。
そんな大胆なことをやってのける女のようには思えないのである。
もちろん、目撃証言の魚屋の言い分にも悪意は感じられない。
この男がまさに狂言師のような立ち回りようで
一連の流れを混乱させる役のようにもみてとれるのだが
そこがドキュメンタリーとフィクションの曖昧さのなかで
絶妙な効果を発揮しているのだ。
この映画の面白さが、確かにドキュメンタリーの体裁をとるフィクション
つまりはメタフィクション映画であることは明らかだが、
それもこれも、監督イマムラ自身の悪意が効いているからに他ならない。
映画的に成功しているといえるのは、まさにそこなのだ。
ただひとり演者として選ばれた露口茂は
そうした映画のマジック、トリックのなかで
かなり疲労困憊したというし、実際は存在の薄い役回りを演じている。
がしかし、この人物が、俳優である以上
映画のなかでの役割を熟知し
カメラを前に「人は演技をしてしまうもの」ということでの
監視者としておかれているようにも思えてくる
露口でさえも犠牲者、つまり映画の生け贄として利用されるのだ。
カメラを向けられた対象が必ずしも真実を語っているわけではない。
むしろ、演者になってしまうのが、カメラという道具の魔力であり
それこそが映画の醍醐味なのではないか、といっているように思えるのである。
前半のドキュメンタリー然とした展開から
ラストシーンの真実をめぐる混乱への移行は、
子供の声で「ねえもう終わり、もう帰っちゃうの?」という
ある種、サクラのような声が嬉々として聞こえ、
そこで決まったようにかちんこが鳴って終わるのである。
そのあとで、ネズミが女優然として「もう終わりね」というナレーションをつぶやく。
露口=イマムラの声で「時間だね。映画は終わった、でも現実は終わらない」
そう告げられることで、行き着くところのないこの映画の不毛さの余韻を象徴して終わるのだ。
「この映画はフィクションであり、そのあたり勘違いしないで下さい」
イマムラはそう念を押す。
なぜなら、フィクションであるということが、
この映画の救いであり、成功なのだという確信があるからである。
この映画は「蒸発者をめぐる考察」をしただけであり
その実態が導き出されたわけでもない。
それどころか、問題の論点は「真実とはなにか?」であり
真実は誰にもわからない、という帰結の中で
映画に出演したという勲章はさておき、
登場人物たちのだれもがトクをしないばかりか
悶々とくすぶり続けるであろう裏方の運命を背負わされるだけである。
まったくもって不快な思いしか残さない映画になっている。
そのあたりの執拗さは、他の今村映画にも見受けられる本質だが
ここに、真実という生々しい現実がかぶってくるあたりに
映画としての面白さが広がっている。
作りの手の意図をはるか超えた次元で、まぎれもない傑作に仕上がっているのだ。
結局のところ、蒸発者大島裁は単なるダシに過ぎないのである。
彼自身がどこでどう生きているか、死んでいるか、
また、どのような経路で姿を消したのか、
彼が会社の金を使い込もうが、婚約者の他に女関係があろうがなかろうが
そんなことはどうでもよいことなのである。
それにまつわる社会の証言者たちもしかり、
こうして、映画人イマムラは、ありとあらゆる使えるモノを使って
みごとなメタフィクションを生み出すことに成功した映画なのである。
The Blondie : Shayla
ブロンディの「EAT TO THE BEAT」のなかの一曲で、工場で働いていたシェイラが、最後の給料を受け取ったあとに失踪したという内容の「SHAYLA」。こちらはもっとポエティックな詩情あるストーリーテリングな曲だけど、失踪つながりということで。デビー節の効いた良い曲だな。










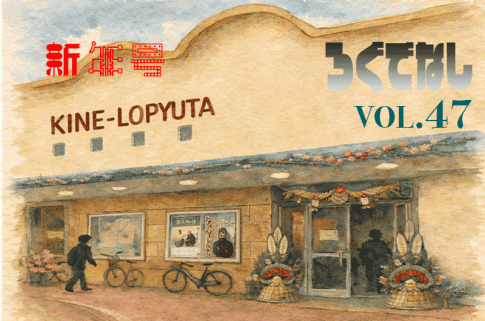


コメントを残す