誰よりも現代をゆく廃材おじさん、この人を見よ
現代美術と言われるジャンルには
最近ほとんど興味を失ってしまっている。
表現そのものに対する関心はといえば
それは全く消え失せてはいない。
もちろん、全てをひとくくりにはできないが
アートはアートであり、現代美術がどうこう
という話でもないところでの興味がある。
仮にその中に大竹伸朗という現代美術のモンスターを置くとなると
その意味合いは百八十度変わってくる。
彼は、無論、現代美術の作家という枠など
最初から超越してしまっているからだ。
その大竹伸朗氏が、先だっての東京オリンピックの
公式アートポスターを手がけたのは知っていたが
大竹伸朗の活動の場なら、もっと他にある気がするものにとっては
新鮮な驚きには値しなかった。
2006年、東京都現代美術館での大規模展
『大竹伸朗 全景 1955-2006』は今尚記憶に残っている
感動的な美術展の体験の一つである。
その圧倒的量の凄さ、エネルギーの凄さ、そして多才さ。
もうこれはぼくにとっちゃ、なんていうのか、
ひとつの事件といっていいぐらい衝撃だった。
なによりも、自分がいままで知っているかのように
思っていた大竹伸朗像が
はっきり甘っちょろい表層の情報だと認識させられたものだった。
何より驚いたのが「ダブ平&ニューシャネル」と称する
妙ちくりんな音楽小屋のようなものがあって
そこで、楽器が遠隔操作による演奏のしかけが施されてあるのだが、
となりの小さな小屋で
だれかが音をモニターでいじっているだけのように思えた光景は
実際その目の前に行くと、なんと大竹本人ではないか!
すっ、すごいとつぶやき
思わずびっくり仰天した瞬間であった。
大竹伸朗が、レフティーのギターでインプロをやっていたのだ。
その衝動たるや言葉を失ってしまった。
これはまさに、現代アートの巨人(ちょっと変な言い方だけど)の姿を
目の当たりにした思いがして
鳥肌が立ちそうな、そんなショックを受けた。
掛け値なし、大竹伸朗が生み出すものは半端なくすごい。
コーラジュの洪水、ジャンク廃品の海、
落書きやメモすべてがこの上なく美しいのだ。
まあ、ここでいう「美」の概念は、
圧倒的な力、というかエネルギーというか混沌というか
そういうものを併せ持った
ひとつの宇宙との遭遇のことをいっているつもりだ。
大竹伸朗はかつて美術学校を頓挫し
北海道の牧場で働いたり、
ロンドンくんだりまで自分探しの旅に出て、
いわば衝動というものに突き動かされてきた人である。
そうして本物のアートに出会って開眼した
本物のアーティストでもあるということは実に興味深い。
そこでラッセル・ミルズやホックニーに出会い、
そして音楽をも体験し、聖地ロンドンで
時代の洗礼を浴びたことが全ての礎になっているのだという。
その後直島での作品も含め、大竹伸朗の世間的価値は
じわじわと高みに上って席巻して行った気はするのだが、
それでも、まだまだこの偉大なアーティストへの理解としては
足りてはいないように思われる。
無論、世間の評価などに左右されず、
大竹伸朗は今も昔も何か得体の知れない
内なるマグマのような衝動によって駆り立てられ、
そして希求する姿勢を
今もなお継続している希有なアーティストである。
大竹伸朗のアートは一言で語りつくせないのだが
世間が知っている大竹伸朗は一部だってことに気づくことが、
その世界の深遠さの入り口となる。
カタチあるものからの再構築と無からの表出とがあって
ジャンクもあればコラージュ、単純に軽いタッチのイラストや
『ジャリおじさん』のような絵本もある。
ダブ平のような音楽装置もあれば、
直島での銭湯『I♥湯(アイラブゆ)』なんかもある。
無国籍、時代背景をランダムに構築し
大衆の気を絶妙にくすぐりながら
まったく重厚なもの、これぞ現代アートと呼ぶものまで
とにかく圧倒的カオスに満ち満ちているのである。
冷静にその軌跡を追うと、彼自身
“塊”というものに非常にこだわったアーティストであることが
浮かび上がってくる。
ロンドンのポートペローの蚤の市で、
マッチの広告から始まった有名なスクラップブックは
今では60冊をもこえている。
そのほか『大竹伸朗 全景 1955-2006』のカタログもそうだが、
大竹伸朗は数々の美しい本、アートブックを作ってきた。
本とは、いってみれば紙の集合物である。
そこに何が印刷されているかだけが問題だが、
そこの大竹伸朗の全身全霊のワークが
とても美しい装丁で丹念に組み上げられている。
それらはまさに芸術品と言ってさしつかえないものばかりだ。
その原点にスクラップブックというものがあり、
スクラップブックこそは
まさに大竹伸朗の芸術的指針が込められた重要なものとしてある。
おそらく、彼が死ぬまで続く壮大な“日記”なのであろう。
あらゆるものがアートになり、そしてアートとは
自己発見の延長上にある思いの発露として存在するものなのだ
ということが証明されてゆく。
小学校のときから、彼はアニメキャラの落書きや絵を好んで描き
作文では自分が将来なりたいものに
「古いものを守りたい」と書いた少年であった。
小さいときから、彼は一環したヴィジョンをもっているのだ。
そして、彼の中に音楽への偏愛が刻み込まれ、
エログロから崇高な神までを宿した
二十一世紀のポップスター、あるいは錬金術師なのかもしれない。
その作品を湛然と見渡せば、
マックス・エルンストやクルト・シュビッタース、
そしてラッセル・ミルズ。
あるいはアンディ・ウォーホールにラウシェンバーグ、
ピカビアやピカソ、ホックニー、デュシャンなどなど
錚々たる芸術家に触発されながら活動を続けてきたことがわかる。
音楽活動もまた、彼の重要な表現の一環であり
ロンドンでは、ワイヤーのメンバーである
ルース・ギルバートにグレアム・ルイス、
そして大竹伸朗にラッセル・ミルズで
「クルパ・カポル」というサウンドパフォーマンスをやっていた。
(「全景」ではそのビデオが上映されていた)
ちなみに、ラッセル・ミルズとは、
ロンドンで美術学校のラッセルの卒業作品に
大竹が出会い打ちのめされたアーティストであり、
以後の大竹に多大な影響を与えてきた人物である。
音楽に造詣が深い美術家というべきか。
ミュージシャンとの親交もあつく、
UnDark名義のアルバムでは
そういったミュージシャン人脈とのコラボレーションで
イーノ兄弟、デヴィッド・シルヴァアン、ビル・ラズウェル、
マイケル・ブルック、ピーター・ガブリエル、
コクトー・トゥインズのロビン・ガスリーなどが参加して出来上がった、
ダークアンビエント、ダークエレクトロニカになっている。
情緒とエレクトロニクスを多用した音のランドスケープは
そのままラッセルのアートワークに見いだされる情緒そのものである。
とにかく、大竹伸朗ほど作品を見るには覚悟のいるアーティストもいない。
語るにもそれ相応の覚悟が必要だということが
だんだんわかってきたので、このあたりで〆たいところだが、
少なくとも何かを表現する人間、
あるいはそれを試みようとする人間にとって、
これほど確かな道標はないと思う。
自分が現代美術がつまらないと思うのは、
実はその部分である気がしている。
頭でっかちで、いくら観念的に優れ高尚的であれ形而上学であれ、
人間としての熱情から生み出されたエネルギーが感じられない世界に
さして惹かれはしないのだ。
いわゆる現代美術の一つに大きな壁がそこに立ちはだかってくる。
もっとも、大竹伸朗は現代美術の作家という枠に
収まりきれないアーティストだと最初に書いたように
その可能性が無限に広がりを見せるアーティストである。
仮に、あたまでっかちな感じでとらえているひとには、
まず、絵本『ジャリおじさん』をおすすめしよう。
子供ならずとも、まずは大人が読むべく絵本なのかも知れない。
「ジャリ ジャリ」という「こんにちは」という挨拶の言葉で始まる。
本家ジャリおじさんのひげ(はなげ?)は
鼻の頭にまで移動してる(!)。
で、このジャリおじさんは、あおい海好き。
あるとき気づくと長い道がのびている。
あるいてゆくとピンクいろののそのそワニくん出会い、
つれだってすすむこの冒険物語の結末はいかに?
うむ。結局意味なんて必要ないかもしれない。
めぐりめぐれば等身大の自分がある。
山は山である、的な感じがすがすがしく、
ある意味こりゃあすこぶる禅的な話である。
そんな作品をも作れる大竹伸朗。
そこがこのアーティストの本質なのだ。
Puzzle Punks : Puzoout
インプロビゼーション以前の、何物にも回収されることなくひたすら無軌道に半永久的に発散され続けるノイズコラージュの闇、といってしまえばそれまでだが、もとをただせば、80年代初頭に大竹伸朗とボアダムズの山塚EYEとのユニット「JUKE/19」にはじまる「パズル・パンクス」は、自動演奏マシン「ダブ平」による無機質な繰り返しとともに、大竹伸朗と山塚EYEのカオスが合体して、ひとつの宇宙としての巨大な音響空間となって目の前に、形をともなって現れるのだ。’96年セカンドアルバム「BUDUB」発表直後の録音らしいが、お蔵入りとなっていたという幻のセッションが『PUZZOO』の実態だ。この表出せぜるをえないノイズの動物たちのエネルギーを体感せよ。それは音楽などではない。むろん、美術でもない。それはまさに魂の叫びだ。









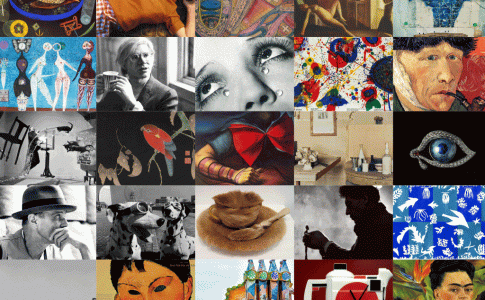



コメントを残す