しっとりさらっとジャパニーズシティポップの洗礼を
雨と合う音楽は、やっぱりいいなと思う。
日本という風土に合うんだろうな、きっと。
で、いきなりシティポップなんて言葉を、そこに無理やりこじつけよう、
なんていうつもりはないのだけれど、
ふと、シティポップと雨の相性って案外わるくないよな、
なんて思い始めて、曲をひとつひとつ味わうようにきいていると、
なるほど、あながちこれって的外れなんかじゃないな、
ってなことがわかってくるわけなんだ。
もっとも、これは僕自身のポリシー、というか
音楽の聴き方において、あまりジャンルというものは執着がないし
分類すらも意味をなさないのであり、
わざわざ、シティポップなるものを
得意げに語ろうという魂胆があるわけでもない。
あくまで、自分がこれまで無意識に聴いていた曲が
なるほど、シティポップというジャンルとして呼ばれているんだよな、
という程度の思いを、ここで再確認しているに過ぎないってことだ。
とはいうものの、今、世界で日本のシティポップ人気が高まりを見せ
そのクオリティ、その実力の程が再発見されている事実は喜ばしき事態であり、
改めて、その音楽の豊かさにひとりごちるのである。
そもそも、シティポップとはなんぞやといわれて
即答するにうまい言葉が出てこないし
あえて、世の解釈は、ひとまず置いておくとして、
我が認識上では、大衆に支持されうる都会的センスの下に、
メロディやリズムが心地よいもの、
あるいは、どこかで郷愁を帯び、琴線に触れてくるようなもの、
というような、漠然とした理解で聴いているのだと思う。
それは主に、70年代半ばから80年代前半に集中した、
一つの音楽の傾向として捉えているわけなんだが、
幸か不幸か、我が愛するシティポップの楽曲および、シンガー、ミュージシャンたちは
そもそもがシティポップのカテゴリーを軽く超越するだけの
技量と幅広いレンジを誇っている人たちであり、
何も、狭義に限定するつもりは毛頭ないのである。
なんだか、一人小難しい論調へと邁進してしまったが、
雨とシティポップという組み合わせは、
実に、きってはきれぬ関係性を持っているものだな、ということを
ただ曲を追っているうちに直感的に感じているだけのことであり、
特別の根拠も縛りもない。
自分にとって、都合の良い解釈ではあるが、一つの聴き方として
少なくとも、人が無条件で忌み嫌う雨の呪縛を
シティポップの軽妙さで解消しうることは間違いないんじゃないか、なんて思うのだ。
ここにあげるソングリストを聞いていると、どれも素晴らしいんだけれども
みんな根っこでつながっていて、
やはり、それは脈々と今日まで流れる日本のポップミュージックシーンの
根幹のような気がしているんだな。
雨は手のひらにいっぱい:シュガーベイブ from『SONGS』
レイニー・サタデイ&コーヒー・ブレイク:大橋純子&美乃家セントラルステーション from『RAINBOW』

あの一風堂のギタリスト、土屋昌巳が在籍していた、というのが、この大橋純子&美乃家セントラル・ステイションである。当時は学園祭に引っ張りで、学園祭のクイーンとして君臨していた大橋純子の歌唱力は、日本のジャニス・ジョップリン、とまではいわないが、今聞いても素晴らしい。公私にわたるパートナーであるキーボードの佐藤健をはじめ、バックのメンバーの腕も確かであり、日本のシティポップ全盛期に君臨したバンドのひとつとして、堂々その名が刻まれている。
こぬか雨:伊藤銀次 from『DEADLY DRIVE』

第二期シューガーベイブのギタリストでもある伊藤銀次は、脱退後、大瀧詠一らとナイアガラへとむかってゆくのだが、これはその後に出したソロ『DEADLY DRIVE』からの一曲。フェンダーローズ、ピアノ、そしてホーン&ストリングスアレンジには坂本龍一。僕が好きなシティポップ間でのミュージシャン達は、みんなどこかでかぶっているから、全体で日本のポップミュージックの全盛期の母体を形成していたんだなって思う。それにしても、伊藤銀次という人が、あの長寿番組『笑っていいとも!』のテーマソングを作った人だってことすらも、忘れれられてゆくんだろうと思うと、少し寂しさがこみあげてくる。
サブタレニアン二人ぼっち:佐藤奈々子 from『Funny Walkin’』

元祖渋谷系、元祖ウィスパリング・ヴォイスなんて言い方もされる佐藤奈々子。同時に彼女はカメラ片手に写真家としてもワールドワイドに広告業界でも活躍した人だ。そんな彼女の自由な感性が炸裂する名盤『Funny Walkin’』から、代表曲ともいえるこの「サブタレニアン二人ぼっち」は、彼女を世に知らしめたあの佐野元春が曲を書き、アレンジには、ルパンの大野雄二が、実に洒脱なジャズ〜フュージョンテイストを持ち込んで、今聞いても色褪せないクール&ラブリーに仕上げている。これまた名曲だな。
さりげなくジンジャーエール:越美晴 from 『Make Up』

いまでこそ、細野晴臣周辺のミュージシャンとして、
定番のように聴いているコシミハルだが、
当時はまったく眼中になかったというのが正直なところである。
が、あるとき突如テクノ回帰した彼女の存在には驚いたものだがにわかに興味をかきたてられるや、
ひとたび気をゆしてしまうとそのすべてを受け入れたくなるもので、当時の越美晴名義の歌謡曲〜シティポップ路線を
今改めて聞き直してみると、悪くはないのである。
もっとも、当人にすれば、あんまり触れて欲しくないのかもしれないが・・・
雨の夜明け:大貫妙子 from『Romantique』

教授と幸宏がサポートするこの曲にひろがるヨーロピアンムードには、まるで向こうの映画を見ているようなそんな空気感がある。けだるく、ポエティックな雨と夜明けの組み合わせは、いたってイマジネーティブな大人のフィーリングをくすぐってくるのだ。それこそは、このアルバムで展開される「ロマンチック」そのものなんだと思う。ター坊に関しては、今更説明不要なのだが、個人的には、やっぱりシュガーベイブ時代を含む、70年から80年代にかけての、まさにシティポップ全盛期の曲の方が好みなんだよな。
駅:竹内まりや from『REQUEST』

ユーミンにしても、中島みゆきにしてもそうだが、やはり女性のSSWの描く世界は結構ヘビーな男女関係の女心が歌われてきた。若い男子には理解できないところだが、あまり歌詞には注目されないなか、それはそれでまたシティポップの流れにある重要なものだ。この竹内まりやの名曲「駅」にしても実に切ない。そしてなによりウエッティだ。雨の日にこれを聴いていると、だんだんその世界の深みにはまってゆく気がしてくる・・・もっとも、竹内まりやには、もっと軽くライトなポップ感性をもちあわせている曲がたくさんあるのだから他を聞けばいいのだが、雨の日にはなぜかこの曲がぴったりなのだ。
Rainy Walk:山下達郎 – from 『MOONGLOW』

今では夏も、冬も、そして梅雨も、
山下達郎の音楽なしで過ごせない身体になっている。
シティポップの代表選手はまぎれもなく、この達郎だろう。
とはいえ、わざわざシティポップという言葉を出してきて、
彼を語るのは簡単だが、それぐらい、一体化している山下達郎という人が、日本のポップミュージックにもらした貢献度は偉大だ。
まさに至宝だといっていい。そのことは声を大にしていっておこう。
この軽やかな「Rainy Walk」を聞きたまえ。雨の日に静かにステイホームなんかしている場合か、そう思うのだ。
そして決まりごとのように、週末はダウンタウンへと繰り出したくなるのが
まさに達郎マジックというやつか。
雨に泣いてる:柳ジョージ&レイニー・ウッド from『WEEPING IN THE RAIN』

日本に数少ないR&B〜ブルース感覚をもった柳ジョージという人を、わざわざシティポップのくくりでとりあげていいものか、はわからないけれども、この曲にしてもバンド名にしても、いわゆる雨の似合うミュージシャンということでとりあげてみることにする。ショーケンが刑事役をつとめたテレビドラマ「死人狩り」の主題歌に使用されたのがこの『WEEPING IN THE RAIN』。ドラマの方はまったく記憶がないけど、機会があったら観てみたい。
RAINY DAY:吉田美奈子 from『モノクローム』

吉田美奈子は外せないのです。これはいうまでもなく、達郎の曲で、達郎版の『RIDE ON TIME』に収録の「RAINY DAY」ももちろんいいんだけど、あえて吉田美奈子バージョンを聴いてほしい。できればデュエットでもしてくれれば最高なんだけどね。不思議なことに、達郎バージョンからは街の灯りを取り込んだカクテルカラー、吉田美奈子バージョンは文字通り淡い感じのモノクロームトーンのイメージがするのです。






![[門戸無用]MUSIQ](https://lopyu66.com/wp-content/uploads/2020/11/misiq-1-485x300.gif)


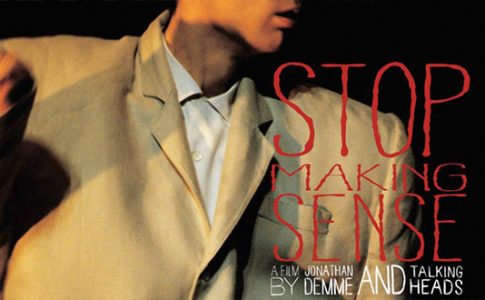



シティポップの源流、シュガーベイブの名曲揃いのナンバーの中でも、「雨は手のひらにいっぱい」は屈指の名曲だと思う。達郎がソロになっても好んで取り上げるナンバーだが、このあたりのフィルスペクター調のアレンジは、大瀧詠一のアイデアらしい。この演奏は、 1976年4月1日萩窪ロフトでのライブバージョンから。うーん、こういうのを生で観た人は羨ましい限りだ。と同時に、当時の主流の音楽から隔たっていたという理由で、セールスに結びつかなかったというのがにわかに信じられないな。